async [ディスク・レビュー]
今日はブルーノート東京ライブ・ストリーミングだけではなくひさしぶりに坂本龍一教授の作品を聴いてみようと思いました。
学生のときは、YMOの大ファンでしたから。3人編成、トリオが大好きでしたので。その後、戦場のメリークリスマスとかその都度耳にしてきましたが、ちょっと自分が離れてしまっていたこともあり、ひさしぶりに坂本教授の作品を聴きます。
4年前の2017年に大変話題になったasyncを聴いてみようと思いました。
async
坂本龍一
坂本龍一
8年ぶりのソロ・リリース。そしてその当時、癌発見ということで、非常に人生の節目になった大きな作品だったと推測します。盟友オノ・セイゲン氏とともに京都で録ったのではないでしょうか?
つい先日のニュースでも癌の転移を知り驚きました。いろいろな覚悟をされていると慮りますが、これからも停まることなく、更なるアーティストとしての邁進を期待して祈っております。
asyncを拝聴しましたが、これは抽象美というか、非常に哲学的な作品ですね。坂本教授の美意識の世界観をそのまま音として表現したものではないか、と思います。なんか自分には、現代アート、現代美術のあの抽象的な世界観を感じますね。
素晴らしいです。
自分が坂本教授に抱いている印象は、非常にアート的で繊細な美意識を持っていて、それはいままでリリースされているアルバムでもよくわかりますね。
あと、ミュージシャンとしてだけではなく、音楽業界の今後の行く末にも関心を持たれ積極的に発言されている姿は、本当に素晴らしいのひとことです。
今日は”おうちタイム”なので、いままでの坂本作品をいろいろ聴いてみましょう。
ストリーミングは本当に便利ですね。
ただ音楽家にとってお金になるのかどうかは知りませんが。(笑)
ただ音楽家にとってお金になるのかどうかは知りませんが。(笑)
話題になった当時ではなく、4年後のいまasyncを聴いての遅すぎる称賛でスミマセン。(笑)
オノ・セイゲン氏は、ソニーとともに、DSD推進、イマーシブ・オーディオの旗頭として活躍している日本のサウンド・エンジニアのパイオニア的存在なのは、もうみなさんよくご存じだと思うのだけれど、実際どういう音、サウンドを作る人なのかは、じつは自分はよく聴いたことがなかったんですよね。(笑)
ちゃんと対峙して聴いたことがなかった。
この坂本教授のasyncを聴いてみて抱いたサウンドの印象は、非常に実験的なサウンドですよね。立体感が素晴らしいです。計算されつくした意識した音作りをしますね。
造り込まれている感が凄いです。
ふつうにスタジオやホールでミュージシャンが演奏する音楽をそのままちょっといじって加工するという感じではないです。
それは坂本教授のasyncの作品のコンセプトがそうなのかもしれませんが。
PCオーディオのストリーミングでのふつうの2chステレオなんだけれど、非常に立体的で3D的に聴こえます。
オブジェクトベースで音源を空間配置しているような感じで、ある効果音は自分の頭の後ろのリアから聴こえてきたりしますし、前方のステレオのサウンドステージも、その音源の種類に応じてその空間に現れる位置が、前後奥行きや左右に、ポッポッといろいろ違う位置からその都度現れる感じで非常に立体的です。
まさに造り込まれている感、空間の座標軸を徹底的に計算しつくしたサウンドですね。
非常に人工的です。(笑)
ふつうの音楽を聴いている感じじゃないです。
ふつうの音楽を聴いている感じじゃないです。
結論として、ガッカリしなくてよかった、というところでしょうか。(笑)
最新のイマーシブもいいけれど、今度は、自分が普段聴いているSACDサラウンドでのサウンドを聴いてみたいです。やっぱり普段自分が聴いている自分の物差しで確認してみたいですね。
やっぱり造り込まれている感の強いサウンドだけではなく、”音楽”をどのように録るのか、を聴いてみたいです。
オノ・セイゲン氏が録ったサラウンド音源は、ファントムセンターで録っていたという話をちらっと聞いたこともあるので、やっぱり自分の耳でじかに確認してみたいです。
ヤノフスキのベートーヴェン観 [ディスク・レビュー]
もともと、この1月10日にリリースされたばかりのヤノフスキ&WDR響によるベートーヴェン交響曲全集のレビューをおこなおうとして日記にする予定で、書いていて思わずヤノフスキ全般のことに広がってしまい、仕方がないので日記をふたつに分けることにした(笑)というのが真相である。
ベートーヴェン交響曲全集
マレク・ヤノフスキ&ケルンWDR交響楽団(5CD)
ご覧のようにレーベルはPENTATONEである。ちょっと不満なのは、ふつうのPCM 2ch ステレオなのである。しかも、先売された第5番、第6番はSACDだというのに、全集のCD-BOXになった途端、CD全集となってしまった。
これはあまりに残念だよね。
ヤノフスキでPENTATONEとこれば、絶対にSACD5.0サラウンドだ。いままでヤノフスキの全集といえば、ベルリンフィルハーモニーでのワーグナー全集BOX、ジュネーブ・ヴィクトリアホールでのスイスロマンドとのブルックナー全集BOX、いずれも看板のSACD5.0サラウンドでの全集である。
しかもベートーヴェンイヤー250周年を祝してのアニバーサリーイヤーでのリリースなら尚更、看板のSACDサラウンドでリリースするべきではなかったか?
いろいろ推測したりする。このコロナ禍、メジャーレーベルでも苦しい経営を余儀なくされている昨今、マイナーレーベルは、さらにその経営難の厳しさを増すであろう。
SACDでリリースするのはコストがかかりますからね。
そういうコスト面からの理由であるならば、事情はよくわかるにしろ、でもやはり悲しい。クラシック界の王道中の王道であるベートーヴェン交響曲全集をPENTATONEからリリースするなら、ぜひSACD5.0サラウンドでやり直してほしいものだ。
当録音は2018年10月から2019年11月にかけて、当団の本拠地ケルン・フィルハーモニーにて収録された。ヤノフスキのベートーヴェンといえばNHK交響楽団とで、第3番「英雄」そして第九演奏会を披露して話題となった。
また、2019年11月のケルンWDR交響楽団とも来日公演をやっており、第6番「田園」を披露した。その圧倒的な統率力とパワフルなエネルギーの中にも繊細な響きを作り上げる巨匠ならではの演奏を聴かせてくれた。
その当時は、ヤノフスキと良好な関係にあった日本クラシック音楽界。
いつでも実現できるような気がして、特に足を運ばなかった。東京・春・音楽祭で圧倒的なエンターテイメントを繰り広げてくれるから、という本筋が待ち受けているという自分の想いがあったことも確かである。でもまさか、まさかのコロナ禍な世の中になってしまい、もうこんなに遠い世界になってしまうとは・・・
本当に行かなかったことをいますごい後悔しています。
マエストロももう80歳を超える高齢だし、いつ再会できるか・・・
東京春祭のパルジファルも本当に大期待だけれど、果たしてきちんと来日できるのか・・・など、不安いっぱいである。
そんな中で届いたヤノフスキの渾身のベートーヴェン交響曲全集。
しっかりと楽しませていただいた。
録音は、2chステレオとしても十分な高音質なサウンドで自分は満足することができた。オーケストラとしての基本である厚みのある音、音像の明晰さ、音場の広大な感じもよく表現されていて、とてもいいステレオ録音である。
ヤノフスキのベートーヴェンは、前日記でも書いたとおりの内容を地で行くヤノフスキの音楽の作り方そのものであり、引き締まった音で、明晰で快速テンポでサクサクと進む感じで切れ味鋭いけれど、男らしい雄大なベートーヴェンとも言えるような出来具合にもなっていた。
非常に引き締まっていて、切れ味鋭いですよね。
ヤノフスキ・テンポでヤノフスキの音楽だなぁと思いました。
ヤノフスキ・テンポでヤノフスキの音楽だなぁと思いました。
ここは鳴らし処と思ったところは、極端なまでにダイナミックレンジを深く、その全レベル幅を使い切った録音の仕方をする。特に意表をつかれ、こういう音の収め方、表現は普通はしないよな、と思ったところに第九でティンパニーを思いっきり前へ前へ出すような大音量で録っているところだ。
こういう第九はあまり聴いたことがない。そしてまさに疾風のごとく超高速で駆け抜ける第4楽章のエンディング。いやぁヤノフスキ先生もなかなか個性的である。N響との第九公演ではその解釈に賛否両論で物議を醸した、というようなことをSNSで読んでいたが、なるほど、このことか、と思ったこともある。
自分は第1番から第9番まで、すべて自分の好みで大好きな演奏であった。非常に男らしく雄大でありながら、切れ味鋭い、そんなベートーヴェンである。
王道の演奏だと思う。
1,2番もいいし、特に2番は大好きですね。3番は最高、4番もいい。5番は一番大好きで最高。6番、のだめ7番もいい。8番は1番小さな小品だけれど、じつはこれはベートーヴェンのあまり公にできない女性との恋について書かれた作品で、最近自分のマイブームなのである。いいな~とほのぼの感じ入ってしまう。そして第九はなにをや況やである。
みんな好きだったけれど、第3番「英雄」が特に素晴らしい。
N響との日本公演でも「英雄」を取り上げており、マエストロにとって第3番「英雄」はとても大切な曲なのである。
「エロイカ」は、「19世紀の「春の祭典」」だと私は考えています。ストラヴィンスキーの「春の祭典」が20世紀初頭の爆弾だとしたら、「エロイカ」は19世紀の交響曲の爆弾です。交響曲の歴史でこれほどの飛躍を遂げた曲はありません。作品の長さだけでなく、特に第1楽章の展開部など、対立する主題が弁証法的に高まっていく様は驚くべきものがあります。それから、第2楽章の葬送行進曲におけるとてつもない表現。まさに19世紀初頭から未来を指し示した作品なのです。
とにかくヤノフスキ先生らしい、非常に切れ味鋭い男らしいベートーヴェンだったので、やっぱりSACD5.0サラウンドで出してほしかったな~と思うところです。
ベートーヴェンの交響曲全集という王道中の王道を、SACD5.0サラウンドで収録している録音というのは、あまりないのではないでしょうか?
それをPENTATONEがやらなくてどうする?
という感じなのだが。。。(笑)
ラトル&ウィーンフィル ベートーヴェン交響曲全集 [ディスク・レビュー]
2002年にムジークフェラインザールで録音されたラトル&ウィーンフィルによるベートーヴェン交響曲全集は、ベーレンライター版の使用、ノンビブラートなどのピリオド奏法的なアプローチ、それによる乾いたドライな響き、そしてラトル独特のアクセントを効かせた解釈で、クラシック界に物議を醸した。
好き嫌いがはっきり分かれ、いままで我々が慣れ親しんできたベートーヴェンの交響曲像を根底から覆すような驚きの連続であった。
長く伝統的スタイルによるベートーヴェンに親しみ、それが正統的なベートーヴェンだと信じている人が聴けば、少なからずショックを受けると思う。
サー・サイモン・ラトルは2002年からベルリンフィルの芸術監督・首席指揮者に就任することが決まっていた時期で、自分は彼に注目していたので、その時のタイミングでリリースされたこのラトル&ウィーンフィル盤をすかさず入手して聴いた。
そうするとそのあまりに斬新な解釈とそのアプローチに驚き、ベルリンフィルにとってもっとも重要な作曲家であるベートーヴェンの交響曲について、こんな解釈をする人が天下のベルリンフィルに就任したら、それこそ栄光ある歴史がメチャメチャにされてしまうのでは、と危惧を抱いたものであった。(笑)
それだけ衝撃であった。
このラトル&ウィーンフィル盤は、こんなのベートーヴェンの交響曲じゃないと頭から排除する人も当時多かった。
そんな想い出のあるラトル&ウィーンフィル盤を久しぶりに聴いてみようと思った。
ベートーヴェン交響曲全集
ラトル&ウィーン・フィル(5CD)
ラトル&ウィーン・フィル(5CD)
いま聴いてみると、当時驚愕したほどの衝撃はなく、そんなに違和感もなく、いいんじゃないと肯定的な自分がいる。とても普通というか全然受け入れられる範疇のものだった。
全然普通である。
当時なにをそんなに驚いていたのか、と不思議に思うくらいである。
周りの批評に感化されたり、影響されていたこともあったかもしれない。
周りの批評に感化されたり、影響されていたこともあったかもしれない。
ただ、9番の第4楽章の合唱の部分とか、やっぱりう~んと唸ってしまうところは当時と変わらない印象である。
その理由に、いまは当時と比べて古楽奏法的なアプローチが増えてきて、我々が耳にすることも多くなり、それ自体抵抗なく自然に受け入れられるようになったということがあるのではないだろうか。
ラトルはベーレンライター版という最新研究を反映したスコアを用いているのだが、テンポ、デュナーミク、音楽記号の扱いが従来のブライトコプフ版とは微妙に違っており、しかもラトル独自の演出で、リズムがかなり攻撃的に感じられる。
全般的に快速テンポである。
やっぱり3番「英雄」が一番素晴らしい。それは一番普通っぽいというかノーマルな解釈だからである。(笑)従来通りという感じ。王道の演奏である。これぞ英雄という王道を行ってくれる。
1番、2番も全然いい。すごくいい。違和感なし。当時あれだけ変なアクセント、ドライな響きと思っていたのが嘘のように平常で重厚な響きに聴こえる。
6番「田園」も名演ですね。4番、5番「運命」も全然いい。
9番だけ、特に第4楽章の合唱の部分だけどうしてもやはり自分には拒否反応がある。
ラトルの解釈は好き嫌いを分けてしまうところがあると思う。
ラトルの解釈は好き嫌いを分けてしまうところがあると思う。
いままで聴いたことのないアドリブ的な歌いまわしや、合唱の粗さや薄さが際立ち、これは第九の合唱じゃないよ、とどうしても思う。
最後の合唱の部分はもっとも歓喜で盛り上がる最高潮のところである。この軽さ、粗さはどうしても自分のイメージ通りとはいえず、受け入れがたいかな。合唱は、手兵のバーミンガム市交響楽団合唱団のコーラスを迎えていますね。
ラトルはベートーヴェンの音楽に取り組む前にバロック音楽を徹底的に勉強したという。そうした道筋はニコラウス・アーノンクールをいわば模したもので、両者の解釈に共通するところも少なくない。
ロマン的なベートーヴェン像に見直しを加え、19世紀のベートーヴェンが生きた時代に彼の音楽が持っていた前衛性を明らかにする解釈の根源は似通っている。
アーノンクールが定期的にウィーンフィルに客演して古典派の新たな解釈を可能としたところも見逃せない。カール・ベームやヘルベルト・フォン・カラヤンが指揮台に立っていた頃のウィーンフィルならラトルの解釈を受け入れられる余地はなかったはずだ。
そんなところにもラトルのこのウィーンフィル盤のルーツを見ることができると思う。
ラトルは、このベーレンライター版を、最近のベルリンフィルのときに作成したベートーヴェン交響曲全集でも採用している。
このベーレンライター版について解説を試みよう。(引用元:ライナーノーツ)
この録音で使用したベーレンライターの原典版は、1996年から2000年にかけて発表された。それまではもっぱら1862~1865年のプライトコプフ・ウント・ヘルテル版が使われていたが、その重大な欠点が1世紀という年月を経て正されることになった。修正のポイントは大きく3つある。
まずは、ベートーヴェンが書き直した決定的な手稿譜があったことである。1862年に紛失したとされていたものが見つかったのだ。特に「田園」の清書楽譜(第1版からの複写)の発見である。1953年の洪水で浸水したものが、1984年、オランダで発見された。
緩徐楽章のスコアには、ベートーヴェンの指示(サインつき)がはっきり残っており、これを見ると、ヴァイオリンにミュートをつける指示は、それまで思われていたように校正の段階でベートーヴェンが取り消したのではなく、写譜を担当した者が単に見落としていたのだ、ということがわかる。今回は彼の指示を活かし、これによって楽章全体の雰囲気が大きく変わった。
第2に、オリジナル(手稿譜や第1版)を見返し、ブライトコブフのチェックの抜けがいくつか見つかったこと。彼は古いスコアにおいて一見問題のないと思われる箇所について特に綿密な確認を行っていたわけではなかったようだ。例えば、第9番最終楽章のトルコ風行進曲の終わりの部分でベートーヴェンは、歓喜のニ長調の合唱への架け橋としてホルン・パートに変則的なタイを加えている。今までの版ではそのままになっているが、今回は、研究者、演奏者ともに新しい解釈をしている。
第3に、ほぼ全ての資料(いかに多くの資料がこの100年間を生き抜いてきたことに驚く)を確認し、完璧な原典資料体系を再構築したことだ。例えば、第9交響曲のトリオの終わりのヴァイオリン・パートのように、あらゆる資料でいままでの解釈が違っているとなれば、どこかで間違いが起こったという事実とともに、ベートーヴェンの意図していたものは何だったのかを正確に知ることができる。
問題はこれの3つの違いを自分はきちんと聴きとれていたのか、ということだ。(笑)
現在のベートーヴェン交響曲の大半が、このベーレンライター版を採用しているなら、いまの時点でラトル&ウィーンフィル盤を聴いても違和感があまり湧かないのもつじつまが合う。
いずれにせよ、ラトルという人は、このベートーヴェンの交響曲に限らず、特に十八番のマーラーについてもそうであったように最新の研究結果に常にアンテナが敏感な指揮者で、新しい挑戦をし続けていた指揮者であったということだ。
そこが従来通りの伝統的な解釈を好む保守的なファン層から反発を買う要因にもなっていたところなのだと思う。自分はそういう前向きなところが好きでラトルを支持している側のファンである。
そんな”ベートーヴェンの交響曲全集”というクラシックの王道中の王道の分野で、エポックメイキングだったこの録音はぜひ一度聴いていただきたいと思っている至極の一枚である。
内田光子さんのディスコグラフィー [ディスク・レビュー]
自分が所有している内田光子音源の紹介をしていこう。
内田光子さんの音をずっと録り続けてきているのは、ポリヒムニアのエベレット・ポーター氏である。ピアノ録音としては、やや空間を広く拾っていて、ピアノの音がとても鮮明だ。でも決していじり過ぎず加工的でない自然なテイストがとてもいい。さすがな職人芸だと思う。
デビュー当時の録音と比較すると、新しい録音になるにつれて、洗練されてきて、聴きやすい耳障りがいい自然な録音になってきているように思う。
最近のとくにベートーヴェンのピアノ・ソナタのアルバムの音は段違いに音が良くて驚いた。一発目の出音を聴いたとき、びっくりした。いままでのアルバムとは全然違うのである。
段違いに音がいい。
響きがとても豊かで打鍵の響きが空間に漂うさまがとても美しい。
オーディオマニア好みの音のように感じる。
オーディオマニア好みの音のように感じる。
先の日記ではベートーヴェンのことはあまり言及しなかったが、内田光子さんのベートーヴェンピアノ・ソナタもシリーズで取り組んでいて、新しい録音なので、きっとこのシリーズ、みんなこんな感じで音がいいのかもしれない。
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ早く全集BOX化してほしいです。絶対買います!
シューベルト ピアノ・ソナタ集(8CD)
内田光子
内田光子
まさに自分にとって、内田光子さんのCDといえばこれなのである。
問答無用のトップに持ってこさせていただきました。
問答無用のトップに持ってこさせていただきました。
とにかく自分にとって難解だったシューベルトのピアノ・ソナタの魅力を教えてくれた神様バイブルでもあるのだ。「死ぬ時にはシューベルトを弾いていたい」と語る内田光子さんが1997年1月31日、シューベルト生誕200年を祝う誕生日にリリースを開始したシューベルト・チクルスが8枚のCDで完結したものである。内田さんの審美眼によって選び抜かれたレパートリーのみが、磨きぬかれたタッチでここに刻まれている。シューベルトを弾くために3年の月日を費やして調整した内田自身のピアノをムジークフェラインに運び、モーツァルト録音でも数々の名盤を生み出したプロデューサー、エリック・スミスのもとで行われた録音である。
内田光子さんが世界にブレークしたきっかけになったのが、このモーツァルトのピアノ・ソナタ。内田さんの原点です。内田光子さんの世界的な名声を決定づけたソナタ全曲録音のセット化。ロンドンのウィグモア・ホールでおこなわれたソナタ全曲演奏会(1982年)の大成功を受けてレコーディングされたもので、平行しておこなわれたコンチェルト録音ともども、一躍世界の中心へと押し出す契機となった記念碑的な名盤である。
このモーツァルトのピアノ協奏曲全集もそうです。ソナタ全集と並んで、内田光子の世界的な名声を決定づけた名盤。内田光子さんの原点はモーツァルトで、モーツァルトの作品に関して「音楽の本質を捉えた解釈者」として国際的にも定評があるのです。
モーツァルト ピアノ協奏曲第18番、第19番
内田光子、クリーヴランド管弦楽団
内田光子、クリーヴランド管弦楽団
モーツァルト ピアノ協奏曲第23、24番
内田光子&クリーヴランド管弦楽団
内田光子&クリーヴランド管弦楽団
内田光子さんのモーツァルト ピアノ協奏曲全集は、じつは自分的には、ブレークしたイギリス室内管の録音より、こちらのクリーヴランド管弦楽団との再録音のほうが好きである。やはり新しい録音だし、音が洗練されてますね。演奏もより円熟味に達しています。より進歩した先進的な解釈を楽しめます。自分の原点であるモーツァルトは、やはり再録音しておきたいなにかadditionalなものがあったのでしょう。クリーブランド管弦楽団ので全集も完成させてほしいです。
自分がヨーロッパに住んでいたとき、アムスに住んでいた同期の友人が、この実演に接した公演で、それがそのままCDになったということで、自分も記念に購入しました。録音はやや古い感じがしますが、コンセルトヘボウ・ホールのあの滞空時間の長い響きがよくわかる録音です。
“最後の巨匠”と賞され、90歳を迎えた2002年に惜しまれつつ引退したクルト・ザンデルリングに対する内田さんの敬愛はよく知られているところで、ザンデルリングの引退コンサートではモーツァルトのコンチェルトを共演、感動のあまり終演後に涙を浮かべたというエピソードも。このベートーヴェン録音も、内田さん自身のたっての希望でザンデルリングとの共演が実現したもので、当時のインタビューで「ザンデルリングとでなければベートーヴェン録音はありえない」とまで語っていたそうです。
ベートーヴェン ピアノ協奏曲全集
内田光子、サイモン・ラトル&ベルリン・フィル(3SACD)
内田光子、サイモン・ラトル&ベルリン・フィル(3SACD)
これはまさに自分の時代の録音ですね。(笑)やっぱり最高です。
録音も素晴らしいです。ラトル&ベルリンフィルはEMI時代は録音のクオリティに恵まれませんでしたが、自主制作レーベルになってから抜群に録音のクオリティがよくなりましたね。王者に相応しい録音になりました。
自分がここに挙げているのはSACDのほうです。CDのほうも別にあります、CDのほうは映像のBDとセットになっています。やっぱりSACDはいいです。
この公演の模様は、Digital Concert Hall(DCH)でも全部コンプリートしました。
シューマン:女の愛と生涯、リーダー・クライス作品39、ベルク:7つの初期歌曲
レシュマン、内田光子
レシュマン、内田光子
グラミー賞を受賞した記念すべきアルバムです。自分もびっくりしました。しかも自分がもっとも敬愛する歌曲、シューマンの女の愛と生涯。この曲でグラミー賞を受賞してくれるなんて、なんか嬉しいというか縁を感じました。
これは最高に音がいいです!一発目の出音を聴いたとき、びっくりしました。いままでのと全然違います。段違いに音がいいです。日記ではあまりベートーヴェンのことは言及しませんでしたが、内田光子さんのベートーヴェン ピアノ・ソナタもシリーズで取り組んでいて、新しい録音なので、きっとこのシリーズ、みんなこんな感じで音がいいんでしょうね。ベートーヴェンも早く全集BOX化してほしいです。絶対買います!
曽根麻矢子さんのチェンバロを聴く [ディスク・レビュー]
曽根麻矢子さんのチェンバロの実演は、じつは、ここ数年縁があって、2回ほど体験することができた。
サラマンカホール30周年記念ガラコンサート、そしてハクジュホール・リクライニング・コンサートである。
まさに日本はもちろんのこと世界を代表するチェンバロ奏者の第一人者と言ってもいいだろう。
前回のハクジュホール・リクライニング・コンサートのときに、曽根麻矢子 J.S.バッハ連続演奏会の情報を知ったのである。
スイス在住のチェンバロ制作者デヴィッド・レイが曽根麻矢子のために長い時間をかけて制作した18世紀フレンチモデルの楽器を使用し、バッハのチェンバロ主要作品を5年をかけて演奏する話題のコンサート・シリーズがハクジュホールでスタートする。
これは絶対行かないといけないでしょう!
チェンバロといえばやはりバッハだと思うし、そのバッハの曲、ゴルトベルグ変奏曲、平均律クラヴィーア曲集、イギリス組曲、フランス組曲・・・などなど蒼々たる名曲ぞろい。
チェンバロは、オーダーメイドであるのが基本だが、このコンサートのために18世紀フレンチモデルの特注品。
足掛け5年をかけて演奏する。
このツィクルスは全部コンプリートしてもいいと思います。
それだけ価値のある連続演奏会だと思いますよ。
しかもハクジュホールは、音響が非常に優れていて、室内内装デザインも芸術的な独特の意匠。自分の大のお気に入りのホールでもある。
こういった大掛かりな連続演奏会は、過去にもあって、浜離宮朝日ホールで、2003年からの全12回、6年にわたるJ.S.バッハ連続演奏会、そして上野学園エオリアンホールで、2010年から2014年までの全12回のF.クープランとラモーのチェンバロ作品全曲演奏会。
今回3回目の連続演奏会になる。
普段、チェンバロを聴くことや、チェンバロの演奏会が開催されること自体、そしてそのチェンバロ・コンサートに行くこと自体、なかなか経験できないレアな体験だと思うので、これは絶対行きのコンサートだと思っていました。
もちろんチケットを取っていて、楽しみにしていた第1回の演奏会のゴルトベルグ変奏曲。(2020/9/24)
なんと!残念ながらコロナ禍で来年3月へ延期が決定。
もうすごい楽しみにしていたのにガッカリもいいとこ。
このコンサートの感想も併せて、ディスコグラフィーも数枚買いそろえて、まとめて日記を書く予定だったのだけれど、まさに失意の日々。
来年3月まで待てないので、まずはディスクレビューでも日記にしようと思って、この日記を書いている。
(c)Noriyuki kamio
曽根麻矢子プロフィール
桐朋学園大学附属高校ピアノ科卒業。高校在学中にチェンバロと出会い、1983年より通奏低音奏者としての活動を開始。1986年ブルージュ国際チェンバロ・コンクールに入賞。その後渡欧を重ね、同コンクールの審査員であった故スコット・ロスに指導を受ける。ロスの夭逝後、彼の衣鉢を継ぐ奏者としてエラート・レーベルのプロデューサーに認められ、1991年に同レーベル初の日本人アーティストとしてCDデビューを果たした。
以後イスラエル室内オーケストラのツアーや録音に専属チェンバリストとして参加するほか、フランスおよびイタリア等のフェスティバル参加、現代舞踊家とのコラボレーションなど国際的に活躍。
日本国内でもリサイタル、室内楽と積極的な音楽活動を展開するとともにテレビ、ラジオへの出演、雑誌「DIME」でのエッセイ連載、「いきなりパリジェンヌ」(小学館)の刊行など多才ぶりを見せている。
(曽根麻矢子 Official Website)
チェンバロは、やはりバロック時代の音楽の楽器ですね。
やはりバッハだと思う。
ご自身のディスコグラフィーを俯瞰させていただくと、やはりチェンバロ奏者としてのキャリアは、バッハを主軸に置いていらっしゃるのがよくわかる。ほとんどのバッハの名曲はすべて録音してきて網羅されていると言っていいと思う。
インタビューでも、「バッハが大好きで熱中し、レコードを聴き知識を貪るなかで、どうしてもバッハをチェンバロで弾いてみたい! と熱望するようになりました。」と答えている。
今回じつにひさしぶりにバッハを聴いたわけだけれど、音楽って、近代に近づくにつれて、造形、音楽の型が凝ってきて、世俗的な感じになってくるように思うのだけれど、バロック時代のバッハの音楽は、とてもピュアで純粋というか、本当の意味で音楽の原型を聴いているような感じがしますね。本当にシンプル。
基本に立ち戻るという感じがします。
たまにはバッハを聴くのもいいです。
チェンバロという楽器の発音の仕組み、奏法、音色、ピアノとの違いなど、日記にして自分の理解を確固たるものにしたが、やはりあの音色は独特ですね。
倍音を多く含んだこの独特の複雑な音色。
いかにも弦をはじいて発音しているという弾力性のある音。
いかにも弦をはじいて発音しているという弾力性のある音。
この光沢のある艶感をいかに出せるか?
そして教会や礼拝堂で演奏しているのがよくわかる残響感、空間感など、この音色とあいまって、まさにチェンバロ独特の世界。
チェンバロのオーディオ再生というのは、なかなか難しいのでは?と思います。オーディオ再生、システムの実力が試される。得手不得手の方々が出てくるのは当然のような気が。。
チェンバロの録音って、生音で聴いているより、その光沢感がより強調されている、そういう調理が施されているような気がします。
あと、チェンバロは、ピアノと違って音の強弱をつけることができないので、全曲通して聴いているとどうしても一本調子に聴こえてしまうところがありますね。しかもバッハの曲など、どんどん疾走していく感じで煽られるので、そういう意味で緩急のある現代曲と違って、興奮のつぼがちょっと違うような気がします。
曽根さんは、このチェンバロ楽器で強弱をつけることができない、ということにインタビューでこう反論している。
「バロック時代、鍵盤の1つの音に対して音量を増減させる意識「その音を強く弾こう・弱く弾こうという」はありませんでした。しかし、重厚さを求める部分では楽譜に音がたくさん書かれており、比較的静かな部分では音数も少なくなっていますので、音量に関して楽譜に書かれている以上の何かを付け足す必要はないのです。音の強弱に関して、時代の求める感性が違うと言えるでしょう。
ピアノと異なる機能の1つとして、例えば、このチェンバロには上下二段の鍵盤がありますが、上鍵盤と下鍵盤とでは違う音色の音が出ます。レジスター(音色の選択機構)によって、はじく弦の数を変えることもできます。
1つの鍵盤に対して3 本の弦が張られており、その内の1本は他 2 本より1オクターヴ高い音の出る4フィートの弦です。基本的に鍵盤を押せば1本の弦をはじきますが、上下の鍵盤を連結し、下鍵盤と上鍵盤を同時に鳴らしたり、レジスターを操作することによってはじく弦の数を変えたりすることで、音量を変化させられます。」
クレシェンド(だんだん強く)、ディミヌエンド(だんだん弱く)はできないのか?
「それについても、とてもよく質問されます(笑)。
クレシェンドもディミヌエンドも出来ます!
クレシェンドもディミヌエンドも出来ます!
確かにピアノと比べると強弱の幅は小さいですが、弦をはじくということは、はじかせ方によって響き方を変えられるということでもあります。そもそも私達の聴覚は、音量の大小だけで強弱を判別しているわけではありません。
音色や響きの違いによっても、音の広がりや狭まりを感じることが出来るのです。例えば、音の切り方 (鍵盤から指を離すことで、弦にダンパーがかかり消音するといったチェンバロならではの機構を生かし、その瞬間を調節すること)を工夫し、まるで美しいディミヌエンドのように聴かせることだって可能です。弦をどうはじくのか、そして、その音をどう切り上げるのか。演奏する者にはそういった繊細な意識が必要になります。
そしてそれはとてもやり甲斐のあることですし、そもそもチェンバロは、そうした小さな工夫に豊かに応えてくれる楽器なのです。この魅力を、是非生の音を近くで聴き、皆さんに肌で実感していただきたいです!」
じつは自分は、チェンバロの録音といえば、昔から愛聴している音源があるのだ。
α(アルファ)レーベルによるクープランのチェンバロ曲集。(チェンバロ奏者は、スキップ・センペ)
スキップ・センペは、1958年生まれのチェンバロ奏者。アメリカで音楽と美術史を学んだ後ヨーロッパに渡り、アムステルダムでグスタフ・レオンハルト等に学んだ。彼は古楽アンサンブル「カプリッチョ・ストラヴァガンテ」を1986年に設立、演奏解釈と装飾においてそれまでになかったような自由な表現を実現し、即興的で創造性の高い演奏は高い評価を得ている・・・とある。
α(アルファ)レーベルと言えば、自分はこの音源なのである。
英国グラモフォン大賞で、今年のレーベル・オブ・ザ・イヤー2020を見事に獲得したα(アルファ)レーベル。自分は、それを祝して、このスキップ・センペのチェンバロ曲集、たった1枚で、α(アルファ)レーベルについて熱く語ってみようと思ったが、それにはやはり無理があるので(笑)、やめておいた。
独特のカラーがあって、いいレーベルですよね。
録音もいいです。
自分も大好きなレーベルです。
録音もいいです。
自分も大好きなレーベルです。
このチェンバロ音源は非常に録音がよくて、聴いた瞬間、虜になってしまった。
それ以来、自分の拙宅オーディオオフ会で、お客さんの心を最初の一発で鷲掴みにするための1発目にかける必殺音源となったのだ。
スキップ・センペのチェンバロの録音の音って、かなり個性的である。
普通のチェンバロ録音の音ではない。
普通のチェンバロ録音の音ではない。
ある意味、生演奏で聴くチェンバロの音からは、かなりかけ離れたオーディオライクな音なのだ。確かに衝撃的にいい音。でもそれは自然のチェンバロの音ではない。。。そんな感じなのだ。
いかにもオーディオマニアが喜びそうな音。
チェンバロの音がちょっと電気っぽいんですよね。いかにもエンジニアがいじっている、やり過ぎ感、というような。
もちろんこの音に拒否反応を示す方もいた。
自然ではない、という理由で。
自然ではない、という理由で。
スキップ・センペは、「演奏解釈と装飾においてそれまでになかったような自由な表現を実現した奏者」とあるから、これがまさしく彼らしい音なのだろう。
自分は、この音源に2005年頃に知り合って、以来15年間、チェンバロといえば、必ずこの録音を思い出すくらい愛聴してきたのだ。
それでは曽根麻矢子さんのディスコグラフィーを聴いていくことにしよう。
レーベルはエイベックス・クラシックス。
驚いたのは、リリースしている音源は、ほとんど全部と言っていいほど高音質フォーマットなのだ。バッハの代表曲は、ほとんど全部SACDハイブリッド。そしてBlu-SpecCD、HQCDなどである。
Blu-SpecCDは、CDのピットを読むための光ピックアップをBlu-Rayのものを使うことで高音質を狙ったもの、HQCDは、光ディスクの記録媒体自体の材質改善することで高音質を狙ったフォーマットである。
自分は、この時点で、この高音質指向型の姿勢にものすごい好印象。(笑)
イギリス組曲(English Suites) 2, 3, 6
曽根麻矢子
曽根麻矢子
フランスの名門レーベルERATOの名プロデューサーであるミシェル・ガルサンにスコット・ロスの遺志を継ぐ奏者として認められ、世界デビューを果たした名アルバム「バッハ:イギリス組曲集」。
曽根麻矢子のチェンバロ奏者としての記念すべき世界デビュー盤。ERATOからのリリース。鳴り物入りだったのである。やはり、曽根麻矢子のチェンバロを聴くなら、まずなによりも最初にこれを聴かないと始まらないだろう。基本中の基本というところでしょうか。
これは素晴らしいかったですね。イギリス組曲は、いかにもバッハの曲らしい、なんか均等な打鍵のリズムで、煽られるような疾走感で迫ってくる感じがとても際立つ曲ですね。そのような快感を感じる曲です。
録音も素晴らしいです。
やっぱりこのアルバムは、他のアルバムと比較することのできない特別な立ち位置にあるアルバムですね。もっとも大切なアルバムと言っていいのではないでしょうか?
ゴルトベルク変奏曲
曽根麻矢子 (2008)
ベストセラーを記録したワーナー盤(1998年12月)以来、10年ぶり2度目の「ゴルトベルク変奏曲」の録音。プロデューサー/エンジニアには、ハルモニア・ムンディやアストレで「長岡鉄男外盤A級セレクション」を連発したニコラ・バルトロメ氏を起用。10年前の録音では、フレンチ・モデルを使用したが、この盤は「平均律」で使用した超大型ジャーマン・タイプを使用。
もう長岡鉄男氏の名前が出てくること自体(笑)、オーディオライクというか、高音質指向型でうれしい。
でも自分が聴いた分には、ちょっと音の指向が他盤とかなり違う。なんか奥に引っ込んだ感じの音像で、湿っぽい淑やかな音色である。これはこれでありかな、と思います。ほかとちょっと毛色が違いますね。
ゴルトベルグ変奏曲は、やはりバッハの王道の曲ですね。本当にいい曲です。この曲を聴いたのは、グレングールドのを聴いて以来だから、本当にひさしぶりです。
じつはチェンバロ録音を聴くときに、いつも不思議に思うことがあって、それは1曲の演奏終了後に”ガクン”という暗騒音が入ること。必ず曲終了後にこのノイズが入る。
これは曽根さんだけでなく、スキップ・センペ盤でもそうだし、チェンバロ特有のノイズのようだ。この暗騒音の正体を知りたい。(笑)
自分の予測では、鍵盤から指を離すことで、弦にダンパーがかかる音なんじゃないかな、と思うのだ。正しいかわかりませんが。
暗騒音はいいですね。ピアノのペダル音とか、奏者のブレスとか、生々しくていいです。録音に暗騒音が入ることを嫌う人も多いが、自分は大賛成の派です。
バッハの「平均律クラヴィーア曲集」は、ベートーヴェンの32曲のピアノ・ソナタと並んで「鍵盤楽器奏者の聖書」とも呼ばれている。第1巻の冒頭を飾る優美なプレリュードは、後にフランスの作曲家グノーが編曲した「アヴェ・マリア」のメロディとして世界中で親しまれている。
使用された楽器は、ドレスデンの宮廷音楽家兼楽器製作者だったゴットフリ-ト・グレープナーが生涯最後の1739年に製作した楽器をモデルに、デイヴィッド・レイが製作したもの。パリ音楽院が所有しているが、この録音のために特別に貸し出された。
最初の1発目の出音を聴いた瞬間、自分は、
えっえっえっ?うそ?ほんと?
そのあまりの音の良さにびっくり!
これは録音がいい!!!
これは録音がいい!!!
思わず、慌ててライナーノーツでエンジニアとか確認。
そうしたら、なんと録音エンジニアではないけれど、アーティスティック・ディレクション(Artistic Direction)という肩書で、あのスキップ・センペの名前がクレジットされている!
そう!チェンバロ録音といえば、自分が長い間愛聴してきた、あのα(アルファ)レーベルのチェンバロ音源のチェンバロ奏者である。
自分が、無意識に思わず耳に反応してしまったのは、15年間もの間、彼の独特の音色に深く洗脳されていたためで、そりゃ聴けばすぐに反応する訳です。
アーティスティック・ディレクションというのは、どういうスタンスの立場かわかりませんが、その名称からおそらくこのアルバムの作品の方向性とかを指導する立場なのでは、と推測します。
しかもお互いが映っている写真まで撮影されている!
左からオルガン制作者のデヴィッド・レイ、そしてスキップ・センペ、そして曽根麻矢子。
えええぇぇぇ~。(笑)
苦節15年!!!
自分は、スキップ・センペがこういう容姿の方だとは、いまこの写真を見てはじめて知りました。(笑)
こんな縁があるとは。
曽根麻矢子さんは、欧州でのチェンバロ奏者としてのキャリアを築いていくうえで、最初に才能を見出してくれたスコット・ロスはもちろんのこと、このスキップ・センペといった、テンペラメント豊かな演奏家達の薫陶を受けてきて現在に至るのである。
いやあ驚いた。
しかもそのライナーノーツでは、曽根さんはこう書いている。
この収録が終わった後、録音を聴いてみて驚き、笑ったこと!
「この音色はスキップ!」
まわりの音色と明らかに違うんです。なるほどー、こんなに人によって音色が違うものなんだ。これは自分にとって一番面白いこのCDの聴きどころです。
・・・・・・
そうだろう、そうだろう。彼の音は独特だからね。ちょっと電気っぽい、エンジニアがいじり倒しているような音色。
曽根さんご本人も、これがスキップの音色ってすぐわかるほど、スキップのこの音色ってチェンバロ界では有名なんですね。誰もが知っていることなんですね。
自分は、本当に驚きました。
曽根麻矢子のチェンバロのアルバムをぜひ1枚と推薦するならば、自分はぜひこの「平均律クラヴィーア曲集第1巻全曲」をお勧めします。(笑)
スキップの音色はかなり独特なので、これは生音のチェンバロの音ではない、自然じゃないと拒否反応を示す方もいらっしゃると思うので、改めて、曽根麻矢子のチェンバロのアルバムをチョイスするならばこの1枚というなら、このアルバムを推薦します。
いわゆるベスト盤、イタリア協奏曲、フランス組曲、ゴルトベルグ協奏曲、無伴奏パルティータのシャコンヌとまさにバッハの名曲ぞろい。
そしてスキップの音色の平均律クラヴィーア曲集も入っている。(冒頭です。やはりスキップの音色は一発目の出音がインパクトあるのです。)
やはりこのCDを選ぶのが1番無難だと思います。
本当にいいアルバムです。
フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ集
有田正広、曽根麻矢子
有田正広、曽根麻矢子
最新の新譜ですね。
有田正広氏4回目のバッハのソナタ録音はモダン・フルートによる新境地。
フルートとチェンバロの右手が対等に掛け合うオブリガート・チェンバロ付きのソナタが選ばれ、録音で初共演となる曽根麻矢子との絶妙なアンサンブルが繰り広げられている録音。
ジャケットに用いられた絵画は佐伯祐三(1898-1928)の「絵具箱」(大阪中之島美術館所蔵)。
聴いてみると、対等というよりは、録音というフィルタを通すなら、フルートがあくまで主旋律で主役。録音レベルも高く前へ前へと出てくる。
チェンバロは通奏低音というか伴奏のような感じで、録音レベルも低く、奥に引っ込んだ感じで、陰ながら支えているように聴こえる。
ただそれは録音の仕掛け上そのようにしているというだけであって、旋律的には決してどちらが主役というよりは、ちゃんとお互い対等のかけあいの曲のように感じます。
フルート、美しい!
こんなに癒される音色とは、ひさしぶりに感動です。
フルートとチェンバロはほんとうに相性の合う素晴らしいコンビネーションですね。
いいアルバムです。
いいアルバムです。
ハクジュホールでのバッハ連続演奏会。
チェンバロは、オルガン製作者デヴィッド・レイのカスタムメイド。
チェンバロはオーダーメイドの世界。
チェンバロはオーダーメイドの世界。
平均律クラヴィーアのアルバムでも、デヴィッド・レイのオルガンを弾いていることから、それ以来ずっとよいパートナー関係なのでしょう。
この連続演奏会は、ぜひコンプリートするだけの価値はあると思いますよ。
それだけチェンバロのコンサートはなかなか貴重な体験だと思います。
ライナー・マイヤールさんの逆襲 [ディスク・レビュー]
アナログレコードを発明したのは、エミール・ベルリナーというドイツ・ハノーファー出身のアメリカの研究者。
のちのレコードプレーヤーの原型である、円盤式蓄音機「グラモフォン」を作った。この「グラモフォン」の製造・販売のために「ベルリーナ・グラモフォン」という会社を設立する。
ベルリーナ・グラモフォンは、ビクタートーキングマシンを経てRCAレコードとなり、また、英国支店はグラモフォン・カンパニーを経てEMIへ、さらに、ドイツにおいてはDG(ドイツ・グラモフォン)と、音楽業界に大きな影響を与える企業の源になった。
DG(ドイツ・グラモフォン)はハノーファーに技術センターのエミール・ベルリナー・スタジオ(Emil Berliner Studios)を設立する。その名称は、もちろんレコード発明者のエミール・ベルリナーに由来している。
いわゆるDGの黄金期のレコード、すなわち録音は、すべてこのEmil Berliner Studiosでおこなわれた。そののち、Emil Berliner Studiosは、DGから独立して、ベルリンに拠点を構えて、録音専門会社として現在に至る。
エミール・ベルリナー・スタジオには 2人のエース、トーンマイスターがいて、それが、 ライナー・マイヤール氏とウルリッヒ・ヴィッテ氏。 まさにDGの黄金期の作品は、この2人によって作られてきたといっていい。
ヴィッテ氏は、サウンド的にはギュンター・ヘルマンスの後継者といった存在で、 いかにもDGという王道を行く、密度感があって中間色のグラディエーションが濃厚、 それでいて肌触りの自然なオーケストラ録音をものにしていた。
一方でマイヤール氏は、DGに新しい風をもたらした。 彼の代表作は ブーレーズ指揮ウィーンフィルのマーラー3番やガーディナー指揮のホルスト「惑星」 などで、とても瑞々しく色彩的に鮮やかで かつダイナミックな録音を身上としていた。
あれから数十年、いまはライナー・マイヤールさんの部隊となった。もういまや若手を育成して いかないといけないことから、マイヤールさんはプロデュース業にシフトしている。
ダイレクトカッティングは、いまやEmil Berliner Studiosの代名詞。
ダイレクト・カッティングは、演奏された音が、直接オーディオトラックに入り、アナログレコード(ラッカー盤)の溝に刻まれる最短経路。もちろんあとで編集で修正することは不可能だし、演奏の方もミスは許されない一発勝負。
この方式ってある意味、相当昔の原始的な方式であって、それを時代を遡ってなぜいまの時代にこの方式に挑戦するのか。
自分は、それはいままで説明してきたEmil Berliner Studiosの伝統から、レコードの発明者、オリジネーターとしての立場、そのレコード録音の原点に立ち戻ることに挑戦しているのではないだろうか、と思っていたりする。(自分の予想です。)
そしてそこには、ギリギリの緊張感の中で挑戦する男のロマンみたいなものがあるに違いない。
「コンサートでもない、伝統的なレコーディングでもない、両方の長所を取り込んだセッション。」
数年前に、ノイマンのカッティング・レースは、その多くが破棄された。
残存する少数のマシーンは、いまや何10万ユーロものの価値がある。
残存する少数のマシーンは、いまや何10万ユーロものの価値がある。
Emil Berliner Studiosには、このダイレクトカッティングするカッティングマシンがある。何十キロもするこの大装置を、コンサートホールのコントロールルームに運び込んで、まさに一発勝負のカッティングをする。
このマシンを持っていること自体、大変なことだし、それをダイレクトにラッカー盤に刻み込む作業こそ、まさに伝統的職人のなせる業なのだろう。(日本のキング関口台でも、ダイレクトカッティング用のマシンを導入したのを最近知りました。)
だから、このダイレクトカッティングで制作されたレコードは恐ろしく貴重で値段も高い。しかも販売限定枚数が決まっています。
Emil Berliner StudiosがいままでリリースしてきたダイレクトカットLPは2枚あって、ラトル&ベルリンフィルは8万円!ハイティンク&ベルリンフィルのブルックナー第7番は3万円!である。
ここまでがいままでの背景を説明する序章・プロローグである。
あ~疲れた。(笑)
自分はいままで、ダイレクトカットLPはあまりに値段が高いし、しかも自分はアナログ再生は腰掛程度であまり熱心なマニアではないので、ダイレクトカットLP自体はスルーをしていた。
でも舞夢邸で聴かせてもらった感動、そして第2弾ハイティンク盤が3万円台と手に届く範囲であったので、購入してみることにした。さらに第1弾のラトル盤も中古市場で一気に揃えた。
ハイティンク盤はあまり自分の録音の嗜好に合わなかったが、ラトル盤は素晴らしいと思った。
それ以降、自分はアナログLPのコレクションは全然ないけれど、Emil Berliner StudiosがリリースするダイレクトカットLPだけは、全部コンプリートしていこう、と決意したのである。
ダイレクトカットLPはある意味、普通ではない特殊なレコードですからね。
ラトル盤が素晴らしくて、ハイティンク盤がいまいちだったのは、ラトル盤はワンポイント録音でハイティンク盤はマルチマイク録音だからだと、自分は推測した。
そうしたら、なんとハイティンク盤をリリースしたばかりなのに、即座に第3弾がリリースされるという。
第3弾は、ヤクブ・フルシャ指揮バンベルク交響楽団の演奏によるスメタナ「わが祖国」である、という。ヤクブ・フルシャはチェコ人指揮者で、まさにチェコ音楽、ボヘミア派音楽を自分のトレードマークにしてきた若手指揮者である。
これはまさしく自分を挑発しているよなぁ~。(笑)
偶然な出来事とはいえ、マルチマイク録音のハイティンク盤をよし、としなかった自分へのライナー・マイヤールさんのリベンジ、逆襲と思ってしまったのである。(笑)
世界限定1111枚で自分のは、314枚目。
今回のLPは33回転ではなく、45回転ですね。
45回転の方が音がいいとされていますね。
今回リリースされた記事では、ワンポイント録音なのか、マルチマイク録音なのか、きちんと明記されていなかった。
収録:2019年7月25,26日、ヨーゼフ・カイルベルト・ザール、コンツェルトハレ、バンベルク
録音:
レコーディング・プロデューサー&エンジニア:ライナー・マイヤール
カッティング・エンジニア:シドニー・クレア・メイヤー
マイク:ゼンハイザーMKH800 Twin and MKH30
カッティング・マシン:ノイマンVMS80
カッティング・ヘッド:ノイマンSX74
製造:オプティマル
レコーディング・プロデューサー&エンジニア:ライナー・マイヤール
カッティング・エンジニア:シドニー・クレア・メイヤー
マイク:ゼンハイザーMKH800 Twin and MKH30
カッティング・マシン:ノイマンVMS80
カッティング・ヘッド:ノイマンSX74
製造:オプティマル
でもマイクが2種類明記されていることから、メイン用とアンビエンス用の2種類という意味なのだろう、と思った。どちらもゼンハイザーである。
演奏は、2019年に、バンベルクのヨーゼフ・カイルベルト・ザールというホールで録音された。
この写真をみると、メインのステレオペアのマイクの他に、左右にモノラルの補助マイクがあるように見える。普通のマルチマイクのセッション録音は、もっと楽団員の隙間にスポットマイクが林立している感じなのだけれど、ダイレクトカッティングは編集できないから、スポットマイクを多用できない訳で、最小限、前方中央と前方左右にとどめたのかもしれない。
自分が実際レコードを聴いてみると、これは完璧なマルチマイク録音だな、と判断したのだが、それは打楽器群など、オーケストラの遠方席にいる楽器群の音が、かなり近くで録っている、拾っているような迫力感、明晰さがあって、また各セクションの音の録音レベルも大きくて、全体的にみんな近いところで録っているように聴こえたからである。
全体として遠近感をあまり感じなかったです。
ワンポイントで録っていると、いわゆる指揮者のすぐ背面の高いところから録っている聴こえ方で遠いポジションの楽器ほど遠く聴こえて、全体的に遠近感のある聴こえ方がします。
いわゆるワンポイントの聴こえ方をする、という感じですね。
各セクションともかなり解像感があって明晰性があって、そういう迫ってくるような迫力を感じたので、これは完全にマルチマイクだな、と思ったのですが、その後にこの日記を書くために、この写真を見つけて、スポットマイクがほとんど見当たらないのに愕然としました。(笑)
ちょっと謎です。
録音は総評として、かなり素晴らしかったです。
まず、これがマルチマイク録音なら、位相合わせの難しさなどで、音場感が潰れてしまっているのではないかと心配をしましたが、まったくそういうことがなく、かなり完璧な録音といっていい。
まずなにより録音レベルが高いですね。
自分に迫ってくるような聴こえ方がしますね。
自分に迫ってくるような聴こえ方がしますね。
サウンドに迫力があって、部屋中にふわっと広がっていくような自然な音場感、自分は当初マルチマイクだと思っていたので、それにしてはあまりに自然でシームレスな広大な音場感なので、さすがマイヤールさん、と驚きました。
そして各セクションが均等に明晰でマイクに近い聴こえ方がするので、自分が理想としている広大な音場、明晰な音像を両立させているのでは、としこたま驚きましたです。
この両方を両立させることは、大変難しいことなのです。
録音がいいかどうかって、最初に針を落としたときに奏でられる出音でわかってしまうものなんですね。その後、いくらずっと聴いていても印象が途中で変わることはほぼないです。
緊張しながら、最初の出音を聴いたとき、ハープのボロロンという音が、なんとも潤いのある響きで空間を漂う雰囲気がなんとも堪らなかった。
凄い空間感を感じた瞬間。
ハープって低域から高域まで、すごい音域の幅が広い楽器なので、これを万遍なく拾ってあの雰囲気を出すのって録音ではすごい難しいことなので、それが完璧だったので驚きました。
そして、あとオーケストラがトゥッティに入ったときのあの迫力感、音場感が完璧。
これはオーケストラとしては完璧な録音。
オーケストラ録音で大切なことは、あのホールに鳴り響く音場をいかにすっぽり丸っと取り込むか、ということですから。
ダイナミックレンジがしっかり取れた、そういう器が大きくないと、こういう風には録れないですね。
自分としては、かなり満足できた録音といっていいと思いました。
素晴らしかった。
もし、ハイティンク盤に続き、第3弾でも自分の意に添わなかったから、黙っていよう、沈黙していようと思っていましたから。ダイレクトカッティングっていかに難しいものなのか、ライナー・マイヤール、Emil Berliner Studiosの俊英部隊を以てしても難しいものなのだ、と自分を納得させようと思っていましたから。
いまこうやってお世辞をいっさい使わず、堂々と称賛の日記をかける幸せ。
同時に、ライナー・マイヤールさん部隊の職人技、高いスキル。
プロとしての意地をしっかり受け止めました。
プロとしての意地をしっかり受け止めました。
もうさすが!としかいいようがない。
どうしてこういういい録音がダイレクトカッティングで実現できたのかは、もちろん厳密に導き出せるわけもありません。それは、職人、プロの世界ですね。
Emil Berliner Studiosは、オランダのポリヒムニアと並んで、自分の最も尊敬する録音仕事人である、という認識をさらに強くしたと言っていいと思います。
(あ~かなりホッとした。(笑)第3弾リリースの報を聴いたときから、ずっと心配、悩みの種でしたので。)
黒沼ユリ子さんの音源を聴く [ディスク・レビュー]
いよいよ音源の方を聴いていこう。
普通の物販CDサイトを見ても、黒沼ユリ子さんのCDはほとんど売っていないのだ。レコーディング活動も活発におこなっていたと思うのだが、おそらく大半が廃盤となっていてあまり録音という形では現在に残っていない。
いや活躍した時代から、当然アナログLPが主流だろうということで、中古市場を探ってみると結構存在した。すかさずこの3枚をゲットした。
黒沼ユリ子さんの所属レーベルは、ビクターエンターテイメントとCBSソニーである。
まずCDのほうから堪能したい。
Czech Violin Works-martinu, Janacek, Smetana:
黒沼ユリ子(Vn)Panenka(P)
黒沼ユリ子(Vn)Panenka(P)
”チェコ・ヴァイオリン音楽選”というタイトルのこのCDは、チェコの作曲家マルティヌー、ヤナーチェク、そしてスメタナというところのヴァイオリン・ソナタを集めた作品。
パートナーのピアノは、ヤン・パネンカ。
ヤン・パネンカは、黒沼ユリ子さんがヴァイオリン・ソナタをやるときの永遠のパートナーである。プラハ生まれ、チェコのピアニスト。プラハ音楽院でフランティシェク・マクシアーンに師事、ついでレニングラード音楽院でパーヴェル・セレブリャーコフに師事。1999年7月12日没。
この録音は、1971年7月5日~8日というたった3日間でレコーディングされたもので、プラハのドモヴィナ・スタジオで収録されている。
おそらく黒沼さんがメキシコに移住した後に、プラハをたびたび訪れ、演奏会、録音をしているので、この録音もその一環のものなのであろう。
このCDの中で、黒沼さんは、”チェコ人と音楽と私”というタイトルで寄稿をされている。まさにチェコへの熱い気持ちが書かれており、それを全文ぜひ紹介してみたい。
●チェコ人と音楽と私 黒沼ユリ子
1958年の晩秋、私は生まれて初めてプラハに降り立ちました。それまで全く未知の国での未知の街、未知の人々の暮らすところへ。でもそこには私を結びつけたただ一つの理由がありました。
それが「音楽」だったのです。
ドヴォルジャークという人がチェコ人であることを知り、その人のヴァイオリンとチェロの協奏曲や「スラブ舞曲集」などを聴くにつけ、それらが何と人間的なぬくもりと同時に人生の悲しみも濃い、また歓びに満ちて踊るリズムに溢れているかに感動していたからです。
一体チェコという国はどんな国でプラハはどんな街で、そこにはどんな人々が、どんな風に暮らしているか・・・全く謎の中に入っていく感じでした。
チェコに行ってみて、そこに暮らしてみて、人々と交わり、彼らの自然の風景の中に身を置き、過去から現代までの歴史を知ってみて、今初めて「チェコ人にとっての音楽」とも呼べる「何か」が分かってきたような気がしています。
中央ヨーロッパの小さな民族であるチェコ人たちは、独立国の「ボヘミア王国」として中世から近世にかけて発展していました。すでに1348年にはプラハには、「カレル大学」が開設されていたり、優れた学問や文化の中心的存在でもあったのですが、その大学長で哲学者の僧侶ヤン・フスが、腐敗したローマ・カトリックを批判して宗教改革運動を起こしたにも関わらず、「和解協定を結ぶため」と約束されて出向いたスイスでの公聴会で捕らえられ、1415年には火刑に処されました。
そこから所謂フス戦争が15年も続いたり・・・この歴史的ルーツは、今日の全チェコ人の中にあるのです。ドヴォルジャークの先輩にあたるスメタナは、交響詩「わが祖国」に、「リブシェ」という建国の神話的歴史から、「フス戦争」を描くターボルなどチェコ民族の複雑で苦悩に満ちた歴史を、見事に音楽で描き残しています。もしその理由をひと口で表現することを試みるなら、大国に自らの国の運命を翻弄され続けたチェコ人たちが、いかにして自己を見失わず今日まで生き抜いて来れたかの、最大のエネルギーの源泉が「音楽」にあり、「文学ではなく音楽」で証明したかったから、と言えるのではないかと、私は思うのです。
それは「昨日のこと」とも言える20世紀においても「然り」なのです。第二次世界大戦終了後すぐの1946年に、いちはやく「国際音楽祭・プラハの春」をスタートさせ、東西の冷戦の中にあっても両側からの音楽家たちがプラハに集まって「音楽」を演奏しながら出会うチャンスを作ったり、政治的にはまだ言論の自由が縛られていた1950年代にもコンサート・ライブは盛んで、人口100万のプラハにある3つのオペラ劇場も4つのコンサートホールも常に音楽を求める聴衆で溢れていました。
チェコ人にとって「音楽のない生活など想像もつかない」と言うことを、態度で示されているのを眼前に見るようだったのです。ニーチェも「音楽もない人生、それは間違った人生だ」と言っています。
1958年11月から62年の春までのプラハでの留学生生活と、その後の30年ほどの間、ほぼ2~3年おきには演奏旅行に招かれたり、レコード録音のために滞在してきたチェコという国は、その後の私の人生にとっての「第二の祖国」であり、「音楽」が自然に泉からあふれ出る土地なのです。
スメタナやドヴォルジャークのみならず、ヤナーチェクやマルティヌーの音楽を聴いたり、彼らの作品を弾いたりしているときの自分の精神状態が、なぜか一番落ち着き、自然で、幸せな気持ちになるからです。それは「音楽」という食べ物にも似た「何か」によって精神に栄養がゆきわたり、非日常的な時間の中に身をゆだねることによって、宇宙をさまようことも可能にしながら、と同時に、自分を小さな昆虫ででもあるかのように客観視できたり、水の流れのような平衡感覚を取り戻すことも出来たりする「音楽の不思議な力」を、チェコ人たちがいかに大切にしながら彼らの長い歴史を歩んできたかを学ばせてくれたからかもしれません。
スメタナは「チェコ人の生命は音楽にあり」と言い残しました。
ドヴォルジャークは「自分は一介の平凡で真面目なチェコ人です」と言いながら、あのような「自然に心から生まれたような音楽」を残し、チェコ人の団結を音楽で強め、新しい国を作る手助けまでもしていました。
「小さい国でもいい。文化的レベルが高ければ・・・」というチェコ人の精神は音楽によって支えられ、「音楽があるから」なのでしょうねぇ。何しろ国歌が19世紀のチェコの作曲家シュクロウブのオペラのアリアの一節「我が故郷よ、いずこに」なのですから・・・。
熱い熱筆ですね。いままで何回にも分けて日記で語ってきたことが、じつはこのCDのライナーノーツに全部書いてあるのでは?という感じですね。(笑)
では、このCDを聴いてみます。
1971年度録音とは思えないくらいS/Nがよくてクリアな録音。
まずそこに驚きました。
まずそこに驚きました。
でもいまの現代録音の趣とはちょっと違う感じがしますね。
いまは、全体の音場を捉える空間をまず録って、そこから各楽器にスポットマイクで各声部をはっきり捉えるという手法で、(それはオーケストラでも室内楽でも、です。)実際オーディオで聴いてみるとまず全体の空間感を感じて、その中で鳴っているという立体的な聴こえ方をしますが、この1971年当時はそこまで空間を意識せず、ふつうのオンマイクの録音のように感じます。
それはホール録音ではなく、スタジオ録音というのもあるかもしれませんね。
そこが違うかな、というくらいで、あとは全然ふつうにすんなりと自分の中に受け入れることができます。でもそれって意識的な聴き方をしているだけで、ふつうに聴いている分には全然わからない程度のこと。
いまの録音とまったく違わないといってもいいと思います。
本当に素晴らしい録音だと思います。
本当に素晴らしい録音だと思います。
クリアな感じ、鮮度感、そして明晰な質感など、全体に音の輪郭がキリっとしていて、メリハリの効いたとてもいい録音ですね。感動します。
艶感のあるヴァイオリンの音色、硬質で響きが豊かなピアノの音色。
ヴァイオリンとピアノとのバランス。
ヴァイオリンとピアノとのバランス。
本当にいい感じ・・・。
後述するアナログLPは、やはり年代物の中古LPだけあって、入手困難であること、またスクラッチノイズもそれなりにあるので、黒沼ユリ子の演奏をいい状態で聴きたいなら、このCDしかないと思います。
黒沼ユリ子さんの録音を聴くなら、この1枚でしょう!
なにせ、黒沼音楽人生の大本命のチェコ音楽、チェコの作曲家、マルティヌー、ヤナーチェク、スメタナですから。
マルティヌー、ヤナーチェク、スメタナのヴァイオリン・ソナタ。
おそらくいままでもあまり聴いていない作品だと思う。
おそらくいままでもあまり聴いていない作品だと思う。
チェコ音楽って自分の場合スメタナかドヴォルジャークでしたから。マルティヌーは数年前にPENTATONEの新譜で児玉麻里・児玉桃姉妹の録音で接したぐらいです。
マルティヌーはいいですね。バッチリ自分の好みだと思いました。
このCD全曲通して思ったのは、渋い旋律だということ。東欧の民族色的な音色といえばそれまでだけれど、どこか実験的書風というか、捉えどころのない、形式の枠にとらわれない自由な書風といえるのではないでしょうか?
クラシック古典派の正統派というより、もっと新世代寄りの現代音楽をもっと聴きやすくした感じのように思いました。
最後のスメタナが一番お気に入りになりました。
スメタナは、チェコ民族の自民族意識(ナショナリズム)の高揚のために、もっぱらチェコの民話や伝説、史実などをテーマに作品を書き続けたと言われ、いわゆるそういう心情を煽るような情熱的な旋律が得意とするところですね。聴いていてそういう情緒的だけどどこか哀愁を感じるようなメロディの美しさを感じます。
あとで紹介するフォーレのヴァイオリン・ソナタを録音しているアナログLPのライナーノーツに林光氏の解説文が記載されているのですが、その中に、
黒沼ユリ子のレコードでは、チェコの音楽が一番多いのであるが、その中でも、この永遠のパートナー、パネンカとのコンビで演奏しているヤナーチェクの「ソナタ」は、私がとくに高く評価したいと思っているものだ。と同時に、この演奏には、黒沼の音楽の本質といっていい特徴がよくあらわれている。
なになに?
この解説文を偶然読んで、慌ててもう一回このCDに戻ってそのヤナーチェクのソナタを聴き返しました。
あやうくそのままスルーするところでした。(笑)
堂々の大曲ですね。森林の中の大樹。そんな感じの本当に大きな器の曲。ヤナーチェクの世界をもう少し理解しないとその極みを理解できないような気がします。独特の世界がありますね。ヤナーチェクの世界を強く意識しないと自分に響いてこない曲だと思います。何回も何回も聴き込むことが必要ですね。
じつに素晴らしい作品群でした。
お薦めの特選盤です。
つぎに中古市場で購入したLPの数々。
、
これも盟友ヤン・パネンカとのヴァイオリン・ソナタ
ラヴェルのヴァイオリン・ソナタ
マルティヌーの間奏曲
プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ長調 作品94
マルティヌーの間奏曲
プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ長調 作品94
やっぱりアナログLPはいいですねぇ。
こんな感じでライナーノーツが広い誌面で充実していますね。
とても正統派の解説文です。
黒沼ユリ子のヴァイオリンはボヘミア派の伝統の忠実な継承者である、と断言していますね。
アナログLPの中ではこれが1番好きですね。
ラヴェルのヴァイオリン・ソナタはあまり聞いたことがないですが、ラヴェルの中で唯一の1曲だけの作品のようですね。
当時のジャズ・ブルースの語法が取り入れられていて、当時のパリの楽壇に一種のジャズ・ブームが巻き起こっていたことを物語っているようです。
黒沼さんの超絶技巧が冴えわたっていて、リズミカルでスピーディーな曲の展開に圧倒されます。
三善晃・ヴァイオリン協奏曲
諸井誠・ヴァイオリンとオーケストラのための協奏組曲
諸井誠・ヴァイオリンとオーケストラのための協奏組曲
黒沼ユリ子:ヴァイオリン
若杉弘・指揮
管弦楽:読売日本交響楽団
若杉弘・指揮
管弦楽:読売日本交響楽団
三善晃、諸井誠という日本の作曲家は、知りませんでした。
おもに現代音楽の作曲家なのでしょうね。
おもに現代音楽の作曲家なのでしょうね。
若杉弘さんも懐かしすぎですね。
やはり現代音楽はオーディオ的に音がよく感じます。
漆黒の中の鋭音という感じで、鳥肌が立つ作品です。
漆黒の中の鋭音という感じで、鳥肌が立つ作品です。
黒沼さんは、こういうジャンルの音楽も積極的にチャレンジしていたんですね。
フォーレ
ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調作品13
ヴァイオリン・ソナタ第2番ホ短調作品108
黒沼ユリ子:ヴァイオリン
ヤン・パネンカ:ピアノ
ヤン・パネンカ:ピアノ
1975年10月20,21,24日の3日間、チェコのスプラフォン・スタジオにて録音されたものです。
フォーレいいですねー!!!
この作曲家のソナタも普段あまり聴かないし、日本のプロモーターもあまりコンサートで採用しない作曲家ですよね。フォーレのソナタがこんなに素敵なんて目からウロコでした。
フォーレは、フランスの作曲家で、むしろ小規模編成の楽曲を好み、室内楽作品に名作が多いとされている。それぞれ2曲ずつのピアノ五重奏曲、ピアノ四重奏曲、ヴァイオリン・ソナタ、チェロ・ソナタと、各1曲のピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲がある。
ラヴェルやドビュッシーのようなフランス音楽特有の浮遊感、色彩感豊かな感じでもなく、結構メリハリの効いた感じの作風です。でもとても美しい、万人に受けやすい不偏のメロディーですね。
このヴァイオリン・ソナタを聴いて、すっかりフォーレの大ファンになってしまいました。
以上、黒沼ユリ子の音源を聴いてきましたが、ヴァイオリニストとしての奏法も現代のヴァイオリニストとまったく遜色なく、堂々とたるもので目の前で演奏している姿が目に浮かぶようでした。
”チェコ音楽を奏でるヴァイオリニスト”というのは、やはりとてもユニークな個性が際立っていて、それがひとつのヴァイオリン奏者としての個性的なカラーになっていますね。
チェコやチェコ音楽ってかなり個性的なのではないでしょうか?
それはその国の歴史諸共、ひとつのワンセットになっていて、とてもコンパクトながらも独特のカラーがあって、とてもユニークですね。
自分はすごく魅力的だと思います。
素晴らしい音源でした。
PENTATONEの新譜:アラベラ・美歩・シュタインバッハーの奏者人生としての転機 [ディスク・レビュー]
いったいいつまで続くのか、コロナ禍でちょっとした鬱スランプであったのと、最近は1日中仕事のことで頭がいっぱいで、プライベート活動、SNSどころではなかった。普段の楽しい自分の生活スタイルを崩しつつあった。
アラベラさんの新譜も6月中旬にはすでに入手していて、すでに聴き込んでいたのだが、なかなか筆が進まなかった。ようやく気分一新。取り組みたいと思う。
ヴィヴァルディ:四季、ピアソラ:ブエノスアイレスの四季
アラベラ・美歩・シュタインバッハー、ミュンヘン室内管弦楽団
アラベラ・美歩・シュタインバッハー、ミュンヘン室内管弦楽団
今回の新譜は、とても有名なヴィヴェルディの四季と、ピアソラのブエノスアイレスの四季をカップリングしたアルバム。ヴィヴァルディとピアソラの曲を交互に演奏していくという試みである。
ヴィヴァルディの四季:春・夏・秋・冬は本当に有名な曲で、クラシック初級編ともいえる敷居の高さを感じないみんなから好かれている曲ではないだろうか?一方で、ピアソラのブエノスアイレスの四季は、これも有名な曲ではあるが、ポピュリズムというより、もうちょっとクセのある特定ジャンルに族するような特殊性があって、玄人好みでとても熱くなる曲である。
自分は、とくにタンゴ、ピアソラの世界が大好き。
とにかく情熱的で、あの南米の赤くて熱いパッションが弾けるような旋律は、聴いていて血が騒ぎますね。自分は、このタンゴ、そしてさらにその発展形のピアソラのアルゼンチンものの音楽が大好きで、南米アルゼンチン独特の民族色の強い旋律が非常に自分に嵌るというか、聴いていてツボにくる、自然と体でリズムをとってしまう心地よさを感じてしまう。
ムード音楽的演奏から、マランドのように歯切れの良いリズムを重視したアルゼンチンスタイルなど様々なスタイルがあるのだが、共通するのは、やはり夕暮れどきが似合って、激しいリズムの後にくるゆったりとしたメロウな旋律が漂うようなムードがとてつもなく堪らない。。。なんて感じである。(笑)
特に自分はピアソラが好き。アルゼンチンタンゴの世界に、クラシック(バッハのバロックも!)やジャズなどの音楽を融合させたアストル・ピアソラという人によって創作されたジャンルの音楽なのだが、タンゴ特有の強いビートの上にセンチメンタルなメロディを自由に展開させるという独自の音楽形態を作り出して、単に踊るためのタンゴの世界から一皮もふたかわもむけた素晴らしい音楽の世界を作り出した人だ。
ピアソラの音楽は、リベルタンゴやブエノスアイレスの四季など、絶対みなさんなら聴いたことがあるはず、というくらいの超有名曲ぞろい。
ピアソラのブエノスアイレスの四季といえば、自分はオランダのアムステルダム・シンフォニエッタのChannel Classicsのアルバムが愛聴盤。以前ディスク・レビューで紹介したことあります。
ピアソラ:ブエノスアイレスの四季、
ゴリホフ:ラスト・ラウンド、ヒナステラ:弦楽オーケストラのための協奏曲
アムステルダム・シンフォニエッタ
ゴリホフ:ラスト・ラウンド、ヒナステラ:弦楽オーケストラのための協奏曲
アムステルダム・シンフォニエッタ
ぜひ聴いてみてください。
この曲の自分のリファレンスとなっているアルバムです。
この曲の自分のリファレンスとなっているアルバムです。
もしマーラーフェスト2020が開催中止になっていなければ、アムステルダム・コンセルトヘボウのリサイタル・ホールで、このフェスティバルで、マーラー所縁の曲でアムステルダム・シンフォニエッタを初体験できる予定だったのに、返す返す残念で堪りません。こちらから海外に出向かないと、縁のないアーティストですね。
今回のアラベラさんの新譜は、ヴィヴァルディの四季とピアソラのブエノスアイレスの四季を交互に、春・夏・秋・冬の順番で交互に並べているのだ。
南半球の四季、ブエノスアイレスの四季は、夏から始まる。
ピアソラが作曲していった順番も夏→秋→冬→春だ。そういう意味で、合うのかな、とも思うのだが、これが全然違和感なく、アルバムとしての統一感があって、曲の並びがすごく自然だ。
ヴィヴァルディは各季節に3楽章づつあるが、ピアソラのブエノスアイレスの四季は各季節に1楽章の構成だ。やっぱりヴィヴァルディの四季は名曲中の名曲だけあって、音楽が整っているというか、全体として、形式感、様式美があって、日本のように四季がはっきりと違う美しさを表現していますね。
優美に輝く「春」、うだるような暑さと天候の変化を見事に表現した「夏」、収穫を祝う「秋」、凍てつく「冬」。本当にこんな感じで各季節に個性があってメリハリがあって、曲として形式感が整っている。名曲中の名曲だと思う。
ブエノスアイレスの四季は、これは本当に情熱的でエモーショナル、官能的で陰影のあるグルーヴ感に酔いしれる。カラーで言えば、情熱の赤だ。もう自分には堪らない。この曲は本当に自分にはクルものがある。
ブエノスアイレスの四季は、もともとバンドネオン、ヴァイオリン、ギター、ピアノ、コントラバスという編成による作品なのだが、この録音ではペーター・フォン・ヴィーンハルト編曲によるヴァイオリンと室内オーケストラ版で収録されている。
特に夏や秋ではおそらく原曲はバンドネオンが表現していると思われるグリッサンドなところも、ヴァイオリンではスライド奏法させて弾いているような感じで、もう鳥肌モノである。
秋では重音奏法のオンパレードと言う感じで、アラベラさんの超絶技巧が冴えわたる。
このアルバムでは、従来にも増して、アラベラさんの技術力の高さ、安定力を再認識する感じだ。もうヴァイオリニストのキャリアとしても中堅どころ。超一流の技術力を兼ね備えた実力派ヴァイオリニストと堂々と宣言してもいいだろう。
そしてなんといっても、自分にとってブエノスアイレスの四季といえば、冬。自分はこの曲ではこの季節が1番好きだ。次から次へとたたみ掛けてくるような熱いパッションを感じる旋律で、とにかくかっーと激しく燃える。
最高である。
ヴィヴァルディは、冒頭の春の第1楽章が有名だが、自分は夏や冬が好き。やはり激しくて燃えるのがいいのだ。やっぱり自分は熱いのが好きなのだろう。(笑)
今回のパートナーはミュンヘン室内管弦楽団。
ドイツ・ミュンヘンを本拠地とする室内オーケストラである。
アラベラさんとは縁が多いオケで、演奏を聴くと、そのアンサンブル能力の高さ、弦の厚み、弦楽としての発音能力などとてもすばらしいオーケストラだと毎度のことながら思う。
2018年7月に、ミュンヘン=ゼンドリンク、昇天教会で録音された。
録音は、エンジニア&バランスにジャン=マリー・ヘーセン氏、編集、ミキシングにエルド・グロード氏といういつもの安定の最強タッグ。
いつもにましてオーディオ的に作り上げた感のあるテイストで、いつもの彼女のアルバムとはちょっと違う録音テイストである。よりオーディオマニア好みに仕上がっている。
いままでとちょっとプロモーションが違うのは、アルバムの発売に伴い、先行でストリーミングによるシングルリリースを先駆けたことだった。彼女の妊娠で、アルバムが当初よりも1年延期になったのだが、ストリーミング・シングルという新しいプロモーションが実現したのも、曲の録音がすでに完成している過程でのひとつの試みなのだろう。
2019年9月20日にピアソラ ブエノスアイレスの四季”秋”
2020年1月25日にヴィヴァルディ四季の”冬”
2020年1月25日にヴィヴァルディ四季の”冬”
すべてのストリーミング・プラットフォームで配信された。
今回、アラベラさんはライナーノーツで、こんなことを書いている。
ヴィヴァルディの四季は、クラシック音楽の歴史の中でももっとも有名な作品のひとつだと思います。おそらくその中の一部の楽章は、誰もが知っていることでしょう。正直なところを申しますと、この曲を録音した作品は、世の中にはもう数えきれないくらい存在すると思いますので、この作品を取り上げることは少々躊躇したところがありました。でも、それは別に気にすることではない。私にとっては最初のレコーディングなのだ、と思うことにしました。
特に完全にタイプの異なるピアソラの四季とのコンビネーションは、ピアソラの作品の中でも特にこの曲を長いこと愛してきて、とてもメランコリックで熱情のあるこの曲とカップリングすることが私の夢だったのです。
私の親愛なる友人、ペーター・フォン・ヴィーンハルトによって美しくアレンジされ、それをもってみなさんとこの情熱的な旅をシェアできることをとても幸せに思います。
アラベラ・美歩・シュタインバッハー
自分も正直、アラベラさんの次のアルバムはなんであろう?と期待していたとき、それがヴィヴァルディ四季と知ったときは、ちょっとがっかり(笑)というか、う~ん、ありふれているな、と思ったことは確かである。
やはりアラベラさんもそう感じていたんだね。
でもピアソラの四季とのコンビネーションが一気にアルバムに多様性を生んだ。
ピアソラのエモーショナルな曲がアラベラさんも大好きだったことはとてもうれしい。
ピアソラのエモーショナルな曲がアラベラさんも大好きだったことはとてもうれしい。
でも自分はこの新譜で、改めて、ヴィヴァルディ四季の曲として完成度の高さ、美しさを再度認識した次第である。
アラベラさんの演奏家人生として、今はひとつの岐路、転機にあるように思える。
2004年デビューで着実にキャリアを重ねていった。自分は、2011年頃から応援を始めたファンとしては遅いほうだったが、自分が応援を始めたときからいわゆる演奏家としての絶頂のときだったのではないか、と感じている。
それこそ、ピークは2015年のヘンゲルブロック&NDRとの日本縦断ツアーで、大阪、東京、名古屋を追っかけしたこと、そして2019年に至るまで彼女は全世界のコンサートホール&全世界のオーケストラと共演を重ね、忙しくワールドツアーを転々としていたのだ。
まさに演奏家人生としてはピーク、頂点と言っていいと思う。
演奏家人生のひとつの転機となったのは、やはり結婚。そして子供を授かったこと。
SNSに投稿する写真は、上のようにいままでと違って一変した。(笑)
SNSに投稿する写真は、上のようにいままでと違って一変した。(笑)
子供を持つことになった女性アーティストは、いままでの尖った格好良さ、ビジュアルな方向性から、より母性本能が表面に出てくる柔和で優しい人間性が滲み出るようになって、アーティストとして、より、もっと人間性として深いところに達観するのではないか、と思う。
いままでの路線とは違ってくるように思えます。
そして誰もが体験している、まさかのコロナ禍。
アフターコロナの時代、クラシックのオーケストラやアーティストはみんな手探り状態で今後どうやって活動を続けていくべきか、を暗中模索している。
これは彼女にもあてはまるだろう。育児と重なる時期と言うこともあるが、間違いなくいままで通りと簡単には事は運ばないような気がする。
これは彼女だけではない。
みんな苦労している。
その洗礼を彼女も受けるに違いない。
みんな苦労している。
その洗礼を彼女も受けるに違いない。
願わくは、彼女には(もちろんみんなにもですが。)幸せが待っていてほしい。
あのNDRと日本縦断ツアーをしていた頃のようにまた復活して輝いてほしいと思う次第なのです。
ダイレクトカッティングはワンポイント録音がいい [ディスク・レビュー]
ベルリンフィルのダイレクトカットLPを購入した。ラトルのブラームス交響曲全集のときは、悩んだのだけれど定価が8万円台だし、自分はアナログは腰掛け程度でメインストリームではないので、見送った。
今回、第2弾のハイティンクのブルックナー交響曲第7番が出ることになり、それが3万円台なので、価格的にも範疇内なので、つい誘惑に負けて購入してしまった。
そうすると、どうしても第1弾のラトル盤も揃えたくなる。
買っておけばよかったなーと後悔だ。
買っておけばよかったなーと後悔だ。
いまラトルのダイレクトカットLPはなんと中古市場で25万から30万で取引されているという大変なプレミア盤なのだ。そんなとき、舞夢さんが、こっそりラトル盤、ヤフオクに出てます、と教えてくれた。11万5千円だ。おう!これはターゲット内。でも終了時間間際で跳ね上がるのだろうな、と思い、15万までなら出そう!という覚悟を決めた。
そしていざ勝負。なんと誰も入札せず、自分だけが入札してあっさり11万5千円で落札できた。
ラッキー!である。しかも新品未開封なのだ。舞夢さん、ありがとう!
こうなるとラトル盤、ハイティンク盤と完遂することができた。
届いてじっくり聴き込もうと思ったが、なにせアナログ再生は、最近すっかりご無沙汰である。日記を紐解けば、2016年にアナログプレイヤーを購入して再生して以来だから、じつに4年ぶりだ。
学生時代にコレクションした100枚のLPを再生したい、ということ、そして昨今のアナログブームから、やはりプレイヤー持っていないとダメだろう、という想いから購入したのだ。
でも腰掛け程度だから、高級なターンテーブルを購入するつもりもなく、ソニーのPS-HX500というアナログ出力をPCにDSD5.6MHzで取り込めるという付加機能が売りの安いプレイヤーを購入した。カジュアル向けのプレイヤーですね。
アナログが本筋ではない自分にはこの程度で十分である。でもそれ以来、すっかり死蔵扱いで、埃をかぶり、その上にCDが山積みされている状態であった。
4年ぶりに動かすし、きちんと音が鳴るのかな、とも思い、恐る恐る鳴らしてみた。
この日のためにインターコネクトのケーブルも新調した。
この日のためにインターコネクトのケーブルも新調した。
アルゲリッチ盤とグリモー盤で鳴らしてみた。
案の定、聴くに堪えない酷い音。
こりゃあかん!ということで、調整開始。
久しぶりアナログ触るから、もう試行錯誤。
こりゃあかん!ということで、調整開始。
久しぶりアナログ触るから、もう試行錯誤。
ハム音が鳴ったりで、かなりケアレスミスも多く、あーだ、こーだとやること3時間半。
ようやく4年前に聴いていた感じのサウンドに戻ってきた。
久しぶりにオーディオやったという感じ。(笑)
ようやく4年前に聴いていた感じのサウンドに戻ってきた。
久しぶりにオーディオやったという感じ。(笑)
ラトルのダイレクトカットLPは、舞夢邸で聴かせてもらったことから、舞夢さんにメッセージして、いろいろアナログのことを教えてもらった。
気になるのはアナログ再生時のゲインが低く、CD再生時より15dBも低い。
舞夢さんのアドヴァイスは、「確かにディスクによっては録音レベルが低いものはありますが、この盤の録音レベルは特に低いわけではないようです。(拙宅の場合はCDと大差ない音量差です)考えられるのは、カートリッジの種類(MM、MC)とのマッチングです。AMPのPhonoイコライザーは、RIAAカーブで周波数特性を元に戻すと共に、レベルを昇圧しますが、これはMMカートリッジの再生レベルまでです。通常、MCカートリッジはMMカートリッジよりも出力が低いために、MCヘッドアンプもしくはMC用の昇圧トランスを使用して出力レベルを補正します。
アンプ側でMC、MMの切り替えはできるようになっておりませんでしょうか。少なくともAVアンプにPhonoポジションがあるので、イコライザーアンプは入っていると思われますが…。ちなみに拙宅のアンプではポジション切り替えがあり、MCカートリッジをMMポジションで聴くと仰るようにかなりゲインが低く、それに伴ってS/Nも大幅に劣化します。でも、もし、カートリッジがMMでこの症状だとしたら、どちらかの機材に不具合がある可能性がありますね。
あと、もうひとつ、カートリッジシェルはアームから外せますよね?期待薄ですが、ここの接点を布で(できればアーム側も綿棒で)磨いてみてください。」
ソニーのプレイヤーは、MMカートリッジ。MMのフォノイコライザー内蔵のようだ。
だからゲイン不足というのは機器の不具合なのか?(笑)
まぁとりあえずこのままAMPのVOL上げてそのまま続行。
だからゲイン不足というのは機器の不具合なのか?(笑)
まぁとりあえずこのままAMPのVOL上げてそのまま続行。
カジュアル向けのプレイヤーなので、固定アームでカートリッジ交換不可能とずっと思っていたけれど、そうではないようだ。
ゼロバランス、針圧3gも再調整。なんとインサイドフォースキャンセラーも調整できるのだ。(笑)
いろいろ調整したけれど、オーディオオフ会でオーディオの友人宅で聴くような、あのアナログ特有の太くて濃い濃厚な音ってやっぱり無理なんだな。
アナログLPはダイナミックレンジ(Dレンジ)は狭いけれど、CDのように音域をカットしたりしていないから周波数レンジ(Fレンジ)は広くて、かなり濃い音が楽しめるはずなのだが、う~む、厳しい・・・。
やっぱりカートリッジの差が大きいかな。5万円のプレイヤーだからこんなもんかな、と妥協。
久しぶりにアナログ聴くから、グリモーさん&バイエルン響のブラームス、なんと途中で針飛びしてしまい、前へ進まない。えっ4年前に数回聴いただけで、そのまま保管していただけなのに、なのに、なぜ?目視しても傷や障害物もなさそう。
ショック。大好きな盤なので、中古市場で買いなおしました。(完全限定版だからいまは売ってないんですよね。)
後日レコード店で相談してみよう。
まっこんな感じなのである。
ようやくアナログ再開の準備は整った。
ようやくアナログ再開の準備は整った。
ベルリンフィルのダイレクトカットLP。
とにかく高級品そのもので、最初触るのはすごく怖かった。
ラトル盤は、500枚完全限定。あっという間に即完売だった。
ラトル盤は、500枚完全限定。あっという間に即完売だった。
ハイティンク盤は、1884枚完全限定。
自分のシリアル番号は、ラトル盤は450番(/500番)
ハイティンク盤は、1428番(/1884番)
ハイティンク盤は、1428番(/1884番)
ハイティンク盤(なんと日本語解説がついている。ラトル盤にはなかったことだ。)
ラトル盤
ベルリンフィル・レコーディングスによる制作との宣伝だったが、中を見たらやはりエミール・ベルリナー・スタジオ(Emil Beliner Studios)による制作だった。まぁ、EBSはもともとDGの中にいたレコーディングス技術部隊でDG時代のベルリンフィルを録音していたのだから、別に問題はなし。
ライナー・マイヤールさんプロデュースだ。
さっそくハイティンク盤から聴いてみる。
ハイティンク盤は、2019年5月に行われたベルナルド・ハイティンクのベルリン・フィルにおける最後の演奏会、ブルックナー「交響曲第7番」をダイレクトカットLPで収録しようとした試みだったのだ。
ハイティンクは、ベルリンフィルとも200回以上の演奏会をおこなった縁の深い指揮者で、そんなハイティンクに対して花道を飾ってあげようというプレゼントだったようだ。
ディスクの最終面(LP2‐B面)にはハイティンクとベルリン・フィル団員のサインが刻み込まれている。
ダイレクトカット録音は、マイクで採音された演奏を、直接ラッカー盤面に刻み込んでいく方法で、編集はいっさいない。もちろん演奏自体も失敗が許されないから、すべてにおいて一発勝負なのだ。
従来のようなアナログマスターテープを介さないからテープヒス音もない、高音質という触れ込み。
ハイティンク盤を聴いて、そして引き続いてラトル盤を聴く。
聴き比べてみて、自分が想ったこと。
それはオーケストラ録音の難しさ。
ジャズやポップスはオンマイク録音、クラシックはオフマイク録音と言われる。
オーケストラ録音って、やっぱり音場型録音だと思うのですよね。
あのコンサートホール全体に響き渡る音場をそのまま、まるっと抱え込むというかその音場空間をそっくりそのまま捉え録音するのがオーケストラ録音の基本なのだと思うんですよね。それがまず第1前提で、その次に各楽器の解像感や分離感などを追求していくような順番なのだと思うのです。
コンサートホールで生演奏を聴いている、あの感覚を蘇らせるには、やはりあの全体の音場感がファースト・プライオリティ。
ラトル盤はワンポイント録音だった。
舞夢さんの話では、ハイティンク盤ではアンビエンス・マイクを使ったマルチマイク録音だそうだ。メインマイク3本とサブマイク2本の5本構成された構成だったようだ。
ハイティンク盤とラトル盤を聴き比べると、自分はこの差がサウンド的な印象を決める決定的な要因のように思えた
結論からすると、自分はマルチマイク録音のハイティンク盤より、ワンポイント録音のラトル盤のほうがよかった。
ハイティンク盤は、音場感が潰れている感じで音が伸びてこないというか、平面的で空間を感じないのに対し、ラトル盤はすごく音が伸びる感じで、ホール空間がそのまま目の前に現れるような感じがした。ラトル盤はホール感がありますね。
よくワンポイント録音は音場感をそのまますっぽり取り込めることができ、自然な音場感を得ることができる反面、マルチマイク録音は、メインマイクの他に、スポットマイクなどで採音し、それを後で、パッチを充てるように継ぎはぎしていくから、位相がぐちゃぐちゃになり、位相合わせなどの調整が難しくて自然じゃない。だからマルチマイク録音はダメ、と言い切る方がいらっしゃるが、自分はそうは思わないです。
確かにワンポイント録音だと抜け感がいいというか、スコーンと抜けるような空間感があって、いいのだけれど、逆にワンポイントだから各セクションが遠くて、解像感や分離感が悪くて団子のように聴こえるというデメリットありますね。あと、マイクから遠いからオーケストラが持っている躍動感の表現も苦手ですね。
そういうのを解決するのに、補助のスポットマイクで録ってあとで、継ぎ足しする訳ですが、そういうワンポイント録音の苦手な部分を補ってくれるのだと思います。
指揮者の背面の天井近く高いところにメインマイクがあって、そこで全体の音場をキャプチャーして、そういう解像感や分離感、躍動感などをそっと後から補完してあげるというそんな作業なのではないでしょうか?
確かにマルチマイクって継ぎはぎだから、聴いていて、抜け感が悪くて、どこか空間が詰まっている感じで、抜けるような自然な音場感という感じはしないかもしれませんが、それってエンジニアの腕次第だと思うんですよね。
自分が普段聴いているレーベルはマルチマイク録音が主流ですが、きちんと位相合わせの技が妙で、シームレスに繋がってそういう不自然さを感じないし、広大な音場、明晰な音像を両立させていると思います。
すべてエンジニアの腕次第だと思うのです。
音声信号で、位相って本当に大事なパラメータです。音声信号の時間軸の管理、調整のことです。
今回、ハイティンク盤で音場が潰れてホール感を感じないのは、マルチマイク録音で録ったものを、きちんと後でその継ぎはぎのときの位相合わせなどの編集ができないからだと思うのです。
ダイレクトカット録音は、もちろん編集はいっさいなしのマイクで採音した音をダイレクトに盤面にカッティングするのでそういうマルチマイクで録った音の位相合わせなどがきちんとできていなかったのでは、と思うのです。
なぜハイティンク盤をマルチマイクで録ったかと言うと、それはブルックナーが大編成を要するので、ワンポイントだと全体を捉えられないという理由からそうしたのだと思います。
でもマルチマイク録音は編集してなんぼの世界ですね。
エンジニアが徹底的に編集を施して、きちんと継ぎ目をスムーズにして、位相合わせして、完成度をあげて初めて成果がでるやり方ですね。
ダイレクトカット録音はそれができないから、簡単なミックスでは、どうしてもそういうつなぎ目がうまくいかず、位相がぐちゃぐちゃになって空間、音場感を壊してしまうのでは?と思うのです。
ライナー・マイヤールさん率いるエミール・ベルリナー・スタジオ(Emil Berliner Studios)という最高の技術スタッフを以てしてもこんな感じの印象だから、やはり難しいことなのだと思います。
ラトル盤はすごいです。とにかくすごい空間感、ホール感でよく鳴るというか、自分の5万円の安いプレイヤーでこれだけ鳴るのは、やはりオーケストラ再生冥利だと思います。グリモーさん&バイエルン響もオーケストラ演奏ですが、全然ラトル盤のほうが凄かったので、やはりダイレクトカット録音はすごいと思ったほどです。
編集がいっさいできないダイレクトカット録音では、やはりワンポイント録音のほうがいいのではないか、というのが自分の導き出した結論です。
もちろん最初からそんなことを思いつくはずもなく、ハイティンク盤を聴いて、う~ん。ラトル盤を聴いて、う~ん。なんでこんなに違う感じなのだろう、ということを感じて、自分で後で無理やりこじつけて理論づけただけなのです。
つじつまが合うようにした後付け理論なのです。
もちろん間違っているかもしれないです。
反論も多いと思います。甘んじて受けます。
反論も多いと思います。甘んじて受けます。
自分の安いプレイヤーではハイティンク盤をきちんと鳴らし切れていないだけなのかもしれません。(その可能性も大きい。)
そういう考え方からすると、いまのライブストリーミング配信も生放送ストリーミングは編集できないから、ワンポイントマイクでやるのが一番自然な音場感、ホール感を得ることができて、いい音で視聴者に音を届けることができると思うのです。
アーカイブは、あとで、じっくりエンジニアが編集して完成度をあげていい音にすることができるから、そういう意味でマルチマイクでいいかもしれませんね。
ベルリンフィルのDCHなんてそうやっていると思います。
オーケストラ録音って本当に難しいです。
今回のダイレクトカットLPについては、もともと舞夢邸で聴いたことが最初の縁でしたが、舞夢さんにはいろいろお世話になりました。
ここにお礼を申し上げます。
ポリヒムニアのSocial Distancingな録音 [ディスク・レビュー]
今日6月25日は、日本のオーケストラ団体が立て続けに、活動再開に向けて、その指針を発表した日だった。やはり1番中心で大きな柱になっているのが、東京都交響楽団(都響)であろう。
自分たちが、日本のオーケストラの中心になって、この難局を乗り越えていく旗頭になっていこうという強い気構えを感じる。
都響は、今月の11日、12日に新型コロナ対策を踏まえた今後のコンサート活動について、東京文化会館で数々の実験を踏まえた試演をやっている。
その実験結果とその今後の方針についての指針を今日発表した。
「演奏会再開への行程表と指針」を策定
そうか、そうか・・・。
こんなロードマップ。
なんか具体的に見えてきた感じですね。
なんか具体的に見えてきた感じですね。
マーラーの交響曲のような大編成を聴けるようになるのは、まだ先ですね。
合唱などの声楽が1番高い障壁になりますね。
合唱などの声楽が1番高い障壁になりますね。
上記のリンク先にあるPDF資料を一読してみてほしい。その試演での実験結果をここまで専門的に分析してデータ化しているのは、驚きである。自分は、このPDF資料の中で1番興味を惹かれ、なによりも単刀直入で簡潔に書いてあってわかりやすい資料3。
1番読みやすく、端的にポイントを抑えているように思えた。
試演後に、関係者でミーティングした議事である。
(奏者からの飛沫)
◆ 数値の解析はこれからだが、思ったよりも粒子は飛んでいない印象。
◆ フルートは息が良く出ると聞いていたが、しぶきが大量に飛ぶということは無かった。
◆ 歌手は、飛沫は飛ぶが、大きめの粒子、下に落ちていくような粒子が多い印象。
◆ 舞台上でも、管楽器の真ん前、弦楽器の真後ろで計測していた限りでは、そこで数値が大きく変わることもなく、もう少し詰めてもあまり変わらないと思う。ひな壇に上がったとしても基本的には同じだろう。
(奏者間の距離についての医師の見解)
◆ ヨーロッパでは、1.5mとか 1mとかのガイドラインがあるようだが、まずは普通どおり並んでも良いのではないか。
◆ 医師も、患者と 1mは離れない程度で外来診療を行っているが、必ずマスクをし、一人診察が終わるごとに、手洗い、アルコール消毒をすれば、そう簡単にうつされるものではない。
◆ オーケストラでも、むしろそのような、練習場に入る時の手洗いなどを守っていただければ、活動を再開できるのではないか。
◆ ディスタンスは取れるのなら取った方が良いのだが、基本的には 1m取れば十分感染予防できる。むしろ、通常の感染予防対策、手洗いや体温チェックなどが大事。
◆ 数値の解析はこれからだが、思ったよりも粒子は飛んでいない印象。
◆ フルートは息が良く出ると聞いていたが、しぶきが大量に飛ぶということは無かった。
◆ 歌手は、飛沫は飛ぶが、大きめの粒子、下に落ちていくような粒子が多い印象。
◆ 舞台上でも、管楽器の真ん前、弦楽器の真後ろで計測していた限りでは、そこで数値が大きく変わることもなく、もう少し詰めてもあまり変わらないと思う。ひな壇に上がったとしても基本的には同じだろう。
(奏者間の距離についての医師の見解)
◆ ヨーロッパでは、1.5mとか 1mとかのガイドラインがあるようだが、まずは普通どおり並んでも良いのではないか。
◆ 医師も、患者と 1mは離れない程度で外来診療を行っているが、必ずマスクをし、一人診察が終わるごとに、手洗い、アルコール消毒をすれば、そう簡単にうつされるものではない。
◆ オーケストラでも、むしろそのような、練習場に入る時の手洗いなどを守っていただければ、活動を再開できるのではないか。
◆ ディスタンスは取れるのなら取った方が良いのだが、基本的には 1m取れば十分感染予防できる。むしろ、通常の感染予防対策、手洗いや体温チェックなどが大事。
◆ 一方で、歌手については比較的飛んでいるという話。感染症学では、基本的には 2m飛ぶと言ったら、安全をとってその倍の距離を取れば良いと言われる。舞台から観客席をどれぐらい空けたらいいかというのは、その辺りから分かってくるのではないか。
(奏者のマスク着用)
◆ マスクはした方がそれに越したことは無いが、本番の時は外しても良いのでは。
◆ むしろ控室などでの何気ない会話、食事をとる時などに、気を付けた方が良い。
(奏者のマスク着用)
◆ マスクはした方がそれに越したことは無いが、本番の時は外しても良いのでは。
◆ むしろ控室などでの何気ない会話、食事をとる時などに、気を付けた方が良い。
(大リハーサル室の状況)
◆ 大きな通気口があり、広さとしては非常に広い、容積が大きいので、問題ない。
◆ 空気の流れの確認は必要かもしれない。
◆ 練習は原則としてマスクをするなど、多少通常よりも感染予防を徹底していけば大丈夫。
◆ ホールより狭いとしても、肩と肩がくっつくような状態で演奏するわけではない。
◆ むしろロビーで休憩する時の方が心配。病院では、食堂でも、向かい合わせになるな、基本的にしゃべるな、ということを言っている。
(管楽器の結露水)
◆ もし感染している人が演奏していたのだとしたら、結露水には接触感染のリスクが生じる。
◆ 今回やっていただいたように、吸水シートに必ず捨てるようにすることは必要。
(PCR検査)
◆ PCR検査というのは確証にはならない。
◆ リハーサルの時など、指揮者は楽団員に、大きな声で呼びかけることもある。楽団員の安心のため、という意味で、例えば指揮者のみPCR検査をするということは考えられるかも知れない。
◆ 大きな通気口があり、広さとしては非常に広い、容積が大きいので、問題ない。
◆ 空気の流れの確認は必要かもしれない。
◆ 練習は原則としてマスクをするなど、多少通常よりも感染予防を徹底していけば大丈夫。
◆ ホールより狭いとしても、肩と肩がくっつくような状態で演奏するわけではない。
◆ むしろロビーで休憩する時の方が心配。病院では、食堂でも、向かい合わせになるな、基本的にしゃべるな、ということを言っている。
(管楽器の結露水)
◆ もし感染している人が演奏していたのだとしたら、結露水には接触感染のリスクが生じる。
◆ 今回やっていただいたように、吸水シートに必ず捨てるようにすることは必要。
(PCR検査)
◆ PCR検査というのは確証にはならない。
◆ リハーサルの時など、指揮者は楽団員に、大きな声で呼びかけることもある。楽団員の安心のため、という意味で、例えば指揮者のみPCR検査をするということは考えられるかも知れない。
自分が1番ビビッと反応したのは、奏者間の距離についての医師の見解。
「ヨーロッパでは、1.5mとか 1mとかのガイドラインがあるようだが、まずは普通どおり並んでも良いのではないか。」
そうか!そうか!よくぞ言ってくれた。
アフターコロナ&ウィズコロナで、自分がニューノーマルどころか、アブノーマル(笑)だと思っているのは、あのステージ上での奏者間の距離と、観客席の間引き。これがなくなれば正常に戻れる。
医師のコメントは、奏者間の距離だけの言及だけれど、観客席については、クラシック聴衆は静かに聴いているし、ブラボーなし、咳エチケットがあれば、そんな飛沫の危険性は少ないと思うんですよね。普通にお客さんを入れてもいいのでは?と思います。
早くそういうポイントでの確証がほしい。
ここが一番重要でもある。
あと、奏者のマスク。これも不要。見苦しいです。(笑)
「一方で、歌手については比較的飛んでいるという話。感染症学では、基本的には 2m飛ぶと言ったら、安全をとってその倍の距離を取れば良いと言われる。舞台から観客席をどれぐらい空けたらいいかというのは、その辺りから分かってくるのではないか。」
う~ん、これは予想はしてけれど、声楽はやっぱり厳しいなぁ。自分は声楽コンサート大好きなので。声楽は生で聴くと本当に興奮度は半端ないです。声楽こそ、生に限ると言ってもいい。
ヨーロッパは、Social Distancingについては、結構うるさい。
ガイドラインがかなりしっかりしている。
アムステルダム・コンセルトヘボウのSocial Distancing対応のオーケストラ配置。客席をとっぱらって、平土間にオケを配置して、1.5m/1.75mなどの奏者間の距離を取る。指揮者はステージ傍で、そこから奥行きにオケが展開するイメージ。
コンセルトヘボウには1.5mのSocial Distancingを命ずるロゴステッカーが貼られている。
控室替わりのブレイク時のドリンクコーナーも距離感を持ってチェロケースが。。。
自分は、この写真を見たとき、なんか間違っているだろう。(笑)これが今後のニューノーマルになるんだったら、ごめん被りたいところもいいとこだ。早く元の世界に戻れ!と思ったものだ。
このときのリハーサルの指揮者がグスタボ・ヒメノ。
そう、RCOの首席打楽器奏者から指揮者に上り詰めた才人だ。
そう、RCOの首席打楽器奏者から指揮者に上り詰めた才人だ。
自分はヒメノ指揮RCOの来日公演をサントリーホールで聴いたことがある。ソリストはユジャ・ワン。2015年だったかな。素晴らしかったよ。ヒメノは袖に下がるときに小走りに速足で去っていくのがなんか奇妙と言うか、大舞台に慣れていなさそうで初々しかった。
上の写真はあくまでリハーサルで、それは録音のためだと思っていた。
ヒメノは、現在ルクセンブルク・フィルの首席指揮者である。
ヒメノは、現在ルクセンブルク・フィルの首席指揮者である。
この写真で録音したPENTATONE新譜がこれだと思っていた。
もちろんさっそく買って聴いてみた。
この写真のオケ配置、奏者間距離で果たしてちゃんと音がまとまって聴けるの?
音場や音像が膨らんじゃって、ダメなんじゃないの?
この写真のオケ配置、奏者間距離で果たしてちゃんと音がまとまって聴けるの?
音場や音像が膨らんじゃって、ダメなんじゃないの?
これはポリヒムニアの腕の見せ所。腕前拝見とさせていただこう、と思っていたのだ。
さっそく聴いてみたところ、自分は青ざめた。
もう全然普通にいい録音。コロナ以前のふつうのホール録音と変わらない出来で、自分はぶったまげた。さすが技術集団、ポリヒムニア。やってくれるなぁ、と舌を巻いた。
まったくの普通通りの録音テイストなのだ。
どうやってんのかな?とも思った。
実際自分がこの新譜を聴いたのは2~3週間前だったのだが、そのときにすぐに日記にすることをためらった。日本では各オーケストラが奏者間距離をいろいろ試行錯誤でやっていて、距離があるとやはり隣の奏者の音の聴こえ方が違ってくるし、アンサンブルもやりずらい。
もう真剣モードでみんな議論している。
そんな中に、いや~1.5m/1.75mで平土間でやっても、全然普段と変わらないいい録音!なんてことは言えない。(笑)いいづらい雰囲気で躊躇って、自分の心の中だけに収めておくことにした。
そのあとブックレットを読み進んでいくうちにこの話の落としどころが待っていた。(笑)
録音日時、録音場所が、2019年7月と11月となっていて、ルクセンブルク・フィルハーモニーとなっていた。
あれ?コンセルトヘボウじゃないの?
しかもこの日時って、コロナ以前では???
しかもこの日時って、コロナ以前では???
これがルクセンブルク・フィルハーモニー。写真は、コロナ以後にヒメノ&ルクセンブルク・フィルが1.5mの奏者間距離を開けて、無観客生ライブ配信をする、という写真だ。
ルクセンブルク・フィルハーモニーはご覧のように、シューボックスのコンサートホール。シューボックスで程よいエアボリュームだし音響も良さそう。このホール空間で、コロナ以前の普通のオケ配置で録ったなら、そりゃいい録音になるに違いない。(笑)
そりゃ昔と変わらないいい録音に違いない。
ポリヒムニアのエンジニアは若手育成のため、若手を積極的に起用していた。
ポリヒムニアのエンジニアは若手育成のため、若手を積極的に起用していた。
コンセルトヘボウのあのオケ配置は、指揮者は確かにグスタボ・ヒメノだけれど、オーケストラはRCOなのでした。それもベートーヴェン7番とドヴォルザーク8番を、このコンビでコンセルトヘボウから無観客生ライブ配信するためのリハーサルだったのだ。
自分はこのベト7は、ストリーミングで聴きました。
やっぱりこのご時世、まだ奏者間距離をどうとるか、は試行錯誤のときで、これで録音、商品にするまでの決断はできないのでしょう。まだ無観客でライブストリーミングする段階で止まっているというか・・・。
奏者間距離を取ると、やはり全体のオーケストラのサウンドに影響はあると思います。それは商品として聴いている自分たちのような聴衆もそう感じるけれど、なによりも指揮者、奏者にも違和感あるはず。
普通に従来の密の状態の方が音はいいですね。それで、ずっと歴史を作ってきたのですから。
コンセルトヘボウの写真のあの平土間配置であんなすごいサウンド造られたら、と思ったら興ざめでしたが、世間はまだそこまで行ってないし、いや行ってほしくないという感じでもありましょうか?(笑)
ルクセンブルク・フィルハーモニーで今回の新譜で作業を進める指揮者グスタボ・ヒメノとピアノソリストのデニス・コジュヒン。
デニス・コジュヒンは本当に素晴らしいピアニストですね。英国グラモフォンの記者からは、自分が売れること、そういうポピュリズムから最も遠い位置にいるピアニスト、と評されるほど、玄人好みというか渋い立ち位置が自分は大好きです。
フランクという作曲家は、普段はあまり聴かない作曲家ですが、この新譜を聴いていると本当にその大物作曲家と言っても過言ではないその筆致に感動します。
完成度の高い作品だと思います。
この新譜、自分の愛聴盤に間違いなくなりそう。
BISの室内楽 [ディスク・レビュー]
今日からサントリーホールCMGオンライン(チェンバーミュージックガーデン有料ライブ配信)がスタートしている。ライブストリーミング配信で有料というのがうれしい。
日本のクラシック業界でそういう流れを作るのは、まずサントリーホールが1番最初にやってほしい、という想いがあったので、とてもうれしい。
プラットフォームに、イープラスの「Streaming+」を使うという。
チケット業者のイープラスからそれが出てくるというのが意外だったけれど、この「Streaming+」って具体的にどのようなものなのかもうちょっと詳しく知りたいと思っていた。
イープラスのチケット制の動画ストリーミング・サービス「Streaming+」がグランドオープン
この記事を読んで、なるほどなぁ、と思いました。イープラスってチケット販売企業、ライブ・エンタテインメント事業企業として約20年間に渡り実績やノウハウを培ってきた企業だからこそ、こういう課金EC系のシステムには持ってこい、というかアイデア満載なのだと思うのでした。
いくら技術開発力が高くても、ビジネスのアイデアがないとダメで、そのビジネス・アイデアが豊富だからこそいろいろなEC系のビジネスのアプリケーションを展開できる発想があるのだと思いました。
チケット販売はもちろんのこと、プロモーション、グッズ販売などの販促関係もろもろ。
ライブストリーミングが今後主流になるなら、こういう課金EC系のビジネスを母体にアイデア豊富に持っている企業体が結構大きいアドヴァンテージがあるかもしれませんね。
なるほど世の中って、需要のあるところにビジネスが流れるんだな、とつくづく思いました。
自分は技術系なので、やはり気にするのは、配信環境(インターネット回線、機材、運用方法)と信号処理のCodec。Streaming+がどのようなCodecを使っているかは知りませんが、いまは世の中が急いで要求しているので、普及フォーマットを使っているのでしょう。
でもゆくゆくは、夢のある高画質・高音質フォーマットの信号処理を期待したいです。こういう伝送系の信号処理と課金EC系は配信システムの中では別途に分けて考えてもいいですね。あとでガッチャンコする感じで。。。
イープラスは、もちろんクラシックだけではなく、ポップス、ロック、ジャズなどの音楽系、舞台、トークイベントなど幅広いエンターテイメントを手掛けているので、それが全部ライブストリーミング配信になったら、それこそ、そういうライブイヴェントに紐づいて関連する販促ビジネスなどの課金EC系は宝の山というか大儲けしそうな感じですね。
期待したいです。
さて、日記の本題は、じつはそこではなくて(笑)、サントリーホールCMGオンラインは室内楽のお祭り。ひさしぶりに室内楽をたっぷりと聴きたいなと思ったのでした。
なにせ、去年の年末から半年間ずっとマーラーばっかり聴いてきたので(笑)、そろそろ衣替えをしないとという感じです。また最近深夜遅くまで音楽を聴いていることが多く、そういう場合大編成の大音量は聴けないので、室内楽を聴くケースが多い。
できればひさしぶりにBISの録音が聴きたい衝動にかられたのです。
BISはワンポイント録音のさきがけのレーベル。マイクからほどよい距離感がある完璧なオフマイク録音。温度感が低めでクールなサウンド。録音レベルは小さいんだけれど、ダイナミックレンジが広く、結構オーディオマニア好みのサウンド作りなのである。
しかもSACD 5.0サラウンド。
BISに所属しているカルテットで室内楽を堪能したいなぁという猛烈な衝動にかられる。あのクリスタルなサウンドで、隙間感のある室内楽を聴くと、もう最高!みたいな感じ。
いままでBISの録音制作を手掛けてきたトーンマイスター5人が独立して、「Take 5 Music Production」という別会社を設立している。
主なミッションは、BISの録音制作を担う、ということで、フィリップス・クラシックスの録音チームが、ポリヒムニアになったことや、ドイツ・グラモフォンの録音チームが、エミール・ベルリナー・スタジオとなったことと同様のケースのように確かに思えるのだが、ただ唯一違う点は、現在もBISには、社内トーンマイスターが在籍して、音に関わる分野の責任を持っていることなのだという。
いま最近のレーベルは、社内に録音スタッフを持たず、外注先に委託することが多いというのが現状である。大変な金食い虫でもあるし、そのほうがコスト削減で効率的なのであろう。外注のほうがより技術的にも専門的なスキルを持った業者が多いことも確かだろうし、レーベル社内で、そういった職人を育てていくだけでも大変なことだ。
でも、それってレーベルごとに受け継がれてきている伝統サウンドというものが、もう崩れてきて存在しない、ということを意味していてオーディオファイルにとって寂しい限りでもあるのだ。
DGであれば、骨格感のある硬派な男らしいサウンド。
1960年代ステレオ黎明期を一斉に風靡したDECCAマジックなどなど。
1960年代ステレオ黎明期を一斉に風靡したDECCAマジックなどなど。
そのレーベルごとに、そのサウンド、という特徴があって、それを堪能するのがオーディオマニアの楽しみでもあった。マニアはいつのまにか、レーベル単位で、その録音されているサウンドを想像することができた。でもいまは外注だから、それこそコスト重視で、アーティストごとにいろいろ違う外注に切り替えていたりしたら、それこそレーベルごとにサウンドの統一感なんて難しいことになる。
なんかそういう時代になってきているのは、なんとも寂しいなぁと思う限り。
BISもそんな流れの一環にあって、「Take 5 Music Production」という外注も請け負える団体にすることで、BISのタレントだけではなく、いろいろな録音ビジネスの受注を受け入れるようにビジネス拡大しているのだ。
いろんなところで、あのBISサウンドが聴けるかもしれない。(笑)
BISのトーンマイスターでは、やはり自分はなんと言っても、Hans Kipfer氏。(現在Take 5 Music Production) 彼が録音、ミキシング、バランス・エンジニアを担当してきた曲を一番多く聴いてきた。
BISサウンドといえば彼というイメージが多い。
Take 5 Music Productionの俊英たち。(その名の通り、5人によるチームなのです。(笑))
BISのサウンドエンジニアは、みんなコアなRMEユーザーですね。
そして驚くことにオリジナルマスターは96/24でやっているのだ。
このハイレゾの時代に。
そして驚くことにオリジナルマスターは96/24でやっているのだ。
このハイレゾの時代に。
それであれだけ素晴らしい録音を作り上げるのだから、録音ってけっしてスペックで決まるものではない、という最もいい一例であろう。
ポリヒムニアも同じことを言っていて、いい録音を作り上げるのは、ハイスペックで録るということに拘っていなく、またそれが絶対条件でもなく、もっと基本的なことがあるんだよね。
それは彼らが世に送り出している作品にすべて現れている、と言っていいと思う。
BISの室内楽を無性に聴きたく、6枚を緊急購入。
キアスクーロ四重奏団
いまをときめくアリーナ・イヴラギモヴァ率いるカルテット。イブラギモヴァ大ファンです。(笑)2005年に当時英国王立音楽大学(RCM)で学んでいた友人を中心に結成したカルテット。団体名の「Chiaroscuro(キアロスクーロ)」は美術用語で、コントラストを印象づける明暗法や陰影法を意味する。
全員がガット弦とピリオド楽器を使い、チェロ以外は立奏する。
完全なイブラギモヴァのカルテットと言っていい。
完全なイブラギモヴァのカルテットと言っていい。
去年の2019年の4月に来日しており、これはぜひ行きたかったんだが、マーラーフェストのための予算確保のために見送ってしまった。いま考えれば本当に愚かなことをしたものだ。
シューベルト弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」、第9番
キアロスクーロ四重奏団
キアロスクーロ四重奏団
ハイドン弦楽四重奏曲集 Op.20 第2集
キアロスクーロ四重奏団
キアロスクーロ四重奏団
キアロスクーロ・カルテットいい!もう実演体験しなかったのは一生の不覚。オーディオでもわかる精緻なアンサンブル。古楽器特有のもさっとした感覚がするのだけれど、古楽器でないと表現できないこの時代特有の評価観ありますね。もうこれは頭の評価脳を切り替える必要ありますね。イブラギモヴァがぐいぐい引っ張っていってるのがよくわかる。目の前に、そのシーンが浮かんでくる。やっぱりイブラギモヴァのSQなんだと思いますね。
このカルテット、古典派と初期ロマン派のレパートリーを看板としてきたようなのだが、フランスAparteレーベルよりベートーヴェン、モーツァルト、シューベルト、メンデルスゾーンのディスクをリリースして好評なのだそうだ。そしてBISレーベルに録音を残しているのが、このシューベルトとハイドン。
かなりベテランなんですね。BISに移籍してからはハイドンが注目ですかね。
やっぱりSACDサラウンドで、BISサウンドがいいです。BISで室内楽を聴きたい!というのがきっかけなのですから。
トリオ・ツィンマーマン
ゴルトベルク変奏曲~弦楽三重奏版
トリオ・ツィンマーマン
トリオ・ツィンマーマン
ノンノンさんは、女性ヴァイオリニストしか日記にしないと思われているかもしれないが(笑)、そんなことないのである。
フランク・ペーター・ツィンマーマンは、男性ヴァイオリニストの中でもとりわけ昔からずっと注目していて、大ファンである。
特に彼のトリオであるこのトリオ・ツィンマーマンの室内楽の大ファン。
BISのベートーヴェン弦楽三重奏が愛聴盤で、数週間前にひさしぶりに聴いたら感動してしまって、BISの室内楽のSACDが聴きたい、大量に買おうと思ったのは、それがきっかけだったのである。
トリオ・ツィンマーマンは2007年に結成。「トリオは自分にとってベストなアンサンブル」と語るツィンマーマンが、長年ベストなアンサンブルができる演奏者を探し、若き天才ヴィオラ奏者アントワーヌ・タメスティと、タメスティが信頼を寄せるチェリスト、ポルテラに巡り合いトリオ・ツィンマーマンが結成された。
このトリオはとにかくすごい切れ味のサウンド。剃刀のような切れ味の瞬発力で、自分は男性トリオとしてのエクスタシーの極致を感じてしまう。女子バレーの後に、男子バレーを見る、女子テニスの後に、男子テニスを見る。それぐらいの衝撃がある。
そこに男性奏者の凄さ、底力というのをマジマジと感じてしまうのだ。アンサンブルの完成度の高さもそうだけど、自分はこのキレッキレッのサウンドにメロメロなのだ。いかにも男性的。トリオ・ツィンマーマンは全員すべて名器ストラディヴァリウスを使用している。その音色もエレガントの極みともいえるこの上なく美しい音色なのだ。
このアルバムもゴルドベルグ変奏曲を弦楽三重奏版にアレンジしたものだけれど、言うことないですね。ますます大ファンになりました。
グリンゴルツ・カルテット
メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲、エネスコ:弦楽八重奏曲
グリンゴルツ・クヮルテット、META4
グリンゴルツ・クヮルテットとMETA4がメンデルスゾーンとエネスコの八重奏曲を録音したアルバム。自分は両カルテットともはじめて体験するけれど、これまた素晴らしいですね。普段、弦楽八重奏という室内楽を聴く機会があまりないだけに、とても新鮮でいい刺激でした。
やっぱり音数が多いですね。(笑)
室内楽を聴くたびに想うこと。
それはやっぱり室内楽独特の各楽器のこまやかなフレージングやニュアンスが手にとるように感じられるということ。特に実演に接するとそれがはっきりわかりますね。特にフレージングの妙は、大編成よりも室内楽のほうがわかりやすい。
楽譜をどう読む、どう解釈するかは、その息継ぎとか段落感など、演奏者の解釈によるところが多いと思うけれど、その解釈の仕方でずいぶん曲の印象が違ってきますね。自分は同じ曲なのに、このフレーズ感の解釈の仕方の違いであのアーティストの演奏はすごくよかったのに、このアーティストのは全然ダメだな、がっかり。。。というのをオーディオや室内楽の実演で山のように経験しています。というか日常茶飯事です。(笑)
フレージングは、声楽でもっと顕著に現れますね。
声質もいい、声量も抜群にある、いい声しているのに、その歌を聴いていると全然自分に響いてこない、さっぱり感動できないという歌手もいます。それはやっぱりフレーズ感、フレーズの収め方がこなれていない、というか自分の歌にできていないから、その歌について経験不足から来るものなのだと自分は思っています。
あのシャンソン歌手のバルバラの歌も、一見早口で語りかけているだけのように見えて、じつにカッコいい歌い方だと思ってしまうのは、そこに音楽的フレーズ感があるからなのだ、と思うのです。
だから音楽の演奏でフレージングって結構というか一番大事なポイントなんじゃないかと素人ながら思ったりする訳です。
室内楽はそこが一番はっきりとわかりますね。
しかし、これだけBISの室内楽を聴いたら、もう言うことなし!
まったく思い残すことないです。
まったく思い残すことないです。
やっぱりBISの録音、最高!!!
DGの新譜:リサさまの美しいメロディで旅する世界の都市とチャップリンへのトリビュート [ディスク・レビュー]
リサさま、カッコいい
ジャケット買いとはこのことを言うのだろう。この新譜リリースのニュースが出たとき、よし、これは買い!久しぶりにまたリサさまフィーバーで盛り上がろうと決意した。
![240[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2405B15D.jpg)
「シティ・ライツ」
リサ・バティアシュヴィリ、ティル・ブレナー、
マクシミリアン・ホルヌング、ミロシュ、ラクヴェリ&ベルリン放送交響楽団
ジャケット買いとはこのことを言うのだろう。この新譜リリースのニュースが出たとき、よし、これは買い!久しぶりにまたリサさまフィーバーで盛り上がろうと決意した。
![240[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2405B15D.jpg)
「シティ・ライツ」
リサ・バティアシュヴィリ、ティル・ブレナー、
マクシミリアン・ホルヌング、ミロシュ、ラクヴェリ&ベルリン放送交響楽団
http://ur0.work/w0Tt
実際、このアルバム・コンセプトを理解して、ひと通り聴いてみると、じつに素晴らしいアルバムで自分の永遠の愛聴盤になること間違いなしと確信した。
普通にクラシックの作曲家の作品を取り上げるものではなく、いわゆるコンセプト・アルバムである。
2019年に生誕130年をむかえたチャップリンの音楽と映画に触発されたメドレーを作るというリサ・バティアシュヴィリとニコラス・ラクヴェリのアイデアが、リサさまの生活する主要都市に基づいた自伝的コンセプトへと発展したというのが事の発端のようだ。
今回、クリエイティヴ・ディレクターとして、リサ・バティアシュヴィリとニコロズ・ラクヴェリの2人がクレジットされている。
「リサ・バティアシュヴィリと個人的・音楽的な繋がりがある世界の11都市と、そこに関連する美しいメロディーでその都市を旅し、そしてチャップリンにトリビュートする。」
これがこのアルバムのコンセプト。
ミュンヘン/パリ/ベルリン/ヘルシンキ/ ウィーン/ローマ/ブエノスアイレス/ニューヨーク/ロンドン/ブダペスト/トリビシ
最後のトリビシは、ジョージア国(グルジア)の首都のこと。
リサさまは、このトリビシで生まれた。生まれ故郷の街である。
彼女はトリビシに生まれ、ミュンヘンで学び、ヘルシンキのシベリウス・コンクールでキャリアをスタートし、ベルリンを精神的なホームタウンとみなしている。
「私はこれらの都市の音楽、文化、人々への私の愛を表現し、これらの都市にとって何が特別であるかを前向きかつ具体的な方法で探求したかったのです」。
楽曲はクラシック、映画音楽、民謡、と多岐にわたり全てが新編曲で録音されている。
実際、このアルバム・コンセプトを理解して、ひと通り聴いてみると、じつに素晴らしいアルバムで自分の永遠の愛聴盤になること間違いなしと確信した。
普通にクラシックの作曲家の作品を取り上げるものではなく、いわゆるコンセプト・アルバムである。
2019年に生誕130年をむかえたチャップリンの音楽と映画に触発されたメドレーを作るというリサ・バティアシュヴィリとニコラス・ラクヴェリのアイデアが、リサさまの生活する主要都市に基づいた自伝的コンセプトへと発展したというのが事の発端のようだ。
今回、クリエイティヴ・ディレクターとして、リサ・バティアシュヴィリとニコロズ・ラクヴェリの2人がクレジットされている。
「リサ・バティアシュヴィリと個人的・音楽的な繋がりがある世界の11都市と、そこに関連する美しいメロディーでその都市を旅し、そしてチャップリンにトリビュートする。」
これがこのアルバムのコンセプト。
ミュンヘン/パリ/ベルリン/ヘルシンキ/ ウィーン/ローマ/ブエノスアイレス/ニューヨーク/ロンドン/ブダペスト/トリビシ
最後のトリビシは、ジョージア国(グルジア)の首都のこと。
リサさまは、このトリビシで生まれた。生まれ故郷の街である。
彼女はトリビシに生まれ、ミュンヘンで学び、ヘルシンキのシベリウス・コンクールでキャリアをスタートし、ベルリンを精神的なホームタウンとみなしている。
「私はこれらの都市の音楽、文化、人々への私の愛を表現し、これらの都市にとって何が特別であるかを前向きかつ具体的な方法で探求したかったのです」。
楽曲はクラシック、映画音楽、民謡、と多岐にわたり全てが新編曲で録音されている。
去年の2019年9〜11月頃に録音されているので、ちょうど世界がCOVID-19のパンデミックに見舞われる直前だったのが幸いした。世界中でロックダウン、外出自粛の中で、おそらくはリモートワーク、もしくはスタジオで密にならないように1人での作業など制約があったと思われるが、なんとかアルバムという形にこぎつけ世にリリースできた、ということなのだろうと思う。
アルバムに参加したのは、リサさまのほかのソリストとして、
ティル・ブレナー(トランペット)
マクシミリアン・ホルヌング(チェロ)
ミロシュ(ギター)
ケイティ・メルア(ヴォーカル)
そして管弦楽にベルリン放送交響楽団。
指揮は、クリエイティヴ・ディレクターのニコロズ・ラクヴェリである。
リサさま所縁の11の都市に纏わる曲は、以下の通り。
1. シティ・メモリーズ/チャップリン:テリーのテーマ(ライムライト)〜サンチェ
ス:すみれの花売り(街の灯)〜ダニデルフ:ティティナ(モダン・タイムス)〜チャッ
プリン:Awakening(ライムライト)〜チャップリン:モダン・タイムスのテーマ
2. ミュンヘン/バッハ:われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ BWV.639
3. パリ/ルグラン:パリのヴァイオリン(心のパリ)
4. ベルリン/シーゲル:ベルリンのスーツケース
5. ヘルシンキ/Trad.:イヴニング・ソング
6. ウィーン/J.シュトラウス1世:狂乱のギャロップ
7. ローマ/モリコーネ:愛のテーマ(シネマ・パラダイス)
8. ブエノスアイレス/ピアソラ:ブエノスアイレスの四季から「南へ帰ろう」
9. ニューヨーク/ドヴォルザーク:家路
10. ロンドン/ケイティ・メルア:ノー・ベター・マジック
11. ブダペスト/Trad.:ひばり
12. トリビシ/カンチェリ:ヘリオ・ビーチェボ〜トヴリス・パンテリ〜ラメント〜ス
ティクス
全体の印象としては、クラシックのアルバムを腰を据えてしっかりと聴こうという感じのアルバムではなく、世界の都市を脳内でイメージしながら、その美しいメロディを聴きながら、リラックスして聴くBGM的な聴き方をするアルバムのような感じがした。
最高のBGMである。
本当に美しくて優しいアルバム。
脳内にいっぱいアルファ波が出ます。
そして多様性があって、けっして美しい優しいだけの1本調子にならないドラマがあると思う。
アルバムの最初から最後まで、なんか映画を見ているような完結された作品性・ドラマがあります。
最初の1発目に聴いたときは、あまりに美しい作品に、思わず夢中になりましたから。夢中になって5回リピートして聴きました。冷静になって分析的に聴けるようになったのは4回目あたりからかな。
このアルバムを聴いていると世界を旅行をしている感じに錯覚するし、優雅で優しい気持ちになれる。それぞれの都市に割り振られた曲は、おそらくリサさまとラクヴェリの2人で相談して決めたものだと思われるが、リサさまの強い想い入れのようなものを感じますね。
それぞれの都市に対する想い入れをそのままその曲に託した感じ。
これはやっぱりクラシックのアルバムじゃないね。
リサさまのヴァイオリンは、全体的によく泣いていて、よく歌っていたと思います。
これから11都市を巡り世界旅行をする気分になる訳だが、特に自分が気に入った印象的な曲をかいつまんで感想を一言コメントで残していきたい。
まずアルバム冒頭のチャップリンのテーマ。
これが今回のアルバムのもっとも大事な主題テーマである。
「ライムライト」という映画。
1952年製作のアメリカ合衆国の映画。チャールズ・チャップリン監督。
チャップリンが長編映画で初めて素顔を出した作品で、同時にアメリカでの最後の作品となった。
キャッチコピーとして「美しきバレリーナに よせる心を秘めて 舞台に散った道化の恋… 名優の至芸と 愛の名曲でうたい上げる 感動のチャップリン・シンフォニー。」なんて宣伝されていた。
この映画でチャップリンが作曲した「テリーのテーマ」。
第45回(1972年)アカデミー作曲賞受賞。
これがこの冒頭の曲なのだが、これは誰もが聴いたことのある有名な曲ですね。
一度聴いたら絶対忘れられないテーマ。誰もが惹かれる旋律ですね。
映画音楽って本当にいいですね。
リサさまのヴァイオリンは朗々と鳴っています。
3曲目のパリ。
ルグラン:パリのヴァイオリン(心のパリ)。
パリの街の景観が頭にそのまま浮かんできそうなアンニュイな雰囲気があって素敵。
自分がお上りさんになってパリの街を歩いているのが思い浮かぶ感じ。
4曲目のベルリン。
シーゲル:ベルリンのスーツケース。
ムーディな雰囲気。
ピアノがふっと入ってくるところから一気に雰囲気が変わる。
トランペットがいいですね。
後半は、ジャズ的な感じになり、あのベースラインを刻む独特のリズム感、スィング感とかもう完全にジャズの世界。
6曲目のウィーン。
J.シュトラウス1世:狂乱のギャロップ。
なんかあのシュトラウスの曲とは思えないコケティッシュな感じがいいですね。
ひょっとしたらVPOのニューイヤーコンサートで披露されている曲かも?
7曲目のローマ。
モリコーネ:愛のテーマ(シネマ・パラダイス)
ここはこのアルバムの最高の頂点の盛り上がりでしょう。
涙腺の弱い自分はここで、ついに号泣。
「ニュー・シネマ・パラダイス」1988年公開のイタリア映画。
エンニオ・モリコーネの音楽「愛のテーマ」である。
映画音楽でヘンリー・マンシーニとエンニオ・モリコーネは自分の最強の2本柱。
モリコーネの「愛のテーマ」は誰でも絶対聴いたことのある有名な旋律。
これをリサさまのヴァイオリンとホルヌングのチェロが交互に白いキャンパスにカラフルに音色を描いていく。
泣くよ、絶対に。。。
自分は号泣でした。
このモリコーネの「愛のテーマ」で、コロナで荒んだ心を一気に癒してくれ、ぐっと心に染みてくる。ここがそんな最高のボルテージだと思います。
![84866466_2872050109505455_200177525039562752_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_84866466_2872050109505455_200177525039562752_o5B15D.jpg)
8曲目のブエノスアイレス
ピアソラ:ブエノスアイレスの四季から「南へ帰ろう」
もうこれは情熱の赤。
たっぷりエコー、リバーブを効かせ、空間、エアボリュームの広さを感じるスケール感の大きいサウンド。ミロシュのギターが、ボロンという感じでその広い空間で鳴るのが気持ちいい。街の喧騒の音が素敵ですね。
10曲目のロンドン
ケイティ・メルア:ノー・ベター・マジック
なんともいえない哀愁を帯びたメロディ。
ちょっとボサノバ風のケイティ・メルアのヴォーカルがいいです。
11曲目のブダペスト
Trad.:ひばり
リサさまの超絶技巧が、これでもか、これでもか、と冴えわたります。
このアルバムで一番激しい曲だと思います。
聴いていて痺れます。
12曲目のトリビシ
カンチェリ:ヘリオ・ビーチェボ〜トヴリス・パンテリ〜ラメント〜スティクス
この曲はオーディオ的に最高に美味しいサウンド。
広大なダイナミックレンジ、縦軸の沈み込みの深さ、音のトランジェント、すべてにおいて、オーディオ的なエンタメ性を感じる曲です。
録音の会場は、RBB(Rundfunk Berlin-Brandenburg) Großer Sendesaal。ベルリン放送交響楽団はベルリンの放送局の専属オケだから、その放送局のスタジオだと推測します。アラベラさんがPENTATONEの録音でよくベルリン放送交響楽団と共演しているので、そこでよくその録音会場として使っていたのを記憶しています。
録音評は、2chステレオとは思えない情報量の多さ、音数の多さで、これだけ部屋中に広がる音場感の広さはサラウンドも真っ青という感じ。DGらしい音色の骨格感や定位感も定番通りというところでしょうか。
空間の捉え方や楽器音とのバランス感覚、位置感覚も自分好みです。自分が好みとする録音ポリシーは広大な音場と明瞭な音像を両立させる、というところにあります。この2点を両立させる、というのは、現場では言うは易し、行うは難しというところですね。リサさまの弦の解像感、ゾリゾリ感堪んないです。
録音、ミキシングは、ジョナサン・アレン。バランス・エンジニアは、セバスチャン・ナットケンパー、コロネリウス・ダースト、ジョージ・ガヴァーヤッゼの3人が担当しています。
録音時のスナップショットです。
Photo is copyrighted by Lisa Batiashvili FB
(左から右へ)
ティル・ブレナー(トランペット)
リサ・バティアシュヴィリ
ニコラス・ラクヴェリ(クレエイティヴ・ディレクター)
![96023313_3068448519865612_6257421790088265728_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_96023313_3068448519865612_6257421790088265728_o5B15D.jpg)
(左から右へ)
ティル・ブレナー(トランペット)
リサ・バティアシュヴィリ
(左端から)
リサ・バティアシュヴィリ
ニコラス・ラクヴェリ(クレエイティヴ・ディレクター)
(右端から)
ジョナサン・アレン(プロデュース、録音、ミキシング)
ケイティ・メルア(ヴォーカル)
コロナ前で本当に良かった。(笑)
このアルバムは、今年の自分の最高の愛聴盤になる、間違いなく。
最後に、この新譜のプロモビデオをアップしておきます。
マーラー歌曲集 [ディスク・レビュー]
Mahler Festival 2020が、Mahler Festival Onlineに代替えになってしまうことで、モチベーションがぐっと下がってしまったことは仕方がないが、マーラーの歌曲については、どうしてもマーラー日記として書き残してしまったことなので、完遂したい。
あくまで自分の経験であるが、他の作曲家の歌曲と比べると、マーラー歌曲は、ややしっくり来ないというか自分のモノとして馴染むまで時間がかかった過去がある。
マーラーの歌曲としては
がある。
その原因は、このドイツ語原題のほうが、まず頭に入る訳だが、それと邦題とのマッチングがどうも苦手で、聴いていてどの歌曲が、どの原題、邦題なのかいまひとつピンと来ないというのがあった。
実際音楽を聴いてみて、その旋律を聴けば、すぐにわかるのだけれど、それが原題、邦題とすぐに一致しないという感じであろうか。
ずいぶん長い間、そういう状態でほったらかしにしていた感じである。
音楽の旋律として聴いている分には、本当に佳曲というか、素晴らしい曲ばかりなのである。あと、マーラー歌曲というのは、その旋律の引用など、マーラー交響曲と非常に関係が深く、実際の実演でも歌曲単体として演奏される、というより、必ず交響曲とペアで演奏されることのほうが多い。
マーラー歌曲は、いわゆるオーケストラ稿と室内楽稿と両方のバージョンがあり、今回のマーラーフェスト2020ではメインホールではオーケストラバックにソリスト独唱者が歌うオーケストラ稿(そしてそれは関連性の深い交響曲とペアで演奏される)と、リサイタルホールでピアノとソリスト独唱者が歌う室内楽稿と両方のコンサートが開かれる予定であった。
本当に貴重な体験だったのだけれど残念の一言。
今回、このマーラー歌曲ではずっと昔から愛聴しているPENTATONEの録音でそれぞれの曲を紹介していきたいと思う。
さすらう若者の歌、亡き子をしのぶ歌、リュッケルト歌曲集
アリス・クート、マルク・アルブレヒト&オランダ・フィル
アリス・クート、マルク・アルブレヒト&オランダ・フィル
2017年に発売されたアルバムだが、そのときに購入してよく愛聴していたのだが、ラックのどこかに埋没してしまい見つからないので、もう一度購入したら、ジャケット違いが届いた。(笑)中身は同じようである。
レーベルの方で、ジャケット変更したのかな?もう断然メゾ・ソプラノのアリス・クートのジャケットのほうが断然いいと思うのだが。
このアルバムは、マーラー歌曲のアルバムとしては最高の部類に入る大のお気に入りのアルバムなのである。録音が素晴らしいのと、メゾ・ソプラノ アリス・クートの澄み切った高音域の声、そしてさすらう若者の歌、亡き子をしのぶ歌、リュッケルト歌曲集というマーラー歌曲でもっとも取り上げられ歌われる頻度が高い有名曲が入っているのがお気に入りの理由である。
オーケストラ版で、指揮にマルク・アルブレヒト、管弦楽にオランダ・フィルハーモニー管弦楽団である。マーラー歌曲としてなら、ぜひこのアルバムを推薦したい。
非常にクオリティの高い完成度のアルバムである。
指揮のマーク・アルブレヒトはPENTATONEと契約しているレーベルお抱えの指揮者で、オランダフィルと数々の名録音を残してきている。ワーグナーとR. シュトラウスの解釈および現代音楽への傾倒で高く評価されている指揮者であるが、キャリア初期の頃は、ウィーンのグスタフ・マーラー・ユーゲント管弦楽団でクラウディオ・アバドのアシスタントに指名されたこともあり、マーラーを得意としている。PENTATONEへの録音でも、このオランダフィルとマーラー録音を数枚残している。
自分は、このアルバムを聴いて、とにかく感動したのが、イギリスのメゾ・ソプラノであるアリス・クートの歌唱力である。本当に澄み切った高音域という感じで、しかもメッゾらしい定位感、安定感があって、太く柔らかな低音がその声質の根底にあるので、その高音域の輝きがさらに映えるというすばらしい抜群の声質の持ち主なのである。
とにかく彼女の歌唱力には驚きます。
見事にマーラー歌曲を歌いきっている。
このアルバムで彼女の果たしている役割は大きいと思う。
このアルバムで彼女の果たしている役割は大きいと思う。
アリス・クートは、1968年にリヴァプール郊外のフロッドシャムに生まれたイギリスのメゾ・ソプラノ。ロンドンのギルドホール音楽演劇学校とマンチェスターで学んだのち、ナショナル・オペラ・スタジオで研鑽を積んで注目されるようになり、イギリスのほか、メトロポリタン歌劇場やサンフランシスコ歌劇場、バイエルン国立歌劇場などでも活躍中。これまでにブリギッテ・ファスベンダー賞、キャスリーン・フェリアー賞などを受賞、リートとオペラの両分野に才能を発揮している。(HMV掲載情報)
「さすらう若者の歌」は、マーラーの歌曲集のうち、統一テーマによって作曲された最初の連作歌曲集である。低声とピアノ(もしくはオーケストラ)伴奏のために作曲されている。マーラー自身の悲恋に触発されて作曲されたものと信じられている。
マーラー歌曲の最も有名な作品の一つである。
聴いてみるとすぐに分かる。あっこれは交響曲第1番「巨人」第1楽章で使われている旋律だ、とういうことが。(笑)マーラー自身の作詞によるが、マーラーお気に入りのドイツ民謡集「子供の魔法の角笛」に影響されていると言われている。この歌詞を書いた若きマーラーは報われない片思いの女性歌手に夢中になったのだ。
「リュッケルト歌曲集」は、マーラーが1901年から翌1902年にかけて完成させた連作歌曲集の呼称。これはマーラーの作品の中でも最も素直な幸福感にあふれている歌曲集と言われている。ちょうどアルマと婚約・結婚した頃なので、全てにその幸福感が満ち溢れているのだ。
「亡き子をしのぶ歌」は、グスタフ・マーラーが作曲した声楽とオーケストラのための連作歌曲である。妻のアルマから縁起でもない曲を書かないで、と怒られたのだが、この歌曲集の痛ましさは彼がこの曲集を書いた4年後に、マーラーがまさに娘マリアを猩紅熱によって4歳で失ったという事実によって増大させられるのだ。
この3つの歌曲集をアリス・クートがものの見事に歌い上げる、このアルバムは本当に感動します。ぜひ聴いてみてほしい。
そしてマーラー歌曲の中でも自分が最も大好きなのが、「大地の歌」。
大地の歌は、もう歌曲というジャンルでは括れない交響曲と言ってもいいくらいの大規模な曲である。初演は、マーラーの死後であり、愛弟子であるブルーノ・ワルターによっておこなわれている。
「大地の歌」というメインタイトルに続き、副題として「テノールとアルト(またはバリトン)とオーケストラのための交響曲」とあり、通常マーラーが9番目に作曲した交響曲として位置づけられるが、連作歌曲としての性格も併せ持っており、ピアノとソリストのための室内楽版も存在するため、「交響曲」と「連作歌曲」とを融合させた作品と考えられる。
大地の歌は第6楽章から成り、メゾ・ソプラノとテノール(あるいはバリトン)が交互に楽章を分担して歌っていくため、自分は、この大地の歌を聴くと、本当にもう単なる歌曲としてだけは括れない交響曲に匹敵するスケール感の大きさがあって、「交響曲と歌曲の融合作品」と言える、のは合点がいくところなのである。
本当聴いていると荘厳な感じで、最終楽章のメゾ・ソプラノの消え去っていくような終止を聴いていると、いままでの壮大な6楽章の物語がここに終わる、という感じで鳥肌が立ってくるのである。それだけ聴いたという充実感、満足感が素晴らしすぎる。
また、この大地の歌にはこんな逸話が残っている。
いわゆる「第九」のジンクス、「第九」の呪い、である。
「大地の歌」は、交響曲第8番に次いで完成され、本来ならば「第9番」という番号が付けられるべきものだった。しかし、ベートーヴェンが交響曲第10番 (ベートーヴェン)を未完成に終わらせ、またブルックナーが10曲の交響曲を完成させたものの、11番目にあたる第9交響曲が未完成のうちに死去したことを意識したマーラーは、この曲に番号を与えず、単に「大地の歌」とした。その後に作曲したのが純然たる器楽作品であったため、
これを交響曲第9番とした。マーラーは続いて交響曲第10番に着手したのだが、未完に終わり、結局「第九」のジンクスは成立してしまった、という通説。
これを交響曲第9番とした。マーラーは続いて交響曲第10番に着手したのだが、未完に終わり、結局「第九」のジンクスは成立してしまった、という通説。
マーラーが歌詞に採用したのは、ハンス・ベートゲ編訳による詩集「中国の笛-中国の叙情詩による模倣作」である。
この大地の歌でお勧めな録音が、さきほど紹介したアリス・クート独唱で、マーク・アルブレヒト指揮オランダフィルという全く同じコンビでPENTATONEに録音している「大地の歌」である。
さきほど絶賛したメゾ・ソプラノのアリス・クートは、「大地の歌」を得意としていたジャネット・ベイカー、ブリギッテ・ファスベンダーの教えも受けていて、この録音をする前に、すでに実演では「大地の歌」を何度も歌っていたんだそうですね。
この録音自体は、PENTATONEの初期の頃の録音で、2012年の録音。
なんとヤクルトホールでの録音なんですね。
なんとヤクルトホールでの録音なんですね。
ヤクルトホールは、いまや幻のホール。
初期のPENTATONEの録音ではオランダフィルのフランチャイズとしていたホールでした。
初期のPENTATONEの録音ではオランダフィルのフランチャイズとしていたホールでした。
以前調査したときは、アムステルダム市内にある「バース・ファン・ベルラーヘ(Beurs van Berlage)」という施設内に「ヤクルトホール」という小ホールがあるようで、そこではないか、という確信が得られていた。旧証券取引所で、アムステルダム中央駅から徒歩10分弱くらい。
このホールはアムステルダムの中心部ダム広場に近く 地元ではBEURS(バース)と呼ばれる歴史的建造物・旧証券取引場の中にある。BEURS自体は 非常に大きな建物で その中のおそらくかつての宴会場だったと思われる大きな広間がコンサート・ホールに改装され、ヤクルト・ホールと名付けられているのだ。
天井が非常に高い直方体、まさにシューボックスという空間で席は1F平土間だけで バルコニー席は無く 全部で1000席ぐらい。コンセルトヘボウの伝統を受け継いでステージは高い。オランダ・フィルは、ここを本拠地としており、リハーサルと演奏会両方で使っているとのことだった。
今回のマーラーフェスト2020でアムステルダムに行ったときに、ぜひこのヤクルトホールを演奏会かなにかで訪問したかったのだが、調査してもらったところ、普通のプレゼンテーション会場としての機能しかなく、もうコンサートホールとしての機能はないとのことであった。
うぅぅ~残念!
このヤクルトホールでの録音の大地の歌。素晴らしい録音です。初期のPENTATONEの録音らしい、ちょっといじっている感の多いテイストだけど、聴いていてオーディオマニア的には最高の録音。なんか懐かしい感じがしました。
メゾ・ソプラノのアリス・クートと、テノールのブルクハルト・フリッツの掛け合いの熱唱が素晴らしい。ブルクハルト・フリッツは、なんかあのワーグナー歌手のロバート・ディーン・スミスになんか声質が似ています。
典型的な二枚目スターの声ですね。
「大地の歌」の映像作品として、忘れらないのが、マーラー没後100周年記念コンサートとしてベルリンフィルハーモニーで演奏された「大地の歌」
アバド&ベルリンフィル、そしてメゾ・ソプラノにアンネ・ゾフィー・フォン・オッター、テノールにヨナス・カウフマン。もう最高の布陣ですね。自分がマーラーに熱く嵌まり込んでいた2011年の旬の時に体験した演奏です。
いまでもベルリンフィルのDCHで鑑賞可能です。
児玉麻里さんのベートーヴェン・ピアノ協奏曲全集 [ディスク・レビュー]
児玉麻里さんは、ベートーヴェンという作曲家をテーマにそのピアニスト人生を捧げてきた、とても計画的な演奏家人生を送ってきたのであろう。
自分たちのようなエンドユーザーには、その作品がリリースされたときに、初めてそのことに気づくのだが、作品を創作して世に送り出す立場からすると、もう何年も前から計画的に考えていないとこのようなことは実現不可能のように思える。
児玉麻里さんのベートーヴェン愛については前回の弦楽四重奏曲のピアノ編曲版でのご本人の寄稿を紹介した。
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全集では、2003年から2013年にかけての11年間かけて、そしてベートーヴェンの弦楽四重奏曲のピアノ編曲版、そしてベートーヴェン ピアノ協奏曲全集を2006年から2019年にかけての13年かけて完成させた。
まさに”ベートーヴェンにピアニスト人生を捧ぐ”である。
さっそく聴かせていただいた。
児玉麻里さんのベートーヴェン ピアノ協奏曲全集。
ベートーヴェン生誕250周年記念イヤーへの大きなプレゼントである。
児玉麻里さんのベートーヴェン ピアノ協奏曲全集。
ベートーヴェン生誕250周年記念イヤーへの大きなプレゼントである。
ピアノ協奏曲全集(第0~5番)、ロンド、三重協奏曲、他
児玉麻里、ケント・ナガノ&ベルリン・ドイツ交響楽団、
コーリャ・ブラッハー、ヨハネス・モーザー(4SACD)
ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集は、それこそマーラー音源と同じにように、自分にとっては18番のマイテレトリーで、たくさんのピアニストの音源を持っているのだが、今回の児玉麻里さんの録音は、その最高位に位置する録音のよさ。さすが最新録音。やっぱり新しい録音はいいな、と思いました。
オーディオ・ファイルには堪らない素晴らしいプレゼントになりました。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集をSACDで、というのは、なかなかありませんよ。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集をSACDで、というのは、なかなかありませんよ。
これはキングインターナショナルによる日本独自企画の限定盤のようなんですね。
SACDで実現できた、というのもそれが大きい理由でした。
ベルリン・クラシックスから提供のハイレゾ・マスターを用いて、キング関口台スタジオにて、SACDマスタリングを施した、とのこと。
SACDサラウンドではなく、SACD2.0ステレオになります。
旦那さまのケント・ナガノ氏とベルリン・ドイツ交響楽団(DSO)との共演による作品。2006年、2013年、2019年と大きく3回に渡って、ベルリン・イエス・キリスト教会、テレデックス・スタジオ・ベルリン、ベルリン・シーメンスヴィラの3箇所で録音された。
第1番~第5番だけではなく、本作品には、第0番、ピアノと管弦楽のためのロンド、エロイカ変奏曲、ピアノ・ヴァイオリン・チェロと管弦楽のための三重協奏曲が入っている。
第0番というのは、ベートーヴェンの処女協奏曲で、番号が振り割れられていない、珠玉の聖典集の仲間入りを果たすことのできなかった作品である。作曲開始の年齢は13歳から14歳と言われている。
児玉麻里さん曰く「自筆譜を手にしたときの衝撃は計り知れません。ベートーヴェンが触れたインクを目にすることができたのですから。」
この手稿譜はベルリン州立図書館に所蔵されており、オーケストラ譜が記載されていないため、未完成作品として扱われている。ただ最初の二楽章に関しては短い加筆譜とともに、どの楽器が弾くべきか、という簡潔な指示がされており、二十世紀初頭にはこうした指示書きをベースとしたスコアも出版されているそうだ。
しかし研究が進み、若きベートーヴェンへの理解が深まると同時に、いままで通説とされてきた解釈が必ずしも作曲者本人の意図ではないのではないか、という見解が児玉麻里さんとケント・ナガノ氏の間にも生まれてきた。
お二人の目的は、世間一般に広く浸透している、しかつめらしい活力の氾濫とも呼べる巨匠のイメージを払拭し、ハイドンやモーツァルトに通ずる「生きる喜び」に溢れた少年の姿を描くことだったという。
録音年月日を見ると、通常の第1番~第5番までは、2013年にはすでに録音は終わっていたようなんですね。だから通常のベートーヴェン・コンチェルトとしてリリースするならもう少し早い時期に出来たはずなのだけれど、この第0番の発見、そしてこの自筆譜のお二人による共同作業による研究でどのように音として再現するか、という準備に時間がかかったのだと思います。
この第0番の録音は最新の2019年に行われています。
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第0番を聴けるのは、このディスクが初めてだと思います。
自分がこの第0番を聴いた印象。
これはベートーヴェンじゃない!(笑)
とても綺麗で美しい曲で、まるでモーツァルトみたいな作品だと思いました。
ベートーヴェンらしくない。あのベートーヴェン独特の様式感、様式美とは全然違う世界。
とても綺麗で美しい曲で、まるでモーツァルトみたいな作品だと思いました。
ベートーヴェンらしくない。あのベートーヴェン独特の様式感、様式美とは全然違う世界。
やっぱり13歳~14歳頃に作曲した曲だから、自分の書法というのを模索していた時期の曲なんだな、と思いました。
ケント・ナガノ&児玉麻里による共同研究の末の成果、しかと拝受しました。
今回の自分にとって、さらなる新しい発見は、ピアノ・ヴァイオリン・チェロのトリオ・コンチェルト。これは素晴らしいと思いました。聴いていて鳥肌が立ちました。とくにチェロが、あのヨハネス・モーザーで驚き。これを録ったのは、2006年の頃だから、まだPENTATONEの契約アーティストになる前。相変わらずスピーディーで切れ味鋭い、その男性的なチェロの音色にノックアウト。
第1番~第5番は、やはり安定したベートーヴェンによる巨匠の筆致という感でじつに素晴らしい。
これぞ、まさにベートーヴェンの風格がする曲ですね。第4番、第5番「皇帝」がやはり完成度も高く、人気が高い。とくに第5番「皇帝」が最高傑作と呼ばれているのではないだろうか。
自分は、じつは第4番派なのである。
第4番を愛して止まないファンである。
第4番を愛して止まないファンである。
児玉麻里さんのベートーヴェンを知り尽くした、深い深いベートーヴェン愛によるピアノと、ケント・ナガノ氏&DSOによる堅実で重厚なサウンドが相俟ってじつに素晴らしい作品となっておりました。
今回、この全集を作るうえでお二人がどのようなアプローチをしたのかがYouTubeで紹介されております。ベルリン・イエス・キリスト教会でのセッションのときの様子と、そのときにおこなわれたインタビューの模様がYoueTubeになっています。
内容を抜粋すると、
(ケント・ナガノ氏)
ヨーロッパの音楽の歴史を旅するかのように、その発展が生き生きと目の前に広げられます。音楽構造、様式、和声の再定義と方向転換、音楽の歴史に敏感になることは、指揮者にとって一般的に極めて重要なことです。
総譜は残されていませんが、それは、楽譜に残されている作品が未完成のままか、また不明な理由から失われてしまったからです。
しかし重要なことが現れています。演奏される音符はすべてベートーヴェンの筆によるもので、これらを通して、彼の職人技は完全に発達していったことがわかります。そしてその数年後に天才が芽生えます。
しかし音楽構造、様式、和声を完全に掌握しているという意味で、12歳、14歳の男の子がこれだけの才能を持つと思うと、非常に印象的です。
録音技術は、当時の楽器の移行の時期にあったことを念頭に置きました。楽器の指示には、チェンバロとフォルテピアノが選択肢として挙げられていますが、楽譜の強弱法の記載を見るとベートーヴェンはフォルテピアノをイメージしていたことがわかります。
その為、当時の一般的な演奏方法にしたがってオーケストラの中にフォルテピアノを置き、蓋を外し、より透き通った音響を目指して、現代のスタンウェイのコンサート用グランドピアノよりもフォルテピアノの響きに近づけました。
そうすることにより、麻里さんはより繊細な演奏を実現することができ、オーケストラの伴奏はより軽やかで透き通った響きになりました。その理由から、指揮者はアンサンブル全体の前ではなく横に立ちます。
共に生きた歴史、ソリストが妻であることにより、これには一切問題がありませんでした。しかし、この録音および公演プロジェクトのユニークなところは、当時の音の世界と美学に配慮しようとした点です。
(児玉麻里さん)
過去経験したこととは全く違います。通常はある特定のスタイルを学ぶことで、「もちろん、これはベートーヴェンの言語だ」と考え、もちろん、ベートーヴェンの言語が見えてきますが晩年はまた少し異なります。その為、ベートーヴェンがどのような影響を受け、当時、ベートーヴェンに影響を与えた人物、楽器、歌手、ピアノフォルテの響きなどについてたくさん研究しました。
それとともに現代の楽器で、できるだけベートーヴェンが思い浮かべた響きを蘇らせることに努力を費やしました。
ベートーヴェンはコンチェルトを作曲するうえで、フォルテピアノを強く意識して、児玉麻里さんもピアノフォルテの響きを意識して演奏したという。
フォルテピアノについては、もうみなさんご存じのごとく古典ピアノですが、改めて、その構造、音についてしっかりと理解を深めるために、まとめた形で書いてみますね。
フォルテピアノは18世紀から19世紀前半の様式のピアノを、20世紀以降のピアノと区別する際に用いられる呼称である。これに対して現代のピアノを特に指す場合はモダンピアノという呼称が用いられる。
構造は、フォルテピアノは革で覆われたハンマーをもち、チェンバロに近い細い弦が張られている。ケースはモダンピアノよりかなり軽く、金属のフレームや支柱はモダンピアノに近づいた後期の物を除いては使用されていない。アクション、ハンマーはともに軽く、モダンピアノよりも軽いタッチで持ち上がり、優れた楽器では反応が極めてよい。
音域は、発明当初はおよそ4オクターヴであり、徐々に拡大した。モーツァルトの作曲したピアノ曲は、約5オクターヴの楽器のために書かれている。ベートーベンのピアノ曲は、当時の音域の漸増を反映しており、最末期のピアノ曲は約6オクターヴの楽器のために書かれている。
音は、モダンピアノと同様、フォルテピアノは奏者のタッチによって音の強弱に変化を付けることが出来る。しかし音の響きはモダンピアノとかなり異なり、より軽快で、持続は短い。 また音域ごとにかなり異なる音色を持つ場合が多く、おおまかにいって、低音域は優雅で、かすかにうなるような音色なのに対し、高音域ではきらめくような音色、中音域ではより丸い音色である。
ケント・ナガノ氏が言っているところの、つぎの2つのポイント。
「当時の一般的な演奏方法にしたがってオーケストラの中にフォルテピアノを置き、蓋を外し、より透き通った音響を目指して、現代のスタンウェイのコンサート用グランドピアノよりもフォルテピアノの響きに近づけました。」
普通ピアノの録音をする場合、全体の音場を録るメインマイクとピアノの音色を録るスポットで、後者は、蓋に反射して音が右に流れる方向にスポットマイクを置きますが、今回はピアノの蓋を外したということですから、こんな感じでピアノ・マイクをセッティングしたんですね。
そして
「そうすることにより、麻里さんはより繊細な演奏を実現することができ、オーケストラの伴奏はより軽やかで透き通った響きになりました。その理由から、指揮者はアンサンブル全体の前ではなく横に立ちます。」
ということですから、こんな感じだったんですね。
当時、ベートーヴェンのピアノ協奏曲がどのような形・シチュエーションで演奏されたのかを忠実に現代に復元し、ピアノの音色も当時のフォルテピアノの響きを意識した、という姿勢でお二人は臨んだのがよくわかります。(動画の中の使用されているピアノを見ると、古典スタイルのピアノではないように思いますが、でも響きをフォルテピアノの響きを目指した、と自分は理解しています。)
最後に録音テイストについて。
今回は、キングインターナショナルによる日本独自企画ということで、ベルリン・クラシックスから提供のハイレゾ・マスターを用いて、キング関口台スタジオにて、SACDマスタリングを施した、とのこと。
だから現場で録音をしたスタッフは、ベルリン・クラシックのレーベルのスタッフなのであろう。
ところがブックレットのクレジットには、他にDeutschlandradio Kulturの名が記載されている。
これは思わず反応してしまう。
Deutschlandradio Kulturいわゆる通称DLRは、ドイツの公共放送ドイチュラントラジオ・クルトゥーアのことである。
このDLRによるコ・プロデュースで有名な成果が、PENTATONEから出ているこのヤノフスキ&ベルリン放送響のワーグナーSACD全集なんかそうだ。
2015年の頃、PENTATONEのリリースするアルバムの録音クレジットに、やたらとこのDLRのクレジットが多く、そのときにいろいろ調べて、このコ・プロデュースのことを知った。
ドイツ独特の制度でかなり自分の中で印象深く記憶しているのだ。
この公共放送のDLRという組織は、ドイツ内のクラシック音楽のさまざまな録音をコ・プロデュース(共同制作)している。文字どおりコ・プロデュースというのは共同で原盤を制作するという意味なのだが、このDLRのコ・プロデュースは、作品のラジオ・オンエアを行う目的で、録音技術、録音スタッフ、場合によっては録音場所等を援助しながら制作し、作品のリリース自体は外部レーベルから行うという手法なのだそうである。
つまり自分たちが放送媒体機関、つまりメディアであるが故に、そこでのオンエアをさせるために再生する原盤を作成させる援助をするということ。そして原盤自体は外部レーベルからさせる、ということらしい。
DLRのコ・プロデュースの多くは、ベルリン・フィルハーモニー、コンツェルトハウス・ベルリンと、ベルリン・イエスキリスト教会で行われている。
放送メディアでオンエアさせるために原盤作成を援助するという、この独特のDLRのシステム。これはドイツ独特の制度というか非常に面白い制度である。
DLRは、2006年からこれまでに、200枚以上の作品をコ・プロデュースしている。
いまはディスクビジネスだけでなく、ネット配信ビジネスが大きな柱になりつつあるから、この”原盤”作成の定義の仕方も多少違ってきているだろう。
録音スタッフのクレジットには、このDLRからのスタッフもいる。トーンマイスターとかトーンエンジニアのほかに、トーンテクニックという役職がDLR特有ですね。
この児玉麻里さんのアルバムを作成する予算には、こういうコ・プロデュースによる出資も含まれている大プロジェクトだった、ということだったんですね。
録音テイストは、2chステレオとしては、じつに素晴らしい録音である。
豊かな音場感、明晰でソリッドなピアノの音色、オーディオとして聴くには、最高のオーケストラと、ピアノとの聴こえ方の遠近感のバランス。(生演奏で聴いている分には、もっとピアノは遠く感じるはず。)
全体の聴こえ方としても、D-レンジがすごく大きく、とても広い空間で鳴っている感じがよく伝わってきて自分の好みの録音です。
あとは弦合奏の音色に音の厚みがあって、聴いていてとても和声感ある気持ちの良さがいい。オーケストラのサウンドがオーディオでどう聴こえるか、の最大のポイントは、この弦合奏のサウンドがどう聴こえるかですね。ストリングスをうまく鳴らせないSPは、自分的にはどんなに高級なSPでもアウトです。
うちのヘッポコ2chでもこれだけ鳴るんだから最高です。(笑)
ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集といえば、数多ある自分のコレクションの中で最も愛聴しているのがこれ。
アルフレッド・ブレンデルとサイモン・ラトル&ウィーンフィルによる録音。
PHILIPSがレーベルとして存在していた頃の古い録音ですが、これは自分が1番愛してやまない録音です。ベートーヴェンのピアノコンチェルトといえば、自分にとってこれです。
いまふたたび聴き返してみて、やっぱりブレンデルうまいな~。(^^;;
タッチがじつに軽やかでスピーディで本当にウマいと思いますね。
タッチがじつに軽やかでスピーディで本当にウマいと思いますね。
ブレンデルもベートーヴェン弾きとして有名なピアニストでしたね。
これで児玉麻里さんの”ベートーヴェンにピアニスト人生を捧ぐ”のディスコグラフィー、しっかり全部コレクションしました。
PENTATONEの新譜:児玉麻里さんのベートーヴェン弦楽四重奏のピアノ編曲版 [ディスク・レビュー]
児玉麻里によるベートーヴェン・イヤー2020に贈る最高の変化球。
PENTATONEレーベルによる児玉麻里・児玉桃の姉妹共演の「チャイコフスキー・ファンタジー」に続くキングインターナショナル企画による第2弾だそうだ。
児玉麻里さんのここ最近の録音は、キングインターナショナルが日本独自企画という形でしっかりと日本側からアルバム・コンセプトをサポートしているのが、素晴らしいですね。
現地レーベルに所属する日本人アーティストのアルバムコンセプト含め、企画そのものを日本側からしっかりサポートしていると、そのアーティストのことをよく考えてくれるしいいと思いますね。それじゃ日本のレーベルでいいのじゃないか、と仰いますが、そこは海外レーベルならではのプロモーション、販路など、そこには日本のレーベルでは成し得ないメリットもたくさんありますね。
しっかりと日本側からサポートしてあげるというのは、いままでになかった素晴らしい戦略アプローチだと思います。
児玉麻里さんといえば、ベートーヴェンのスペシャリスト。
児玉麻里さんにとって、ベートーヴェンは特別に大切な作曲家で、これまでにPENATONEに録音してきたベートーヴェン ピアノ・ソナタ全集と、そしてキングインターナショナルによる日本独自企画・限定盤のベートーヴェン ピアノ協奏曲全集と、ベートーヴェンについて大きな主要作品を残してきた。
ベートーヴェン ピアノ協奏曲全集のほうは、旦那さまのケント・ナガノ氏とベルリン・ドイツ交響楽団とのSACD全集。2006年から2019年にかけてベルリン・イエス・キリスト教会で録音されてきた力作だ。ベートーヴェン・ピアノ・コンチェルトは1番~5番であるが、このSACD-Boxには特別に第0番という作品も収録されているのだ。
第0番は、ベルリン州立図書館に所蔵されていた第0番の自筆譜にあたり、緻密なリサーチを経て、両者で丁寧に解釈を深めていったとても貴重な作品。このSACD-Boxはぜひ、ぜひ買わないといけない、と思っていて、そのままになっていたので、さっそくいま注文しました。
もちろんレビュー日記も後日書かせてもらいます。
ベートーヴェンについて、ピアニストとして、そういう大きな偉業を残してきた後なので、今回のPENTATONEへ録音したベートーヴェンの作品は、まさに”変化球”という表現は言い得て妙なのだと思いました。
今回のアルバムは、2つの偉大な業績の後の補巻という位置づけで、なんとベートーヴェンの弦楽四重奏をピアノで編曲した作品を演奏する、というびっくり仰天の内容なのだ。
まさに児玉麻里によるベートーヴェン・イヤー2020に贈る最高の変化球。
「ピアノによるベートーヴェン:弦楽四重奏曲~サン=サーンス、バラキレフ、ムソルグスキー編曲」
児玉麻里
児玉麻里
小澤征爾さんが「クラシック音楽の基本は弦楽四重奏」と仰ったのは有名な話。
また室内楽の最高峰とも云われる弦楽四重奏。
ベートーヴェンの16曲の弦楽四重奏をいま一度じっくり腰を据えて聴いてみたいと思いながら、すでにもう何年・・・。
これを児玉麻里さんのピアノで聴けるのは最高ではないか!
このベートーヴェンの弦楽四重奏曲のピアノ版への編曲者がサン=サーンス、バラキレフ、ムソルグスキーといういずれもピアノ音楽の傑作を残しているひとかどの作曲家である点が素晴らしい。
ベートーヴェンが生涯にわたり作り続けたのは弦楽四重奏曲。
ベートーヴェン好きのピアニストにとり、この世界を担える弦楽器奏者は羨望の存在であった。
ベートーヴェン好きのピアニストにとり、この世界を担える弦楽器奏者は羨望の存在であった。
それが今回実現したということになる。編曲者は大物ながら、児玉麻里さんはあくまでベートーヴェン弾きの側から見た世界を主にしている。児玉麻里さんもベートーヴェンの弦楽四重奏曲をピアノ曲として弾くのはもちろん初めての経験である。
ベートーヴェン:
● サン=サーンス編:弦楽四重奏曲第7番 Op.59-1「ラズモフスキー第1番」
~第2楽章アレグレット・ヴィヴァーチェ・エ・センプレ・スケルツァンド
● サン=サーンス編:弦楽四重奏曲第6番 Op.18-6~第2楽章アダージョ・マ・ノン・トロッポ
● バラキレフ編:弦楽四重奏曲第8番 Op.59-2「ラズモフスキー第2番」~第3楽章アレグレット
● バラキレフ編:弦楽四重奏曲第13番 Op.130~第5楽章カヴァティーナ
● ムソルグスキー編:弦楽四重奏曲第16番 Op.135~第2楽章ヴィヴァーチェ
● ムソルグスキー編:弦楽四重奏曲第16番 Op.135~第3楽章レント・アッサイ
● サン=サーンス編:弦楽四重奏曲第7番 Op.59-1「ラズモフスキー第1番」
~第2楽章アレグレット・ヴィヴァーチェ・エ・センプレ・スケルツァンド
● サン=サーンス編:弦楽四重奏曲第6番 Op.18-6~第2楽章アダージョ・マ・ノン・トロッポ
● バラキレフ編:弦楽四重奏曲第8番 Op.59-2「ラズモフスキー第2番」~第3楽章アレグレット
● バラキレフ編:弦楽四重奏曲第13番 Op.130~第5楽章カヴァティーナ
● ムソルグスキー編:弦楽四重奏曲第16番 Op.135~第2楽章ヴィヴァーチェ
● ムソルグスキー編:弦楽四重奏曲第16番 Op.135~第3楽章レント・アッサイ
モーツァルト:
● ベートーヴェン編:クラリネット五重奏曲 K.581~第4楽章アレグレットと変奏曲
● ベートーヴェン編:クラリネット五重奏曲 K.581~第4楽章アレグレットと変奏曲
興味深いのは、サン=サーンス、バラキレフ、ムソルグスキーが原曲をただピアノに置き換えるのではなく、それぞれのピアニズムを反映させつつ完全なピアノ曲にしていること。
サン=サーンスとバラキレフは難技巧の要求されるピアノ曲が多く、それらと同様のレベルが要求されるものとなっている。超お宝がムソルグスキー編曲による第16番。ムソルグスキーはもっぱら編曲される側の作曲家で、彼の編曲は極めて珍しい。ムソルグスキーはベートーヴェンを崇拝しており、彼の激しく革新的な音楽の原点だったことを認識させてくれるのではないか。この編曲は楽譜が極めて入手困難なためムソルグスキー研究家の間でも伝説となっていたものだそうだ。それがついに音になったということになる。ベートーヴェン最後の弦楽四重奏曲の異常な感覚がムソルグスキーの異常な感覚とあいまって世にも稀な逸品となっている。
おまけとしてベートーヴェンがモーツァルトの名作「クラリネット五重奏曲」のフィナーレをピアノ独奏用に編曲したものも収められている。(HMVサイト記載情報による)
じつにいい素晴らしい企画力。
さっそく聴いてみた。
まず直感的に思ったのは、弦楽四重奏というストリングス的なサウンドを聴いている感じがしない、そんな面影が一切ない、まったく独立した立派なピアノ曲として体を成していることだ。
原曲を知らなければ、オリジナルのピアノ曲としてまったく違和感なく受け入れられる。
ピアノへの編曲版というのはオーケストラの交響曲をピアノ編曲版にしたものというのは何曲か聴いた経験はあるのだが、やはりそこには原曲の面影があって、置き換え感という感覚がどうしても漂ってしまう。(もちろんそのピアノ編曲バージョンはそれはそれでまた大変魅力的ではあります。)
ここではそういうものを感じない完全な独立したオリジナリティを感じますね。
それはやっぱりサン=サーンス、バラキレフ、ムソルグスキーというそれぞれの作曲家独自のピアニズムが色濃く反映されていて、原曲の面影がないからなのだと思います。
とても新鮮に感じます。
そしてやっぱりどうしても感じるベートーヴェンの音楽の様式感。ベートーヴェンのピアノ曲を聴くと、それはショパンでもない、モーツァルトでもない、ベートーヴェンらしい骨格感のある美しさ、厳格さがありますね。
男らしい旋律の中にふっと一瞬現れる女性的な美しい旋律がなんとも堪らなく美しいです。
そういうベートーヴェン音楽特有の様式感って絶対ありますね。
聴いていると、あ~やっぱりベートーヴェンだ、と感じてしまいます。
それは決してベートーヴェン・オリジナルの作品ではなく、サン=サーンス、バラキレフ、ムソルグスキーによる編曲版でもその気高い精神性は間違いなく伝わってきます。
そこはけっして損なわれていないと思います。
児玉麻里さんがベートーヴェンを生涯のライフワークにしているのもよくわかります。
今回のこのPENTATONEの録音は、オランダのヒルフェルムス、MCOスタジオ1で収録された。もうこのヒルフェルムスのMCOスタジオというのは、ポリヒムニアが専属契約してずっと使ってきているスタジオなのだ。PENTATONEの黎明期の録音の頃から大半のディスクでこのクレジットを見かけている。
コンサートホールに出張録音するか、このMCOスタジオなのか、のどちらかである。室内楽の録音が多いが、このようにスペースの大きいスタジオなので、オランダ放送フィルのようなオーケストラの録音でも使用されている。
そもそもオランダのヒルフェルムスというところは、オランダ中部北ホラント州の基礎自治体(ヘメーンテ)。ヨーロッパ最大のコナベーションエリアであるランドスタットの一角を占めているエリアだそうだ。
首都アムステルダムの南東30km、ユトレヒトの北20kmに位置している。1920年代から続く短波ラジオ局のラジオ・ネーデルランドなどのラジオ局、テレビ局が集中しているため、「メディアの街」と呼ばれている。
このスタジオ写真をずっと見てきた自分の予想なのだけれど、このMCOスタジオというのはテレビ、ラジオ公開放送用のスタジオではないか?と思うのだ。
写真で見ると観客席の奥行きが浅いのでコンサートホールとは思えないのだ。そうすると普通に公開録音するため、その観客用の座席で、そのための放送録音スタジオなのではないか、と思うわけだ。
だから壁にはきちんとコンサートホールのように拡散材パネルも装飾されている。
スタジオだから、MCOスタジオ1~5までと複数別れているのだと思う。
メディア街だから、こういう施設が多いのだろう。
メディア街だから、こういう施設が多いのだろう。
PENTATONE、ポリヒムニアはずっとこのMCOスタジオを愛用してきています。
自分はいままでPENTATONEの数多のアーティストがここを使っている写真を数多く観てきました。児玉麻里・児玉桃さんの「チャイコフスキー・ファンタジー」もこのMCOスタジオで収録されました。
児玉麻里さんと録音エンジニア・エルド・グロート氏とピアノ調律師マイケル・ブランデス氏。(c)Mari Kodama FB
ポリヒムニアのバランスエンジニア、録音、編集は、お馴染みエルド・グロート氏。
もう長年自分が聴いてきた期待を裏切らない録音ですね。
ポリヒムニアがピアノ録音を録るとまさにこういう音がします。
ピアノ録音の素晴らしさで定評のあるDGは、どちらかというと硬質でクリスタル感のある音色なんですよね。ピンと張りつめたようなそういう透明感が命みたいな・・・。
でもポリヒムニア、PENTATONEが録るピアノの音は、温度感が高めで、質感の柔らかい音色なんですよね。彼らの録るピアノの音は昔からこういう音がします。
一発の出音を聴いた瞬間、あ~やっぱりと思いました。(笑)
ピアノ録音のオーディオ再生で大切なことは、打鍵の一音一音に質量感が出るような再生ができるかどうか、ですね。このニュアンスが出るとピアノのサウンドは最高の鳴り方をしますね。
児玉麻里さんの今回の録音、じつに素晴らしいです。
期待裏切らないいつも通りのサウンドでした。
期待裏切らないいつも通りのサウンドでした。
最後にブックレットの中に記載されている児玉麻里さんの今回の新譜に対する寄稿コメントを紹介しておこう。
PENTATONEの新譜は、必ずブックレットの中で冒頭にアーティストに寄稿をさせる。
それが彼らのスタイルなのだ。
この児玉麻里さんの寄稿には溢れんばかりのベートーヴェン愛と尊敬の念が記されている。
”真の芸術は、頑強なものである。”
おそらくルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンほど私を大きく揺り動かしてきた芸術家はいないであろう。この数十年間、私はこの個性的な作曲家とともに歩んできた。私は子供のとき、ティーンエージャーのとき、そして学生のとき、そして今なお、コンサートで彼の曲を弾いている。
私はベートーヴェンとともに生きてきたし、彼の音楽を聴いてきた。
そして彼をもっと深く理解したいとずっと努力してきたし、特に、彼の作曲技法の複雑さや深さ、そしてそれが与えるインパクトについて理解したいと思ってきた。この男は実際のところどのような男なの?ときどき、もし私が彼に会えるチャンスがあるとしたら、彼に何を聞くべきかを考えることがある。
この数十年の間、ベートーヴェンは私の芸術作品という観点からだけでなく、自分の人生の哲学者でもあってきた存在だった。それはどうして?それはあきらかに、彼の芸術作品やそう至るまでの中で表現してきた考え方の中に、”真の芸術は、頑強なものである・・・それはけっして見かけのいい綺麗な形に抑制することはできない。”という言葉があるからだ。
彼は耳が不自由であったにもかかわらず、他人と会話をすることを助けた1820年の会話本の中にそう書かれている。この本では、彼にとってあきらかにネガティブなことではなく、そして彼の芸術に関することだけでもなく、個人の尊厳に寄与する個人の自由、人間の主張についての考え方がまとめられている。
しかしながら、同時に、この自由を自分のものとし、それを発展させ、従来の伝統的な考え方を超えるなにか新しいものをつねに探し創作する責務についてもまとめている。
彼の作品にはすべて、己で決め、己で理解すること、そしてそれを前へ動かし成長させることが要求される。これは常に彼自身がおこなってきたことであり、すべての作曲の中に新しい音楽的手法をつねに探しながら、彼の時代の作曲技法を超えるなにかを見つける、そしてそれが彼の曲にある偉大なるダイナミズムにもなる要因ともなっていた。
彼は決して同じことを繰り返さなかった。
私は彼のそのような姿勢をとても楽観主義なものとして捉えていた。彼の作品には大きな希望がある。そして人間は自分の個性を守るためと、それをさらによい方向へ発展させるために、その知性を喜んで使うことができる。彼は自分の人生がもっとも深い暗闇の中にあろうとも決して希望を諦めなかった。
それが私に深い影響を及ぼしてきた彼の音楽である。
ベートーヴェンは間違いなく、私の中にある楽観主義に大きな貢献をしてきた。
このレコーディングでは、私はいつもとはまったく違う側面からベートーヴェンにアプローチした。初めて、彼の弦楽四重奏から抜粋してピアノで演奏した。これは私にとって大変感動的な体験であった。ピアニストとして、私は彼のその弦楽四重奏の作品を聴いてきたが、そのときはそのモダンでパイオニア的な手法という観点から非常に彼を尊敬していた。演奏家にとってピアノを弾かずに、ただ聴いているだけというのは、子供が手の中に収めてみたいという、いわゆる把握したい、触りたいという観念にとらわれているのを禁じられているような感覚に似ている。
それはスコアを勉強して、その作品に深く入り込み、私自身がどのように弾こうか、どのように音楽を奏でていくか、という気持ちからくるものであった。
結果として、サン=サーンス、ムソルグスキーやバラキレフのような有名なベートーヴェンの弦楽四重奏のピアノ編曲版を勉強することでベートーヴェンと彼の作品へ新しくアプローチすることが可能となった。
まず最初にいま私が弾くことができるベートーヴェンの後期の作品のパートを弾く、その3人の作曲家との違いが理解できるように。そしてつぎに私にとって同じような感覚のパートを彼らの作品の中で探して弾けるようになる。そうすることでベートーヴェンにより近づくことができるし、彼を完全に理解することができる。
これらのピアノ編曲版を弾けるようになって、実際のところその作業はピアノ編曲というより、アレンジというか、やや詩的適応という感じの作業なのだけれど、おかげでこれら3人の作曲家がどのようにベートーヴェンを理解しているのか、どのようにベートーヴェンの弦楽四重奏のエッセンスを正確に表現しているのか、そしてどのように彼ら独自の音楽性を盛り込んでいるのか、そしてそれゆえにベートーヴェンが絶えず要求していた頑強さというのを、正確に表現できていたかを学ぶことができた。
このような編曲版を演奏できる機会を得ることができて、たとえベートーヴェンその人の作品でなくても、サン=サーンス、ムソルグスキーやバラキレフ、彼らによるベートーヴェン観を、学ぶことができたのではないか、と思っている。
編曲版で表現されているように、彼らの解釈は、私にとって、よりベートーヴェンに対してより理解が深まり、新しいベートーヴェン像を描き切ってくれたと間違いなく思います。この録音を聴いてくださる皆様方にとっても同じであるように。
児玉麻里
Mari kodama
DGの新譜:庄司紗矢香のベートーヴェン [ディスク・レビュー]
今年2020年は、ベートーヴェン生誕250周年イヤー。
日本のみならず世界中、クラシック業界、ベートーヴェン一色で盛り上がる。そのような中で、自分がベートーヴェンの録音で取り上げたいのは、庄司紗矢香のベートーヴェン・ヴァイオリン・ソナタ全集とベートーヴェン・ヴァイオリン協奏曲の2枚。
ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全集
庄司紗矢香、ジャンルカ・カシオーリ(4CD)
庄司紗矢香、ジャンルカ・カシオーリ(4CD)
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲
シベリウス:ヴァイオリン協奏曲
シベリウス:ヴァイオリン協奏曲
庄司紗矢香、ユーリ・テミルカーノフ&サンクト・ペテルブルク・フィル
なぜ庄司紗矢香さんのアルバムを選ぶのか、というと、自分がいままできちんと庄司紗矢香というヴァイオリニストに面と向かい合っていなかったと感じていたからである。
庄司さんの実演は、いままで2回ほど経験した記憶がある。初めての体験は、水戸芸術館館長で音楽評論家の故吉田秀和さんが命名結成した「新ダヴィッド同盟」。2010年に結成された水戸芸術館専属の室内楽ユニットである。
ヴァイオリン 庄司紗矢香、佐藤俊介
ヴィオラ 磯村和英
チェロ 石坂団十郎
ピアノ 小菅優
庄司さんの呼びかけで集まった、気心の知れた若い音楽仲間と、庄司さんの尊敬する東京クヮルテットメンバーの磯村和英によって構成される。
懐かしいなぁ。あのときはかなり話題になっていました。
佐藤俊介さんもいたんだね。いまやオランダバッハ協会芸術監督への大出世。
佐藤俊介さんもいたんだね。いまやオランダバッハ協会芸術監督への大出世。
小菅優さんもいます。
佐藤俊介さんと小菅優さんのコンビで、松本ハーモニーホールでの公演も聴いたことがあります。
この新ダヴィッド同盟のコンサートを体験したくて、水戸芸術館まで足を運んだのでした。
忘れもしない、2011年12月17日(土)の冬の日のコンサート。
シューベルトやモーツァルト、シェーンベルク、そしてブラームスの室内楽をやった。
それが庄司さんの生演奏を体験した初体験。
でもP席だったんですよね。(笑)
ここに、自分のまず1回目の悔いるポイントがある。
後ろ姿で庄司さんはじめ、みんなの演奏姿を拝見していた。
後ろ姿で庄司さんはじめ、みんなの演奏姿を拝見していた。
記憶が薄っすらだけれど、若手の演奏家らしい初々しくて勢いのある歯切れのいい演奏だったように記憶している。
そして2回目が、これも忘れもしない2012年の10月の東京文化会館の大ホールでの相方ジャンルカ・カシオーリとのヴァイオリン・リサイタル。
リサイタルなのに、小ホールではなく大ホールでやっていた。
おそらく主催者側の判断による集客数目的なのかもしれないが、それでも大ホールが超満員で埋まっていたような記憶がある。
なぜ、このコンサートが自分にとって忘れ得ないのか、というと、ちょうどその数日前かあるいは前日に、ゴローさんが亡くなったからだ。エム5さんの日記でそのことを知って、その翌日か、数日後のコンサートが、この庄司紗矢香さんの東京文化会館大ホールでのヴァイオリン・リサイタルだったのだ。
自分に親しい人が死ぬってこんなにつらいことなのか?
自分の親が死ぬよりショックを引きづっていた。
ステージで庄司さんが演奏するその姿はただ目に映っているだけ。
そしてその奏でるヴァイオリンの音色もただ、左の耳から入って、右の耳に抜けていくだけ。
人を失う悲しみで胸が締め付けられるような苦しみ。
コンサート中に、つい弱音を吐きましたもん。
「こりゃダメだ。全然ダメだ。」
コンサート中に、つい弱音を吐きましたもん。
「こりゃダメだ。全然ダメだ。」
結局、おそらくは名演だったであろう庄司紗矢香のヴァイオリン演奏は、まったく身に入ってこなかった。演奏中、ずっとゴローさんとのセンチな感傷に浸ってばかりいて、まったく演奏を覚えていない。
そのように自分にとって、庄司紗矢香というヴァイオリニストは、不運にもとても残念な体験しかなかった。
録音アルバムは、プロコフィエフのヴァイオリン・ソナタを1枚持っている。
当時、とても話題になったアルバムで、演奏、そして録音とも素晴らしい出来栄えであった。
当時、とても話題になったアルバムで、演奏、そして録音とも素晴らしい出来栄えであった。
あれから8年経過した訳だが、どうしてもここで自分が庄司紗矢香というヴァイオリニストときちんと対峙したい、しっかり自分が理解したいという衝動に駆られ、そのタイミングにベートーヴェンイヤーに相応しいベートーヴェン・アルバムをリリースしてくれたこと。
そしてサロネン&フィルハーモニア管弦楽団の来日公演でソリストとして登場すること。
この2つが相重なって、これはいまがまさに”その時”なのだと思ったのだ。
この2つが相重なって、これはいまがまさに”その時”なのだと思ったのだ。
自分が庄司さんの存在を知ったときの印象は、1999年、パガニーニ国際ヴァイオリン・コンクールにて史上最年少で優勝、という印象が圧倒的に大きくて、数々の名門オケや指揮者との共演を果たし、海外を活動の拠点とするアーティストというイメージがまず頭にあった。
それでどちらかというと”若手の有望株”、”若手スター”、という・・・1999年からずいぶん年数は経っているけれど、いつまで経っても自分の中では永遠の若手で、いわゆる自分の年代とはやや隔世感がある感じ、なぜかちょっと世代のギャップを感じる存在だった。
自分がオヤジなだけだと思いますが。(笑)
やっぱり過去にしっかりとした審美眼で演奏姿を見ていないからだ、と思いました。
だからこそ、今回の実演に接するのは最高に楽しみで最大の試練だと思ったのです。
まず、アルバムからの感想。
ベートーヴェン・ヴァイオリン・ソナタ全集のほうは、2009年~2014年に録音されたものを今回ベートーヴェンイヤーということで、全集発表したもの。ぞれより前に、スプリングソナタこと第5番の「春」やクロイツェル・ソナタの第9番「クロイツェル」などは先行してアルバムとして発売されたようだが、こうやってきちんと全集として全10曲をまとめたものは今回が満を持して発表ということになる。
全曲録音を完成させたとき、2016年に全曲完成記念といういうことで日本縦断ツアーもおこなったようである。ベルリンとハンブルクで録音されたようで、非常に録音がよくて、聴いていてすぐに気に入ってしまいました。
大方の人にとっては、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタと言っても、「春」や「クロイツェル」くらいしか馴染みがないことだろう。自分もそうである。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタを全曲聴くには相当な努力が必要なことは明らか。自分もこの日記を書くためにこのアルバムで全曲通しで聴くことを2回やった。かなりエネルギーを消耗した。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲を通して聴くということは、一人の音楽家がどのように自己の精神と向き合い、どのようにそれを音楽に昇華させていったかということを目の当たりにする、またとないチャンスなのだろう。
録音ではプロコフイエフのソナタしか聴いたことのなかった庄司さんのヴァイオリンだが、きちんと根の張った非常に力強い音を奏でる奏者だな、と感じた。ご本人のシルエットからするとどちらかというと線が細くてパワーがない感じにも思えてしまうのだが、全然その真逆を行く感じだった。
解釈自体もとても現代的なニュアンスを感じ取れる新鮮さがあり、現代を代表するベートーヴェン・ヴァイオリン・ソナタ全集と言っても過言ではない出来上がりとなっている。
ベートーヴェン・ヴァイオリン協奏曲は、シベリウスのヴァイオリン協奏曲とカップリングになっている。
ベートーヴェンは奏者にとって難しいコンチェルトだが、見事な演奏を披露してくれている。
余談になってしまうが、自分にとって、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲で最高のパフォーマンスだと思っているのは、カラヤン生誕100周年イヤーのときのウィーン楽友協会で演奏された小澤征爾さん&ベルリンフィルでアンネ=ゾフィー・ムターの演奏。新しい近代解釈の演奏としてこれに勝る演奏には出会ってませんね。
Blu-ray&DVDになっています。
いままでベートーヴェンのコンチェルトはどこか地味というか、乗り切れないまどろこっしさを感じていたのだけれど、このムターの演奏を見て、この曲の良さがわかったというか、この演奏でこの曲に開眼したのでした。この演奏を観て、ゴローさん曰く、「ムター、ウマすぎなんだよ。」と吐き捨てた瞬間に同席していました。
そういう点から判断してしまうと、なかなか厳しいものがありますが(どうしてもこの曲を聴くと、自分の頭の中にはムターの演奏が教科書として存在してしまうために、どうしても比較してしまうのです。)、庄司さんの演奏も説得力あるものだと思います。
今回、1/23と1/28に開催されたサロネン&フィルハーモニア管の演奏会では、庄司さんはシベリウスとショスターコヴィチの協奏曲を披露してくれた。
あとで、レビューするが、シベリスも良かったけれど、ショスターコヴィチのコンチェルトは凄すぎた!
みんな大絶賛の感想で溢れていたが、まさに”神がかっていた!”というのはまさにその通りだと思う。
庄司さんのショスターコヴィチのアルバムは持っていないので、ストリーミングでもう一回聴いてみる。
ソニーにはなくて、アマゾンにしかないのだが、なんとアダージョ版しかなく、楽章が抜け抜けなんですよね。
なんでそんなことするのかな?
でもその破片のアダージョ版を聴いてもあの晩のあの興奮が蘇ってくる。
もうこれは我慢できない。
もうCD買うしかありませんね。
ショスターコヴィチ ヴァイオリン協奏曲第1番、第2番
庄司紗矢香、リス&ウラル・フィル
あの神がかっていたあの日の演奏をもう一回味わいたいと思います。
サロネンにとって、フィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者、芸術監督としては最後の任期としての来日公演。いままさにサロネン・ウィーク。
東京芸術劇場に馳せ参上した。
1/23の座席
1/28の座席
1/23の日は、当初はサロネン作曲のチェロ協奏曲が演奏される予定だったが、チェロ奏者の急病により、代役として庄司さんが、シベリウスのヴァイオリン協奏曲を演奏することになった。まさに急遽のピンチヒッターである。
8年振りに姿を拝見する庄司紗矢香さん。
女性ヴァイオリニストのノーマルなドレスと違って、パンツスタイルなど、ちょっと新人類っぽくて、やはり自分にとってはいつまで永遠の若手スター、というイメージが崩れない。
シベリウスはおそらくご自身の得意のレパートリーなのだろうけれど、それでも急なピンチヒッター。それで、よくぞここまでの見事な演奏を魅せてくれた。
フィンランドの湖畔の風景がそのまま頭に浮かんできそうな寒色系の旋律、自分の大好きなシベリウスコンチェルトだが、もうゾクゾクと体の震えが止まらなかった。
ようやく直に集中して拝見できた庄司紗矢香のヴァイオリン奏法。
奏法は非常にオーソドックスで教科書のようなクセのない綺麗なフォーム。華奢で細身だが、力強さがあって、剃刀のような切れ味の鋭さがある。音色にキレがあるので、かなり場内を威圧するパワーあります。
細身だけど音量もかなり大音量派です。
音色のキレ、威圧感、そして大音量。。。
と来るので、かなり聴衆に感動させる要素持っていると思います。
それをまざまざと体験させてくれたのが、2日目のショスターコヴィチのヴァイオリン協奏曲。
普段あまり聴かないコンチェルトだけれど、こんなに素晴らしい曲だったとは!(笑)
前衛的で、現代音楽っぽくて、いかにもオーディオファンが喜びそうな音のすき間を確保しながら、エネルギー感のある音を連発。
そして誰もが絶賛した第3楽章のパッサカリアのカンデンツア。
場内シーンと誰一人固唾を飲んで見守る中、延々と雄弁に語り続ける。
そして第4楽章にそのまま流れ込む。
終止のとき、思わず感嘆の漏れ声が出てしまう。
ふつう終演のときは、ブラボーや歓声も客の方で事前に意識系でやっているのが多い中で、今回は、本当に思わず漏れ出てしまったという人間の本能のありのままの声が出てしまった・・・という感じ。
もうこの意識系と本能での歓声(溜息に近い)の違いはあきらかに聴いていて違います。
それだけ、まさに神がかっていました。
自分も鑑賞歴としてはベテランの領域ともいえるヴァイオリンの演奏会で久し振りに興奮しました。(笑)
長い間、庄司紗矢香というヴァイオリニストに抱いていた不完全燃焼な気持ちが一気に吹っ切れた感じでよかったです。
サロネン&フィルハーモニア管の演奏会については、多くの人が書かれると思うので、私の方では割愛。
でもあのすざましいダイナミックレンジの音を、ある決められた器の中にコンプレッション(圧縮)したりしたら、あの迫力って絶対損なわれると思いますね。初日、NHKが収録していましたので、放映されると思います。ライブ生演奏であれだけ大感動したのに、収録放送を見ると、全然迫力がなくてガッカリした、というのは、まさにそういうことだと思います。
(c)庄司紗矢香Twitter
(c)庄司紗矢香Twitter (Hikaru)
東京芸術劇場 海外オーケストラシリーズ
フィルハーモニア管弦楽団
指揮:エサ=ペッカ・サロネン
ヴァイオリン独奏:庄司紗矢香
2020/1/23(木)19:00~
ラヴェル/組曲「クープランの墓」
J.シベリウス/ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
J.シベリウス/ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
休憩(インターミッション)
ストラヴィンスキー/バレエ音楽「春の祭典」
ソリストアンコール
パガニーニ
「うつろな心」による序奏と変奏曲から”主題”
パガニーニ
「うつろな心」による序奏と変奏曲から”主題”
2020/1/28(火)19:00~
J.シベリウス/交響詩「大洋の女神」
ショスターコヴィチ/ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 OP.77
ショスターコヴィチ/ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 OP.77
休憩(インターミッション)
ストラヴィンスキー/バレエ音楽「火の鳥」全曲(1910年原典版)
ソリストアンコール
シベリウス「水滴」
シベリウス「水滴」
オーケストラ・アンコール
ラヴェル「マ・メール・ロワ」より「妖精の園」
ラヴェル「マ・メール・ロワ」より「妖精の園」
シューマン ヴァイオリン協奏曲 [ディスク・レビュー]
アラベラさん、やはり無理だったんだねー。仕方がないね。去年のクリスマスに待望のお子さんを授かり、出産したばかり。本来であれば、今年の3/5(サントリーホール)と3/7(横浜みなとみらい)に、読響とシューマンのヴァイオリン協奏曲を披露してくれるはずだったのだ。
ところがこんなお知らせのハガキが届いていた。
「3月5日(サントリーホール)と3月7日(横浜みなとみらい)に出演を予定していたヴァイオリニストのアラベラ・美歩・シュタインバッハーは、本人の都合により出演できなくなりました。代わって、ドイツの名手カロリン・ヴィトマンが出演します。曲目の変更はございません。」
無理しないでゆっくりと休んでください。お母さんが代わりに面倒見てくれるという感じなのかな、とも思っていたが難しかったようですね。いいよ、いいよ、無理しないこと。
この公演で楽しみにしていたのは、シューマンのヴァイオリン協奏曲。
数多のヴァイオリニストを聴いてきたけれど、そしてたくさんのヴァイオリン・コンチェルトを聴いてきたけれど、シューマンのコンチェルトは聴いた記憶がない。シューマンがヴァイオリンのコンチェルトを作品として遺していた、ということも知らなかった。アラベラさん、なぜシューマンなの?という感じで、とてもレアな体験ができるのかもしれない、と楽しみにしていた。幸いにもピンチヒッターだけれど曲目に変更がないということだから、レアな体験は楽しめそうだ。主催者側の配慮に感謝である。
ピンチヒッターは、カロリン・ヴィトマン。
ミュンヘン生まれの女性ヴァイオリニスト、カロリン・ヴィトマン。彼女の兄は2016年7月に来日し、オーケストラ・アンサンブル金沢を指揮した作曲家、クラリネット奏者イェルク・ヴィトマンであり、彼女自身も来日経験があるなど、すでに日本では知られた存在。
デビュー当初は現代音楽のスペシャリストとして活動していたが、ECMへ録音を行うようになってからは、シューベルトやシューマンなどロマン派の作品でも独自の解釈を施し、雄弁かつ抒情的な演奏を聴かせている。そんなヴィトマンの最新録音は、メンデルスゾーンとシューマンの2作の協奏曲で、有名過ぎるメンデルスゾーンのホ短調と「演奏不能」とまで評されたシューマンの作品を、彼女はオーケストラを絶妙にコントロールしながら鮮やかに描き出している。
ベルリン・フィル、バイエルン放送響、ライプツィヒ・ケヴァントハウス管、フランクフルト放送響などと共演し、ザルツブルク音楽祭などで活躍。ラトル、シャイー、ノリントン、ヤノフスキ、カンブルランらと共演している。ECMレーベルからリリースされたシューマンのヴァイオリン協奏曲のCDは評価が高く、数々の賞を受賞した。
これが彼女の演奏家としてのキャリア。
自分は実演に接したことがないけれど、このキャリアを見る限り、かなりの実力派。一流の最先端の道を歩んできているのがよくわかる。
そしてなんと言っても所属レーベルがECMなんだよね。
調べたらECMから5枚のCDをリリースしている。
調べたらECMから5枚のCDをリリースしている。
シューマンのヴァイオリン協奏曲の入った注目のアルバムがこれ。
メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲、シューマン:ヴァイオリン協奏曲
カロリン・ヴィトマン、ヨーロッパ室内管弦楽団
カロリン・ヴィトマン、ヨーロッパ室内管弦楽団
2014年7月にバーデン・バーデン祝祭劇場で録音されたアルバム。
ヨーロッパ室内管弦楽団は、イギリス・ロンドンを本拠地とする室内オーケストラ。1981年にECユース管弦楽団(現EUユース管弦楽団)の出身者を中心としてクラウディオ・アバドにより自主運営団体として設立された。音楽監督などは置かず、様々な指揮者・ソリストと共演しているが、アバド、ジェームズ・ジャッド、ニコラウス・アーノンクールらが中心に客演している。団員が若く、一般的に敬遠されるノーノやシュトックハウゼンなどの現代音楽もこなすため、アバドなどが録音にこのオーケストラを起用している。
アバド&ヨーロッパ室内管は、何枚かCDを持っているので、親しんでいたが、自分はアバドのオーケストラだと思っていた。でも基本は音楽監督を置かずに、いろいろな指揮者に客演されているオケなんですね。
シューマンのコンチェルト以外にもメンデルスゾーンのコンチェルトも入っている。
自分はおそらく、そして間違いなくいままで通ってきたヴァイオリン協奏曲のコンサートの中で1番実演に接しているのがメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲。アラベラさん1人だけで5回は体験している。もうたくさんヴァイオリニストのメンコンを聴いてきた。
メンデルスゾーンは、おそらく主催者側からすると、1番集客しやすい曲なんでしょうね。
この曲を選んでおけば間違いない・・・というような。。。
女性的で春のシーズンがとても似合う美しい曲ですね。
実演、そして録音と、いろいろなヴァイオリニストのメンコンを聴いてきたので、この曲の演奏を聴けば、そのヴァイオリニストがどのようなタイプの演奏家なのかが、わかってしまうと言っても過言ではない。
今回カロリン・ヴィトマンのこのアルバムに録音されているメンコンを聴いて、彼女に抱いた演奏スタイル。
フレージング、フレーズの納め方は比較的クセのない演奏をするタイプ。かと言って、女性的かというと、そういう感じでもなく、弓の返しとかボーイングの力強さが随所に感じ取れるようなアクセントの強さが曲間の至る所に感じる。かなり男性的な力強い演奏をするヴァイオリニストなのではないか、と思いました。
デビュー当初は現代音楽のスペシャリストだったというから、そういう鋭利感のシャープな切れ味は天性として持ち合わせていると感じますね。
演奏する姿を見たこともなく、ただメンコンの録音を聴いているだけで想像する姿です。
そしてシューマンのヴァイオリン協奏曲であるが、自分は実演でも録音でも聴いたことがない。あれ?シューマンってヴァイオリン協奏曲って書いていたっけ?という感じで寝耳に水だった。
調べてみると、作曲者シューマンの死後80年間忘れ去られていた作品だったそうだ。
わずか2週間程度で作曲されている。
ヨーゼフ・ヨアヒムの要請を受け、またシューマン自身もヨアヒムが弾くベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を聞いて感銘を受け、このヴァイオリン協奏曲を書いた。しかし、なぜかヨアヒムはこのヴァイオリン協奏曲を取り上げることなくシューマンの自筆譜を封印し、クララ・シューマンは「決して演奏してはならない」と家族に言って聞かせていたという。
それは、シューマンがライン川に身を投じる直前に書き上げていたピアノ曲「天使の主題による変奏曲」の主題と協奏曲の第2楽章が酷似していたためだという。
シューマン自身はこの曲を、「天使から教えてもらった曲だ」と語っていた。
結局シューマンのヴァイオリン協奏曲は、1937年にベルリンの図書館でヨアヒムの蔵書から発見されるまで陽の目を見ることはなかった。世界初演はナチス・ドイツの宣伝省主導で、同年11月26日にゲオルク・クーレンカンプの独奏、カール・ベーム指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の共演で行われた。
しかしこのときの演奏は、クーレンカンプ曰く「シューマンの自筆譜のままでは演奏不可能」として、自身が大幅に書き換えた版によるものであった。実際にクーレンカンプが言うように演奏不可能な箇所はあるが、クーレンカンプの改訂は演奏不可能な箇所を修正するだけではとどまらないものとなっていたそうだ。
また、パウル・ヒンデミットもこの改訂にかかわった(ノルベルト・ホルニック)。翌12月にセントルイスでアメリカ初演を行ったユーディ・メニューインが「自分こそが真の初演者」と宣言するほどであった。
20世紀後半以降に録音の増えてきている曲であるが、それでもシューマンの他の協奏曲に比べると今日も演奏の機会は少ない、とのこと。
どうりで知らないはずだ。
だからいまのシューマンのヴァイオリン協奏曲というのは、シューマン以外の人による改訂版なんだね。シューマンのこのコンチェルトは、よく「演奏不能」と呼ばれているのは、こういう経緯がある、ということもわかりました。
さっそくシューマンのヴァイオリン協奏曲を聴いてみたい。
それも今回のピンチヒッターのカロリン・ヴィトマンの録音で。
それも今回のピンチヒッターのカロリン・ヴィトマンの録音で。
こういうときにストリーミングは大活躍します。
CDを買うまでいかず、とりあえずどんな曲なのかを聴いてみたい、というだけの目的。
すぐその場で検索して聴けちゃうのだから本当に便利。
すぐその場で検索して聴けちゃうのだから本当に便利。
そして実際聴いてみて、よかったらパッケージソフトのほうも買えばいい。
自分はやはり気に入った音源は物理媒体として手元に残しておきたい所有感の旧世代の人なので。
自分はやはり気に入った音源は物理媒体として手元に残しておきたい所有感の旧世代の人なので。
こういうストリーミングの利便性は、Spotifyを昔からやっている人は当たり前のことなのかもしれないけれど、自分はストリーミングはつい最近始めたので、その利便性に今さながら感心している。
Spotifyはやっぱりロッシー(損失)の非可逆の圧縮音源なんですよね。
これが自分は気に入らなかった。
これが自分は気に入らなかった。
音楽データを圧縮するということは、特に高域成分が失われている場合が多く、音のアタック感とか失われ、聴いていると、角がとれた丸みの帯びた音に聴こえるんですよね。
ポータブルオーディオで聴いている分は、そういう圧縮音源の態様はあまり気にならないのだけれど、きちんとしたオーディオ装置で聴くと一発でわかってしまう。きちんと本気出して椅子に座ってオーディオ鑑賞しようとすると、圧縮音源はとても鑑賞に堪えられないです。
元の音のデータを削ってしまうということは、やはりしてはいけないことです。
どうしても伝送路が細く、データ容量を少なくしないといけないというコンシューマ的な理由以外では・・・です。
だから自分はSpotifyに手を出さなかった。自分がストリーミングをやるならハイレゾ・ストリーミングから始める、とずっと誓っていたのでした。
日本にも2つのハイレゾ・ストリーミングがローンチしたけれど、自分の使い方は、ソニーのmora qualitasがメインでAmazon Music HDがサブという位置づけ。
やっぱりソニーのほうが音がいいから。
ソニーで楽曲検索して、希望の曲が存在しなかったら、Amazonのほうで探す、という使い方。
さっそく今回のカロリン・ヴィトマンのシューマンのヴァイオリン協奏曲をmora qualitasで検索。
そうするとあった!
全アルバム5枚とも登録されていた。
さすがECMレーベルだけあって、どのアルバムもジャケットがECM特有の寒色系の感じがいいですね。
さっそくシューマンのヴァイオリン協奏曲を聴いてみる。
有名なヴァイオリン協奏曲というのは、やはりきちんとした音楽としての造形がありますね。
ポップスでいうところのフックの仕掛け(聴いている人がついつい惹きつけられるサビのメロディ)がきちんと存在するし、音楽としての型がきちんとしている。
シューマンのヴァイオリン協奏曲を聴いていると、そこら辺のいわゆる音楽の型というのが、曖昧でこなれていないというか、聴いている側にとって脳裏に焼き付けられるほどのインパクトがどうしてもありませんね。散文的な構造なんですよね。
そこに2週間足らずで作曲した推敲を重ねた作品ではないこと、シューマンのヴァイオリン協奏曲へのアプローチが手探りであったことが慮れます。
だから自分のものにするには、何回も聴き返さないといけない。
それでも曲としての特徴を捉えるのは難しかった。
それでも曲としての特徴を捉えるのは難しかった。
いわゆるヒット・ソングではないと思います。
でも何回も聴き返すと、そのわかりにくさのベールが剥がれてきて、その渋さ、自分への引っ掛かり方がわかってきます。
結構ヴァイオリンが走ってオーケストラを引っ張っていくという感じよりも、対等な感じですね。オーケストラの重厚な弦の音色が朗々と鳴るパートが多く、結構自分はヴァイオリン協奏曲としてはちょっと珍しいなと思いました。
対等な関係といえば、あのベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲と同じですね。
たぶんヴァイオリニストにとってやりずらいというか難しい曲なのかもしれません。
たぶんヴァイオリニストにとってやりずらいというか難しい曲なのかもしれません。
そもそもこのシューマンがヴァイオリン協奏曲を作曲しようと思ったきっかけが、シューマン自身がヨーゼフ・ヨアヒムが弾くベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を聞いて感銘を受けことから、このヴァイオリン協奏曲を書いたと言われている。
だからベートーヴェンのコンチェルトに似ているのもそりゃ当たり前のことなのかもしれない。
ヴァイオリンのソロパートも結構ハイスキルなテクニックがあり、カロリン・ヴィトマンの男性的なパワフルな奏法と相まって、スリリングを味わえます。
そしてその第2楽章が美しいです。
シューマンのヴァイオリン協奏曲。
曲としての全体のイメージ、音楽の型を捉えるのは難しい曲だけれど(いわゆる渋い曲)、ヴァイオリニストとしてはテクニックが必要な曲。というのが自分のこの曲への第一印象です。
3/5(サントリーホール)、3/7(横浜みなとみらい)で、この曲の実演に接するわけですが、正直貴重な経験だし、かなり楽しみになってきました。
PENTATONEの新譜:クラリネット奏者 アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ デビュー! [ディスク・レビュー]
これは思わずジャケット買いしてしまうだろう!(笑)その瞳にす~っと吸い込まれるように魅了されるそのシルエット。まさに、いつしかカラヤンの前に颯爽と現れたザビーネ・マイヤーの再来のような衝撃だ。
何者なのだろう?
このたび、PENTATONEレーベルと長期契約を締結し、このレーベルからデビューしたクラリネット奏者である。この情報を掴んだときは、まだ日本のサイトに十分な情報が掲載されていなかったので、騒然な騒ぎになってしまったが、それも落ち着いてきて、どうやら素性が判明したようだ。
![64826168_2304901013109158_2799493935896985600_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_64826168_2304901013109158_2799493935896985600_n5B15D.jpg)
クラリネット奏者アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ。
ベルギー出身である。
最難関のコンクールとして知られるミュンヘン国際音楽コンクールで優勝(2012年)後、英BBC選出の“新生代アーティスト” やボルレッティ=ブイトーニ財団アワード2018を受賞するなど、今最も期待される新進気鋭のクラリネット奏者なのだそうだ。
ザビーネ・マイヤー、ヴェンツェル・フックス、アレッサンドロ・カルボナーレ、パスカル・モラゲスといった錚々たるクラリネット奏者に師事してきたヴァウヴェは、2017年夏のBBCプロムスのデビュー後、2018年にはロイヤル・アルバート・ホールやカドガン・ホールにてトーマス・ダウスゴー指揮BBCスコティッシュ交響楽団との共演でモーツァルトのクラリネット協奏曲を披露するなど、イギリスを中心に全ヨーロッパで注目を集めている俊英である。
ベルギー出身で、イギリス中心に活躍している、というのが素晴らしい!
間違いなく自分の人生に関与してくる運命のスターだ。(笑)
現在は、ベルギー・ブリュッセルに在住で、アントワープ王立音楽院やムジカ・ムンディ音楽学校で教鞭を取っているようだ。
![53738093_1052083261640352_1570930141582852096_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_53738093_1052083261640352_1570930141582852096_n5B15D.jpg)
現在は、クラリネットのソリストとして華々しくデビューしたが、今後は、ザビーネ・マイヤーのように、どこかのオーケストラの木管セクションのクラリネット奏者としてもキャリアを広げつつ、アルバムはソリストとして出していくという二束のわらじの選択肢になっていくのだろう。
自分は木管楽器ではオーボエが1番大好きなのであるが、名だたるオーボエ奏者も、みんなそうだ。オーケストラの首席奏者として活躍しながら、ソロのアルバムも出す、というような路線。
まさに木管奏者の王道の道ですね。
ソリストとしてのみの道だと、やはり音楽家としての音楽性の素養を磨いていくには不十分。
オーケストラの奏者としての経験を積むのは絶対必要ですね。
どこのオーケストラに所属することになるのか、いまから楽しみである。
でも現在、ベルギーの音楽学校に勤務していることから、職業としての専任音楽家としてどこまでやれるか、の判断はありますね。
2012年のミュンヘン国際コンクールで優勝して、音楽家として生きていく道筋を立てて、その後の5年間、いろいろな名クラリネット奏者に師事をして、満を持して2017年夏のBBCプロムスでデビューということだから、本当につい最近出てきた奏者なんだね。
そして今年2019年にPENTATONEと長期契約して、アルバムのほうでもデビューだ。
ご覧のような美人でフォトジニックな奏者で、音楽的才能も抜群。あとはこれから何十年もかけて、自分をどう成長させていくか。。。まさにこれからの奏者だ。
PENTATONEはじつにいい仕事、NICE JOBをしたと思うよ。
敢えて、難を言わせてもらうならば、名前が難しすぎて読みづらい、ということだろうか?(笑)ベルギー人はみんなこのような名前だからね。スターの要件のひとつとして、誰からも名前を簡潔に呼びやすい、というのがあります。それがちょっと心配です。
その後、たぶん略した愛称ニックネームみたいなものが、みんなが作ってくれると思うよ。
今回PENTATONEからアルバム・デビューするにあたって、アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ本人、そしてPENTATONEのVice President レナード・ローレンジャー氏がライナー・ノーツにこのような寄稿をおこなっている。
●ライナーノーツのアンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェのコメントからの引用。
いま、PENTATONEレーベルのアーティスト・ファミリーの仲間入りができたことは、とても熱狂的に感じています。
私の芸術的なパーソナリティのすべての側面を映しだした今回のレコーディング・アルバムは、私の心の奥深くに大切に思っている音楽を表現するための第2の声を見つけることができたようなものだと思っています。PENTATONEと私の目的は、極めて優れたクオリティ、そして音楽の激しい感情を素直に解釈することでした。
私は、まもなくこの作品をリスナーにシェアすることに少しスリリングな気持ちを抱いています。
レナード・ローレンジャー氏とそのハイクオリティーでカリスマな彼のチームといっしょに仕事ができたことは、最も感動した経験だったし、これからもきっとそうでしょう。私のファースト・ソロ・アルバム、”ベル・エポック”のリリース、そしてこれからまたコラボしていく作品のリリースをとても楽しみにしております。
●PENTATONE Vice President レナード・ローレンジャー氏のコメントからの引用
私は、ここ数年のアンネリエンのキャリアをずっと追ってきて、ますます彼女への関心が深まる感じであった。そしてとうとう我がレーベルのファミリーに加わってくれて、とても興奮している。彼女は、並外れた芸術性、音楽的才能、そして演奏技術を兼ね備えており、レパートリーやインストゥルメンタルが持ちうる可能性の領域に対して絶え間ない好奇心と欲望に満ち満ちている。
我々は、彼女が今後、素晴らしい活躍、発展をしていくことを心から望んでいる。
![19060181_714687748713240_8654931065745440117_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_19060181_714687748713240_8654931065745440117_n5B15D.jpg)
木管はオーボエが1番大好きなのであるが、クラリネットも好き。
でもオーボエ奏者ほどの熱の入れ方ではなく、自分が過去の日記のディスクレビューで、どれだけクラリネット奏者を取り上げいたのかというと自分の記憶では、ザビーネ・マイヤーとBISのマルティン・フレストくらいなものだった。
とくにマルティン・フレストは、とてもユニークなクラリネット奏者で、彼自身オーケストラに所属せず、クラリネットを吹きながら、ダンスで踊ることもできる、という一風変わった奏者なのだ。
いわゆるクロスオーバー的エンターテナーという立ち位置で、クラシックに限らずいろいろなジャンルの名曲をクラリネットでフィーチャリングした小作品集が得意なのだが、単に演奏するだけでなく、本当に歌って踊れるユニークなエンターテナーでもあるのだ。
アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェもそういうクロスオーバー路線を狙っていくという可能性もありますね。でも、やっぱりせっかくコンクール優勝で、名奏者に師事でクラシック路線でデビューしたのだから、自分はまずクラシックの王道路線でがんばって欲しい。クロスオーバーはその後でもいいし、やろうと思えば、いつでもやれると思うから。
クラリネットの音色というのは、とにかく耳に優しい。同じ木管楽器でもフルートやオーボエと比較しても、クラリネットは丸みの帯びたソフトな質感で、ほんわかしていて、聴いていてとても癒される。
アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェが実際どのようなクラリネットの吹き方をするのか、その演奏姿をぜひ観てみたいと思い、YouTubeで探してみたらあった。
今回のデビューを祝して、PENTATONEが彼女のプロモ・ビデオを作っているのだが、これはあまりに幻想的にイメージを作りすぎで、顔もよく見えないし、演奏している姿も見えない。これはあまり役に立たないと思う。格好良く造りすぎですね。(笑)
気持ちはわかるけれど、もっと実質的のほうがいいです。
YouTubeには、それ以外にも彼女の演奏姿があるコンサートはたくさんアップされていた。
BBCプロムス2017やモーツァルトのクラリネット協奏曲も上がっていたので、しっかり観てみた。
美人で背筋がピンとしていて、クラリネットを吹く姿はじつに正統派スタイル。
素晴らしかった。
そして最後に、ようやくこの日記の本命であるディスク・レビューである。

ベル・エポック
クラリネット作品集
アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ
アレクサンドル・ブロック&リール国立管弦楽団
http://
デビュー・アルバムのタイトルは、「ベル・エポック」。
ドビュッシーの第1狂詩曲、世界初録音であるパリを拠点に活躍するマンフレート・トロヤーン(1949-)のラプソディ、イェーレ・タジンズ(1979-)編曲によるピエルネの「カンツォネッタ」とヴィドールの「序奏とロンド」、そしてルチアーノ・ベリオ(1925-2003)編曲のブラームスの「クラリネット・ソナタ第1番」である。
共演するオーケストラは、アレクサンドル・ブロック指揮のリール国立管弦楽団。
アルバムタイトルのベル・エポック(Belle Epoque、仏:「良き時代」)とは、19世紀末から第一次世界大戦勃発までのパリが繁栄した華やかな時代、及びその文化を回顧して用いられる言葉なのである。単にフランス国内の現象としてではなく、同時代のヨーロッパ文化の総体と合わせて論じられることも多い。
このパリがもっとも繁栄した華やかな時代「ベル・エポック」をタイトルに持ってくるというのは、このアルバムで選ばれた作曲家にきちんと現れているのだ。
クロード・ドビュッシー(フランスの作曲家)
マンフレート・トロヤーン(パリを拠点とする作曲家)
ガブリエル・ピエルネ(フランスの作曲家、指揮者)
シャルル=マリー・ヴィドール(フランスのオルガン奏者、作曲家)
このようにブラームスを除く曲は、すべてフランスの作曲家による作品。
そこにこのアルバムがフランス・パリへのオマージュであることが意図されたものであることがわかる。
なぜ、彼女がこのようなパリ・オマージュの作品をデビュー作品に持ってきたのか、その意図は、もっと厳密にライナーノーツを読めば書かれているかもしれない。少なくともベルギーという国は、多国言語を母国語とする国で、下がフランス語圏、上がオランダ語圏、そして右端がドイツ語圏、そして共通語に英語というようなマルチリンガルな国。
首都のブリュッセルは、地域別に言えばオランダ語圏なのだが、使われている公用語は、フランス語だ。自分が住んでいたときも、レストランのメニューはほとんどフランス語だった。
彼女が現在住んでいるのはブリュッセルでフランス語圏であるし、勤務している音楽学校での研究テーマなのか未明だが、そこからのパリ・オマージュがあってもなんら別に不思議でもない。
さて、さっそく聴いてみた印象。
冒頭のドビュッシーは、じつに彼らしい色彩感のある印象派の曲らしいテイストで、クラリネットの旋律がとても美しい。
2曲目のマンフレート・トロヤーンは現在パリを拠点に活躍する作曲家とのことであるが現代音楽ですね。全体としては前衛的なアプローチなのだけれど、楽章によって美しいクラリネットの旋律が垣間見れるなどの隠し味があって、粋な感じがするお洒落な構成の曲。いつも思うのだが、現代音楽って、隙間の美学というか、空間をうまく利用していて、とても録音がよく聴こえるのはいつも不思議です。この2曲目は、とりわけ録音がよく聴こえます。
3曲目のピエルネは、なんと可愛らしい曲なんだろう、というくらい美しいメロディ。
自分は最初に聴いたときに、その可愛らしさに一瞬にして心奪われた。クラリネットを主旋律に持ってきた編曲ヴァージョンであるが、これはじつに可愛い女性的な曲です。
4曲目のブラームスのソナタ。これがこのアルバムのメイン・ディッシュですね。これもクラリネットを主旋律に持ってくる編曲ヴァージョン。この曲はメイン・ディッシュらしい堂々とした如何にもブラームスらしい大曲。このアルバムは、どちらかというとクラリネットが主体でオーケストラの音が控えめな感じのバランスなのだけれど、この曲だけは、オーケストラの音もしっかり聴こえてきます。ロマン派らしい我々に馴染みやすい名曲である。
最後の5曲目のヴィドール。これもクラリネットとオーケストラとの掛け合いがとても美しくて可愛い感じがする曲。とても女性的で美しい曲ですね。
全体的に柔らかくて優しい質感のする女性らしいテイストに仕上がっている。2曲目の現代音楽以外は、とてもメロディラインが美しい曲ばかりで、クラリネットの音の主旋律が、どの曲もじつに効果的に、その美しさの骨格を作り上げていると言っていい。
「ベル・エポック=パリが繁栄した華やかな時代」というタイトルにふさわしい収録曲も、そのようなセンスのする曲ばかりであった。
サウンドの録音評であるが、いつものPENTATONEサウンドと変わらず期待を裏切らない出来栄えだった。
柔らかい質感、広い音場感ですね。クラリネットのあの耳に優しい、丸みを帯びたソフトな質感は万遍なく捉えられ、じつに美しく再現されている。
ただ、クラリネットがいくぶんメインにフィーチャリングされている感があって、オーケストラがあまり目立たない感じするのだが、4曲目のブラームスではオーケストラも大活躍であった。
録音スタッフは、録音プロデューサー&バランス・エンジニアにエルド・グロード氏。(プロデューサーに昇格!。。笑笑)録音エンジニアに、フランソワ・ゲイバート氏、編集に、ローラン・ジュリウス氏。
ポリヒムニアも、若い世代をどんどん育成していくべく、新しい人材にどんどんチャレンジさせていますね。こういう新しいスターのアルバム制作では、絶好のチャンスです。
アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェの公式HPもあります。リンクを貼っておきます。
http://
新しい時代のスターの誕生は、いつになっても、とてもフレッシュな気持ちになれるし、彼女も、今後PENTATONEを引っ張っていく主力スターとなっていくことを心から願っています。
何者なのだろう?
このたび、PENTATONEレーベルと長期契約を締結し、このレーベルからデビューしたクラリネット奏者である。この情報を掴んだときは、まだ日本のサイトに十分な情報が掲載されていなかったので、騒然な騒ぎになってしまったが、それも落ち着いてきて、どうやら素性が判明したようだ。
![64826168_2304901013109158_2799493935896985600_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_64826168_2304901013109158_2799493935896985600_n5B15D.jpg)
クラリネット奏者アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ。
ベルギー出身である。
最難関のコンクールとして知られるミュンヘン国際音楽コンクールで優勝(2012年)後、英BBC選出の“新生代アーティスト” やボルレッティ=ブイトーニ財団アワード2018を受賞するなど、今最も期待される新進気鋭のクラリネット奏者なのだそうだ。
ザビーネ・マイヤー、ヴェンツェル・フックス、アレッサンドロ・カルボナーレ、パスカル・モラゲスといった錚々たるクラリネット奏者に師事してきたヴァウヴェは、2017年夏のBBCプロムスのデビュー後、2018年にはロイヤル・アルバート・ホールやカドガン・ホールにてトーマス・ダウスゴー指揮BBCスコティッシュ交響楽団との共演でモーツァルトのクラリネット協奏曲を披露するなど、イギリスを中心に全ヨーロッパで注目を集めている俊英である。
ベルギー出身で、イギリス中心に活躍している、というのが素晴らしい!
間違いなく自分の人生に関与してくる運命のスターだ。(笑)
現在は、ベルギー・ブリュッセルに在住で、アントワープ王立音楽院やムジカ・ムンディ音楽学校で教鞭を取っているようだ。
![53738093_1052083261640352_1570930141582852096_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_53738093_1052083261640352_1570930141582852096_n5B15D.jpg)
現在は、クラリネットのソリストとして華々しくデビューしたが、今後は、ザビーネ・マイヤーのように、どこかのオーケストラの木管セクションのクラリネット奏者としてもキャリアを広げつつ、アルバムはソリストとして出していくという二束のわらじの選択肢になっていくのだろう。
自分は木管楽器ではオーボエが1番大好きなのであるが、名だたるオーボエ奏者も、みんなそうだ。オーケストラの首席奏者として活躍しながら、ソロのアルバムも出す、というような路線。
まさに木管奏者の王道の道ですね。
ソリストとしてのみの道だと、やはり音楽家としての音楽性の素養を磨いていくには不十分。
オーケストラの奏者としての経験を積むのは絶対必要ですね。
どこのオーケストラに所属することになるのか、いまから楽しみである。
でも現在、ベルギーの音楽学校に勤務していることから、職業としての専任音楽家としてどこまでやれるか、の判断はありますね。
2012年のミュンヘン国際コンクールで優勝して、音楽家として生きていく道筋を立てて、その後の5年間、いろいろな名クラリネット奏者に師事をして、満を持して2017年夏のBBCプロムスでデビューということだから、本当につい最近出てきた奏者なんだね。
そして今年2019年にPENTATONEと長期契約して、アルバムのほうでもデビューだ。
ご覧のような美人でフォトジニックな奏者で、音楽的才能も抜群。あとはこれから何十年もかけて、自分をどう成長させていくか。。。まさにこれからの奏者だ。
PENTATONEはじつにいい仕事、NICE JOBをしたと思うよ。
敢えて、難を言わせてもらうならば、名前が難しすぎて読みづらい、ということだろうか?(笑)ベルギー人はみんなこのような名前だからね。スターの要件のひとつとして、誰からも名前を簡潔に呼びやすい、というのがあります。それがちょっと心配です。
その後、たぶん略した愛称ニックネームみたいなものが、みんなが作ってくれると思うよ。
今回PENTATONEからアルバム・デビューするにあたって、アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ本人、そしてPENTATONEのVice President レナード・ローレンジャー氏がライナー・ノーツにこのような寄稿をおこなっている。
●ライナーノーツのアンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェのコメントからの引用。
いま、PENTATONEレーベルのアーティスト・ファミリーの仲間入りができたことは、とても熱狂的に感じています。
私の芸術的なパーソナリティのすべての側面を映しだした今回のレコーディング・アルバムは、私の心の奥深くに大切に思っている音楽を表現するための第2の声を見つけることができたようなものだと思っています。PENTATONEと私の目的は、極めて優れたクオリティ、そして音楽の激しい感情を素直に解釈することでした。
私は、まもなくこの作品をリスナーにシェアすることに少しスリリングな気持ちを抱いています。
レナード・ローレンジャー氏とそのハイクオリティーでカリスマな彼のチームといっしょに仕事ができたことは、最も感動した経験だったし、これからもきっとそうでしょう。私のファースト・ソロ・アルバム、”ベル・エポック”のリリース、そしてこれからまたコラボしていく作品のリリースをとても楽しみにしております。
●PENTATONE Vice President レナード・ローレンジャー氏のコメントからの引用
私は、ここ数年のアンネリエンのキャリアをずっと追ってきて、ますます彼女への関心が深まる感じであった。そしてとうとう我がレーベルのファミリーに加わってくれて、とても興奮している。彼女は、並外れた芸術性、音楽的才能、そして演奏技術を兼ね備えており、レパートリーやインストゥルメンタルが持ちうる可能性の領域に対して絶え間ない好奇心と欲望に満ち満ちている。
我々は、彼女が今後、素晴らしい活躍、発展をしていくことを心から望んでいる。
![19060181_714687748713240_8654931065745440117_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_19060181_714687748713240_8654931065745440117_n5B15D.jpg)
木管はオーボエが1番大好きなのであるが、クラリネットも好き。
でもオーボエ奏者ほどの熱の入れ方ではなく、自分が過去の日記のディスクレビューで、どれだけクラリネット奏者を取り上げいたのかというと自分の記憶では、ザビーネ・マイヤーとBISのマルティン・フレストくらいなものだった。
とくにマルティン・フレストは、とてもユニークなクラリネット奏者で、彼自身オーケストラに所属せず、クラリネットを吹きながら、ダンスで踊ることもできる、という一風変わった奏者なのだ。
いわゆるクロスオーバー的エンターテナーという立ち位置で、クラシックに限らずいろいろなジャンルの名曲をクラリネットでフィーチャリングした小作品集が得意なのだが、単に演奏するだけでなく、本当に歌って踊れるユニークなエンターテナーでもあるのだ。
アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェもそういうクロスオーバー路線を狙っていくという可能性もありますね。でも、やっぱりせっかくコンクール優勝で、名奏者に師事でクラシック路線でデビューしたのだから、自分はまずクラシックの王道路線でがんばって欲しい。クロスオーバーはその後でもいいし、やろうと思えば、いつでもやれると思うから。
クラリネットの音色というのは、とにかく耳に優しい。同じ木管楽器でもフルートやオーボエと比較しても、クラリネットは丸みの帯びたソフトな質感で、ほんわかしていて、聴いていてとても癒される。
アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェが実際どのようなクラリネットの吹き方をするのか、その演奏姿をぜひ観てみたいと思い、YouTubeで探してみたらあった。
今回のデビューを祝して、PENTATONEが彼女のプロモ・ビデオを作っているのだが、これはあまりに幻想的にイメージを作りすぎで、顔もよく見えないし、演奏している姿も見えない。これはあまり役に立たないと思う。格好良く造りすぎですね。(笑)
気持ちはわかるけれど、もっと実質的のほうがいいです。
YouTubeには、それ以外にも彼女の演奏姿があるコンサートはたくさんアップされていた。
BBCプロムス2017やモーツァルトのクラリネット協奏曲も上がっていたので、しっかり観てみた。
美人で背筋がピンとしていて、クラリネットを吹く姿はじつに正統派スタイル。
素晴らしかった。
そして最後に、ようやくこの日記の本命であるディスク・レビューである。

ベル・エポック
クラリネット作品集
アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ
アレクサンドル・ブロック&リール国立管弦楽団
http://
デビュー・アルバムのタイトルは、「ベル・エポック」。
ドビュッシーの第1狂詩曲、世界初録音であるパリを拠点に活躍するマンフレート・トロヤーン(1949-)のラプソディ、イェーレ・タジンズ(1979-)編曲によるピエルネの「カンツォネッタ」とヴィドールの「序奏とロンド」、そしてルチアーノ・ベリオ(1925-2003)編曲のブラームスの「クラリネット・ソナタ第1番」である。
共演するオーケストラは、アレクサンドル・ブロック指揮のリール国立管弦楽団。
アルバムタイトルのベル・エポック(Belle Epoque、仏:「良き時代」)とは、19世紀末から第一次世界大戦勃発までのパリが繁栄した華やかな時代、及びその文化を回顧して用いられる言葉なのである。単にフランス国内の現象としてではなく、同時代のヨーロッパ文化の総体と合わせて論じられることも多い。
このパリがもっとも繁栄した華やかな時代「ベル・エポック」をタイトルに持ってくるというのは、このアルバムで選ばれた作曲家にきちんと現れているのだ。
クロード・ドビュッシー(フランスの作曲家)
マンフレート・トロヤーン(パリを拠点とする作曲家)
ガブリエル・ピエルネ(フランスの作曲家、指揮者)
シャルル=マリー・ヴィドール(フランスのオルガン奏者、作曲家)
このようにブラームスを除く曲は、すべてフランスの作曲家による作品。
そこにこのアルバムがフランス・パリへのオマージュであることが意図されたものであることがわかる。
なぜ、彼女がこのようなパリ・オマージュの作品をデビュー作品に持ってきたのか、その意図は、もっと厳密にライナーノーツを読めば書かれているかもしれない。少なくともベルギーという国は、多国言語を母国語とする国で、下がフランス語圏、上がオランダ語圏、そして右端がドイツ語圏、そして共通語に英語というようなマルチリンガルな国。
首都のブリュッセルは、地域別に言えばオランダ語圏なのだが、使われている公用語は、フランス語だ。自分が住んでいたときも、レストランのメニューはほとんどフランス語だった。
彼女が現在住んでいるのはブリュッセルでフランス語圏であるし、勤務している音楽学校での研究テーマなのか未明だが、そこからのパリ・オマージュがあってもなんら別に不思議でもない。
さて、さっそく聴いてみた印象。
冒頭のドビュッシーは、じつに彼らしい色彩感のある印象派の曲らしいテイストで、クラリネットの旋律がとても美しい。
2曲目のマンフレート・トロヤーンは現在パリを拠点に活躍する作曲家とのことであるが現代音楽ですね。全体としては前衛的なアプローチなのだけれど、楽章によって美しいクラリネットの旋律が垣間見れるなどの隠し味があって、粋な感じがするお洒落な構成の曲。いつも思うのだが、現代音楽って、隙間の美学というか、空間をうまく利用していて、とても録音がよく聴こえるのはいつも不思議です。この2曲目は、とりわけ録音がよく聴こえます。
3曲目のピエルネは、なんと可愛らしい曲なんだろう、というくらい美しいメロディ。
自分は最初に聴いたときに、その可愛らしさに一瞬にして心奪われた。クラリネットを主旋律に持ってきた編曲ヴァージョンであるが、これはじつに可愛い女性的な曲です。
4曲目のブラームスのソナタ。これがこのアルバムのメイン・ディッシュですね。これもクラリネットを主旋律に持ってくる編曲ヴァージョン。この曲はメイン・ディッシュらしい堂々とした如何にもブラームスらしい大曲。このアルバムは、どちらかというとクラリネットが主体でオーケストラの音が控えめな感じのバランスなのだけれど、この曲だけは、オーケストラの音もしっかり聴こえてきます。ロマン派らしい我々に馴染みやすい名曲である。
最後の5曲目のヴィドール。これもクラリネットとオーケストラとの掛け合いがとても美しくて可愛い感じがする曲。とても女性的で美しい曲ですね。
全体的に柔らかくて優しい質感のする女性らしいテイストに仕上がっている。2曲目の現代音楽以外は、とてもメロディラインが美しい曲ばかりで、クラリネットの音の主旋律が、どの曲もじつに効果的に、その美しさの骨格を作り上げていると言っていい。
「ベル・エポック=パリが繁栄した華やかな時代」というタイトルにふさわしい収録曲も、そのようなセンスのする曲ばかりであった。
サウンドの録音評であるが、いつものPENTATONEサウンドと変わらず期待を裏切らない出来栄えだった。
柔らかい質感、広い音場感ですね。クラリネットのあの耳に優しい、丸みを帯びたソフトな質感は万遍なく捉えられ、じつに美しく再現されている。
ただ、クラリネットがいくぶんメインにフィーチャリングされている感があって、オーケストラがあまり目立たない感じするのだが、4曲目のブラームスではオーケストラも大活躍であった。
録音スタッフは、録音プロデューサー&バランス・エンジニアにエルド・グロード氏。(プロデューサーに昇格!。。笑笑)録音エンジニアに、フランソワ・ゲイバート氏、編集に、ローラン・ジュリウス氏。
ポリヒムニアも、若い世代をどんどん育成していくべく、新しい人材にどんどんチャレンジさせていますね。こういう新しいスターのアルバム制作では、絶好のチャンスです。
アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェの公式HPもあります。リンクを貼っておきます。
http://
新しい時代のスターの誕生は、いつになっても、とてもフレッシュな気持ちになれるし、彼女も、今後PENTATONEを引っ張っていく主力スターとなっていくことを心から願っています。
カラヤン・ベルリンフィルの普門館ライブを聴く。 [ディスク・レビュー]
先日、12月に取り壊しということで、最後のお別れをしてきた普門館。そこでおこなわれた1977年の伝説のライブ、いわゆる「カラヤン&ベルリンフィルの普門館ライブ」を聴いてみた。
じつは4~5年前に友人から無料でいただいたサンプルCDが3枚あった。
(リンクにはSACDを貼っておきます。)
![545[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5455B15D.jpg)
交響曲第1番、第3番『英雄』
カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://
![546[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5465B15D.jpg)
交響曲第2番、第8番
カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://
![549[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5495B15D.jpg)
交響曲第9番『合唱』
カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://
発売自体は、CDであれば2010年という事だから、時代から遅れること8年目にしてようやく聴いた。(笑)やっぱり自分の中には”普門館=巨大な空間で音響劣悪”、というイメージが蔓延っていたので、どうしても聴いてみようという気にならなかった。そのまま死蔵状態でラックの肥やしになっていた。
それが普門館にお別れできて、日記を書いたことで、これはぜひ聴いてみたいと思うようになっていたのだ。
TOKYO FMによる録音で、当時TOKYO FMの名プロデューサーだった東条碩夫氏(現・音楽評論家 &ジャーナリスト)があたり、さらにストコフスキーも絶賛した腕前の日本が誇る名エンジニア故若林駿介氏を動員、万全の体制で臨んだもの。
いまはDSD新リマスターもされていて、SACDにもなっている。
結論!
自分が想像していた以上に、かなりいい録音だった!
これは驚いた。
あれだけ空間が広いと音が散って、反射する壁も遠いから、響きがない直接音主体のサウンドだろうと思っていたが、予想以上によく鳴っていた。
あまりによく鳴るんで、あれ~?という感じで驚く。
広い空間というハンデキャップを感じさせないところがミソで、どちらかというとオンマイクっぽい録り方で、いまの録音のような空間はあまり感じない。
現代のオーケストラ録音のようなオーケストラの音場をすっぽり包み込んでさらに余裕がある器の大きさがある訳ではなく、オケ全体を録る最低限のキャパはあったという感じ。
それよりも驚くのは、SPからの出音の鳴りっぷり、そのゴージャスな音。
音のシャワーみたいな凄さ。これには驚いてしまう。
1977年の録音でこれだけの音が録れていればスゴイとしかいいようがない。
最初、もちろん録音スタッフの芸術作品の賜物、見事な優秀録音、と賛辞を述べたいと思ったが、もちろんそれもあるのだが、もっと大事なことを考えついた。
それはカラヤン&ベルリンフィルのサウンド自体がスゴイということだ。
まさに音の暴力(笑)。
そのゴージャスで戦車のように鳴らしまくる音って、まさにカラヤン時代のベルリンフィルってそうじゃなかったのかな?と思ったのだ。
自分もここ数年来カラヤンを聴いていない。
すっかり忘れていた。。。
異常なまでに分厚い弦、そして嫋やかな木管、そして金管の圧倒的大咆哮。まさに戦車なみなのだ。
とにかくよく鳴る。
いまのベルリンフィルをはじめ、現在のオーケストラでここまで有機的に鳴らすオケってまずないだろう。
ジジイじゃないけど、あの頃は凄かった・・・だ。
具体的にそのスゴサを表現するには、いつもと同じVOLで聴いているのに、今日はマンションの大家さんから、ついに苦情が入ってしまった。(笑)
当時普門館で実演を聴いた人たちは、何だか、遠くで勝手に演奏しているのを、こっちも勝手に聴いているような、そんな印象。つまり、音が自分のいるところまで飛んでこない。だから、いま思い返してみても、「とにかく広くて、カラヤンも遠くにいて、何だかよくわからなかった」・・・そんな感想を言っていた人は、この録音を聴いたらなんと思うだろう?(笑)
まったく別世界のサウンドが聴けてしまう。
それだけ、ステージ周りにがっちりマイクセッティングを施し、よくそのサウンドを余すことなく拾えた。つまり広い空間の影響を受けないように、ステージからの音をじかに拾っちゃおうという感じだったんだろう?
そしてミキシング、整音もよくできている。
じつは4~5年前に友人から無料でいただいたサンプルCDが3枚あった。
(リンクにはSACDを貼っておきます。)
![545[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5455B15D.jpg)
交響曲第1番、第3番『英雄』
カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://
![546[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5465B15D.jpg)
交響曲第2番、第8番
カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://
![549[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5495B15D.jpg)
交響曲第9番『合唱』
カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://
発売自体は、CDであれば2010年という事だから、時代から遅れること8年目にしてようやく聴いた。(笑)やっぱり自分の中には”普門館=巨大な空間で音響劣悪”、というイメージが蔓延っていたので、どうしても聴いてみようという気にならなかった。そのまま死蔵状態でラックの肥やしになっていた。
それが普門館にお別れできて、日記を書いたことで、これはぜひ聴いてみたいと思うようになっていたのだ。
TOKYO FMによる録音で、当時TOKYO FMの名プロデューサーだった東条碩夫氏(現・音楽評論家 &ジャーナリスト)があたり、さらにストコフスキーも絶賛した腕前の日本が誇る名エンジニア故若林駿介氏を動員、万全の体制で臨んだもの。
いまはDSD新リマスターもされていて、SACDにもなっている。
結論!
自分が想像していた以上に、かなりいい録音だった!
これは驚いた。
あれだけ空間が広いと音が散って、反射する壁も遠いから、響きがない直接音主体のサウンドだろうと思っていたが、予想以上によく鳴っていた。
あまりによく鳴るんで、あれ~?という感じで驚く。
広い空間というハンデキャップを感じさせないところがミソで、どちらかというとオンマイクっぽい録り方で、いまの録音のような空間はあまり感じない。
現代のオーケストラ録音のようなオーケストラの音場をすっぽり包み込んでさらに余裕がある器の大きさがある訳ではなく、オケ全体を録る最低限のキャパはあったという感じ。
それよりも驚くのは、SPからの出音の鳴りっぷり、そのゴージャスな音。
音のシャワーみたいな凄さ。これには驚いてしまう。
1977年の録音でこれだけの音が録れていればスゴイとしかいいようがない。
最初、もちろん録音スタッフの芸術作品の賜物、見事な優秀録音、と賛辞を述べたいと思ったが、もちろんそれもあるのだが、もっと大事なことを考えついた。
それはカラヤン&ベルリンフィルのサウンド自体がスゴイということだ。
まさに音の暴力(笑)。
そのゴージャスで戦車のように鳴らしまくる音って、まさにカラヤン時代のベルリンフィルってそうじゃなかったのかな?と思ったのだ。
自分もここ数年来カラヤンを聴いていない。
すっかり忘れていた。。。
異常なまでに分厚い弦、そして嫋やかな木管、そして金管の圧倒的大咆哮。まさに戦車なみなのだ。
とにかくよく鳴る。
いまのベルリンフィルをはじめ、現在のオーケストラでここまで有機的に鳴らすオケってまずないだろう。
ジジイじゃないけど、あの頃は凄かった・・・だ。
具体的にそのスゴサを表現するには、いつもと同じVOLで聴いているのに、今日はマンションの大家さんから、ついに苦情が入ってしまった。(笑)
当時普門館で実演を聴いた人たちは、何だか、遠くで勝手に演奏しているのを、こっちも勝手に聴いているような、そんな印象。つまり、音が自分のいるところまで飛んでこない。だから、いま思い返してみても、「とにかく広くて、カラヤンも遠くにいて、何だかよくわからなかった」・・・そんな感想を言っていた人は、この録音を聴いたらなんと思うだろう?(笑)
まったく別世界のサウンドが聴けてしまう。
それだけ、ステージ周りにがっちりマイクセッティングを施し、よくそのサウンドを余すことなく拾えた。つまり広い空間の影響を受けないように、ステージからの音をじかに拾っちゃおうという感じだったんだろう?
そしてミキシング、整音もよくできている。
でも拍手の音がマイクとの距離感からして不自然で大きすぎるのが、いかにも作ってる感がある。(笑)
まさに1977年当時の録音としては絶妙なクオリティの高さで、よくこんなマスターテープが残っていたものだ、と驚く。
1970年代のカラヤン時代最強のサウンドは、まさにすごいサウンドだった!
それがこの録音からよくわかるのだ。
ここまで凄ければ、どうしても聴いてみたいのが、第5番の「運命」。
![547[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5475B15D-b3ad2.jpg)
交響曲第5番『運命』、第6番『田園』
カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://
東条碩夫氏が大絶賛した 「第5番「運命」の普門館での演奏は、彼等が残した如何なるレコーディングにおける演奏にも増して凄まじい力感に溢れているといえる。」。
このコメントにもうノックアウトだ。(笑)
この普門館ライブの中でも最高傑作が第5番「運命」だというのだから、これはぜひ聴いてみたい。
立て続くコンサートチケット購入で、緊縮財政を組んでいる昨今、この誘惑に勝てるだろうか・・・?(笑)
まさに1977年当時の録音としては絶妙なクオリティの高さで、よくこんなマスターテープが残っていたものだ、と驚く。
1970年代のカラヤン時代最強のサウンドは、まさにすごいサウンドだった!
それがこの録音からよくわかるのだ。
ここまで凄ければ、どうしても聴いてみたいのが、第5番の「運命」。
![547[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5475B15D-b3ad2.jpg)
交響曲第5番『運命』、第6番『田園』
カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://
東条碩夫氏が大絶賛した 「第5番「運命」の普門館での演奏は、彼等が残した如何なるレコーディングにおける演奏にも増して凄まじい力感に溢れているといえる。」。
このコメントにもうノックアウトだ。(笑)
この普門館ライブの中でも最高傑作が第5番「運命」だというのだから、これはぜひ聴いてみたい。
立て続くコンサートチケット購入で、緊縮財政を組んでいる昨今、この誘惑に勝てるだろうか・・・?(笑)
BISの新譜:アンネ・ゾフィー・フォン・オッター、原点回帰する。 [ディスク・レビュー]
アンネ・ゾフィー・フォン・オッターの声には気品がある。歌い方も最高に格好いい。
自分が愛する最高のディーヴァである。
それぞれの歌手の声質(声紋)というのは、指紋と同じで、その人固有に決まっている特質。オッターの声は、その中でも数少ない「心をつかむ歌声にある1/fのゆらぎ特性」を持った声なのだ。
ヒトラーが、非人道的で残虐な言動を繰り返していたのにも拘らず、そのスピーチに大衆が酔ってしまう現象に、彼の声質に「1/fのゆらぎ」の特性が含まれているからだ、という。
同じくキング牧師などの「I have a dream......」に代表される名演説などもそうだ。
人の心を動かす、感動させるには、ひとつのリズムというか韻を踏むというか、人の心を高揚させる、決まった法則のリズム態があるのだ。
以前日記にもした自分の信条みたいなものなのだが、今回、オッターの新譜を聴いて、ますますその意を強くした。
この「1/fのゆらぎ」特性を持った声質の歌手というのが、日本歌手で言えば代表的なのが美空ひばりだという。他にもMISIA、宇多田ヒカル、松任谷由実、徳永英明、吉田美和などが挙げられている。
誰もが持てる才能でもなくて、持って生まれた声質、ある特定の歌手のみに見られるこの才能。
自分の大好きなオペラ歌手の世界にあてはめてみる。
1/fゆらぎは交感神経の興奮を抑え、心身共にリラックスした状態を作る、とあるから、感覚的に考えると、やはり低音部よりも高音部だろう。
女性なら、ソプラノ、そしてメゾ・ソプラノ。男性ならテノール。
女声は、アルトの下からソプラノの上までで、164.81Hzから1174.66Hz、男声ならバスの下からテノールの上までで65.4Hzから466.16Hzあたりなのだそうだ。
ソプラノで1KHz、テノールで500Hz・・・人間の声の高さって、周波数で表せばそんなものなのか? 自分は、ソプラノであれば、~10KHzはいくものだと思っていた。
男性歌手にしろ、女性歌手にしろ、80Hzから1280Hzの4オクターブあることは間違いないようだ。
ただ、音の高さ、低さだけの問題で、そのような人を恍惚とさせることはできないのだ。
もっと複雑な要素が入り混じる。
「1/fのゆらぎ」というのは、パワー(スペクトル密度)が周波数fに反比例するゆらぎのこと。(ただしfは0よりおおきい、有限な範囲。) ピンクノイズとも呼ばれ、具体例として人の心拍の間隔や、ろうそくの炎の揺れ方、電車の揺れ、小川のせせらぐ音などが例として挙げられている。
もっと感覚的には、
「規則正しい音とランダムで規則性がない音との中間の音で、人に快適感やヒーリング効果を与える。」
「規則的なゆらぎに、不規則なゆらぎが少し加わったもの」
こんな感じだ。
まさに、人の心をつかむ歌声には、かならずこの「1/fゆらぎ」特性が存在する。
そのような天性の声質を持っている人は、自分ではまったく意識していないのだろうけれど、聴いている人に対してそのような心地よさを必然と与えるもので、そこを科学的に分析すると、そのような現象がみられるということなのだと思う。
自分にとって、オッターの声は、まさにその直球ど真ん中にあてはまる、と確信していて、史上最高のディーヴァなのだ。
オッターは、ご存知スウェーデンの歌姫で、ベテラン中のベテラン。オペラに限らず、宗教曲、歌曲リートを始め、そしてクラシックに限らずジャズ、シャンソンなど、いろいろなジャンルをこなすそのレパートリーの広さは他を卓越している。
本当に才能の豊かな歌手。
1983年デビューだからまさに自分らの世代の歌手。
自分的な想い出で、心に残っているのは、R.シュトラウスの「ばらの騎士」の名演、そして、ちょうどベルリンフィルではアバド時代にあたり、アバドから溺愛を受けて、よく招聘されていたのを覚えている。
この世代では最も優れた声楽家の一人として認められていて、世界の一流指揮者、オーケストラ、歌劇場から常に、求められ続けられている。
最近は、オペラは引退なのか?リサイタル系中心の活動のようにも思えるが、アルバムのほうもきちんと定期的にリリースしてくれるからファンとしても有難い。
オッターは、DG専属契約歌手なのだが、スウェーデン人として、たとえばスウェーデン歌曲集だとか自分の故郷に関連するテーマがあったりするときは、北欧の高音質レーベルBISからアルバムを出している。
BIS前作の「夏の日」。
まさにスウェーデン歌曲集を集めたもので、近来稀に見る優秀録音だと自分は思っていた。BISらしいちょっとオフマイク気味のワンポイント録音が、マイクからの程よい距離感を感じさせ、絶妙な空間感がある。
これを超える優秀録音はでるのだろうか?
最近のDGのアルバムも素晴らしかったが、正直スタジオ録音のせいなのか、ややデッドに感じてしまい、歌っているところの空間や広がりをあまり感じないのが、自分には不満で、歌や曲は好きなのだけれど、録音が好きじゃないというパラドックスな状態だった。
この「夏の日」効果もあって、自分はオッターのBIS録音は絶対いい!という確信めいたものがあった。だから、今回オッターのBIS新譜がでる、と聞いた瞬間、もう胸ときめいたことは言うまでもない。
![833[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8335B15D.jpg)
「シンプル・ソング」
アンネ・ゾフィー・フォン・オッター、ベンクト・フォシュベリ(オルガン)、他
http://
今回の新譜はオッターにとって、まさに原点回帰のアルバムとなった。
そういうコンセプトを企画としてぶちあげたのだろう。
なによりもジャケットがいい!いかにも音が良さそうだ。
ジャケットのセンスがいいアルバムは、絶対曲もいいし、音もいい。
スウェーデンの宮廷歌手アンネ・ゾフィー・フォン・オッターのキャリアは、彼女が生まれたストックホルムの聖ヤコブ教会から始まった。教会の青少年合唱団で歌い、教会で行われているバッハの「マタイ受難曲」コンサートのソロに起用され、1982年、最初のソロ・コンサートをこの教会で行なった。この時に共演したベンクト・フォシュベリとは、その後30年以上に渡る共演が続いている。
今回のオッターの新譜「シンプル・ソング」は、この聖ヤコブ教会でセッション録音されたアルバムなのだ。
まさに原点回帰。ここからオッターのキャリアは始まった。
聖ヤコブ教会という名の教会は、それこそヨーロッパの至る国にある教会で、今回話をしているのはストックホルムにある聖ヤコブ教会のこと。
ストックホルム 聖ヤコブ教会
教会の内装空間の写真も探したが、どれもストックホルムではない聖ヤコブ教会のものばかり。
今回のアルバムは、まさにオッターが最も大切にしている珠玉の17曲を選んだもので、「宗教」と「心」でつながる17の曲。「典礼の手かせ足かせを逃れ、自然に湧き出る賛美の心を高らかに歌え」を基本のスタンスに歌っているのだそうだ。
アルバム全体を聴いて感じるのは、やはりパイプオルガンの音色がとても強烈で、アルバム全体のトーンを支配している感じがする。
でも実際は、ヴァイオリン、チェロ、フルート、ヴィオラ、ハープ、それにエレキギター!などかなり多彩な音色に囲まれているのだ。
とにかく聴いていて、とてもいい曲ばかり。
前作の「夏の日」とはまたちょっと趣が違う良さがある。
かなり毛色が違う。
気配としては、宗教曲の色が強い感じがするかな。
アルバムのタイトルになった「シンプル・ソング」は、バーンスタインのミサ曲。
どこかで聴いたことがあると思ったら、マーラーが交響曲第3番と第2番の楽章とした「子供の不思議な角笛」の詩による2曲も入っている。
そしてシュトラウス歌曲も2曲。「たそがれの夢」、「あした!」
リストのアヴェ・マリアもこれまた素晴らしくいい。アヴェ・マリアは本当にどの作曲家の曲でも究極に癒されるね。
自分が1番心ときめいたこのアルバムの中の最高の曲は、ラストに入っている曲。
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」の「すべての山を登れ」。
なんて、カッコイイ曲なんだ!
オッターが最高に素敵に見えてしまう最高の曲だ。サウンド・オブ・ミュージックは当然よく知っているけれど、こんなドライブ感の効いた格好よさは、かなり興奮した。オッターの歌い方もかっこいいよね。この曲に完全にやられました。
パイプオルガンが最高に主張する曲。このアルバムの中で一番オルガンが目立っている曲。もうトラポの1曲リピート機能を使って、ずっと1日中繰り返して聴いています。(笑)
でもこの日記を読んでくれている読者はそんなことを聞きたいのではないだろう?(笑)
わかってるって。(^^)
録音超絶素晴らしいです!
やっぱりオーディオファンにとって、このファクターは絶対譲れないところ。
この新譜を紹介するには、ここを一番言いたかった。
昨今の録音技術の進歩は凄い。最近リリースされる新譜は、みんな音が洗練されているよね。いかにも新しい録音という感じです。
ダイナミックレンジ32bitで録ってるのかな?(笑)
それだけ縦軸の深さ(レベルの高低)が素晴らしい。
いや周波数レンジのほうも384KHzはいっているかな?それだけ高低音域の横軸の両側に、す~っと伸びていて解像感高いです。
1発目の出音で、その洗練された空気感がすごくて鳥肌が立つ。
いい録音かどうかは、最初の出音を聴いただけで、もうわかっちゃうんだよね。あとは、ずっと聴いていてもその印象が変わることはほとんどあまりない。
教会らしい大空間にいることがよくわかり、オッターの声がよく通るのだ。
部屋がその教会の大空間にワープしたかのような空間感だ。
情報量も多いし・・・でもこんなことはごちゃごちゃオーディオ術語を並べ立てて話すのはまさに野暮というもの。
黙って聴いてくれれば、それでいい。
このオルガンの低域のボリューム感を出すのがオーディオ・スキルかもですね。
クレジットを見ると、驚いたことにマスターフォーマットは、PCM 96/24だそうだ。(驚)
いまどき、こんな昔の諸元でこれだけの素晴らしい録音ができちゃうのは、やっぱり教会独特の空間、残響の長さなどの残響感の賜物なんだろうし、それに単にスペックが高ければいい録音ができるほど甘い世界じゃない、ということかね。
やっぱりエンジニアの編集、ポスプロの世界もかなり大きなウェートを占めるのだろう。
いかに奥行き感、立体感を出すか、など彼らのセンス、腕の見せ所だ。
その他の機器は、BISなので、RMEのヘビーユーザー。DAWはもう定番のPyramix。
今回の録音プロジェクトは、Take5 Music Productionがおこなっている。
いままでBISの録音制作を手掛けてきたトーンマイスター5人が独立して、「Take 5 Music Production」という別会社を設立しているのだ。 主なミッションは、BISの録音制作を担う、ということで、フィリップス・クラシックスの録音チームが、ポリヒムニアになったことや、ドイツ・グラモフォンの録音チームが、エミール・ベルリナー・スタジオとなったことと同様のケースのように思えるのだが、ただ唯一違う点は、現在もBISには、社内トーンマイスターが在籍して、音に関わる分野の責任を持っていることだ。
Take5のメリットは、これまで通りBIS作品の制作を担いながら、同時に他のレーベルの制作も担当できる、さらには、ダウンロードのプラットフォームも構築していくという視野が持てるというところにある。
BISは基本は、マスターはPCM 96/24だね。彼らは昔からそう。
Take5は最近、パリで賞を受賞したみたいで乗っています。
今回の録音は、プロデューサー&サウンド・エンジニアは、Marion Schwebel氏。編集やミキシングもそうだ。
Nice Job!でした。
では、ちょっと、その聖ヤコブ教会でのセッション録音の様子を。

聖ヤコブ教会のパイプオルガン。
1976年に設置されたマークセン・オルガンです。

オルガンを弾いているのが、オッターの長年のずっとパートナーだったそのピアニストとして知られるベンクト・フォシュベリ。BIS前作の夏の日でもパートナーとして録音に参加していました。今回オルガンのレジストレーション(オルガンのストップを決めること)を担当したのも彼の息子のミケール・フォシュベリでした。

オッター様、絶好調!
教会の大空間によく声が通ってます。
とにかく教会の大空間、そしてこのパイプオルガン、そしてオッターの声、堪らんサウンドです!

アルバム・トップの「シンプル・ソング」では、なんとエレキ・ギターも入ります。(ボロンという感じ)弾いているのは、なんと!オッターの息子さんです!! 今回の録音は、家族全員参加してのアットホームな録音だったんですね。

今回のマイクは、ノイマン、DPAそしてSchoepsのマイクを使ったようですが、オッターの声を録っているのはノイマンですかね。ステレオ配置セッティングです。

自分が愛する最高のディーヴァである。
それぞれの歌手の声質(声紋)というのは、指紋と同じで、その人固有に決まっている特質。オッターの声は、その中でも数少ない「心をつかむ歌声にある1/fのゆらぎ特性」を持った声なのだ。
ヒトラーが、非人道的で残虐な言動を繰り返していたのにも拘らず、そのスピーチに大衆が酔ってしまう現象に、彼の声質に「1/fのゆらぎ」の特性が含まれているからだ、という。
同じくキング牧師などの「I have a dream......」に代表される名演説などもそうだ。
人の心を動かす、感動させるには、ひとつのリズムというか韻を踏むというか、人の心を高揚させる、決まった法則のリズム態があるのだ。
以前日記にもした自分の信条みたいなものなのだが、今回、オッターの新譜を聴いて、ますますその意を強くした。
この「1/fのゆらぎ」特性を持った声質の歌手というのが、日本歌手で言えば代表的なのが美空ひばりだという。他にもMISIA、宇多田ヒカル、松任谷由実、徳永英明、吉田美和などが挙げられている。
誰もが持てる才能でもなくて、持って生まれた声質、ある特定の歌手のみに見られるこの才能。
自分の大好きなオペラ歌手の世界にあてはめてみる。
1/fゆらぎは交感神経の興奮を抑え、心身共にリラックスした状態を作る、とあるから、感覚的に考えると、やはり低音部よりも高音部だろう。
女性なら、ソプラノ、そしてメゾ・ソプラノ。男性ならテノール。
女声は、アルトの下からソプラノの上までで、164.81Hzから1174.66Hz、男声ならバスの下からテノールの上までで65.4Hzから466.16Hzあたりなのだそうだ。
ソプラノで1KHz、テノールで500Hz・・・人間の声の高さって、周波数で表せばそんなものなのか? 自分は、ソプラノであれば、~10KHzはいくものだと思っていた。
男性歌手にしろ、女性歌手にしろ、80Hzから1280Hzの4オクターブあることは間違いないようだ。
ただ、音の高さ、低さだけの問題で、そのような人を恍惚とさせることはできないのだ。
もっと複雑な要素が入り混じる。
「1/fのゆらぎ」というのは、パワー(スペクトル密度)が周波数fに反比例するゆらぎのこと。(ただしfは0よりおおきい、有限な範囲。) ピンクノイズとも呼ばれ、具体例として人の心拍の間隔や、ろうそくの炎の揺れ方、電車の揺れ、小川のせせらぐ音などが例として挙げられている。
もっと感覚的には、
「規則正しい音とランダムで規則性がない音との中間の音で、人に快適感やヒーリング効果を与える。」
「規則的なゆらぎに、不規則なゆらぎが少し加わったもの」
こんな感じだ。
まさに、人の心をつかむ歌声には、かならずこの「1/fゆらぎ」特性が存在する。
そのような天性の声質を持っている人は、自分ではまったく意識していないのだろうけれど、聴いている人に対してそのような心地よさを必然と与えるもので、そこを科学的に分析すると、そのような現象がみられるということなのだと思う。
自分にとって、オッターの声は、まさにその直球ど真ん中にあてはまる、と確信していて、史上最高のディーヴァなのだ。
オッターは、ご存知スウェーデンの歌姫で、ベテラン中のベテラン。オペラに限らず、宗教曲、歌曲リートを始め、そしてクラシックに限らずジャズ、シャンソンなど、いろいろなジャンルをこなすそのレパートリーの広さは他を卓越している。
本当に才能の豊かな歌手。
1983年デビューだからまさに自分らの世代の歌手。
自分的な想い出で、心に残っているのは、R.シュトラウスの「ばらの騎士」の名演、そして、ちょうどベルリンフィルではアバド時代にあたり、アバドから溺愛を受けて、よく招聘されていたのを覚えている。
この世代では最も優れた声楽家の一人として認められていて、世界の一流指揮者、オーケストラ、歌劇場から常に、求められ続けられている。
最近は、オペラは引退なのか?リサイタル系中心の活動のようにも思えるが、アルバムのほうもきちんと定期的にリリースしてくれるからファンとしても有難い。
オッターは、DG専属契約歌手なのだが、スウェーデン人として、たとえばスウェーデン歌曲集だとか自分の故郷に関連するテーマがあったりするときは、北欧の高音質レーベルBISからアルバムを出している。
BIS前作の「夏の日」。
まさにスウェーデン歌曲集を集めたもので、近来稀に見る優秀録音だと自分は思っていた。BISらしいちょっとオフマイク気味のワンポイント録音が、マイクからの程よい距離感を感じさせ、絶妙な空間感がある。
これを超える優秀録音はでるのだろうか?
最近のDGのアルバムも素晴らしかったが、正直スタジオ録音のせいなのか、ややデッドに感じてしまい、歌っているところの空間や広がりをあまり感じないのが、自分には不満で、歌や曲は好きなのだけれど、録音が好きじゃないというパラドックスな状態だった。
この「夏の日」効果もあって、自分はオッターのBIS録音は絶対いい!という確信めいたものがあった。だから、今回オッターのBIS新譜がでる、と聞いた瞬間、もう胸ときめいたことは言うまでもない。
![833[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8335B15D.jpg)
「シンプル・ソング」
アンネ・ゾフィー・フォン・オッター、ベンクト・フォシュベリ(オルガン)、他
http://
今回の新譜はオッターにとって、まさに原点回帰のアルバムとなった。
そういうコンセプトを企画としてぶちあげたのだろう。
なによりもジャケットがいい!いかにも音が良さそうだ。
ジャケットのセンスがいいアルバムは、絶対曲もいいし、音もいい。
スウェーデンの宮廷歌手アンネ・ゾフィー・フォン・オッターのキャリアは、彼女が生まれたストックホルムの聖ヤコブ教会から始まった。教会の青少年合唱団で歌い、教会で行われているバッハの「マタイ受難曲」コンサートのソロに起用され、1982年、最初のソロ・コンサートをこの教会で行なった。この時に共演したベンクト・フォシュベリとは、その後30年以上に渡る共演が続いている。
今回のオッターの新譜「シンプル・ソング」は、この聖ヤコブ教会でセッション録音されたアルバムなのだ。
まさに原点回帰。ここからオッターのキャリアは始まった。
聖ヤコブ教会という名の教会は、それこそヨーロッパの至る国にある教会で、今回話をしているのはストックホルムにある聖ヤコブ教会のこと。
ストックホルム 聖ヤコブ教会
教会の内装空間の写真も探したが、どれもストックホルムではない聖ヤコブ教会のものばかり。
今回のアルバムは、まさにオッターが最も大切にしている珠玉の17曲を選んだもので、「宗教」と「心」でつながる17の曲。「典礼の手かせ足かせを逃れ、自然に湧き出る賛美の心を高らかに歌え」を基本のスタンスに歌っているのだそうだ。
アルバム全体を聴いて感じるのは、やはりパイプオルガンの音色がとても強烈で、アルバム全体のトーンを支配している感じがする。
でも実際は、ヴァイオリン、チェロ、フルート、ヴィオラ、ハープ、それにエレキギター!などかなり多彩な音色に囲まれているのだ。
とにかく聴いていて、とてもいい曲ばかり。
前作の「夏の日」とはまたちょっと趣が違う良さがある。
かなり毛色が違う。
気配としては、宗教曲の色が強い感じがするかな。
アルバムのタイトルになった「シンプル・ソング」は、バーンスタインのミサ曲。
どこかで聴いたことがあると思ったら、マーラーが交響曲第3番と第2番の楽章とした「子供の不思議な角笛」の詩による2曲も入っている。
そしてシュトラウス歌曲も2曲。「たそがれの夢」、「あした!」
リストのアヴェ・マリアもこれまた素晴らしくいい。アヴェ・マリアは本当にどの作曲家の曲でも究極に癒されるね。
自分が1番心ときめいたこのアルバムの中の最高の曲は、ラストに入っている曲。
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」の「すべての山を登れ」。
なんて、カッコイイ曲なんだ!
オッターが最高に素敵に見えてしまう最高の曲だ。サウンド・オブ・ミュージックは当然よく知っているけれど、こんなドライブ感の効いた格好よさは、かなり興奮した。オッターの歌い方もかっこいいよね。この曲に完全にやられました。
パイプオルガンが最高に主張する曲。このアルバムの中で一番オルガンが目立っている曲。もうトラポの1曲リピート機能を使って、ずっと1日中繰り返して聴いています。(笑)
でもこの日記を読んでくれている読者はそんなことを聞きたいのではないだろう?(笑)
わかってるって。(^^)
録音超絶素晴らしいです!
やっぱりオーディオファンにとって、このファクターは絶対譲れないところ。
この新譜を紹介するには、ここを一番言いたかった。
昨今の録音技術の進歩は凄い。最近リリースされる新譜は、みんな音が洗練されているよね。いかにも新しい録音という感じです。
ダイナミックレンジ32bitで録ってるのかな?(笑)
それだけ縦軸の深さ(レベルの高低)が素晴らしい。
いや周波数レンジのほうも384KHzはいっているかな?それだけ高低音域の横軸の両側に、す~っと伸びていて解像感高いです。
1発目の出音で、その洗練された空気感がすごくて鳥肌が立つ。
いい録音かどうかは、最初の出音を聴いただけで、もうわかっちゃうんだよね。あとは、ずっと聴いていてもその印象が変わることはほとんどあまりない。
教会らしい大空間にいることがよくわかり、オッターの声がよく通るのだ。
部屋がその教会の大空間にワープしたかのような空間感だ。
情報量も多いし・・・でもこんなことはごちゃごちゃオーディオ術語を並べ立てて話すのはまさに野暮というもの。
黙って聴いてくれれば、それでいい。
このオルガンの低域のボリューム感を出すのがオーディオ・スキルかもですね。
クレジットを見ると、驚いたことにマスターフォーマットは、PCM 96/24だそうだ。(驚)
いまどき、こんな昔の諸元でこれだけの素晴らしい録音ができちゃうのは、やっぱり教会独特の空間、残響の長さなどの残響感の賜物なんだろうし、それに単にスペックが高ければいい録音ができるほど甘い世界じゃない、ということかね。
やっぱりエンジニアの編集、ポスプロの世界もかなり大きなウェートを占めるのだろう。
いかに奥行き感、立体感を出すか、など彼らのセンス、腕の見せ所だ。
その他の機器は、BISなので、RMEのヘビーユーザー。DAWはもう定番のPyramix。
今回の録音プロジェクトは、Take5 Music Productionがおこなっている。
いままでBISの録音制作を手掛けてきたトーンマイスター5人が独立して、「Take 5 Music Production」という別会社を設立しているのだ。 主なミッションは、BISの録音制作を担う、ということで、フィリップス・クラシックスの録音チームが、ポリヒムニアになったことや、ドイツ・グラモフォンの録音チームが、エミール・ベルリナー・スタジオとなったことと同様のケースのように思えるのだが、ただ唯一違う点は、現在もBISには、社内トーンマイスターが在籍して、音に関わる分野の責任を持っていることだ。
Take5のメリットは、これまで通りBIS作品の制作を担いながら、同時に他のレーベルの制作も担当できる、さらには、ダウンロードのプラットフォームも構築していくという視野が持てるというところにある。
BISは基本は、マスターはPCM 96/24だね。彼らは昔からそう。
Take5は最近、パリで賞を受賞したみたいで乗っています。
今回の録音は、プロデューサー&サウンド・エンジニアは、Marion Schwebel氏。編集やミキシングもそうだ。
Nice Job!でした。
では、ちょっと、その聖ヤコブ教会でのセッション録音の様子を。

聖ヤコブ教会のパイプオルガン。
1976年に設置されたマークセン・オルガンです。

オルガンを弾いているのが、オッターの長年のずっとパートナーだったそのピアニストとして知られるベンクト・フォシュベリ。BIS前作の夏の日でもパートナーとして録音に参加していました。今回オルガンのレジストレーション(オルガンのストップを決めること)を担当したのも彼の息子のミケール・フォシュベリでした。

オッター様、絶好調!
教会の大空間によく声が通ってます。
とにかく教会の大空間、そしてこのパイプオルガン、そしてオッターの声、堪らんサウンドです!

アルバム・トップの「シンプル・ソング」では、なんとエレキ・ギターも入ります。(ボロンという感じ)弾いているのは、なんと!オッターの息子さんです!! 今回の録音は、家族全員参加してのアットホームな録音だったんですね。

今回のマイクは、ノイマン、DPAそしてSchoepsのマイクを使ったようですが、オッターの声を録っているのはノイマンですかね。ステレオ配置セッティングです。


みんなで検討中・・・。
現場でのセッション録音は、大体現場のミキシングでそのほとんどの完成度が決まってしまいます。あとでレーベル・スタジオでどうにかしようと思ってもそんなに大きくは変わらないもの。現場が勝負。事件は現場で起こっているんだ!(笑)
この方が、Take5のMarion Schwebel氏なのかな?(笑)
オッターは、今年の3月に旦那さまが、#MeTooのセクハラ告発で、責められて、自殺してしまうという悲劇があったばかり。人生のパートナーを失って、どれほどの落胆、心中いかなるものか、察するに余りあるが、どうか前向きに頑張ってほしい。
自分も最近心が折れるとは、まさにこのことか!と思ったことがあったが、人生はプラス指向で生きることの大切さを学んだばかり。
オッター様、がんばれ!!!
アルゲリッチのショパンコンクール1965 [ディスク・レビュー]
自分のクラシック・ピアノへの開眼、その基本は、ポリーニ、アルゲリッチだった。
いままでどれだけの彼らのアルバムを聴いて来たことだろう。両人ともショパンコンクールで世に出たある意味ショパン系ピアニストなのだが、その後の活躍はショパンに限らず、いろいろな作曲家の作品を世にリリースして幅広い芸術の域を我々に示してきてくれた。
その中でも、やっぱり自分の中でアルゲリッチに対する想いは、絶大なものがある。
やっぱり彼女はとても激情家で、恋多き女性、そしてあの剃刀のように切れのいい強打鍵のパワフルな演奏スタイル、すべてにおいて、生きる伝説カリスマなのだ。
彼女の最大の魅力は、やはりとても人間っぽいというところだと思う。
とても恋多き女性、ショパンコンクールの審査結果に納得がいかずボイコット事件、つい最近では、元夫のデュトワの#MeTooによるセクハラ告発問題で、デュトワが干されたときも、まっさきにその発信国になったアメリカの公演を全キャンセル、そして自分がピアノのソリストとしての公演の指揮者にデュトワを指名とか・・・その気性の激しさ、そしてすぐさま行動に移すその積極性、あきらかにアルゲリッチだ。
彼女には、強い心、自分の芯というものがあって、それがぶれない。
彼女の実演に接したときでも、ピアノに座るなり、演奏の前の心の準備のような間を置くことなどなく、座るなり、さっさと弾き始めてしまうのだ。(笑)
そういうあっけらかんとした器の大きさというか、からっとした性格がいかにもアルゲリッチらしくとてもいい。
けっしてエリート然とした近寄りがたい演奏家というよりは、もっと愛情の深さ、激情家、失敗も多々あるといったその波瀾万丈な人生にとても人間っぽい俗っぽさ、誰からも愛される秘密がそこにあるのではないのではないか、と思ってしまう。
アルゲリッチのドキュメンタリー映画も結構観ている。
「いろんな作曲家を弾いてきたけれど、やっぱり自分はシューマンがとても好きなんだと思う。
シューマンの曲を弾いていると、とても幸せな気持ちになり、自分に合っていると思う。」
そんなことを発言していて、とても興味深かった。
ふだんの生活もたくさんの若い演奏家、いわゆる取り巻きとも言える仲間たちといっしょに暮らしていて、慕われている。そこには、若者たちに自分のいままでの演奏家としての糧を伝えていっていることは間違いないことだ。
日本ともとても所縁が深く、別府アリゲリッチ音楽祭をやってくれて毎年必ず日本の地を踏んでくれている。本当にありがたいことです。
衝撃の1965年のショパンコンクール優勝を経て、まさに若い頃から第1線で活躍しつつ、現在ではもうレジェンド、カリスマ的な神々ささえ感じる。
コンクールというのは、ある意味、演奏家が世に出るためにひとつのきっかけなのかもしれないが、大事なのはコンクール優勝ではなく、そのコンクールの後。
コンクールで優勝して名を馳せても、その後さっぱりで消えていった演奏家のいかに多いことか!
コンクールの後に、つねに第1線で居続けることの難しさ、たとえ浮き沈みが多少あっても、それが晩年に至るまで持続できるというのは、本当に運や巡りあわせもあるかもしれないが、大変なことなのだ。
ショパンコンクールではいろいろな課題曲が演奏されるが、その中でもオオトリのメインは、ショパンピアノ協奏曲第1番。
この曲はもちろん大好きで大好きで堪らない。
この曲の録音で名盤と言われるものは、過去にいろいろある。
じっくり創り込まれた感のある人工的なセッション録音。そしてまさに臨場感を味わえるようなライブ録音。セッション録音やライブ録音でも、このショパンピアノ協奏曲は、本当にいい名盤がたくさんある。
その中で、自分がどうしても忘れられない、この曲だったら、この1枚というのがあるのだ。
それがアルゲリッチが優勝した時の1965年のショパンコンクールでのショパンピアノ協奏曲第1番。
![41Y47N4ZYHL[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_41Y47N4ZYHL5B15D.jpg)
もうすでに廃盤になっていて、中古市場にしか出回らないディスクになってしまったが、自分はこの曲だったら、この演奏がどうしても忘れられない。ある意味、この曲の自分のバイブル的な存在にもなっている。
この曲は、最初にオケの前奏がかなり長い時間あるのだが、このときのコンクールでは、そういうのをかなり端折って略して演奏している。
そしてもうバリバリの当時のライブ録音。観客席の咳き込みなど、リアルにそのままダイレクト録音だ。いまのように編集の時に咳き込みをカットなどという小賢しいことはやらない。
このコンクール盤は、当時雨天の雷だったようで、外で雷が鳴っているのが、何回も演奏中に音として録音されているのだ。(笑)
そういう当時のコンクール・ヴァージョン的に編集されたショパンピアノ協奏曲第1番で、現代の完成度の高い作品と比べると聴き劣りするかもしれないが、自分の中では、この曲で、この盤を超えるものはないと思っている。
とにかくいま聴いても、身震いがするほど、新鮮で衝撃的だ。若い頃に、この録音を聴いて、当時のショパンコンクールでアルゲリッチが優勝した時ってどんな感じだったんだろうな~ということを夢想していたことを思い出す。
その映像がもし残っているならぜひ観てみたいと恋焦がれていた。
だって、1965年の大会に優勝ってことは、もうほとんど自分が産まれた年に優勝してこの世界にデビューしている、ということ。
大変な尊敬の念を抱いていた。
当時、クラシックのジャンルで、ピアノといえば、アルゲリッチから入っていった人だったので、当時猛烈に彼女の録音を買いまくっていくうちに、彼女の原点はこの1965コンクールの演奏にある、ということに行き着いたのだった。
1965年の優勝のときの映像、もちろんこのショパンピアノ協奏曲第1番を弾いている演奏姿を観てみたい、とずっと恋焦がれていた。
そういう過去の偉業、自分がそのときにリアルタイムに接することができなかった事象に、クラシックファンって妙に魅力を感じるそういう人種なのではないか?と自分は常々思っている。
過去の大指揮者、演奏家などの名盤蒐集というジャンルが、クラシック界で根強い人気なのは、なんか自分がリアルタイムに接することのできなかったことに対してなんとも言えないミステリアスな魅力を感じて、そういう探求心魂に火をつける、というか。。。そういう感じってあるのではないだろうか。
1965年のアルゲリッチ優勝大会には、自分はまさにそのような感覚を抱いて相当憧れた。
数年後に、その夢は成就した。
1965年大会アルゲリッチ優勝のときの映像が残っていたのだ!
もちろんメイン課題曲のピアノ協奏曲第1番の演奏。
いまやこれも廃盤になって手に入らないのだが、
ショパン国際ピアノ・コンクールの記録「ワルシャワの覇者」DVD 32枚セット
こういうショパンコンクールの歴史的に残されている貴重な過去の映像を集めた夢のようなパッケージ商品が発売されたのだ。結構高かった。その中に、アルゲリッチ優勝の第7回大会もあるし、なんとポリーニ優勝の第6回大会もあるのだ。
当時ヤフオクで10万くらいの大枚はたいて買ったと思うが、嬉しかった思い出だ。
もちろん白黒画像だが、よく残っていた。あの伝説の水玉模様のドレスを着て、コンクール会場に入場してきて、自分が何回も聴き込んだあのコンクールライブをいま目の前で演奏している。
なんともいえない感動だった。
アルゲリッチらしいピンポンが跳ねるように、鍵盤を軽やかにタッチする場面、後で述べるが、この箇所がこの曲で自分が一番拘るところ。そこを見事に映像として観ることができた。
生きててよかった!と当時真剣に思った。
このDVDセットは、じつは演奏の模様収録だけでなく、インタビューやショパンコンクールの歴史について解説するなど、大半は演奏よりもそういうところに割かれていて、自分は少々退屈に思ってしまった。
愚かなことに、結局アルゲリッチのその場面を見たら、あとはほとんど死蔵という感じだったので、結局売却してしまった。今思えば、ずいぶん勿体ないことをしたと思う。
なぜ、アルゲリッチのショパンコンクール1965の演奏なのか?
アルゲリッチは、その後、後年にこのショパンのピアノ協奏曲第1番を何回も再録している。
でもそこには、自分がコンクールライブ盤で感じたような緊張感、鋭さというのを感じなかった。
どこか、創り込まれている安心な世界での表現で、ビビッとくるほど緊張や感動をしなかった。
追い込まれた極度の緊張感の中でしか起こり得なかった奇跡、そんなミステリーがこのライブ録音にはある。
コンクール独特の緊張感、まさに伝説の名演奏。
この曲のこれに勝る名演奏はない。
アルゲリッチ本人も、このショパンコンクール録音が気に入っていたという話もある。
1965年第7回国際ショパン・コンクールにおいてアルゲリッチが優勝した時のライヴアルバム。
正規盤とこんなジャケット違いのものも当時収集していた。(中身は同じ。)
「ピアノ協奏曲第1番」「スケルツォ第3番」「3つのマズルカ 作品59」で演奏はワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団。24歳という若きアルゲリッチの自由奔放で情熱的な演奏が素晴らしい。
ちなみに、コンクールでの彼女の使用ピアノはスタインウェイでもベーゼンドルファーでもなく、ベヒシュタインだったというのが驚きである。
ポーランドの人々が「ともかくマズルカだけはポーランドを知らなくては弾けない」と言い切りがちなこの曲を、ショパンコンクールの準備をするまでマズルカが何かも知らなかったというこのアルゼンチン出身のピアニストが、そんなうんちくを蹴散らすかのような見事な演奏を披露しているのだ。
なぜ、数多あるショパンピアノ協奏曲第1番の録音の中で、この1965のショパンコンクール盤がいいのか?
いま改めて聴いてみると、アルゲリッチらしい強打腱のオンパレードで緩急はまるでなし、ある意味一本調子で現代の流麗な語り口のピアニストたちの演奏と比較すると、いくぶん乱暴で粗野な印象を受けることは確か。
通常、20分かかる第1楽章を16分で弾いている。
それくらい高速で強打腱、そして一本調子というのが贔屓目なしの率直な感想だろう。
まさに若いよな~という感じの演奏だ。
でも、若かりし頃の自分はこの演奏に惚れ込んだ。
特にこだわったのは第3楽章の冒頭でピアノが最初に入るところ。
ここはアルゲリッチのこのコンクール盤では、まるで鍵盤の上でピンポンが跳ねるように、じつにリズミカルに跳ね上げるように弾く。これが自分には堪らなかった。
それ以来、この曲を聴くときは、この部分はどうなのか?を聴いて、この盤はよい、よくないなどの判断をするようになってしまった。(笑)
ある意味変わってる奴。(笑)
それくらい自分にとって大事な箇所だった。
他のアーティストのこの曲の録音のこの部分は、大抵なめるように、軽やかなにさらっと弾き流すのだ。これが自分には物足りなかった。もっと強く鍵盤を弾くかのようにピンポン的に弾いてくれるのが好きだった。
いままで聴いてきたこの曲の録音では、この部分は大半がさらっと流す弾き方が大勢を占める。
そんな聴き方をするようになったのも、この1965コンクール盤による影響が大きい。
自分にとって、特にピアノは、そのピアニストの解釈によって、そして嵌るきっかけとなった最初の曲に支配されることが多く、その影響のために、いつまで経っても新しく出てくる新譜に対して寛容になれない、という保守的な自分がいる。
ピアノ協奏曲では、自分にとって命のラフマニノフのピアノ協奏曲第3番についてもまったく同じだ。あの曲もアルゲリッチの演奏がリファレンスになってしまっている。
いつまで経っても新しい新譜を受け入れられる寛容さが持てない。
じゃあポリーニの1960年のショパンコンクール優勝のときのこの曲の第3楽章の冒頭のピアノが入るところはどうだったのだろうか?
これもずいぶん悩んだというか、聴きたくて恋焦がれた。(笑)
ポリーニのコンクール時の演奏は、なかなか音源として出なかったので、時間がかかったが、ようやくDGがポリーニ全集ということでBOXスタイルの全集を出してくれた。
その中に、この1960年大会のポリーニによるこの曲の演奏が収録されているのだ。
やった~!とう感じで、もちろん購入した。
聴いた感想は、まぁ~さらっという感じでもないし、ピンポンのように弾く感じでもなく、中庸でした。自分的には、あまり印象に残らなかったような・・・(笑)
後年、この曲に関しては、いろいろな名盤が出たが、自分的に納得いく素晴らしい演奏、録音と思ったのは、クリスティアン・ツィンマーマンの弾き振りによるピアノ協奏曲第1番&第2番。
これは世間の評判通り、自分も素晴らしい演奏だと感じた。
いわゆる創り込まれた芸術の域というか、そういう完成度があった。
あと、ライブ、つまり生演奏ではどうだったか?
記憶がなかなか思い起こせないのだけれど、ウィーンフィルが定期的に毎年サントリーホールで公演する来日公演で、ランランがこの曲を演奏して、そのときは鳥肌が立つくらい興奮した素晴らしい演奏だった記憶がある。
いずれにせよ、時代を超えたピアノ協奏曲の名曲中の名曲ということで、ふっと思い立ち日記にしてみた。ピアノ協奏曲を語る上では忘れられない、そして絶対避けては通れない1曲だ。
そういえば、来年?ショパンコンクールがまたやってくるのではないだろうか?
あの場で、また新しい時代のスターが生まれるのだろう、きっと。
いままでどれだけの彼らのアルバムを聴いて来たことだろう。両人ともショパンコンクールで世に出たある意味ショパン系ピアニストなのだが、その後の活躍はショパンに限らず、いろいろな作曲家の作品を世にリリースして幅広い芸術の域を我々に示してきてくれた。
その中でも、やっぱり自分の中でアルゲリッチに対する想いは、絶大なものがある。
やっぱり彼女はとても激情家で、恋多き女性、そしてあの剃刀のように切れのいい強打鍵のパワフルな演奏スタイル、すべてにおいて、生きる伝説カリスマなのだ。
彼女の最大の魅力は、やはりとても人間っぽいというところだと思う。
とても恋多き女性、ショパンコンクールの審査結果に納得がいかずボイコット事件、つい最近では、元夫のデュトワの#MeTooによるセクハラ告発問題で、デュトワが干されたときも、まっさきにその発信国になったアメリカの公演を全キャンセル、そして自分がピアノのソリストとしての公演の指揮者にデュトワを指名とか・・・その気性の激しさ、そしてすぐさま行動に移すその積極性、あきらかにアルゲリッチだ。
彼女には、強い心、自分の芯というものがあって、それがぶれない。
彼女の実演に接したときでも、ピアノに座るなり、演奏の前の心の準備のような間を置くことなどなく、座るなり、さっさと弾き始めてしまうのだ。(笑)
そういうあっけらかんとした器の大きさというか、からっとした性格がいかにもアルゲリッチらしくとてもいい。
けっしてエリート然とした近寄りがたい演奏家というよりは、もっと愛情の深さ、激情家、失敗も多々あるといったその波瀾万丈な人生にとても人間っぽい俗っぽさ、誰からも愛される秘密がそこにあるのではないのではないか、と思ってしまう。
アルゲリッチのドキュメンタリー映画も結構観ている。
「いろんな作曲家を弾いてきたけれど、やっぱり自分はシューマンがとても好きなんだと思う。
シューマンの曲を弾いていると、とても幸せな気持ちになり、自分に合っていると思う。」
そんなことを発言していて、とても興味深かった。
ふだんの生活もたくさんの若い演奏家、いわゆる取り巻きとも言える仲間たちといっしょに暮らしていて、慕われている。そこには、若者たちに自分のいままでの演奏家としての糧を伝えていっていることは間違いないことだ。
日本ともとても所縁が深く、別府アリゲリッチ音楽祭をやってくれて毎年必ず日本の地を踏んでくれている。本当にありがたいことです。
衝撃の1965年のショパンコンクール優勝を経て、まさに若い頃から第1線で活躍しつつ、現在ではもうレジェンド、カリスマ的な神々ささえ感じる。
コンクールというのは、ある意味、演奏家が世に出るためにひとつのきっかけなのかもしれないが、大事なのはコンクール優勝ではなく、そのコンクールの後。
コンクールで優勝して名を馳せても、その後さっぱりで消えていった演奏家のいかに多いことか!
コンクールの後に、つねに第1線で居続けることの難しさ、たとえ浮き沈みが多少あっても、それが晩年に至るまで持続できるというのは、本当に運や巡りあわせもあるかもしれないが、大変なことなのだ。
ショパンコンクールではいろいろな課題曲が演奏されるが、その中でもオオトリのメインは、ショパンピアノ協奏曲第1番。
この曲はもちろん大好きで大好きで堪らない。
この曲の録音で名盤と言われるものは、過去にいろいろある。
じっくり創り込まれた感のある人工的なセッション録音。そしてまさに臨場感を味わえるようなライブ録音。セッション録音やライブ録音でも、このショパンピアノ協奏曲は、本当にいい名盤がたくさんある。
その中で、自分がどうしても忘れられない、この曲だったら、この1枚というのがあるのだ。
それがアルゲリッチが優勝した時の1965年のショパンコンクールでのショパンピアノ協奏曲第1番。
![41Y47N4ZYHL[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_41Y47N4ZYHL5B15D.jpg)
もうすでに廃盤になっていて、中古市場にしか出回らないディスクになってしまったが、自分はこの曲だったら、この演奏がどうしても忘れられない。ある意味、この曲の自分のバイブル的な存在にもなっている。
この曲は、最初にオケの前奏がかなり長い時間あるのだが、このときのコンクールでは、そういうのをかなり端折って略して演奏している。
そしてもうバリバリの当時のライブ録音。観客席の咳き込みなど、リアルにそのままダイレクト録音だ。いまのように編集の時に咳き込みをカットなどという小賢しいことはやらない。
このコンクール盤は、当時雨天の雷だったようで、外で雷が鳴っているのが、何回も演奏中に音として録音されているのだ。(笑)
そういう当時のコンクール・ヴァージョン的に編集されたショパンピアノ協奏曲第1番で、現代の完成度の高い作品と比べると聴き劣りするかもしれないが、自分の中では、この曲で、この盤を超えるものはないと思っている。
とにかくいま聴いても、身震いがするほど、新鮮で衝撃的だ。若い頃に、この録音を聴いて、当時のショパンコンクールでアルゲリッチが優勝した時ってどんな感じだったんだろうな~ということを夢想していたことを思い出す。
その映像がもし残っているならぜひ観てみたいと恋焦がれていた。
だって、1965年の大会に優勝ってことは、もうほとんど自分が産まれた年に優勝してこの世界にデビューしている、ということ。
大変な尊敬の念を抱いていた。
当時、クラシックのジャンルで、ピアノといえば、アルゲリッチから入っていった人だったので、当時猛烈に彼女の録音を買いまくっていくうちに、彼女の原点はこの1965コンクールの演奏にある、ということに行き着いたのだった。
1965年の優勝のときの映像、もちろんこのショパンピアノ協奏曲第1番を弾いている演奏姿を観てみたい、とずっと恋焦がれていた。
そういう過去の偉業、自分がそのときにリアルタイムに接することができなかった事象に、クラシックファンって妙に魅力を感じるそういう人種なのではないか?と自分は常々思っている。
過去の大指揮者、演奏家などの名盤蒐集というジャンルが、クラシック界で根強い人気なのは、なんか自分がリアルタイムに接することのできなかったことに対してなんとも言えないミステリアスな魅力を感じて、そういう探求心魂に火をつける、というか。。。そういう感じってあるのではないだろうか。
1965年のアルゲリッチ優勝大会には、自分はまさにそのような感覚を抱いて相当憧れた。
数年後に、その夢は成就した。
1965年大会アルゲリッチ優勝のときの映像が残っていたのだ!
もちろんメイン課題曲のピアノ協奏曲第1番の演奏。
いまやこれも廃盤になって手に入らないのだが、
ショパン国際ピアノ・コンクールの記録「ワルシャワの覇者」DVD 32枚セット
こういうショパンコンクールの歴史的に残されている貴重な過去の映像を集めた夢のようなパッケージ商品が発売されたのだ。結構高かった。その中に、アルゲリッチ優勝の第7回大会もあるし、なんとポリーニ優勝の第6回大会もあるのだ。
当時ヤフオクで10万くらいの大枚はたいて買ったと思うが、嬉しかった思い出だ。
もちろん白黒画像だが、よく残っていた。あの伝説の水玉模様のドレスを着て、コンクール会場に入場してきて、自分が何回も聴き込んだあのコンクールライブをいま目の前で演奏している。
なんともいえない感動だった。
アルゲリッチらしいピンポンが跳ねるように、鍵盤を軽やかにタッチする場面、後で述べるが、この箇所がこの曲で自分が一番拘るところ。そこを見事に映像として観ることができた。
生きててよかった!と当時真剣に思った。
このDVDセットは、じつは演奏の模様収録だけでなく、インタビューやショパンコンクールの歴史について解説するなど、大半は演奏よりもそういうところに割かれていて、自分は少々退屈に思ってしまった。
愚かなことに、結局アルゲリッチのその場面を見たら、あとはほとんど死蔵という感じだったので、結局売却してしまった。今思えば、ずいぶん勿体ないことをしたと思う。
なぜ、アルゲリッチのショパンコンクール1965の演奏なのか?
アルゲリッチは、その後、後年にこのショパンのピアノ協奏曲第1番を何回も再録している。
でもそこには、自分がコンクールライブ盤で感じたような緊張感、鋭さというのを感じなかった。
どこか、創り込まれている安心な世界での表現で、ビビッとくるほど緊張や感動をしなかった。
追い込まれた極度の緊張感の中でしか起こり得なかった奇跡、そんなミステリーがこのライブ録音にはある。
コンクール独特の緊張感、まさに伝説の名演奏。
この曲のこれに勝る名演奏はない。
アルゲリッチ本人も、このショパンコンクール録音が気に入っていたという話もある。
1965年第7回国際ショパン・コンクールにおいてアルゲリッチが優勝した時のライヴアルバム。
正規盤とこんなジャケット違いのものも当時収集していた。(中身は同じ。)
「ピアノ協奏曲第1番」「スケルツォ第3番」「3つのマズルカ 作品59」で演奏はワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団。24歳という若きアルゲリッチの自由奔放で情熱的な演奏が素晴らしい。
ちなみに、コンクールでの彼女の使用ピアノはスタインウェイでもベーゼンドルファーでもなく、ベヒシュタインだったというのが驚きである。
ポーランドの人々が「ともかくマズルカだけはポーランドを知らなくては弾けない」と言い切りがちなこの曲を、ショパンコンクールの準備をするまでマズルカが何かも知らなかったというこのアルゼンチン出身のピアニストが、そんなうんちくを蹴散らすかのような見事な演奏を披露しているのだ。
なぜ、数多あるショパンピアノ協奏曲第1番の録音の中で、この1965のショパンコンクール盤がいいのか?
いま改めて聴いてみると、アルゲリッチらしい強打腱のオンパレードで緩急はまるでなし、ある意味一本調子で現代の流麗な語り口のピアニストたちの演奏と比較すると、いくぶん乱暴で粗野な印象を受けることは確か。
通常、20分かかる第1楽章を16分で弾いている。
それくらい高速で強打腱、そして一本調子というのが贔屓目なしの率直な感想だろう。
まさに若いよな~という感じの演奏だ。
でも、若かりし頃の自分はこの演奏に惚れ込んだ。
特にこだわったのは第3楽章の冒頭でピアノが最初に入るところ。
ここはアルゲリッチのこのコンクール盤では、まるで鍵盤の上でピンポンが跳ねるように、じつにリズミカルに跳ね上げるように弾く。これが自分には堪らなかった。
それ以来、この曲を聴くときは、この部分はどうなのか?を聴いて、この盤はよい、よくないなどの判断をするようになってしまった。(笑)
ある意味変わってる奴。(笑)
それくらい自分にとって大事な箇所だった。
他のアーティストのこの曲の録音のこの部分は、大抵なめるように、軽やかなにさらっと弾き流すのだ。これが自分には物足りなかった。もっと強く鍵盤を弾くかのようにピンポン的に弾いてくれるのが好きだった。
いままで聴いてきたこの曲の録音では、この部分は大半がさらっと流す弾き方が大勢を占める。
そんな聴き方をするようになったのも、この1965コンクール盤による影響が大きい。
自分にとって、特にピアノは、そのピアニストの解釈によって、そして嵌るきっかけとなった最初の曲に支配されることが多く、その影響のために、いつまで経っても新しく出てくる新譜に対して寛容になれない、という保守的な自分がいる。
ピアノ協奏曲では、自分にとって命のラフマニノフのピアノ協奏曲第3番についてもまったく同じだ。あの曲もアルゲリッチの演奏がリファレンスになってしまっている。
いつまで経っても新しい新譜を受け入れられる寛容さが持てない。
じゃあポリーニの1960年のショパンコンクール優勝のときのこの曲の第3楽章の冒頭のピアノが入るところはどうだったのだろうか?
これもずいぶん悩んだというか、聴きたくて恋焦がれた。(笑)
ポリーニのコンクール時の演奏は、なかなか音源として出なかったので、時間がかかったが、ようやくDGがポリーニ全集ということでBOXスタイルの全集を出してくれた。
その中に、この1960年大会のポリーニによるこの曲の演奏が収録されているのだ。
やった~!とう感じで、もちろん購入した。
聴いた感想は、まぁ~さらっという感じでもないし、ピンポンのように弾く感じでもなく、中庸でした。自分的には、あまり印象に残らなかったような・・・(笑)
後年、この曲に関しては、いろいろな名盤が出たが、自分的に納得いく素晴らしい演奏、録音と思ったのは、クリスティアン・ツィンマーマンの弾き振りによるピアノ協奏曲第1番&第2番。
これは世間の評判通り、自分も素晴らしい演奏だと感じた。
いわゆる創り込まれた芸術の域というか、そういう完成度があった。
あと、ライブ、つまり生演奏ではどうだったか?
記憶がなかなか思い起こせないのだけれど、ウィーンフィルが定期的に毎年サントリーホールで公演する来日公演で、ランランがこの曲を演奏して、そのときは鳥肌が立つくらい興奮した素晴らしい演奏だった記憶がある。
いずれにせよ、時代を超えたピアノ協奏曲の名曲中の名曲ということで、ふっと思い立ち日記にしてみた。ピアノ協奏曲を語る上では忘れられない、そして絶対避けては通れない1曲だ。
そういえば、来年?ショパンコンクールがまたやってくるのではないだろうか?
あの場で、また新しい時代のスターが生まれるのだろう、きっと。
PENTATONEの新譜:アラベラさんのR.シュトラウスへのトリビュート [ディスク・レビュー]
2004年にデビュー。以来14年間のキャリアの中で17枚のアルバムをリリース。もうしっかりとした中堅どころで、レパートリーもかなり豊富。新譜を出すとしたら、あと何があるんだろう?と思っていたが、リヒャルト.シュトラウスとは!

ヴァイオリン協奏曲、小品集(リヒャルト・シュトラウス)
アラベラ・美歩・シュタインバッハー
ローレンス・フォスター&ケルンWDR交響楽団
https:/
これもおそらく、企画段階から本人といろいろ話し込んだ上で決めたと思われ、心の奥深くにある想いへのトリビュート・アルバムとなった。
アラベラさんは、音楽一家の家庭で育った。
お父さんは、バイエルン国立歌劇場のソロ・コレペティートル。(歌劇場などでオペラ歌手やバレエダンサーにピアノを弾きながら音楽稽古をつけるコーチのこと。)
そしてお母さんは歌手。
お父さんは、有名な歌手を家に招き、頻繁にR.シュトラウスの作品を歌ってもらっていたんだそうだ。シュタインバッハー家ではシュトラウスの音楽に満ち溢れており、R.シュトラウスは、アラベラさんにとって最も近い存在の作曲家となった。
お父さんもお母さんも、シュトラウスの大ファン。
なにを隠そう、アラベラさんの名前は、R.シュトラウスの歌劇「アラベラ」からその名をもらったのだ。
自分が小さい子供の頃、お父さんが歌手に稽古をつけているとき、いつも自分はグランドピアノの下に座っていて、さしずめ音楽で満ち溢れた洞窟みたいな感覚だった。
歌劇「アラベラ」からの有名な二重唱は、両親によって家の手すりに刻みこまれていて、自分が記憶にあるときから、ずっとそれは存在していた。
この二重唱への想いは、ついにR.シュトラウスの作品だけで占められたアルバムを録音しよう!という推進力となった。もちろん歌詞はないけれど、その代わり、思い切ってその部分を私のヴァイオリンで奏でようと思った。
歌手たちは許してくれると思うけど。。。
そんな想いのたけをライナー・ノーツに綴っている。
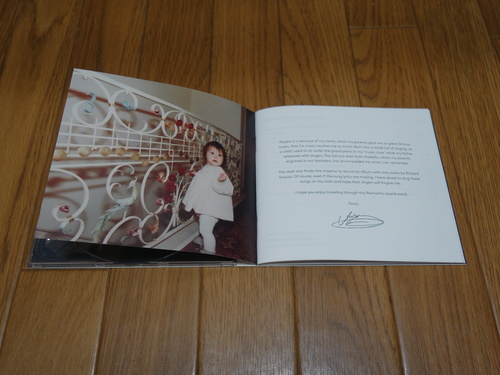
まさか、アラベラさんにとって、R.シュトラウスが、そんなに強烈な運命の作曲家だったとは!
正直いまになって驚かされた。
もちろん、R.シュトラウスは、自分も大好きで、英雄の生涯、ドン・ファン、ばらの騎士、サロメ、そしてなによりシュトラウスで好きなのは、彼の歌曲。もうここにはあげられないくらいたくさんの曲を愛聴してきたので、いまになってそんな告白があると、正直驚かざるを得なかった。
R.シュトラウスは、ドイツの後期ロマン派の作曲家ですね。
彼の書く作品、旋律は、やっぱり感傷的で、とても叙情的。そしてドラマティックな要素もある。
西洋音楽史は、バロック時代~古典派~ロマン派(~そして現代音楽)と大きく3つに大別できると思うが、どの時代も大変魅力的だけれど、自分は、やっぱりロマン派の音楽が好きなんだなぁと思います。ラフマニノフとか。。。
古典派のかっちり型に嵌ったスタイルもいいけれど、やっぱりどこかメランコリックでロマンティックな泣かせるメロディのほうがウルっと来てしまい、感動してしまう。
今回のアルバムは、R.シュトラウスのヴァイオリン協奏曲、そしてアラベラさんが言っていた通り、たくさんのシュトラウス歌曲の数々を歌詞をつけずに、ヴァイオリンで奏でる、いわゆる編曲版、そして運命の歌劇「アラベラ」からの二重唱である「私にふさわしい人が…」で構成されている。
まさに、

ヴァイオリン協奏曲、小品集(リヒャルト・シュトラウス)
アラベラ・美歩・シュタインバッハー
ローレンス・フォスター&ケルンWDR交響楽団
https:/
これもおそらく、企画段階から本人といろいろ話し込んだ上で決めたと思われ、心の奥深くにある想いへのトリビュート・アルバムとなった。
アラベラさんは、音楽一家の家庭で育った。
お父さんは、バイエルン国立歌劇場のソロ・コレペティートル。(歌劇場などでオペラ歌手やバレエダンサーにピアノを弾きながら音楽稽古をつけるコーチのこと。)
そしてお母さんは歌手。
お父さんは、有名な歌手を家に招き、頻繁にR.シュトラウスの作品を歌ってもらっていたんだそうだ。シュタインバッハー家ではシュトラウスの音楽に満ち溢れており、R.シュトラウスは、アラベラさんにとって最も近い存在の作曲家となった。
お父さんもお母さんも、シュトラウスの大ファン。
なにを隠そう、アラベラさんの名前は、R.シュトラウスの歌劇「アラベラ」からその名をもらったのだ。
自分が小さい子供の頃、お父さんが歌手に稽古をつけているとき、いつも自分はグランドピアノの下に座っていて、さしずめ音楽で満ち溢れた洞窟みたいな感覚だった。
歌劇「アラベラ」からの有名な二重唱は、両親によって家の手すりに刻みこまれていて、自分が記憶にあるときから、ずっとそれは存在していた。
この二重唱への想いは、ついにR.シュトラウスの作品だけで占められたアルバムを録音しよう!という推進力となった。もちろん歌詞はないけれど、その代わり、思い切ってその部分を私のヴァイオリンで奏でようと思った。
歌手たちは許してくれると思うけど。。。
そんな想いのたけをライナー・ノーツに綴っている。
まさか、アラベラさんにとって、R.シュトラウスが、そんなに強烈な運命の作曲家だったとは!
正直いまになって驚かされた。
もちろん、R.シュトラウスは、自分も大好きで、英雄の生涯、ドン・ファン、ばらの騎士、サロメ、そしてなによりシュトラウスで好きなのは、彼の歌曲。もうここにはあげられないくらいたくさんの曲を愛聴してきたので、いまになってそんな告白があると、正直驚かざるを得なかった。
R.シュトラウスは、ドイツの後期ロマン派の作曲家ですね。
彼の書く作品、旋律は、やっぱり感傷的で、とても叙情的。そしてドラマティックな要素もある。
西洋音楽史は、バロック時代~古典派~ロマン派(~そして現代音楽)と大きく3つに大別できると思うが、どの時代も大変魅力的だけれど、自分は、やっぱりロマン派の音楽が好きなんだなぁと思います。ラフマニノフとか。。。
古典派のかっちり型に嵌ったスタイルもいいけれど、やっぱりどこかメランコリックでロマンティックな泣かせるメロディのほうがウルっと来てしまい、感動してしまう。
今回のアルバムは、R.シュトラウスのヴァイオリン協奏曲、そしてアラベラさんが言っていた通り、たくさんのシュトラウス歌曲の数々を歌詞をつけずに、ヴァイオリンで奏でる、いわゆる編曲版、そして運命の歌劇「アラベラ」からの二重唱である「私にふさわしい人が…」で構成されている。
まさに、
アラベラ・美歩・シュタインバッハーのトリビュート・アルバム
なのだ。
本人の想いが深いアルバムは、やはり聴き手側にも心の構えが必要。
しっかり心して聴きました。(笑)
パートナーのオーケストラは、ケルンWDR交響楽団。指揮はPENTATONEでもうずっとパートナーでやってきたローレン・フォスター。
シュトラウスのヴァイオリン協奏曲は、ひょっとしたら昔聴いたことがあるかもしれないけれど、おそらく初めてだと思う。星の数ほどあるシュトラウスの有名な曲で、ヴァイオリン協奏曲って正直意外というか、ダークホースというか普段あまり聴かれないレアな曲だと思う。
シュトラウスの唯一のヴァイオリン協奏曲で、初期の作品。古典派風の協奏曲の伝統に従ったかっちり型の曲で、ある意味、シュトラウスの曲らしくない感じなのだが(初期の作品だからね。)なかなか素晴らしい。
オケの重厚な音はさすがだが、どちらかというとヴァイオリンがメロディで走ってどんどんオケを引っ張っていく感じの曲。整然とした形式への志向がある初期の時代に書かれたので、いわゆる古典派の音楽みたいなのだが、その要所要所で、シュトラウスらしい感傷的なロマン的な旋律も垣間見える感じで、不思議な魅力がある。
ヴァイオリン独奏の部分は、結構、技巧的に難しいテクニックを感じるところもあり、激しい部分、朗々と歌っている部分、しっとり聴かせる部分などの緩急のつけかた、ドラマティック。
特に第3楽章がいい!
リズミカルでアップテンポで軽快に走って、重音奏法ありなど、アラベラさんのヴァイオリンが冴えわたって疾走感ある。
レアな曲だが、とてもいい曲だと思いました。
そして、いよいよお楽しみのシュトラウス歌曲。
ここは私はうるさいですぞ。(笑)
自分は歌の世界も好きで、特にオペラ歌手のオペラアリア集みたいなものも好きだが、歌曲、いわゆるリートの世界もとても好き。
歌曲の世界は、ある意味その歌詞の部分に、その曲の価値がある場合が多く、オペラよりその比重は大きいと思う。
その歌詞の部分を削除して、ヴァイオリン1本で、その歌曲の世界を表現しようというのだから、そこに今回のアラベラさんの勝負処がある。
シュトラウス歌曲は、それこそ、エディット・マティス、エディタ・グルベローヴァ、ディアナ・ダムラウの3人が自分の定番というか愛聴盤。ほかの歌手も結構聴いているが、やはりこの3人が多いかな。
5曲の歌曲のヴァイオリン編曲。
いやぁ、どれも聴いたことあるけれど、普段馴染んで聴いている曲で、歌詞がないのはどうも最初やっぱり違和感。(笑)
あれ?って感じ。
でも何回も聴き込んでいると、ヴァイオリンでの表現もなかなか秀逸。あっという間に引き込まれました。
特に自分は、「献呈」と「ツェツィーリエ」が大好き。特に「ツェツィーリエ」はなぜか思いっきり反応してしまう。この曲は、歌で表現した曲で聴くと、その投げセリフ的な歌い方というか、メロディの良さも含め、ものすごく格好良く感じる曲で、シュトラウス歌曲の中でも大好きな曲。
そのヴァイオリン表現も素晴らしかった。
子供の頃に自分の家で歌手たちが、たくさんのシュトラウス歌曲を歌っているのを聴いて育ってきた、その歌曲をシュトラウスへのトリビュートという意味を込めて、歌詞なしでヴァイオリンで表現する!そこに彼女の想いが込められているのだ。
そして最後に運命の、歌劇「アラベラ」からの二重唱である「私にふさわしい人が…」。
自分の名前はこのオペラから付けられた。
そして自宅の手すりには、この有名な二重唱の歌詞が両親によって刻み込まれている。
じつに大河のごとく美しい曲。まさにゆったりと流れる、そこに身を任せていることがいかに心地よいか。
この曲に対する歌詞のありなしには、さほど拘らないので、ヴァイオリンの表現だけで、自分はとても幸せな気持ちになった。あらためて、オペラ「アラベラ」を見直して、この部分のアリアの二重唱を確認してみたいと思う。
アラベラさんの深い想いがつまったアルバム。
とても素晴らしかった。
しっかり受け止めました。
今回の録音は、ケルンWDR交響楽団の本拠地であるケルン・フィルハーモニーで行われたとクレジットがある。
そこに自分の謎があった。(笑)
本人の想いが深いアルバムは、やはり聴き手側にも心の構えが必要。
しっかり心して聴きました。(笑)
パートナーのオーケストラは、ケルンWDR交響楽団。指揮はPENTATONEでもうずっとパートナーでやってきたローレン・フォスター。
シュトラウスのヴァイオリン協奏曲は、ひょっとしたら昔聴いたことがあるかもしれないけれど、おそらく初めてだと思う。星の数ほどあるシュトラウスの有名な曲で、ヴァイオリン協奏曲って正直意外というか、ダークホースというか普段あまり聴かれないレアな曲だと思う。
シュトラウスの唯一のヴァイオリン協奏曲で、初期の作品。古典派風の協奏曲の伝統に従ったかっちり型の曲で、ある意味、シュトラウスの曲らしくない感じなのだが(初期の作品だからね。)なかなか素晴らしい。
オケの重厚な音はさすがだが、どちらかというとヴァイオリンがメロディで走ってどんどんオケを引っ張っていく感じの曲。整然とした形式への志向がある初期の時代に書かれたので、いわゆる古典派の音楽みたいなのだが、その要所要所で、シュトラウスらしい感傷的なロマン的な旋律も垣間見える感じで、不思議な魅力がある。
ヴァイオリン独奏の部分は、結構、技巧的に難しいテクニックを感じるところもあり、激しい部分、朗々と歌っている部分、しっとり聴かせる部分などの緩急のつけかた、ドラマティック。
特に第3楽章がいい!
リズミカルでアップテンポで軽快に走って、重音奏法ありなど、アラベラさんのヴァイオリンが冴えわたって疾走感ある。
レアな曲だが、とてもいい曲だと思いました。
そして、いよいよお楽しみのシュトラウス歌曲。
ここは私はうるさいですぞ。(笑)
自分は歌の世界も好きで、特にオペラ歌手のオペラアリア集みたいなものも好きだが、歌曲、いわゆるリートの世界もとても好き。
歌曲の世界は、ある意味その歌詞の部分に、その曲の価値がある場合が多く、オペラよりその比重は大きいと思う。
その歌詞の部分を削除して、ヴァイオリン1本で、その歌曲の世界を表現しようというのだから、そこに今回のアラベラさんの勝負処がある。
シュトラウス歌曲は、それこそ、エディット・マティス、エディタ・グルベローヴァ、ディアナ・ダムラウの3人が自分の定番というか愛聴盤。ほかの歌手も結構聴いているが、やはりこの3人が多いかな。
5曲の歌曲のヴァイオリン編曲。
いやぁ、どれも聴いたことあるけれど、普段馴染んで聴いている曲で、歌詞がないのはどうも最初やっぱり違和感。(笑)
あれ?って感じ。
でも何回も聴き込んでいると、ヴァイオリンでの表現もなかなか秀逸。あっという間に引き込まれました。
特に自分は、「献呈」と「ツェツィーリエ」が大好き。特に「ツェツィーリエ」はなぜか思いっきり反応してしまう。この曲は、歌で表現した曲で聴くと、その投げセリフ的な歌い方というか、メロディの良さも含め、ものすごく格好良く感じる曲で、シュトラウス歌曲の中でも大好きな曲。
そのヴァイオリン表現も素晴らしかった。
子供の頃に自分の家で歌手たちが、たくさんのシュトラウス歌曲を歌っているのを聴いて育ってきた、その歌曲をシュトラウスへのトリビュートという意味を込めて、歌詞なしでヴァイオリンで表現する!そこに彼女の想いが込められているのだ。
そして最後に運命の、歌劇「アラベラ」からの二重唱である「私にふさわしい人が…」。
自分の名前はこのオペラから付けられた。
そして自宅の手すりには、この有名な二重唱の歌詞が両親によって刻み込まれている。
じつに大河のごとく美しい曲。まさにゆったりと流れる、そこに身を任せていることがいかに心地よいか。
この曲に対する歌詞のありなしには、さほど拘らないので、ヴァイオリンの表現だけで、自分はとても幸せな気持ちになった。あらためて、オペラ「アラベラ」を見直して、この部分のアリアの二重唱を確認してみたいと思う。
アラベラさんの深い想いがつまったアルバム。
とても素晴らしかった。
しっかり受け止めました。
今回の録音は、ケルンWDR交響楽団の本拠地であるケルン・フィルハーモニーで行われたとクレジットがある。
そこに自分の謎があった。(笑)
SNSで公開された、「いま新譜の録音中で~す。」の写真はどう見ても、ケルンフィルハーモニーではないのだ。(笑)
どこかの会館を使っているように思えてしまう。
この写真を観たとき、ポリヒムニアによる録音、またジャン・マリー・ヘーセン氏とエルド・グロード氏による黄金タッグということで、自分は今回も安泰ということで、ホッと安堵した。
でも送られてきた新譜のクレジットを見ると、ちょっと謎だった。
まずプロデューサーが違う。いつものジョブ・マルセ氏ではない。
今回はWDRとPENTATONEの共同プロジェクトのようなのだ。
しかもいつものバランス・エンジニア&編集というクレジットではなく、レコーディング・プロデューサー&編集に、レコーディング・エンジニアにレコーディング・テクニシャンってなんだそれ?(笑)
名前のクレジットも聴いたことのない名前ばかり。
写真ではしっかりジャン・マリー・ヘーセン&エルド・グロード、映っているのに、彼らの名前は見当たらない。
この肩書って、ドイツの放送局のトーンマイスター制度にあるような名前だから、ひょっとしたら今回のポスプロの仕上げは、WDR側でやったのかもしれない。あるいはポリヒムニアいるかもだけど、若手への世代交代で育成かな?
だから、という訳ではないが。。。
最初聴いたときは、いまいちではあった。サラウンドで聴いているのだが、部屋中にふわ~と広がる音場感や縦軸の深さなど、なんかいつもより物足りない感じで、クレジットを見てみたら、やっぱりそうか!という感じだった。
でも何回も聴き込んで、そして休日の本日、大音量で聴いたら、うにゃ、いい録音じゃないか!と納得。最近の新譜はみんなこのパターン。初めのとき聴いてがっかりで、落ち込むんだが、数日後に大音量で聴くと解決するという。。。
自分のシステムのエンジンがかかるのが遅いせいかもだが、ある日、突然急激に良く鳴るようになるのだ。
鳴らし込み必要ですね。
アラベラさんの17枚のディスコグラフィーの中で、過去最高に素晴らしいと思った作品は、ひとつ前の作品のブリテン&ヒンデミットのコンチェルト。その前衛的な音楽スタイル、そしてみごとなまでのダイナミックレンジの広さなど超優秀録音だった。
彼女の最高傑作だと思った。
今回の作品は、最初聴いたときは、そこまでのインパクトはなかったが、徐々にそれに迫りつつある。ずっと聴き込んでいけば、絶対並ぶはず。
なによりもアルバムのコンセプトがとても素晴らしいので、録音も過去最高でないといけない。
ディスコグラフィーは、やはり新しい録音になっていくほど、ユーザへの説得力が増す。
今回のアラベラさんのR.シュトラウスへのトリビュート・アルバムには、絶対に2004年デビュー当初の頃では捉えることができなかった新しい「音のさま」がある。
この「新しい録音を聴こうよ!」のフレーズは、もうすっかり自分のお気に入りで定番。(笑)
来年3月には、また来日してくれるので、自分は毎年お楽しみのアラベラ・フィーバーになりそうだ。
PENTATONEの新譜:ジョナサン・ノット&スイス・ロマンド [ディスク・レビュー]
どういうわけなのか電撃録音スケジュールで、6月に録音して、8月にはリリースするという(正式発売は9月20日です)、こういうのはいままで経験がない。
録音セッションの様子のレポートもなく、いきなりリリースの知らせだったので、なんか唐突な印象を受けた。
おしりは決まっているので、忙しいノットのスケジュールが抑えられなかったのか、はたまたもっと意味深の理由があるのか?
でもその割には、手抜きということもなく、しっかりとした優秀録音でさすがでした。
ジョナサン・ノットは、もう日本のクラシック音楽ファンにはお馴染みすぎで、あまりにも有名な指揮者。2014年1月から東京交響楽団(東響)の音楽監督、首席指揮者を務めて、なんと2026年までの長期政権。
自分も2015年~2017年の3年間、東響の名曲全集の定期会員になり、ミューザ川崎に通った。
録音セッションの様子のレポートもなく、いきなりリリースの知らせだったので、なんか唐突な印象を受けた。
おしりは決まっているので、忙しいノットのスケジュールが抑えられなかったのか、はたまたもっと意味深の理由があるのか?
でもその割には、手抜きということもなく、しっかりとした優秀録音でさすがでした。
ジョナサン・ノットは、もう日本のクラシック音楽ファンにはお馴染みすぎで、あまりにも有名な指揮者。2014年1月から東京交響楽団(東響)の音楽監督、首席指揮者を務めて、なんと2026年までの長期政権。
自分も2015年~2017年の3年間、東響の名曲全集の定期会員になり、ミューザ川崎に通った。
月1回の年12回、3年間で36回体験した訳だ。
なぜ定期会員になろうとしたか、というと家に近いミューザ川崎の音響をぜひ自分のモノに習得したい(2CA,2CBの座席ブロックだった)、そして必ず月1回は、クラシックの音楽演奏会に通いたい、という理由だった。
もちろん毎回ノットが指揮をする訳ではないが、でもノット&東響の演奏会は、もう数えきれないくらい体験したと言っていい。
ジョナサン・ノットの指揮者としての技量はどうなのか?

とても知性溢れる指揮者で、毎回その曲をどのように解釈して我々に提示してくれるのか、を深く考え抜いてくれる指揮者だと思った。1回1回の演奏会がとても深く考えられていた。とてもアイデアマン的なところもあって、いろいろな試みもやってくれた。何の曲だったか、いまは思い出せないけれど、たくさんのメトロノームをステージに載せて、などという実験的な試みも体験したことがある。
自分が思う範囲であるが、毎回自分の考えた解釈で我々に提示してくれたけれど、奇をてらったような感じの演奏解釈はなく、比較的王道スタイルな堂々とした解釈で、工夫を加えたとしても前向きと思えるような膨らまし方をする演奏だと思った。
外れは少なかったように思う。
ノットは、よく現代音楽に代表されるような20世紀の音楽が得意と言われているけれど、この3年間では確かにそういう選曲も多くて、さすがノットのカラー満載と思ったこともあったけれど、古典派やロマン派の音楽もたくさん演奏してくれました。
そんなに偏っていなくて、バランスよい音楽センスだと思います。
この3年間、聴いてきて、東響メンバーからの信頼関係も築き上げてきていると思えた。
なによりもまだまだ若いよね?どんどんこれからも伸びしろのある期待できる指揮者だと思います。
そんな日本では超有名なジョナサン・ノットなのだが、2017年1月からは、なんとスイス・ロマンド管弦楽団の音楽監督・首席指揮者にも就任している。
自分としては、3年間通い、知り尽くした馴染みのある、そして日本でも知名度のある指揮者が、就任してくれてとてもうれしかった。
ノット&東響の録音SACDは、オクタビア・レコード EXTONからよく出ているのだが、ノットがスイス・ロマンドを率いてPENTATONEレーベルに初登場というのはとても興味深い。PENTATONEはスイス・ロマンドの録音をもうかなり長い間担当してきているので、そんなに従来の録音テイストと急激に変わるという事はないと思うし、もう十分その音響を知り尽くしているスイス・ジュネーブのヴィクトリアホールでの録音。
彼らの手中の範囲での作品になるだろうと思っていた。
とにかくノットがスイス・ロマンドの音楽監督になっての第1弾の記念的なSACDリリースである。
![666[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6665B15D.jpg)
R.シュトラウス:泡立ちクリーム、ドビュッシー:遊戯、リゲティ:メロディーエン
ジョナサン・ノット&スイス・ロマンド管弦楽団
https:/
自分の結論から言うと、まったく予想通り!いままでのスイス・ロマンド&PENTATONEのタッグによる録音とまったく変わらない期待を裏切らない、ある意味スイス・ロマンドのファンからすると安心できるような作品に仕上がっていた。
ここ数年のスイス・ロマンドの録音作品は、自分は山田和樹氏による指揮の作品をたくさん聴いてきた。
山田氏のときは、プロデューサーの意向があるのか、山田氏の本人の意向なのか、わからないが、どちらかというと、ひとつの大きな大曲を選ぶというより、もっと耳障りのいいメロディがポップな小作品を詰め込んだ企画パッケージ作品という感じが多かった。
聴いていて、とても気持ちが良くて、なによりも難しくなく楽しい曲が多かったので、そこが十分に楽しめた。
今回のノットの作品を聴くと、やっぱり選曲が違うのか、録音のテイストは変わらないけれど、アルバムを聴いての雰囲気はずいぶん違うように思えた。
R.シュトラウスの泡立ちクリーム。これは何回聴いても本当に楽しくていい曲。メロディが美して楽しい。自分はお気に入りの大好きな曲。ある意味、この曲って、山田氏時代の踏襲という感じで、スイス・ロマンドというのは、こういう曲を演奏するほうが、生き生きしていて、とてもうまいというか似合っているような気がする。
ヤノフスキ時代のブルックナーとかの大曲よりも、ずっとこういう作品のほうが彼らに似合っているし、実際演奏もうまい。スイス・ロマンドというオーケストラは、それこそ第1線級のビッグネームなオーケストラでもないし、どことなく田舎のコンパクトなオーケストラ的なイメージが魅力だったりするので、自分はそういう小規模作品が似合っているように思えたり、実際うまいのは納得いく感じなのだ。
もちろんアンセルメ黄金時代の膨大なDECCA録音による、その引き出し、レパートリーの広さは潜在能力として尊敬はするが、ロシア、フランス、ヨーロッパの作曲家の大曲群よりも、あの名盤スペインのファリャの三角帽子のような演奏(あの鮮烈なDECCA録音は凄かった!)のほうがスイス・ロマンドっぽいなぁ~と思うのは、まだ彼らに対する理解の深みが足りないだろうか?(笑)
ドビュッシーの遊戯やリゲティのメロディーエンは、これがいかにもノットらしい選曲。このアルバムにノット色が濃厚に感じるのは、この2曲があるためだろう。とくにリゲティ。ノットのもっとも得意とする作曲家ですね。
東響の名曲全集でも何回か聴きました。
リゲティのメロディーエンは、じつに魅力的な現代音楽で、とくに録音の良さが滲み出る感じ。
現代音楽は、やはりその空間の出方、空間の広さをいかに感じるかが勝負。すき間のある感じ、音数の少ないその音が、広大な空間にいかに広がっていくかを表現するかが、キーポイントですね。見事でした。
バランスエンジニア&編集はエルド・グロード氏。いつもの安定した録音でしたね。
つい最近まで、Channel Classicsの録音をたくさん聴いてきたので、やっぱり全然テイスト違いますね。録音のテイストは、やはり現場収録や、その後のエンジニアの作り出す音でずいぶんイメージが違うものです。
この新譜、日本では、9月20日から発売開始です。ぜひおススメです!
このジョナサン・ノットとスイス・ロマンドのタッグ、来年の春、日本に初来日する!
これは楽しみ。もちろんぜひ馳せ参じたいと思う。
このタッグが目的なのはもちろんだが、もうひとつ楽しみなのがソリストとして登場する辻 彩奈さん。
躍進著しい若手で、最近の若手ホープの中でも、ものすごく個性的で気になっている存在なのだ。
2016年モントリオール国際音楽コンクール第1位、併せて5つの特別賞(バッハ賞、パガニーニ賞、カナダ人作品賞、ソナタ賞、セミファイナルベストリサイタル賞)を受賞。3歳よりスズキメソードにてヴァイオリンを始め、10歳時にスズキテンチルドレンに選ばれ、東京、名古屋、松本にて独奏を実施。
2009年には全日本学生音楽コンクール小学校の部にて全国第1位、東儀賞、兎束賞を受賞。その他国内外のコンクールで優勝や入賞の実績を持つ。国内外のオーケストラとの共演数多し。。。
など若いのにびっくりするようなスゴイ経歴なのだ。(笑)
でもそのようなエリートな女性ヴァイオリニストにありがちな繊細で華麗な感じというよりは、もっとパワフルで、土の臭いがしそうな強烈な個性を自分は感じてしまう。
最近の岐阜のサマランカホールでのリサイタルで、その存在を知った。最近の東京での公演行きそびれてしまった。実際直接自分の目で観てみたい。 今回のスイス・ロマンドとのソリストとしての共演で、また華々しい世界戦の経験を積むことになるのだろう。
辻 彩奈さんのコンサートは、それまでの間、東京でリサイタルやコンチェルトなどあるかもしれないが、自分は敢えて行くつもりはない。(笑)
来年のスイス・ロマンドのときまでとっておく。そこで初めて体験させていただくことにした。
まだ、若干20歳なんだよね。すでに50歳をとうに過ぎた初老のオヤジが、このような若い女性ソリストに熱をあげるのは、なんか犯罪のような感じで、正直気が引けるというか、ちょっと恥ずかしいことも事実。(笑)
岐阜県出身。まさに、「全部、青い!」のだ。
なぜ定期会員になろうとしたか、というと家に近いミューザ川崎の音響をぜひ自分のモノに習得したい(2CA,2CBの座席ブロックだった)、そして必ず月1回は、クラシックの音楽演奏会に通いたい、という理由だった。
もちろん毎回ノットが指揮をする訳ではないが、でもノット&東響の演奏会は、もう数えきれないくらい体験したと言っていい。
ジョナサン・ノットの指揮者としての技量はどうなのか?

とても知性溢れる指揮者で、毎回その曲をどのように解釈して我々に提示してくれるのか、を深く考え抜いてくれる指揮者だと思った。1回1回の演奏会がとても深く考えられていた。とてもアイデアマン的なところもあって、いろいろな試みもやってくれた。何の曲だったか、いまは思い出せないけれど、たくさんのメトロノームをステージに載せて、などという実験的な試みも体験したことがある。
自分が思う範囲であるが、毎回自分の考えた解釈で我々に提示してくれたけれど、奇をてらったような感じの演奏解釈はなく、比較的王道スタイルな堂々とした解釈で、工夫を加えたとしても前向きと思えるような膨らまし方をする演奏だと思った。
外れは少なかったように思う。
ノットは、よく現代音楽に代表されるような20世紀の音楽が得意と言われているけれど、この3年間では確かにそういう選曲も多くて、さすがノットのカラー満載と思ったこともあったけれど、古典派やロマン派の音楽もたくさん演奏してくれました。
そんなに偏っていなくて、バランスよい音楽センスだと思います。
この3年間、聴いてきて、東響メンバーからの信頼関係も築き上げてきていると思えた。
なによりもまだまだ若いよね?どんどんこれからも伸びしろのある期待できる指揮者だと思います。
そんな日本では超有名なジョナサン・ノットなのだが、2017年1月からは、なんとスイス・ロマンド管弦楽団の音楽監督・首席指揮者にも就任している。
自分としては、3年間通い、知り尽くした馴染みのある、そして日本でも知名度のある指揮者が、就任してくれてとてもうれしかった。
ノット&東響の録音SACDは、オクタビア・レコード EXTONからよく出ているのだが、ノットがスイス・ロマンドを率いてPENTATONEレーベルに初登場というのはとても興味深い。PENTATONEはスイス・ロマンドの録音をもうかなり長い間担当してきているので、そんなに従来の録音テイストと急激に変わるという事はないと思うし、もう十分その音響を知り尽くしているスイス・ジュネーブのヴィクトリアホールでの録音。
彼らの手中の範囲での作品になるだろうと思っていた。
とにかくノットがスイス・ロマンドの音楽監督になっての第1弾の記念的なSACDリリースである。
![666[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6665B15D.jpg)
R.シュトラウス:泡立ちクリーム、ドビュッシー:遊戯、リゲティ:メロディーエン
ジョナサン・ノット&スイス・ロマンド管弦楽団
https:/
自分の結論から言うと、まったく予想通り!いままでのスイス・ロマンド&PENTATONEのタッグによる録音とまったく変わらない期待を裏切らない、ある意味スイス・ロマンドのファンからすると安心できるような作品に仕上がっていた。
ここ数年のスイス・ロマンドの録音作品は、自分は山田和樹氏による指揮の作品をたくさん聴いてきた。
山田氏のときは、プロデューサーの意向があるのか、山田氏の本人の意向なのか、わからないが、どちらかというと、ひとつの大きな大曲を選ぶというより、もっと耳障りのいいメロディがポップな小作品を詰め込んだ企画パッケージ作品という感じが多かった。
聴いていて、とても気持ちが良くて、なによりも難しくなく楽しい曲が多かったので、そこが十分に楽しめた。
今回のノットの作品を聴くと、やっぱり選曲が違うのか、録音のテイストは変わらないけれど、アルバムを聴いての雰囲気はずいぶん違うように思えた。
R.シュトラウスの泡立ちクリーム。これは何回聴いても本当に楽しくていい曲。メロディが美して楽しい。自分はお気に入りの大好きな曲。ある意味、この曲って、山田氏時代の踏襲という感じで、スイス・ロマンドというのは、こういう曲を演奏するほうが、生き生きしていて、とてもうまいというか似合っているような気がする。
ヤノフスキ時代のブルックナーとかの大曲よりも、ずっとこういう作品のほうが彼らに似合っているし、実際演奏もうまい。スイス・ロマンドというオーケストラは、それこそ第1線級のビッグネームなオーケストラでもないし、どことなく田舎のコンパクトなオーケストラ的なイメージが魅力だったりするので、自分はそういう小規模作品が似合っているように思えたり、実際うまいのは納得いく感じなのだ。
もちろんアンセルメ黄金時代の膨大なDECCA録音による、その引き出し、レパートリーの広さは潜在能力として尊敬はするが、ロシア、フランス、ヨーロッパの作曲家の大曲群よりも、あの名盤スペインのファリャの三角帽子のような演奏(あの鮮烈なDECCA録音は凄かった!)のほうがスイス・ロマンドっぽいなぁ~と思うのは、まだ彼らに対する理解の深みが足りないだろうか?(笑)
ドビュッシーの遊戯やリゲティのメロディーエンは、これがいかにもノットらしい選曲。このアルバムにノット色が濃厚に感じるのは、この2曲があるためだろう。とくにリゲティ。ノットのもっとも得意とする作曲家ですね。
東響の名曲全集でも何回か聴きました。
リゲティのメロディーエンは、じつに魅力的な現代音楽で、とくに録音の良さが滲み出る感じ。
現代音楽は、やはりその空間の出方、空間の広さをいかに感じるかが勝負。すき間のある感じ、音数の少ないその音が、広大な空間にいかに広がっていくかを表現するかが、キーポイントですね。見事でした。
バランスエンジニア&編集はエルド・グロード氏。いつもの安定した録音でしたね。
つい最近まで、Channel Classicsの録音をたくさん聴いてきたので、やっぱり全然テイスト違いますね。録音のテイストは、やはり現場収録や、その後のエンジニアの作り出す音でずいぶんイメージが違うものです。
この新譜、日本では、9月20日から発売開始です。ぜひおススメです!
このジョナサン・ノットとスイス・ロマンドのタッグ、来年の春、日本に初来日する!
これは楽しみ。もちろんぜひ馳せ参じたいと思う。
このタッグが目的なのはもちろんだが、もうひとつ楽しみなのがソリストとして登場する辻 彩奈さん。
躍進著しい若手で、最近の若手ホープの中でも、ものすごく個性的で気になっている存在なのだ。
2016年モントリオール国際音楽コンクール第1位、併せて5つの特別賞(バッハ賞、パガニーニ賞、カナダ人作品賞、ソナタ賞、セミファイナルベストリサイタル賞)を受賞。3歳よりスズキメソードにてヴァイオリンを始め、10歳時にスズキテンチルドレンに選ばれ、東京、名古屋、松本にて独奏を実施。
2009年には全日本学生音楽コンクール小学校の部にて全国第1位、東儀賞、兎束賞を受賞。その他国内外のコンクールで優勝や入賞の実績を持つ。国内外のオーケストラとの共演数多し。。。
など若いのにびっくりするようなスゴイ経歴なのだ。(笑)
でもそのようなエリートな女性ヴァイオリニストにありがちな繊細で華麗な感じというよりは、もっとパワフルで、土の臭いがしそうな強烈な個性を自分は感じてしまう。
最近の岐阜のサマランカホールでのリサイタルで、その存在を知った。最近の東京での公演行きそびれてしまった。実際直接自分の目で観てみたい。 今回のスイス・ロマンドとのソリストとしての共演で、また華々しい世界戦の経験を積むことになるのだろう。
辻 彩奈さんのコンサートは、それまでの間、東京でリサイタルやコンチェルトなどあるかもしれないが、自分は敢えて行くつもりはない。(笑)
来年のスイス・ロマンドのときまでとっておく。そこで初めて体験させていただくことにした。
まだ、若干20歳なんだよね。すでに50歳をとうに過ぎた初老のオヤジが、このような若い女性ソリストに熱をあげるのは、なんか犯罪のような感じで、正直気が引けるというか、ちょっと恥ずかしいことも事実。(笑)
岐阜県出身。まさに、「全部、青い!」のだ。
Channel Classicsの新譜:レイチェル・ポッジャーのヴィヴァルディ四季 [ディスク・レビュー]
レイチェル・ポッジャーは今年で満50歳だそうだ。その生誕50周年記念盤らしい。先日のディスコグラフィーの日記では不良品を掴まされ、間に合わなかった。まさにほっかほっかの最新録音。
彼女の作品の中では、バッハと並んで大切な作曲家のヴィヴァルディ。まさにここ最近はヴィヴァルディ・プロジェクトと言っていいほど、充実した作品をリリースしている。
「ラ・ストラヴァガンツァ」、「ラ・チェトラ」、「調和の霊感」とヴァイオリン協奏曲集の名盤を連ねてきたディスコグラフィーに今回加わるのは、「四季」。
ヴィヴァルディの四季といったら、もうクラシックファンでなくとも誰もが知っている名曲中の名曲。
イ・ムジチによる演奏があまりにスタンダード。
なぜ、こんなスタンダードな曲を選んだのだろう、と思うが、まだ学生だった頃のポッジャーが、ナイジェル・ケネディの名録音を聴いて以来、演奏と録音を夢見てきたという想い入れがあるのだそうだ。
自身のアンサンブルのブレコン・バロックを伴って、2017年についに録音が実現、2017年の10月28日には、ブレコン・バロック・フェスティヴァル2017でもこの曲を演奏している。
自分は、このナイジェル・ケネディの名前に思いっきり反応してしまった。(笑)
まさかポッジャーのディスコグラフィーを聴いていて、彼の名前を聞くなんて夢にも思わなかった。
いまからおよそ20年くらい前の2000年はじめの頃に、友人が、ぜひナイジェル・ケネディを聴いてごらんということで彼のディスクを紹介してくれた。ベルリンフィルとの共演のディスクだった。
自分がすごくショックだったのは、ナイジェル・ケネディのヘアスタイルからファッションに至るルックスだった。
まるでパンクそのものだった!
頭の両側を刈り上げ、てっぺんの毛を立たせ、服装もまさにボロボロ。(笑)
品行方正なクラシック界とは、まるで水と油のような印象。
思想的にも過激そうで、なんでこんな感じのアーティストが、しかもベルリンフィルと共演できるのだろう?と不思議で仕方がなかった。
ナイジェル・ケネディはイギリス人。当時ベルリンフィルの芸術監督に就任したばかりの同じイギリス人のラトルが、従来の殻を破る新しい風を・・・という意図があったかどうかは知らないが、結構仲が良かった。
ナイジェル・ケネディは結構、ベルリンフィルと共演した録音をかなりの枚数おこなっているのだ。
自分にはこれがどうも違和感というか信じられなかった。
ある日の公演当日の朝、燕尾服をニューヨークに忘れて来た事に気付き、古着姿で演奏したのがきっかけ。この出来事をきっかけとして、1980年代頃から燕尾服を着なくなり、パンク・ファッションや平服をステージ衣装として用い続けてきた。
これが彼のスタイルなのだ。
生まれは音楽一家に生まれ、高等な音楽教育も受けてきたが、後に自伝の中でこの種のアカデミックな教育と肌が合わなかった事を告白している。
音楽家としての演奏活動は、クラシックに拘らず、ポップ・ミュージシャン(ポール・マッカートニーやケイト・ブッシュなど)との共演、ジャズやジミ・ヘンドリックス作品をフィーチャーしたアルバムの発売、自分のコンサートを「ギグ」と称するなど、音楽ジャンル間のクロスオーバー的な立ち位置で、「音楽思想家」的な色彩を濃厚に帯びた感じのアーティストだった。
もともとEMIに所属していて、一時引退するが、また復活してつい最近ソニー・クラシカルに移籍した。合計30数枚にも及ぶアルバムを出していて、演奏家としても積極的な活動である。
自分は当時、ベルリンフィルとの共演のアルバムを3枚くらい買った。
いまラックからは探し出せないけれど、もう20年前なので、記憶もあいまいだけれど、聴いた感じは、極端に過激で暴力的な演奏とは思えないが、フレージングやアーティキュレーションなど、結構個性ある解釈でふつうっぽくないな~という感じだったと記憶している。
とにかく超個性的な人で、奇才という表現がぴったりで、世界への発信力、影響力も半端なかった。そんなクロスオーバー的な立ち位置の功労を評価され、2000年から2005年にかけて、ドイツのECOクラシック賞など多数の輝かしい受賞歴がある。
友人が自分に彼を紹介してくれたのは、この頃だったので、たぶんその頃、彼が旬だったからなんだろう。
そんな想い出のあるナイジェル・ケネディと、レイチェル・ポッジャーとは自分の中でまったく結びつきようがなく、自分はなんか運命を感じた。
ポッジャーが学生時代に聴いた、そしてそれがきっかけで演奏と録音を夢見てきた「ナイジェル・ケネディのヴィヴァルディの四季」。
これは自分は知らなかった。
今回初めて知って、いろいろ調べたら、とても興味深く、まさにこのヴィヴァルディ四季こそが、ナイジェル・ケネディという演奏家の勝負曲である、ということがわかった。
1989年に発売されたナイジェル・ケネディのヴィヴァルディの「四季」のCDは、クラシックのヒット・チャートでは1位、ポップスまで含めたヒット・チャートで6位となり、クラシック楽壇以外の場でもその名が広く知られる事に。
この「四季」で、クラシック作品として史上最高の売上(200万枚以上)を達成したとギネスブックに認定された。
ナイジェル・ケネディにとって、まさにこの曲こそが自分を世に知らしめるキッカケになった曲だったのだ。
まさに彼の勝負曲だった。
現在に至るまで、時代を変えて、この曲を3回も録音を重ねて来ている。
![41KWOP0J+EL[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_41KWOP0J2BEL5B15D.jpg)
https:/
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲「四季」 Limited Edition
ナイジェル・ケネディ イギリス室内管弦楽団
まさにギネス認定された未贈与の大ヒットとなったのが、このCD。
イギリス室内管弦楽とやっていた。若い!このときはちゃんとしていた服装していた。(笑)
ポッジャーが学生だった頃というのは、たぶんこの1989年の頃だったと思うので、この大ヒットCDのことを指しているに違いない。記録的な世界的大ヒットになって、当時多感だった学生のポッジャーは、このCDを聴いて胸ときめいていたに違いない。
これはちょっと聴いてみたい気がする。
でも上のCDは再発の限定盤なのだ。1989年当時に発売された当時のCDはもう廃盤になっていて入手できない。その頃のジャケットは、いまとちょっと違って、こんな感じ。
![250x250_P2_G4049061W[1].JPG](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_250x250_P2_G4049061W5B15D.JPG)
そして2回目の録音は、それから14年経った2003年の録音。
![415TZV2TJCL[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_415TZV2TJCL5B15D.jpg)
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」(CCCD)
ナイジェル・ケネディ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
https:/
この頃、就任したばかりのラトルに見いだされ、よくベルリンフィルと共演したり、録音をしてCDを出していたりした。そのベルリンフィルとの共演で、この2回目の四季を録音した。
![754[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_7545B15D.jpg)
「四季~ニュー・フォー・シーズンズ」
ナイジェル・ケネディ、オーケストラ・オブ・ライフ
https:/
まさに最初の録音から数えて25年目の3回目の録音。最新録音である。ジャケットを見るとますます尖っていそうだ。(笑)
このバックを務めているアンサンブルは、主にポーランドと英国の若手ミュージシャンで構成されていて、作曲家としてケネディが望んだ通りの、ジャズ、ロック、クラシックのレパートリーと即興を行うことが可能なマルチジャンルのアンサンブルだった。まさに彼のスタイルを貫くには最高のパートナー。
この四季について、彼はこのようにインタビューに答えている。
「はじめてヴィヴァルディの四季を聴いたとき、なんて退屈な曲かと思った。誰もがあくびが出るようなやり方で弾いてたからね。スペインのコンサートでこの曲を弾いていた時、突然、ここに流れる途方もないエネルギー、美しいメロディ、そして激しいコントラストがあることに気付いたんだ。この曲にはミュージシャンとしての僕自身を刻印するに足るあらゆるものがあるってことにね。
25年前に僕が出したCDで、みんなもそのことに気づいてくれたと思う。それから25年経った。25年前と同じように弾くなんてもちろん考えられない。今回のアルバムは、以前の自分とはまったく異なる演奏をしたいと思って手掛けたものだ。
僕にとってヴィヴァルディとは、真にグレイトなメロディ、グレイトなオーケストレーション、途方もないエネルギーのぶつかり合いなんだ。ヴィヴァルディはこの作品の中に、何度も聴きたくなるような、そして何度も演奏したくなるような、恐ろしいほどの生命力を吹き込んでる。今回の僕の四季は、『リライト(書き換え)』とでもいうべきもので、ヴィヴァルディの音楽のエッセンスを発展させたものだ。」
自分が友人の紹介でナイジェル・ケネディの存在を知ったのが2000年の頃。だから彼のこと、このような彼の演奏家としての音楽的背景、バックグランドをよく理解できていなかった。
ナイジェル・ケネディのヴィヴァルディの四季を語るのに、ここまで紙面を割いてしまった。(笑)
ポッジャーが今回、この曲をどうしても録音したかった背景がここにあった。
ポッジャーが、満を持して、この曲を録音するパートナーは、もちろん手兵のブレコン・バロック。
先日の一連のポッジャー日記で詳しく説明したので割愛するが、彼女が音楽面で最も信頼するメンバーだ。
ヨハネス・プラムゾーラー(ヴァイオリン)
ザビーネ・ストッファー(ヴァイオリン)
ジェーン・ロジャーズ(ヴィオラ)
アリソン・マギリヴリー(チェロ)
ヤン・スペンサー(ヴィオローネ)
ダニエレ・カミニティ(テオルボ)
マルツィン・シヴィオントキエヴィチ(チェンバロ、チェンバー・オルガン)
ポッジャーの永年の夢がついに叶ったヴィヴァルディ「四季」の録音。
もちろんChannel Classicsのジャレット・サックスによる録音。
今年、2018年古楽シーン最大級のリリースとなることは間違いない。
![918[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_9185B15D-8ef2b.jpg)
「四季」「恋人」「安らぎ」「ムガール大帝」
レイチェル・ポッジャー、ブレコン・バロック
https:/
自分は、四季という、あまりにスタンダードで無数に録音が存在するこの曲は、あまり枚数を聴いていないので、他と比べて、という比較はできない。
自分が感じたままに従うと、一言でいえば、ポッジャーの四季は、とても激しくて途方もないエネルギーを感じざるを得なく、なんか衝撃的な演奏のように感じた。ある意味インテンポな演奏なのかもしれないが、じつに切迫感があって、剃刀でスパッと切れるような鋭い切れ味があるので、予想以上に速いテンポで軽快に感じる。
これもあくまで自分の予想なのだけれど、ポッジャーの頭の中にあるこの曲のイメージというのは、学生の時に聴いたナイジェル・ケネディの演奏がそのままあるのではないか、と思うのだ。
だから自分はナイジェル・ケネディの四季は聴いたことがないけれど、きっと同じように情熱的で軽快な演奏だったに違いないと予想する。
ポッジャーは、それを自分の演奏で、一寸たりとも違わないように再現したのではないか・・・?。
あるいは、そこを敢えてポッジャーなりの解釈を施したのか・・・?
このディスクはふつうに聴いてはいけない。
かなり録音レヴェルが小さい。
普段の自分が聴く適切音量(大音量です)で聴くには、普段より6目盛りも上げないといけなかった。この再生音量ヴォリュームの調整を間違えると、なんて迫力のない優しい四季なんだろう?と思ってしまうに違いない。
思い切ってグイっとVOLを上げると、ダイナミックレンジがとても深くて、じつに解像度が高くて、その迫力あるサウンドに驚く。
この手の録音手法って最近の流行なのかな?
こういうアプローチって、最近の新譜でじつに多く体験する。
特に、夏と冬のポッジャーとブレコン・バロックとの弦合奏の部分は、聴いている自分にグイグイ迫ってくる恐怖感を感じるくらいで、この掛け合いの部分は、じつにオーディオオフ会向きのエンタメ性のあるサウンドだなぁ、と感じた。
録音がじつに素晴らしい。
いわゆるChannel Classicsのお家芸のやりすぎ感はいっさいなく、とても基本に忠実な音がした。
ポッジャーのディスコグラフィーでは、大体今風なモダンな処理が施されていて、オーディオ的な快楽のような気持ちよさがある。
実音にほんのり響き、エコー感を上乗せする加工をして、それがもとに芋ずる式に全体的なスケール感の大きいサウンドになるという・・・
でもそれってある意味、あまりに安易だよなぁ、と思うこともある。
オーディオマニアであれば、それで大満足かもしれないが、実演など生音に接する機会の多い音楽ファンが聴くと、そこになんらかの違和感を感じるはず。
生音は生音、オーディオ快楽はそれはそれと、ふんぎりのつく人であればいいが。
この今回のポッジャーの四季は、そのような小賢しい施しを感じないのだ。
サウンド的に人工的な仕掛けをあまり感じず、生音の実演に迫るような迫真さがある。
今回の録音は、自分にはとても好意的に思えた。
とても自然なテイストの音がする。
まさに古楽器の響きがする。
ふだん感じる”安易”なサウンドがしないのだ。
本物の音がする。
演奏、そして録音ふくめ、自分が聴いてきた(数少ないが。)ヴィヴァルディ四季の録音では、最高傑作だといっていいと思う。
まさに今年、2018年古楽シーン最大級のリリースと言って過言ではない確かなクオリティだと感じた。
彼女の作品の中では、バッハと並んで大切な作曲家のヴィヴァルディ。まさにここ最近はヴィヴァルディ・プロジェクトと言っていいほど、充実した作品をリリースしている。
「ラ・ストラヴァガンツァ」、「ラ・チェトラ」、「調和の霊感」とヴァイオリン協奏曲集の名盤を連ねてきたディスコグラフィーに今回加わるのは、「四季」。
ヴィヴァルディの四季といったら、もうクラシックファンでなくとも誰もが知っている名曲中の名曲。
イ・ムジチによる演奏があまりにスタンダード。
なぜ、こんなスタンダードな曲を選んだのだろう、と思うが、まだ学生だった頃のポッジャーが、ナイジェル・ケネディの名録音を聴いて以来、演奏と録音を夢見てきたという想い入れがあるのだそうだ。
自身のアンサンブルのブレコン・バロックを伴って、2017年についに録音が実現、2017年の10月28日には、ブレコン・バロック・フェスティヴァル2017でもこの曲を演奏している。
自分は、このナイジェル・ケネディの名前に思いっきり反応してしまった。(笑)
まさかポッジャーのディスコグラフィーを聴いていて、彼の名前を聞くなんて夢にも思わなかった。
いまからおよそ20年くらい前の2000年はじめの頃に、友人が、ぜひナイジェル・ケネディを聴いてごらんということで彼のディスクを紹介してくれた。ベルリンフィルとの共演のディスクだった。
自分がすごくショックだったのは、ナイジェル・ケネディのヘアスタイルからファッションに至るルックスだった。
まるでパンクそのものだった!
頭の両側を刈り上げ、てっぺんの毛を立たせ、服装もまさにボロボロ。(笑)
品行方正なクラシック界とは、まるで水と油のような印象。
思想的にも過激そうで、なんでこんな感じのアーティストが、しかもベルリンフィルと共演できるのだろう?と不思議で仕方がなかった。
ナイジェル・ケネディはイギリス人。当時ベルリンフィルの芸術監督に就任したばかりの同じイギリス人のラトルが、従来の殻を破る新しい風を・・・という意図があったかどうかは知らないが、結構仲が良かった。
ナイジェル・ケネディは結構、ベルリンフィルと共演した録音をかなりの枚数おこなっているのだ。
自分にはこれがどうも違和感というか信じられなかった。
ある日の公演当日の朝、燕尾服をニューヨークに忘れて来た事に気付き、古着姿で演奏したのがきっかけ。この出来事をきっかけとして、1980年代頃から燕尾服を着なくなり、パンク・ファッションや平服をステージ衣装として用い続けてきた。
これが彼のスタイルなのだ。
生まれは音楽一家に生まれ、高等な音楽教育も受けてきたが、後に自伝の中でこの種のアカデミックな教育と肌が合わなかった事を告白している。
音楽家としての演奏活動は、クラシックに拘らず、ポップ・ミュージシャン(ポール・マッカートニーやケイト・ブッシュなど)との共演、ジャズやジミ・ヘンドリックス作品をフィーチャーしたアルバムの発売、自分のコンサートを「ギグ」と称するなど、音楽ジャンル間のクロスオーバー的な立ち位置で、「音楽思想家」的な色彩を濃厚に帯びた感じのアーティストだった。
もともとEMIに所属していて、一時引退するが、また復活してつい最近ソニー・クラシカルに移籍した。合計30数枚にも及ぶアルバムを出していて、演奏家としても積極的な活動である。
自分は当時、ベルリンフィルとの共演のアルバムを3枚くらい買った。
いまラックからは探し出せないけれど、もう20年前なので、記憶もあいまいだけれど、聴いた感じは、極端に過激で暴力的な演奏とは思えないが、フレージングやアーティキュレーションなど、結構個性ある解釈でふつうっぽくないな~という感じだったと記憶している。
とにかく超個性的な人で、奇才という表現がぴったりで、世界への発信力、影響力も半端なかった。そんなクロスオーバー的な立ち位置の功労を評価され、2000年から2005年にかけて、ドイツのECOクラシック賞など多数の輝かしい受賞歴がある。
友人が自分に彼を紹介してくれたのは、この頃だったので、たぶんその頃、彼が旬だったからなんだろう。
そんな想い出のあるナイジェル・ケネディと、レイチェル・ポッジャーとは自分の中でまったく結びつきようがなく、自分はなんか運命を感じた。
ポッジャーが学生時代に聴いた、そしてそれがきっかけで演奏と録音を夢見てきた「ナイジェル・ケネディのヴィヴァルディの四季」。
これは自分は知らなかった。
今回初めて知って、いろいろ調べたら、とても興味深く、まさにこのヴィヴァルディ四季こそが、ナイジェル・ケネディという演奏家の勝負曲である、ということがわかった。
1989年に発売されたナイジェル・ケネディのヴィヴァルディの「四季」のCDは、クラシックのヒット・チャートでは1位、ポップスまで含めたヒット・チャートで6位となり、クラシック楽壇以外の場でもその名が広く知られる事に。
この「四季」で、クラシック作品として史上最高の売上(200万枚以上)を達成したとギネスブックに認定された。
ナイジェル・ケネディにとって、まさにこの曲こそが自分を世に知らしめるキッカケになった曲だったのだ。
まさに彼の勝負曲だった。
現在に至るまで、時代を変えて、この曲を3回も録音を重ねて来ている。
![41KWOP0J+EL[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_41KWOP0J2BEL5B15D.jpg)
https:/
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲「四季」 Limited Edition
ナイジェル・ケネディ イギリス室内管弦楽団
まさにギネス認定された未贈与の大ヒットとなったのが、このCD。
イギリス室内管弦楽とやっていた。若い!このときはちゃんとしていた服装していた。(笑)
ポッジャーが学生だった頃というのは、たぶんこの1989年の頃だったと思うので、この大ヒットCDのことを指しているに違いない。記録的な世界的大ヒットになって、当時多感だった学生のポッジャーは、このCDを聴いて胸ときめいていたに違いない。
これはちょっと聴いてみたい気がする。
でも上のCDは再発の限定盤なのだ。1989年当時に発売された当時のCDはもう廃盤になっていて入手できない。その頃のジャケットは、いまとちょっと違って、こんな感じ。
そして2回目の録音は、それから14年経った2003年の録音。
![415TZV2TJCL[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_415TZV2TJCL5B15D.jpg)
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」(CCCD)
ナイジェル・ケネディ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
https:/
この頃、就任したばかりのラトルに見いだされ、よくベルリンフィルと共演したり、録音をしてCDを出していたりした。そのベルリンフィルとの共演で、この2回目の四季を録音した。
![754[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_7545B15D.jpg)
「四季~ニュー・フォー・シーズンズ」
ナイジェル・ケネディ、オーケストラ・オブ・ライフ
https:/
まさに最初の録音から数えて25年目の3回目の録音。最新録音である。ジャケットを見るとますます尖っていそうだ。(笑)
このバックを務めているアンサンブルは、主にポーランドと英国の若手ミュージシャンで構成されていて、作曲家としてケネディが望んだ通りの、ジャズ、ロック、クラシックのレパートリーと即興を行うことが可能なマルチジャンルのアンサンブルだった。まさに彼のスタイルを貫くには最高のパートナー。
この四季について、彼はこのようにインタビューに答えている。
「はじめてヴィヴァルディの四季を聴いたとき、なんて退屈な曲かと思った。誰もがあくびが出るようなやり方で弾いてたからね。スペインのコンサートでこの曲を弾いていた時、突然、ここに流れる途方もないエネルギー、美しいメロディ、そして激しいコントラストがあることに気付いたんだ。この曲にはミュージシャンとしての僕自身を刻印するに足るあらゆるものがあるってことにね。
25年前に僕が出したCDで、みんなもそのことに気づいてくれたと思う。それから25年経った。25年前と同じように弾くなんてもちろん考えられない。今回のアルバムは、以前の自分とはまったく異なる演奏をしたいと思って手掛けたものだ。
僕にとってヴィヴァルディとは、真にグレイトなメロディ、グレイトなオーケストレーション、途方もないエネルギーのぶつかり合いなんだ。ヴィヴァルディはこの作品の中に、何度も聴きたくなるような、そして何度も演奏したくなるような、恐ろしいほどの生命力を吹き込んでる。今回の僕の四季は、『リライト(書き換え)』とでもいうべきもので、ヴィヴァルディの音楽のエッセンスを発展させたものだ。」
自分が友人の紹介でナイジェル・ケネディの存在を知ったのが2000年の頃。だから彼のこと、このような彼の演奏家としての音楽的背景、バックグランドをよく理解できていなかった。
ナイジェル・ケネディのヴィヴァルディの四季を語るのに、ここまで紙面を割いてしまった。(笑)
ポッジャーが今回、この曲をどうしても録音したかった背景がここにあった。
ポッジャーが、満を持して、この曲を録音するパートナーは、もちろん手兵のブレコン・バロック。
先日の一連のポッジャー日記で詳しく説明したので割愛するが、彼女が音楽面で最も信頼するメンバーだ。
ヨハネス・プラムゾーラー(ヴァイオリン)
ザビーネ・ストッファー(ヴァイオリン)
ジェーン・ロジャーズ(ヴィオラ)
アリソン・マギリヴリー(チェロ)
ヤン・スペンサー(ヴィオローネ)
ダニエレ・カミニティ(テオルボ)
マルツィン・シヴィオントキエヴィチ(チェンバロ、チェンバー・オルガン)
ポッジャーの永年の夢がついに叶ったヴィヴァルディ「四季」の録音。
もちろんChannel Classicsのジャレット・サックスによる録音。
今年、2018年古楽シーン最大級のリリースとなることは間違いない。
![918[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_9185B15D-8ef2b.jpg)
「四季」「恋人」「安らぎ」「ムガール大帝」
レイチェル・ポッジャー、ブレコン・バロック
https:/
自分は、四季という、あまりにスタンダードで無数に録音が存在するこの曲は、あまり枚数を聴いていないので、他と比べて、という比較はできない。
自分が感じたままに従うと、一言でいえば、ポッジャーの四季は、とても激しくて途方もないエネルギーを感じざるを得なく、なんか衝撃的な演奏のように感じた。ある意味インテンポな演奏なのかもしれないが、じつに切迫感があって、剃刀でスパッと切れるような鋭い切れ味があるので、予想以上に速いテンポで軽快に感じる。
これもあくまで自分の予想なのだけれど、ポッジャーの頭の中にあるこの曲のイメージというのは、学生の時に聴いたナイジェル・ケネディの演奏がそのままあるのではないか、と思うのだ。
だから自分はナイジェル・ケネディの四季は聴いたことがないけれど、きっと同じように情熱的で軽快な演奏だったに違いないと予想する。
ポッジャーは、それを自分の演奏で、一寸たりとも違わないように再現したのではないか・・・?。
あるいは、そこを敢えてポッジャーなりの解釈を施したのか・・・?
このディスクはふつうに聴いてはいけない。
かなり録音レヴェルが小さい。
普段の自分が聴く適切音量(大音量です)で聴くには、普段より6目盛りも上げないといけなかった。この再生音量ヴォリュームの調整を間違えると、なんて迫力のない優しい四季なんだろう?と思ってしまうに違いない。
思い切ってグイっとVOLを上げると、ダイナミックレンジがとても深くて、じつに解像度が高くて、その迫力あるサウンドに驚く。
この手の録音手法って最近の流行なのかな?
こういうアプローチって、最近の新譜でじつに多く体験する。
特に、夏と冬のポッジャーとブレコン・バロックとの弦合奏の部分は、聴いている自分にグイグイ迫ってくる恐怖感を感じるくらいで、この掛け合いの部分は、じつにオーディオオフ会向きのエンタメ性のあるサウンドだなぁ、と感じた。
録音がじつに素晴らしい。
いわゆるChannel Classicsのお家芸のやりすぎ感はいっさいなく、とても基本に忠実な音がした。
ポッジャーのディスコグラフィーでは、大体今風なモダンな処理が施されていて、オーディオ的な快楽のような気持ちよさがある。
実音にほんのり響き、エコー感を上乗せする加工をして、それがもとに芋ずる式に全体的なスケール感の大きいサウンドになるという・・・
でもそれってある意味、あまりに安易だよなぁ、と思うこともある。
オーディオマニアであれば、それで大満足かもしれないが、実演など生音に接する機会の多い音楽ファンが聴くと、そこになんらかの違和感を感じるはず。
生音は生音、オーディオ快楽はそれはそれと、ふんぎりのつく人であればいいが。
この今回のポッジャーの四季は、そのような小賢しい施しを感じないのだ。
サウンド的に人工的な仕掛けをあまり感じず、生音の実演に迫るような迫真さがある。
今回の録音は、自分にはとても好意的に思えた。
とても自然なテイストの音がする。
まさに古楽器の響きがする。
ふだん感じる”安易”なサウンドがしないのだ。
本物の音がする。
演奏、そして録音ふくめ、自分が聴いてきた(数少ないが。)ヴィヴァルディ四季の録音では、最高傑作だといっていいと思う。
まさに今年、2018年古楽シーン最大級のリリースと言って過言ではない確かなクオリティだと感じた。
レイチェル・ポッジャーのディスコグラフィー [ディスク・レビュー]
バッハとヴィヴァルディ。レイチェル・ポッジャーの録音は、やはりこの2人の作曲家の作品がいい。バッハは、ポッジャーをいまの名声の立場にまで引き上げてくれた人で彼女のルーツはここにある。ヴィヴァルディは、最新録音技術を駆使して、いままさに取り組んでいるプロジェクト。
もちろん他の作曲家の作品も魅力的だが、自分の11枚を聴き込んでのとりあえず出した結論。
でもバロック音楽も久しぶりに聴くとなんと心地よい音楽なんだろう。
あの明るい軽やかな旋律は、確かにクラシックの音楽の原点だね。
とても癒される。

無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全曲(バッハ)
ポッジャー
http://
1999年に発表した「バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ」は、「古楽器による無伴奏」史上最大のベストセラーを記録した。
この1998年から99年にかけて録音された「無伴奏」の成功で、ポッジャーは一躍世界にその名を轟かせることとなった。
まさに彼女の原点はここにあった。彼女はここからスタートした。
まさにポッジャーを語る上では、絶対外せない名盤なのだ。
古楽器によるバッハ無伴奏。
自分は最初よくわかっていなくて、これはSACDではなくCDなので、スルーしていた。
しかもバッハの無伴奏は、後で紹介する「守護天使」のSACDを持っていたので、尚更スルーだった。ところがポッジャーのことを調べてわかってくると、このCDが彼女のすべての原点でありスタートであることがわかり、急いで今回注文した。
バッハ無伴奏にありがちなロマン派志向の演奏に聴かれるような重苦しさとは全くその対極にある演奏。かなり印象的な速いテンポで進められる。なんか疾走感があって、なにかに掻き立てられるような演奏。かなり情熱的なバッハだと思う。熱いパッションがどんどんこちらに伝わってくる。
かなり訴求力ある。強烈にアピールしてくるバッハ無伴奏だと思う。
録音的には、2chステレオ再生とは思えない空間感で、しかもヴァイオリンの音の芯が太くて、かなり肉厚なサウンド。広い空間を朗々と鳴るその鳴りっぷりに圧倒される。定位感もある。
これは自分のオーディオ・システムに起因するところなのかもしれないが、2chステレオのほうが、かなり厚いサウンドで、これがSACDサラウンドになると、確かに情報量やステージ感は圧倒的に有利になるのだが、音の芯というか、どこか薄いというか線の細いサウンドに感じてしまうのだ。
もちろん他の作曲家の作品も魅力的だが、自分の11枚を聴き込んでのとりあえず出した結論。
でもバロック音楽も久しぶりに聴くとなんと心地よい音楽なんだろう。
あの明るい軽やかな旋律は、確かにクラシックの音楽の原点だね。
とても癒される。

無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全曲(バッハ)
ポッジャー
http://
1999年に発表した「バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ」は、「古楽器による無伴奏」史上最大のベストセラーを記録した。
この1998年から99年にかけて録音された「無伴奏」の成功で、ポッジャーは一躍世界にその名を轟かせることとなった。
まさに彼女の原点はここにあった。彼女はここからスタートした。
まさにポッジャーを語る上では、絶対外せない名盤なのだ。
古楽器によるバッハ無伴奏。
自分は最初よくわかっていなくて、これはSACDではなくCDなので、スルーしていた。
しかもバッハの無伴奏は、後で紹介する「守護天使」のSACDを持っていたので、尚更スルーだった。ところがポッジャーのことを調べてわかってくると、このCDが彼女のすべての原点でありスタートであることがわかり、急いで今回注文した。
バッハ無伴奏にありがちなロマン派志向の演奏に聴かれるような重苦しさとは全くその対極にある演奏。かなり印象的な速いテンポで進められる。なんか疾走感があって、なにかに掻き立てられるような演奏。かなり情熱的なバッハだと思う。熱いパッションがどんどんこちらに伝わってくる。
かなり訴求力ある。強烈にアピールしてくるバッハ無伴奏だと思う。
録音的には、2chステレオ再生とは思えない空間感で、しかもヴァイオリンの音の芯が太くて、かなり肉厚なサウンド。広い空間を朗々と鳴るその鳴りっぷりに圧倒される。定位感もある。
これは自分のオーディオ・システムに起因するところなのかもしれないが、2chステレオのほうが、かなり厚いサウンドで、これがSACDサラウンドになると、確かに情報量やステージ感は圧倒的に有利になるのだが、音の芯というか、どこか薄いというか線の細いサウンドに感じてしまうのだ。
2ch再生のほうが肉厚。
あとで、紹介する「守護天使」は、同じバッハ無伴奏でSACDサラウンドなのだが、なにかどこか音が薄いというか、ワンポイント的に聴こえてあっさり感を感じてしまうのだ。
とにかくこのCDは、ポッジャーを語る上で避けて通れないディスクなのだ。
![867[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8675B15D.jpg)
ヴァイオリン協奏曲集(バッハ)
ポッジャー&ブレコン・バロック
http://
1999年の「バッハ無伴奏」で一躍スターダムにのし上がったポジャーであるが、その後、ピノック率いる古楽器オーケストラ「イングリッシュ・コンサート」や、マクリーシュ率いる「ガブリエリ・コンソート&プレイヤーズ」のリーダーとして活躍。
その後は「エイジ・オブ・エンラントゥンメント管弦楽団」や「アルテ・デイ・スオナトーリ」など複数の古楽器オケに関わり、さらにギルドホール音楽演劇学校と王立ウェールズ音楽大学、デンマーク王立アカデミー、ブレーメン音楽大学でバロック・ヴァイオリンの教授を歴任。
2006年には南ウェールズの田園地帯でモーツァルト音楽財団を設立して若い音楽家を援助し、同地で開催されるブレコン・バロック音楽フェスティヴァルの中心人物として活躍。2008年からはロンドン王立音楽アカデミーでバロック・ヴァイオリンを教えていたりしていた。
まさに、ポッジャーが日本ではあまりその活躍、知名度の高さが知られていないのが不思議なくらいの古楽界ではスターであった。
その名声を徹底的にしたのが、このバッハのコンチェルト。
自分のユニット、ブレコン・バロックを結成したのは、2007年だが、録音したデビューCDは2010年、まさにこのバッハのコンチェルトなのであった。このバッハのヴァイオリン協奏曲は、ユニバーサル批評家の称賛を集めた。
このSACDは、結構自分のオーディオ仲間内でもオーディオオフ会などに使われていた定番のソフトだったのだが、これだけの名声のある録音にしては、自分のオーディオと相性は、じつはあまり良くないのだ。
サラウンドで聴いているのだが、普段のChannel Classicsサウンドよりも、若干控えめで、ふわっと部屋中に広がる音場感が物足りない。ちょっとこじんまりしていて、音量もそんなに大きくない。
あのいつもの前へ前へ出ていくような感じがなく控えめなのだ。
じつはあまり自分は胸ときめかないディスクなのだ。(^^;;
バッハのコンチェルトなら、これもオーディオオフ会で定番ソフトであったDGのヒラリーハーン盤のほうが、ずっと自分のオーディオとは相性が良かった。
でももっと逆の見方をしたら、エンジニアのいじりがない、最も古楽らしい自然な響きがするアルバムだということもいえるのかもしれない。
![361[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_3615B15D.jpg)
モーツァルト:協奏交響曲、ハイドン:ヴァイオリン協奏曲集
ポッジャー、P.ベズノシウク、エイジ・オブ・インライトゥメント管
http://
ポッジャーのヴァイオリンと鬼才ベズノシウクのヴィオラ。2人の名手と2台のストラディヴァリウスの対話が創り出す、「協奏交響曲」。モーツァルトとハイドン。
聴いていて、明るいとても楽しい曲。特にモーツァルトが良い。
弦合奏、ヴァイオリンとヴィオラの掛け合いが素晴らしく、特に解像感がいい。
弦が擦れるような感覚が伝わってくるような緊迫感のあるサウンドなのだ。優秀録音。
チェンバロが重なってくると、いわゆるあの古楽独特の雰囲気のあるサウンドで心地よい。
それに増して、驚くのは、演奏している人たちのアンサンブルの精緻さ、正確さ。
かなりう~んと唸るくらい素晴らしい。
ポッジャーはバッハとヴィヴァルディと断言しちゃったけれど、このモーツァルト&ハイドンもじつに素晴らしいです。
![009[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0095B25D.jpg)
モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲集、
M.ハイドン:二重奏曲集
ポッジャー、J.ロジャース
http://
ブレコン・バロックのメンバーであり英国最高峰のヴィオラ奏者、ジェーン・ロジャースとのデュオによる「モーツァルト&ミヒャエル・ハイドン」。ポッジャーはモーツァルトとハイドンの組み合わせがとても好きだ。
あとで、紹介する「守護天使」は、同じバッハ無伴奏でSACDサラウンドなのだが、なにかどこか音が薄いというか、ワンポイント的に聴こえてあっさり感を感じてしまうのだ。
とにかくこのCDは、ポッジャーを語る上で避けて通れないディスクなのだ。
![867[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8675B15D.jpg)
ヴァイオリン協奏曲集(バッハ)
ポッジャー&ブレコン・バロック
http://
1999年の「バッハ無伴奏」で一躍スターダムにのし上がったポジャーであるが、その後、ピノック率いる古楽器オーケストラ「イングリッシュ・コンサート」や、マクリーシュ率いる「ガブリエリ・コンソート&プレイヤーズ」のリーダーとして活躍。
その後は「エイジ・オブ・エンラントゥンメント管弦楽団」や「アルテ・デイ・スオナトーリ」など複数の古楽器オケに関わり、さらにギルドホール音楽演劇学校と王立ウェールズ音楽大学、デンマーク王立アカデミー、ブレーメン音楽大学でバロック・ヴァイオリンの教授を歴任。
2006年には南ウェールズの田園地帯でモーツァルト音楽財団を設立して若い音楽家を援助し、同地で開催されるブレコン・バロック音楽フェスティヴァルの中心人物として活躍。2008年からはロンドン王立音楽アカデミーでバロック・ヴァイオリンを教えていたりしていた。
まさに、ポッジャーが日本ではあまりその活躍、知名度の高さが知られていないのが不思議なくらいの古楽界ではスターであった。
その名声を徹底的にしたのが、このバッハのコンチェルト。
自分のユニット、ブレコン・バロックを結成したのは、2007年だが、録音したデビューCDは2010年、まさにこのバッハのコンチェルトなのであった。このバッハのヴァイオリン協奏曲は、ユニバーサル批評家の称賛を集めた。
このSACDは、結構自分のオーディオ仲間内でもオーディオオフ会などに使われていた定番のソフトだったのだが、これだけの名声のある録音にしては、自分のオーディオと相性は、じつはあまり良くないのだ。
サラウンドで聴いているのだが、普段のChannel Classicsサウンドよりも、若干控えめで、ふわっと部屋中に広がる音場感が物足りない。ちょっとこじんまりしていて、音量もそんなに大きくない。
あのいつもの前へ前へ出ていくような感じがなく控えめなのだ。
じつはあまり自分は胸ときめかないディスクなのだ。(^^;;
バッハのコンチェルトなら、これもオーディオオフ会で定番ソフトであったDGのヒラリーハーン盤のほうが、ずっと自分のオーディオとは相性が良かった。
でももっと逆の見方をしたら、エンジニアのいじりがない、最も古楽らしい自然な響きがするアルバムだということもいえるのかもしれない。
![361[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_3615B15D.jpg)
モーツァルト:協奏交響曲、ハイドン:ヴァイオリン協奏曲集
ポッジャー、P.ベズノシウク、エイジ・オブ・インライトゥメント管
http://
ポッジャーのヴァイオリンと鬼才ベズノシウクのヴィオラ。2人の名手と2台のストラディヴァリウスの対話が創り出す、「協奏交響曲」。モーツァルトとハイドン。
聴いていて、明るいとても楽しい曲。特にモーツァルトが良い。
弦合奏、ヴァイオリンとヴィオラの掛け合いが素晴らしく、特に解像感がいい。
弦が擦れるような感覚が伝わってくるような緊迫感のあるサウンドなのだ。優秀録音。
チェンバロが重なってくると、いわゆるあの古楽独特の雰囲気のあるサウンドで心地よい。
それに増して、驚くのは、演奏している人たちのアンサンブルの精緻さ、正確さ。
かなりう~んと唸るくらい素晴らしい。
ポッジャーはバッハとヴィヴァルディと断言しちゃったけれど、このモーツァルト&ハイドンもじつに素晴らしいです。
![009[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0095B25D.jpg)
モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲集、
M.ハイドン:二重奏曲集
ポッジャー、J.ロジャース
http://
ブレコン・バロックのメンバーであり英国最高峰のヴィオラ奏者、ジェーン・ロジャースとのデュオによる「モーツァルト&ミヒャエル・ハイドン」。ポッジャーはモーツァルトとハイドンの組み合わせがとても好きだ。
これも先に紹介したアルバムとテイストは似ている。モーツァルトとハイドンはとても明るくて楽しい曲なのがいい。モーツァルトらしいあの軽妙で親しみやすい旋律。それをヴァイオリンとヴィオラの2本で奏でていく掛け合いがシンプルでじつに美しい。先のアルバムは、古楽室内オケとの協奏曲だったが、こちらはヴァイオリンとヴィオラの2本で奏でる。
録音のテイストは、やはりジャレット・サックス。ぶれないというか、変わらない。弦楽器サウンドに必須の解像感がバッチリだ。弦が擦れる音が聴こえてきそうだ。
![614[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6145B15D-0a144.jpg)
守護天使~無伴奏ヴァイオリン作品集~バッハ、ビーバー、タルティーニ、ピゼンデル、他
ポッジャー
http://
ガーディアン・エンジェル、守護天使と題されたこのアルバムは、レイチェル・ポッジャーのお気に入り作品を集めたもの。ポッジャー自身の編曲によるバッハの無伴奏フルートのためのパルティータのヴァイオリン・ヴァージョンに始まり、アルバム・タイトル由来の名曲であるビーバーのパッサカリアで締めくくられる。
先の調布国際音楽祭2018でもこのアルバムから選曲された。
いままでの自分のこのアルバムの位置づけは、ポッジャーの無伴奏を聴くなら、この守護天使、というくらい圧倒的な信頼を持っていた。それは、やはりSACDの5.0サラウンドで収録されているということに他ならない。
でもポッジャーの伝説のデビューCDの無伴奏を聴いてから、少し考え方が変わってきた。
聴き込んでみると確かに最新録音としての完成度は高いのだけれど、一度デビューCDを聴いてしまうと、その音の薄さがどうしても気になってしまう。空間バランス(背景の空間に対して、楽器の響きの広がり)が、どこかワンポイントっぽく聴こえ、オフマイク録音のように感じる。
確かに美音系なので、いい録音だと思うのだが、オーディオマニアというのは、修羅場をくぐってくると、ヒネクレてくるというか、単なる美音では感動しない、というか、サウンドのどこかにエンタメ性を求めたりする生き物。
いまの自分はデビューCDのほうがクル。
でも最新録音としての完成度は高いアルバムだということは間違いありません。
![148[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_1485B15D.jpg)
二重&三重協奏曲集(バッハ)
ポッジャー&ブレコン・バロック
録音のテイストは、やはりジャレット・サックス。ぶれないというか、変わらない。弦楽器サウンドに必須の解像感がバッチリだ。弦が擦れる音が聴こえてきそうだ。
![614[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6145B15D-0a144.jpg)
守護天使~無伴奏ヴァイオリン作品集~バッハ、ビーバー、タルティーニ、ピゼンデル、他
ポッジャー
http://
ガーディアン・エンジェル、守護天使と題されたこのアルバムは、レイチェル・ポッジャーのお気に入り作品を集めたもの。ポッジャー自身の編曲によるバッハの無伴奏フルートのためのパルティータのヴァイオリン・ヴァージョンに始まり、アルバム・タイトル由来の名曲であるビーバーのパッサカリアで締めくくられる。
先の調布国際音楽祭2018でもこのアルバムから選曲された。
いままでの自分のこのアルバムの位置づけは、ポッジャーの無伴奏を聴くなら、この守護天使、というくらい圧倒的な信頼を持っていた。それは、やはりSACDの5.0サラウンドで収録されているということに他ならない。
でもポッジャーの伝説のデビューCDの無伴奏を聴いてから、少し考え方が変わってきた。
聴き込んでみると確かに最新録音としての完成度は高いのだけれど、一度デビューCDを聴いてしまうと、その音の薄さがどうしても気になってしまう。空間バランス(背景の空間に対して、楽器の響きの広がり)が、どこかワンポイントっぽく聴こえ、オフマイク録音のように感じる。
確かに美音系なので、いい録音だと思うのだが、オーディオマニアというのは、修羅場をくぐってくると、ヒネクレてくるというか、単なる美音では感動しない、というか、サウンドのどこかにエンタメ性を求めたりする生き物。
いまの自分はデビューCDのほうがクル。
でも最新録音としての完成度は高いアルバムだということは間違いありません。
![148[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_1485B15D.jpg)
二重&三重協奏曲集(バッハ)
ポッジャー&ブレコン・バロック
http://bit.ly/2NuUoLp
これが、まさに自分の中でのポッジャーの最高傑作。ポッジャーの録音といえば、自分にはこのディスクのことを指す。いままで数多のオーディオオフ会での拙宅、または持ち込ソフトなど、自分のオフ会用のキラーコンテンツだった。
もちろん優秀録音なのだが、なによりもその楽曲の良さが自分には堪らなかった。
クラシックのアルバムというよりは、まるでポップスのアルバムを聴いているような収録曲の1曲1曲すべてにおいて、いわゆるポップスでいうところのフックの効いた(人の心を一瞬にして惹きつけるような旋律のサビの部分)曲ばかりなのだ。
トランスポートのリピート機能をONにして、ずっとエンドレスで聴いていても、1日中かけっぱなしにしても全く飽きがこないくらい自分は相当大好きだった。
このアルバムに収められているのはバッハの4つの多重協奏曲レパートリー。
録音面では、このディスクは2ch再生だとなかなか再生困難で難しい箇所も多い。弦楽器の多重なので、ある意味団子状態で混濁してしまうのだ。サラウンドで聴くと、これが結構各パートの弦楽器が分離して聴こえてスッキリ聴こえてくるのだが、2ch再生だとなかなかハードルが高いディスクだと思う。
システムの解像度分離の良さをテストするディスクとして機能していたところも多かった。
録音がいい!という点では、最近出てきた新しい録音のほうが、さすがに洗練されているとは思うが、このディスクでも十分すぎるくらいお釣りが出るほど素晴らしいサウンドのアルバムだと思う。
ポッジャーの1枚と言ったら、このディスクしかない!
![923[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_9235B15D.jpg)
「ラ・チェトラ」全曲(ヴィヴァルディ)
ポッジャー、オランダ・バロック協会(2SACD)
http://
ポッジャーの録音の中で、最も録音が素晴らしいと思う最新録音。いきなりの冒頭の通奏低音の分厚さにたまげる。いままでのChannel Classicsの録音ポリシーに沿っているのはもちろんのことだが、それ以上に音が分厚くて、ちょっと全体的にやりすぎ感が漂う感じもなくはない。(笑)
これが、まさに自分の中でのポッジャーの最高傑作。ポッジャーの録音といえば、自分にはこのディスクのことを指す。いままで数多のオーディオオフ会での拙宅、または持ち込ソフトなど、自分のオフ会用のキラーコンテンツだった。
もちろん優秀録音なのだが、なによりもその楽曲の良さが自分には堪らなかった。
クラシックのアルバムというよりは、まるでポップスのアルバムを聴いているような収録曲の1曲1曲すべてにおいて、いわゆるポップスでいうところのフックの効いた(人の心を一瞬にして惹きつけるような旋律のサビの部分)曲ばかりなのだ。
トランスポートのリピート機能をONにして、ずっとエンドレスで聴いていても、1日中かけっぱなしにしても全く飽きがこないくらい自分は相当大好きだった。
このアルバムに収められているのはバッハの4つの多重協奏曲レパートリー。
録音面では、このディスクは2ch再生だとなかなか再生困難で難しい箇所も多い。弦楽器の多重なので、ある意味団子状態で混濁してしまうのだ。サラウンドで聴くと、これが結構各パートの弦楽器が分離して聴こえてスッキリ聴こえてくるのだが、2ch再生だとなかなかハードルが高いディスクだと思う。
システムの解像度分離の良さをテストするディスクとして機能していたところも多かった。
録音がいい!という点では、最近出てきた新しい録音のほうが、さすがに洗練されているとは思うが、このディスクでも十分すぎるくらいお釣りが出るほど素晴らしいサウンドのアルバムだと思う。
ポッジャーの1枚と言ったら、このディスクしかない!
![923[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_9235B15D.jpg)
「ラ・チェトラ」全曲(ヴィヴァルディ)
ポッジャー、オランダ・バロック協会(2SACD)
http://
ポッジャーの録音の中で、最も録音が素晴らしいと思う最新録音。いきなりの冒頭の通奏低音の分厚さにたまげる。いままでのChannel Classicsの録音ポリシーに沿っているのはもちろんのことだが、それ以上に音が分厚くて、ちょっと全体的にやりすぎ感が漂う感じもなくはない。(笑)
生音はあきらかに古楽器の響きなのに、録音の味付け(やりすぎ感?。。。笑笑)で、とてもモダンっぽく聴こえる。
まさにChannel Classicsの真骨頂といってもいい。音が分厚いのと情報量多いよね。原音に響きがほんのり乗っている豊かさで、それが音の厚みにつながっていて、そこからさらには全体のスケール感の大きさにつながっている感じ。
芋ずる式です。(笑)
確かにエンジニアの操作感を感じてしまうけれど、いわゆるオーディオ快楽というオーディオマニアが好きそうなサウンドだ。
このアルバムは、ポッジャーの最新のヴィヴァルディ・プロジェクトの1枚である。
ヴィヴァルディは円熟期の大作「ラ・チェトラ」。なんて素晴らしい曲なんだろう!
ヴィヴァルディって本当にバロックらしい、とてもシンプルで明るい調性の曲で素晴らしい。
まさに自分のお気に入りのディスクなのだ。
![863[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8635B15D.jpg)
「調和の霊感」全曲 (ヴィヴァルディ)
ポッジャー&ブレコン・バロック(2SACD)
http://
この1枚も最新のヴィヴァルディ・プロジェクトの中の1枚。
調和の霊感~ピエタ音楽院の教職に就いて8年目、ヴァイオリンと合奏と作曲を教えていたヴィヴァルディが、33歳にして初めて出版した協奏曲集である。
これもブレコン・バロックとタッグを組んでいる。
これはちょっといままでの録音のテイストとちょっと違った趣。原音に響きの潤いが乗っていない。
弦の擦れる音が聴こえてきそうな解像感は高いと思うが、全体的にソリッドな感じ。いままで録音の妙で、古楽の響きもモダン風に化粧をしていたのが、そういうのをいっさいやめて原点に戻った感じ。まさに”古楽の響き”。
でももちろんテイストは違っていても優秀録音であることは間違いありません。
同じヴィヴァルディでもこんなに違うんだね。バロックの明るい解放的な雰囲気というより、もっと求道的で突っ走る感じで疾走感がとてもカッコイイ魅力になっていますね。
![236[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2365B25D.jpg)
「ロザリオのソナタ」(ビーバー)
ポッジャー、シヴィオントキエヴィチ、他(2SACD)
http://
ポッジャーのディスクの中でも3本の指に入る大好きな録音。もちろん録音の優秀さ、そして楽曲の良さという両方において。
ポッジャーがついにビーバーのロザリオ・ソナタを録音した。
スコルダトゥーラ(変則調弦)などの特殊技法も要求され、通奏低音との絡みも重要なビーバーの人気作「ロザリオ・ソナタ」。ビーバーは、オーストリア・バロックの作曲家。その当時のヴァイオリン演奏技法を集大成したと言われる「ロザリオ・ソナタ」が、そんなビーバーの代表作なのだ。
自分は、大昔にちょっと嵌って聴き込んだことがあるが、ずいぶんご無沙汰していた。
そう!ハマるくらいかなり個性的な曲なのだ。ちょっと陰影っぽくて哀愁漂う感じでカッコイイ。
そんなロザリオ・ソナタをポッジャーが録音していたなんて!
これも、かなり録音が素晴らしい!
いわゆる”やりすぎ感”(笑)。
実音にほんのりと響きがのっていて(というか乗せている)、音に厚みがあって、そこから芋ずる式に全体のスケール感が増すという方程式ですね。生音では絶対こうは聴こえないよな、という自信はあります。(笑)
大好きな1枚です。
![918[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_9185B15D.jpg)
「四季」「恋人」「安らぎ」「ムガール大帝」
レイチェル・ポッジャー、ブレコン・バロック
http://
これもヴィヴァルディ・プロジェクトの1環。ポッジャーのまさに最も新しい最近リリースされたホヤホヤの最新録音。
もちろん慌てて買ったのだが、残念ながら届いたディスクは、不良ディスクで、SACD層を読み取らず、CD再生しかできなかった。もちろん返品交換してもらうが、ここでは録音評は差し控える。
間に合わなくて誠に残念!
学生だった頃のポッジャーが、ナイジェル・ケネディの名録音を聞いて以来、演奏と録音を夢見てきたというヴィヴァルディの傑作。
四季なんて、まさに誰もが知っている名曲。なぜこのような名曲を、というのもあるが、そういう理由があったんですね。もちろん今進行しているヴィヴァルディ・プロジェクトと相重なる幸運もあったのでしょう。
新品が届いたら、じっくり聴き込みたいね。
![072[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0725B15D.jpg)
「フーガの技法」
レイチェル・ポッジャー、ブレコン・バロック
http://
2015年に英国王立音楽院(RAM)のバッハ賞を受賞(歴代10番目、女性としては初受賞)したポッジャー。無伴奏、ソナタ、協奏曲と築いてきたバッハ伝説の最新章は、J.S.バッハの対位法の粋を集めた傑作「フーガの技法」に到達。
パートナーは、もちろんブレコン・バロック。
妙なエコー感、やりすぎ感がなく、とても自然なテイストの録音。ある意味、Channel Classicsっぽくない。(笑)
暗めで地味な旋律で、音量、音色などの強弱の振幅変化が乏しく、それが永遠に続くような不思議な感覚の曲である。バッハの対位法は、いろいろ勉強させられることが多く、今尚勉強中のテーマでもある。
以上、ミッションコンプリート!
ご苦労さんでした。
ずばりまとめると、レイチェル・ポッジャーのマイ・フェバリット ベスト3と言えば、
・二重&三重協奏曲集(バッハ)
・「ラ・チェトラ」全曲(ヴィヴァルディ)
・「ロザリオのソナタ」(ビーバー)
ということになります。
ぜひポッジャーを聴いてみたいなら、この3枚をお勧めします。
まさにChannel Classicsの真骨頂といってもいい。音が分厚いのと情報量多いよね。原音に響きがほんのり乗っている豊かさで、それが音の厚みにつながっていて、そこからさらには全体のスケール感の大きさにつながっている感じ。
芋ずる式です。(笑)
確かにエンジニアの操作感を感じてしまうけれど、いわゆるオーディオ快楽というオーディオマニアが好きそうなサウンドだ。
このアルバムは、ポッジャーの最新のヴィヴァルディ・プロジェクトの1枚である。
ヴィヴァルディは円熟期の大作「ラ・チェトラ」。なんて素晴らしい曲なんだろう!
ヴィヴァルディって本当にバロックらしい、とてもシンプルで明るい調性の曲で素晴らしい。
まさに自分のお気に入りのディスクなのだ。
![863[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8635B15D.jpg)
「調和の霊感」全曲 (ヴィヴァルディ)
ポッジャー&ブレコン・バロック(2SACD)
http://
この1枚も最新のヴィヴァルディ・プロジェクトの中の1枚。
調和の霊感~ピエタ音楽院の教職に就いて8年目、ヴァイオリンと合奏と作曲を教えていたヴィヴァルディが、33歳にして初めて出版した協奏曲集である。
これもブレコン・バロックとタッグを組んでいる。
これはちょっといままでの録音のテイストとちょっと違った趣。原音に響きの潤いが乗っていない。
弦の擦れる音が聴こえてきそうな解像感は高いと思うが、全体的にソリッドな感じ。いままで録音の妙で、古楽の響きもモダン風に化粧をしていたのが、そういうのをいっさいやめて原点に戻った感じ。まさに”古楽の響き”。
でももちろんテイストは違っていても優秀録音であることは間違いありません。
同じヴィヴァルディでもこんなに違うんだね。バロックの明るい解放的な雰囲気というより、もっと求道的で突っ走る感じで疾走感がとてもカッコイイ魅力になっていますね。
![236[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2365B25D.jpg)
「ロザリオのソナタ」(ビーバー)
ポッジャー、シヴィオントキエヴィチ、他(2SACD)
http://
ポッジャーのディスクの中でも3本の指に入る大好きな録音。もちろん録音の優秀さ、そして楽曲の良さという両方において。
ポッジャーがついにビーバーのロザリオ・ソナタを録音した。
スコルダトゥーラ(変則調弦)などの特殊技法も要求され、通奏低音との絡みも重要なビーバーの人気作「ロザリオ・ソナタ」。ビーバーは、オーストリア・バロックの作曲家。その当時のヴァイオリン演奏技法を集大成したと言われる「ロザリオ・ソナタ」が、そんなビーバーの代表作なのだ。
自分は、大昔にちょっと嵌って聴き込んだことがあるが、ずいぶんご無沙汰していた。
そう!ハマるくらいかなり個性的な曲なのだ。ちょっと陰影っぽくて哀愁漂う感じでカッコイイ。
そんなロザリオ・ソナタをポッジャーが録音していたなんて!
これも、かなり録音が素晴らしい!
いわゆる”やりすぎ感”(笑)。
実音にほんのりと響きがのっていて(というか乗せている)、音に厚みがあって、そこから芋ずる式に全体のスケール感が増すという方程式ですね。生音では絶対こうは聴こえないよな、という自信はあります。(笑)
大好きな1枚です。
![918[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_9185B15D.jpg)
「四季」「恋人」「安らぎ」「ムガール大帝」
レイチェル・ポッジャー、ブレコン・バロック
http://
これもヴィヴァルディ・プロジェクトの1環。ポッジャーのまさに最も新しい最近リリースされたホヤホヤの最新録音。
もちろん慌てて買ったのだが、残念ながら届いたディスクは、不良ディスクで、SACD層を読み取らず、CD再生しかできなかった。もちろん返品交換してもらうが、ここでは録音評は差し控える。
間に合わなくて誠に残念!
学生だった頃のポッジャーが、ナイジェル・ケネディの名録音を聞いて以来、演奏と録音を夢見てきたというヴィヴァルディの傑作。
四季なんて、まさに誰もが知っている名曲。なぜこのような名曲を、というのもあるが、そういう理由があったんですね。もちろん今進行しているヴィヴァルディ・プロジェクトと相重なる幸運もあったのでしょう。
新品が届いたら、じっくり聴き込みたいね。
![072[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0725B15D.jpg)
「フーガの技法」
レイチェル・ポッジャー、ブレコン・バロック
http://
2015年に英国王立音楽院(RAM)のバッハ賞を受賞(歴代10番目、女性としては初受賞)したポッジャー。無伴奏、ソナタ、協奏曲と築いてきたバッハ伝説の最新章は、J.S.バッハの対位法の粋を集めた傑作「フーガの技法」に到達。
パートナーは、もちろんブレコン・バロック。
妙なエコー感、やりすぎ感がなく、とても自然なテイストの録音。ある意味、Channel Classicsっぽくない。(笑)
暗めで地味な旋律で、音量、音色などの強弱の振幅変化が乏しく、それが永遠に続くような不思議な感覚の曲である。バッハの対位法は、いろいろ勉強させられることが多く、今尚勉強中のテーマでもある。
以上、ミッションコンプリート!
ご苦労さんでした。
ずばりまとめると、レイチェル・ポッジャーのマイ・フェバリット ベスト3と言えば、
・二重&三重協奏曲集(バッハ)
・「ラ・チェトラ」全曲(ヴィヴァルディ)
・「ロザリオのソナタ」(ビーバー)
ということになります。
ぜひポッジャーを聴いてみたいなら、この3枚をお勧めします。
あっ、もちろんこの3枚の他にデビューCDのバッハ無伴奏も、絶対買ってください。
これも外せません!
日本に来日するなんて幻の幻。
オーディオ再生のみの自分の世界の中で生きてきたレイチェル・ポッジャー。
それが実演に接することができて、さらにこうやっていままで買いためてきて、きちんと整理することのなかったディスコグラフィーも自分の頭の中で踏ん切りがついた。
これも予想だにしなかった突然の来日がもたらしたうれしい誤算だろう。
ポッジャーは、現在、自分とまったく同世代の50歳。
実演、間近で観た彼女は全く商業っぽくなく、等身大の自分のスターとして、これからもファンでいて追いかけていくことは間違いないことだと思います。
日本に来日するなんて幻の幻。
オーディオ再生のみの自分の世界の中で生きてきたレイチェル・ポッジャー。
それが実演に接することができて、さらにこうやっていままで買いためてきて、きちんと整理することのなかったディスコグラフィーも自分の頭の中で踏ん切りがついた。
これも予想だにしなかった突然の来日がもたらしたうれしい誤算だろう。
ポッジャーは、現在、自分とまったく同世代の50歳。
実演、間近で観た彼女は全く商業っぽくなく、等身大の自分のスターとして、これからもファンでいて追いかけていくことは間違いないことだと思います。
レイチェル・ポッジャーのディスコグラフィー 序章 [ディスク・レビュー]
自分が所有しているレイチェル・ポッジャーのディスク11枚を完遂した。自分はよくやるのだが、こうやって1人のアーティストのいままでの録音を全部確認することで、そのアーティストが目指しているところの音楽の方向性がわかるのだ。
だから自分にとって、はじめて接するアーティストを聴く場合、すぐにそのアーティストのディスコグラフィーを調べてみる。するとどういう音楽を目指してきているのか、まず理解できる。
まずは、そこを知ることが重要だし、ある意味そのアーティストへの礼儀というものではないか、と思う。
自分がいままで、こういうディスコグラフィーを聴き倒したのは、エディタ・グルベローヴァ、エレーヌ・グリモー、アリーナ・イブラギモヴァそしてこのレイチェル・ポッジャーの4人である。
結構、骨の要る作業なのだ。(笑)
簡単なことじゃない。
![23319463_1887435701269742_423903285334449316_n[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_23319463_1887435701269742_423903285334449316_n5B25D.jpg)
レイチェル・ポッジャーは、それこそ自分が所有している11枚以外にももっと出しているが、彼女を知るには、この11枚を持っていれば、彼女の音楽の方向性、そして録音を楽しむには十分ではないか、と思う。
2枚を新規に買い足したとはいえ、結構ポッジャー・フリークだったんだな、自分。(笑)
ポッジャーの11枚を一通り制覇して、まず思ったことは、Channel Classicsは、本当に録音がいいレーベルだな、と思ったこと。
そして本当に独特なサウンド。ちょっと他の高音質指向型レーベルでは例をみないというか、あまり体験できないサウンド。
「エネルギー感や鮮度感が抜群で、前へ前へ出てくるサウンド、そして空間もしっかり録れていて両立性があること。」
Channel Classicsの録音ポリシーって、こんな風にまとめれるんではないかなぁ、と感じてしまう。
結構各楽器にスポットマイクを多用してオンマイクでがっちり録って、メインで録ったものとうまくミキシングしているような感じがする。そのバランスが見事というか絶妙です。
ポッジャーの11枚を聴くと、新しい録音になっていくにつれて、どんどん録音がよくなっていくのがわかる。新しい録音は、正直、やりすぎ感というか、それはいじり過ぎだろう?(笑)という感もして、生演奏の音からはあまりに乖離している、でも「オーディオ快楽」といおうか、いかにもオーディオマニアが喜びそうな音に出来上がっている印象を抱いた。
一番違和感を感じるのは、あの楽器の音のエネルギー感や鮮度感。ある意味ここが、このレーベルのサウンドの1番の持ち味なのだが、生演奏では、あんなに派手に聴こえません。そこはオーディオライクにデフォルメして調理していることは間違いなし。
でもオーディオってそれでいいのかもしれない。
Channel Classicsは、ジャレッド・サックス氏が創立した会社で、彼のワンマン会社。(笑)
上の写真のように、Channel Classics創立25周年を記念して、「オレがこの25年間で録ったベスト25テイク」というCDを出している。(笑)
Channel Classicsの録音のクレジットを見てもサックス以外のメンバーはいっさい出てこない。
Recording enginner,editing
C.Jared Sacks
とあるだけ。
ライナーノーツに挿入されているレコーディング風景の写真を見てみると、ポッジャーを取り囲んで、エンジニアが数人と議論している写真をよく見るし、ひょっとしたら本当にサックス1人でやっているのかもしれないけれど、実際は、複数タッグでやっているはず。他のエンジニアも可哀想だから、ちゃんとクレジットしてやれよ~と思うのだが、このレーベルでは、こと録音という神聖エリアではこのレーベルでは、サックスは圧倒的な絶対専制君主なのだろう。
ここが、PENTATONEやBIS内での録音エンジニアの立ち位置関係の明らかな違い、と感じるところだ。
大昔に、サックスのインタビューで、彼の録音ポリシーと録音技術についてのインタビューの記事を読んだことがあったのだが、内容は忘れてしまったが、かなり骨のあるしっかりした考えを持っている人なんだな、と思ったことがある。
Channel Classicsのマスタリングルームは、B&W 803D×5本(Nautilusの後に出たやつで、Diamondの前にでたSPです。)、そしてCLASSE 5200のアンプを使っている。
![21740350_10155741368631103_2338211418073587486_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_21740350_10155741368631103_2338211418073587486_n5B15D.jpg)
レイチェル・ポッジャーの録音、彼女の音楽の方向性は、やはりバロック時代の音楽。ことバッハが彼女の音楽の根底にあるのが、はっきりわかる。やはりこの世界にデビューしたのはバッハだし、いまのバロック古楽の世界で名声を得たのもバッハ作品がきっかけだった。
彼女にとって、バッハは特別な存在。
そして最近の最新アルバムでは、ヴィヴァルディを自分のテーマにあげていて、4枚のヴィヴァルディ・アルバムをリリースしている。
彼女のヴィヴァルディへの傾倒ぶりが分かる。
11枚の録音を作曲家別に分けてみると、バッハ(×4枚)。ヴィヴァルディ(×4枚)、モーツァルト、ハイドン、ビーバーとなる。
演奏スタイルの変遷としては、ポッジャー自身がバロック・ヴァイオリンを売りにしている奏者、その部分は不動として、無伴奏で演奏しているアルバム、そして彼女の最も大切なパートナーである古楽演奏の室内楽ユニット、ブレコン・バロック。そしてオランダ古楽界の若き精鋭集団オランダ・バロック協会や、ポーランドの古楽グループ「アルテ・デイ・スオナトーリ」など自分のグループ以外との共演にもとても積極的だ。
特に最近の彼女のライフワークであるヴィヴァルディ・プロジェクト。
ポーランドの古楽グループ「アルテ・デイ・スオナトーリ」と共演した「ラ・ストラヴァガンツァ」、オランダのグループ「オランダ・バロック協会」と共演した「ラ・チェトラ」、 そして自ら結成した古楽グループ「ブレコン・バロック」と共演した「調和の霊感」
この3枚のヴィヴァルディ・アルバムは絶対買いの素晴らしいアルバム、録音だった。
ヴィヴァルディのバロック時代に「協奏曲」というジャンルは確立されていなかったと理解しているが、まさに古楽時代のヴァイオリン協奏曲と言ってもいい名高い名曲を収めた3枚となった。
特にポーランドの古楽グループ「アルテ・デイ・スオナトーリ」と共演した「ラ・ストラヴァガンツァ」の録音は、2002年にリリースされたアルバムだが、これがChannel Classicsとしては初の協奏曲録音となったそうで、ポッジャーのこのレーベルへの貢献ぶりがわかる。
彼女の室内楽ユニット、ブレコン・バロック。
2007年にブレコン・バロック・インストゥルメンタル・アンサンブルを設立し、2010年に録音したデビューCD、バッハのヴァイオリン協奏曲は、ユニバーサル批評家の称賛を集めた。
ブレコン・バロックはチェンバロを含めて6名、各パート1人で編成し、バッハ時代のカフェ・ツィンマーマン・アンサンブルを模し、自由で新しいスタイルの演奏を目指している。
このブレコン バロックが主役として活躍するブレコン・バロック音楽フェスティバルも定期的に開催されていて、ポッジャーはその芸術監督に2006年に就任している。
まさにポッジャーの手兵といっていい存在で、今回の11枚の中でも5枚が、このブレコン・バロックとの競演なのだ。彼女にとって、なくてはならない存在だ。
もうひとつ今回気づいたことは、11枚のうち録音ロケーションの大半がイギリス、ロンドンで行われていることだ。何枚かは、お膝元のオランダでおこなわれている。
こうしてみると、ポッジャーって英国の父とドイツ人の母の間に生まれたイギリス国籍。
今住んでいるところ、活動の本拠地も、イギリス、ロンドンなのかなー?と思ってしまう。
これから本章のディスク紹介に入っていきたい。本当にとてもウィットに富んだ魅力的な11枚のアルバムだった。自分がこれだけバロック音楽の世界を集中的に聴くことも普段はあまりなく、ある意味貴重な体験だった。
長くなりそうなので、いったん日記を2部に分けようと思います。
だから自分にとって、はじめて接するアーティストを聴く場合、すぐにそのアーティストのディスコグラフィーを調べてみる。するとどういう音楽を目指してきているのか、まず理解できる。
まずは、そこを知ることが重要だし、ある意味そのアーティストへの礼儀というものではないか、と思う。
自分がいままで、こういうディスコグラフィーを聴き倒したのは、エディタ・グルベローヴァ、エレーヌ・グリモー、アリーナ・イブラギモヴァそしてこのレイチェル・ポッジャーの4人である。
結構、骨の要る作業なのだ。(笑)
簡単なことじゃない。
![23319463_1887435701269742_423903285334449316_n[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_23319463_1887435701269742_423903285334449316_n5B25D.jpg)
レイチェル・ポッジャーは、それこそ自分が所有している11枚以外にももっと出しているが、彼女を知るには、この11枚を持っていれば、彼女の音楽の方向性、そして録音を楽しむには十分ではないか、と思う。
2枚を新規に買い足したとはいえ、結構ポッジャー・フリークだったんだな、自分。(笑)
ポッジャーの11枚を一通り制覇して、まず思ったことは、Channel Classicsは、本当に録音がいいレーベルだな、と思ったこと。
そして本当に独特なサウンド。ちょっと他の高音質指向型レーベルでは例をみないというか、あまり体験できないサウンド。
「エネルギー感や鮮度感が抜群で、前へ前へ出てくるサウンド、そして空間もしっかり録れていて両立性があること。」
Channel Classicsの録音ポリシーって、こんな風にまとめれるんではないかなぁ、と感じてしまう。
結構各楽器にスポットマイクを多用してオンマイクでがっちり録って、メインで録ったものとうまくミキシングしているような感じがする。そのバランスが見事というか絶妙です。
ポッジャーの11枚を聴くと、新しい録音になっていくにつれて、どんどん録音がよくなっていくのがわかる。新しい録音は、正直、やりすぎ感というか、それはいじり過ぎだろう?(笑)という感もして、生演奏の音からはあまりに乖離している、でも「オーディオ快楽」といおうか、いかにもオーディオマニアが喜びそうな音に出来上がっている印象を抱いた。
一番違和感を感じるのは、あの楽器の音のエネルギー感や鮮度感。ある意味ここが、このレーベルのサウンドの1番の持ち味なのだが、生演奏では、あんなに派手に聴こえません。そこはオーディオライクにデフォルメして調理していることは間違いなし。
でもオーディオってそれでいいのかもしれない。
Channel Classicsは、ジャレッド・サックス氏が創立した会社で、彼のワンマン会社。(笑)
上の写真のように、Channel Classics創立25周年を記念して、「オレがこの25年間で録ったベスト25テイク」というCDを出している。(笑)
Channel Classicsの録音のクレジットを見てもサックス以外のメンバーはいっさい出てこない。
Recording enginner,editing
C.Jared Sacks
とあるだけ。
ライナーノーツに挿入されているレコーディング風景の写真を見てみると、ポッジャーを取り囲んで、エンジニアが数人と議論している写真をよく見るし、ひょっとしたら本当にサックス1人でやっているのかもしれないけれど、実際は、複数タッグでやっているはず。他のエンジニアも可哀想だから、ちゃんとクレジットしてやれよ~と思うのだが、このレーベルでは、こと録音という神聖エリアではこのレーベルでは、サックスは圧倒的な絶対専制君主なのだろう。
ここが、PENTATONEやBIS内での録音エンジニアの立ち位置関係の明らかな違い、と感じるところだ。
大昔に、サックスのインタビューで、彼の録音ポリシーと録音技術についてのインタビューの記事を読んだことがあったのだが、内容は忘れてしまったが、かなり骨のあるしっかりした考えを持っている人なんだな、と思ったことがある。
Channel Classicsのマスタリングルームは、B&W 803D×5本(Nautilusの後に出たやつで、Diamondの前にでたSPです。)、そしてCLASSE 5200のアンプを使っている。
![21740350_10155741368631103_2338211418073587486_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_21740350_10155741368631103_2338211418073587486_n5B15D.jpg)
レイチェル・ポッジャーの録音、彼女の音楽の方向性は、やはりバロック時代の音楽。ことバッハが彼女の音楽の根底にあるのが、はっきりわかる。やはりこの世界にデビューしたのはバッハだし、いまのバロック古楽の世界で名声を得たのもバッハ作品がきっかけだった。
彼女にとって、バッハは特別な存在。
そして最近の最新アルバムでは、ヴィヴァルディを自分のテーマにあげていて、4枚のヴィヴァルディ・アルバムをリリースしている。
彼女のヴィヴァルディへの傾倒ぶりが分かる。
11枚の録音を作曲家別に分けてみると、バッハ(×4枚)。ヴィヴァルディ(×4枚)、モーツァルト、ハイドン、ビーバーとなる。
演奏スタイルの変遷としては、ポッジャー自身がバロック・ヴァイオリンを売りにしている奏者、その部分は不動として、無伴奏で演奏しているアルバム、そして彼女の最も大切なパートナーである古楽演奏の室内楽ユニット、ブレコン・バロック。そしてオランダ古楽界の若き精鋭集団オランダ・バロック協会や、ポーランドの古楽グループ「アルテ・デイ・スオナトーリ」など自分のグループ以外との共演にもとても積極的だ。
特に最近の彼女のライフワークであるヴィヴァルディ・プロジェクト。
ポーランドの古楽グループ「アルテ・デイ・スオナトーリ」と共演した「ラ・ストラヴァガンツァ」、オランダのグループ「オランダ・バロック協会」と共演した「ラ・チェトラ」、 そして自ら結成した古楽グループ「ブレコン・バロック」と共演した「調和の霊感」
この3枚のヴィヴァルディ・アルバムは絶対買いの素晴らしいアルバム、録音だった。
ヴィヴァルディのバロック時代に「協奏曲」というジャンルは確立されていなかったと理解しているが、まさに古楽時代のヴァイオリン協奏曲と言ってもいい名高い名曲を収めた3枚となった。
特にポーランドの古楽グループ「アルテ・デイ・スオナトーリ」と共演した「ラ・ストラヴァガンツァ」の録音は、2002年にリリースされたアルバムだが、これがChannel Classicsとしては初の協奏曲録音となったそうで、ポッジャーのこのレーベルへの貢献ぶりがわかる。
彼女の室内楽ユニット、ブレコン・バロック。
2007年にブレコン・バロック・インストゥルメンタル・アンサンブルを設立し、2010年に録音したデビューCD、バッハのヴァイオリン協奏曲は、ユニバーサル批評家の称賛を集めた。
ブレコン・バロックはチェンバロを含めて6名、各パート1人で編成し、バッハ時代のカフェ・ツィンマーマン・アンサンブルを模し、自由で新しいスタイルの演奏を目指している。
このブレコン バロックが主役として活躍するブレコン・バロック音楽フェスティバルも定期的に開催されていて、ポッジャーはその芸術監督に2006年に就任している。
まさにポッジャーの手兵といっていい存在で、今回の11枚の中でも5枚が、このブレコン・バロックとの競演なのだ。彼女にとって、なくてはならない存在だ。
もうひとつ今回気づいたことは、11枚のうち録音ロケーションの大半がイギリス、ロンドンで行われていることだ。何枚かは、お膝元のオランダでおこなわれている。
こうしてみると、ポッジャーって英国の父とドイツ人の母の間に生まれたイギリス国籍。
今住んでいるところ、活動の本拠地も、イギリス、ロンドンなのかなー?と思ってしまう。
これから本章のディスク紹介に入っていきたい。本当にとてもウィットに富んだ魅力的な11枚のアルバムだった。自分がこれだけバロック音楽の世界を集中的に聴くことも普段はあまりなく、ある意味貴重な体験だった。
長くなりそうなので、いったん日記を2部に分けようと思います。
PENTATONEの新譜:児玉麻里・児玉桃、デボラ&サラ・ネムタクの両姉妹によるマルチヌーの二重奏曲集。 [ディスク・レビュー]
前作の「チャイコフスキー・ファンタジー」が大好評だった児玉麻里・桃姉妹によるPENTATONEでのアルバム製作第2弾。
自分の予想だけれど、たぶんねぇ、この企画、仕掛け人がいると思うのですよ。それも日本人の・・・(笑)
今回の作品のポリヒムニアの録音スタッフも、PENTATONEの黄金時代を築いたといってもいい、エルド・グロード氏が録音エンジニアで、ジャン・マリー=ヘーセン氏がバランス・エンジニアという黄金のタッグ!
まさに自分の青春時代の5.0サラウンドは、この黄金タッグで作られたサウンドで育ってきた、と言っていい。
ポリヒムニアもいつまでもこの2人に頼るのではなく、若い世代を育てていかないといけない。
最近の作品は、若手のエンジニアの名前のクレジットもよく見かける。
もちろん、サラウンドにとって一番重要なバランス・エンジニアは、ジャン・マリさんか、エルド・グロード氏のどちらか一方が担うわけだが。
だから、この2人が、かつての黄金時代のように現場で仲良く揃う、というのは、いまではちょっと信じられないんですよ、自分にとっては。
このこと自体すごいことだし、最大限のおもてなし、とも感じる。
この児玉麻里・桃姉妹の企画に日本人が関与していると薄々感じるのは、そんな最高のおもてなしの配慮を感じるから。
自分のようなレーベル&アーティスト双方の大ファンにとっては、本当にうれしいプレゼント。
感謝しないといけませんね。
PENTATONEのプロデューサーもジョブ・マルセ氏。もう不動の名プロデューサーですね。
そんなプロデューサー案なのか、今回の作品のコンセプトは、とてもマニアックで興味深い。
つねに新しいことにチャレンジしていくマイナーレーベルらしい、すごく斬新なコンセプト。
![085[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0855B15D.jpg)
二重協奏曲集
児玉麻里&児玉 桃、デボラ・ネムタヌ&サラ・ネムタヌ
ローレンス・フォスター&マルセイユ・フィル
https:/
取り上げる作曲家も、オーケストラも自分は、いままで聴いたことがなかった。
作曲家はチェコの作曲家であるボフスラフ・マルチヌー。
![220px-Martinu_1943[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_220px-Martinu_19435B15D.jpg)
20世紀の作曲家で、彼の創作期間としては、チェコ・パリ時代の第1期、そしてアメリカ時代の第2期、最後にヨーロッパ(ニース、ローマ)に戻っての第3期と区分けされるようだ。まさに国際的に活躍した作曲家だったのだが、アメリカに滞在した1940年代が、まさに彼の創作活動の頂点だった。
マルチヌーは、400作を残したじつに多作な作曲家で、そのジャンルも、交響曲/バレエ音楽/管弦楽曲/協奏曲/室内楽曲/ピアノ曲/歌曲/合唱曲/そしてオペラ(歌劇)にまで及び、もうほとんどの曲を作曲しているのではないか、というくらいで驚愕の一言、大変な才能の持ち主であった。
作風も、その創作期間の時代とともに変遷していったようで、第1期の実験的書法、第2期の創作活動の頂点にあたる様々な曲へのアプローチ、そして最後のヨーロッパに戻っての第3期の新古典的、あるいは新印象主義的ともいわれる作風で形式にとらわれない自由な作風。
児玉姉妹の奏する『2台のピアノのための協奏曲』は1943年の絶頂期だった頃の作品。そして、ヴァイオリン、ヴィオラのほうの曲も1950年代ということで、いわゆる脂の乗り切った絶頂のときの作品を堪能できる、という感じなのだ。
自分が、今回のアルバムを聴いて、初マルチヌーを経験したのだが、自分が捉えた彼の作風の印象は、ロマン派などの古典主義のわかりやすい旋律よりも、もう少し難解な筆致で、でも現代音楽のような前衛的で、まるっきり実験的なアプローチでもなく・・・
その中間色にあたるような、程よい革新的な装いを持つ。
でも、その骨子にはややチェコの民族音楽的な旋律も垣間見えて、東欧色豊かで、色彩感のようなグラデーションっぽい音感も味わえて、自分はカッコいいと感じる。
古典主義をもう少し進化させた新古典主義というのが、やはり一番合う表現かな?
自分的にはクル感じの作曲家だ。
そして、オーケストラがマルセイユ・フィルハーモニー管弦楽団。
これも自分には初めて。マルセイユは、ご存知パリについで2番目にフランスでは大きい都市で、コートダジュールとも言われ、港町、いわゆるバカンス都市ですね。
そんなマルセイユがオケを持っているとはもちろん知らなかった。
彼らの情報をネットで調べてみるんだが、ほとんど皆無。ディスコグラフィーも1,2枚ある程度で、本当に未知数のオーケストラ。
なんで、マルセイユ、そしてマルセイユ・フィルなのか?はプロデューサー、企画のみが知る、というところだが、作曲家のマルチヌーは、チェコ出身とはいえ、その壮年期の大半をパリで暮らし、「エコール・ド・パリ」のメンバーとしても活躍していたので、フランスの音楽家にとっても自国の音楽としての自負があるのだろう。
マルチヌーの作品はチェコのスプラフォン・レーベルが熱心に紹介を続けているそうだが、フランス・マルセイユで録って、マルセイユ・フィルのオケで演奏することは、マルチヌーに対するフランス・オマージュの意味合いもあるのだと思う。
今回、このマルセイユ・フィルとの競演ソリストとして、ヴァイオリンとピアノが選ばれた。
「2つのヴァイオリンのための協奏曲」のほうは、フランスのデボラ&サラ・ネムタヌ姉妹。
そして、「2台のピアノのための協奏曲」のほうが、児玉麻里・桃姉妹。
2組の美人姉妹によるヴァイオリンとピアノの競演で、ネムタヌ姉妹はもちろんのこと、児玉姉妹もフランスを拠点にして活躍するアーティスト。
しかも、姉妹用ということで、きちんとヴァイオリンとピアノで、2台デュオで演奏するコンチェルトを、マルチヌーはきちんと作曲していたんだね。協奏曲については、様々な楽器のための30曲近くものの協奏曲を作ったらしいので、本当に興味旺盛で、多才な作曲家だったといえる。
そうすると・・・マルチヌーの曲を、フランスのオケで、フランスで録って、ソリストもフランスに所縁のある2組の姉妹。
なんか、フランスの香りいっぱいで、あまりによく仕込まれているアイデアだと感心しました。(笑)
録音場所は、マルセイユ、フリシュ・ラ・ベル・ド・メ。
わからず。(笑)
ライナーノーツ・ブックレットに、写真が載っていた。
う~ん。微妙。なんか見た感じ、そんなに専用スタジオのようにも見えないし、微妙な感じだが、録音を聴いた限りでは、空間もしっかり録れているし、すばらしかったので、そんなに問題ないのだろう。
でもキッツキッツで録っていたんですね。(笑)
さっそく聴いてみる。
マルチヌーの曲の印象は、既述の通り。カッコいい曲で、自分は気に入った。
自分は、ピアノのほうが、はるかに印象に残るというか、自分の好みに合う。
それは、やはり録音のよさ。
このアルバムを最初聴いたときは、正直なところ、かなり違和感があった。
いままでのPENTATONEサウンドとは、かなり異質な感じ。録音レベルが小さく、オフマイク気味。
PENTATONEサウンドはどちらかというとエネルギー感が大きいほうなのだが、この録音は、音が遠いなーという感じで、例によって最初、なんだ、冴えない録音だなと思い、どうしよう~と焦ってしまった。(笑)
でも音量を思いっきりグイっと上げると、隠されていた録音の良さがわかってきた。
ダイナミックレンジ超深し!!!
これってジャン・マリさんの影響が大きいのかな?
ジャン・マリさんの最近手がけた作品は、みんなこんな感じなのだ。逆にエルド・グロード氏単独の作品は、こういう作風とまたちょっと違うんだな。
音声波形を録る上で大切なパラメーターが、ダイナミックレンジと周波数レンジ。
通称、D-レンジとF-レンジ。
高域⇔低域などの高い音から低い音の幅を表すのが、横軸の周波数レンジ(F-レンジ)。
自分の予想だけれど、たぶんねぇ、この企画、仕掛け人がいると思うのですよ。それも日本人の・・・(笑)
今回の作品のポリヒムニアの録音スタッフも、PENTATONEの黄金時代を築いたといってもいい、エルド・グロード氏が録音エンジニアで、ジャン・マリー=ヘーセン氏がバランス・エンジニアという黄金のタッグ!
まさに自分の青春時代の5.0サラウンドは、この黄金タッグで作られたサウンドで育ってきた、と言っていい。
ポリヒムニアもいつまでもこの2人に頼るのではなく、若い世代を育てていかないといけない。
最近の作品は、若手のエンジニアの名前のクレジットもよく見かける。
もちろん、サラウンドにとって一番重要なバランス・エンジニアは、ジャン・マリさんか、エルド・グロード氏のどちらか一方が担うわけだが。
だから、この2人が、かつての黄金時代のように現場で仲良く揃う、というのは、いまではちょっと信じられないんですよ、自分にとっては。
このこと自体すごいことだし、最大限のおもてなし、とも感じる。
この児玉麻里・桃姉妹の企画に日本人が関与していると薄々感じるのは、そんな最高のおもてなしの配慮を感じるから。
自分のようなレーベル&アーティスト双方の大ファンにとっては、本当にうれしいプレゼント。
感謝しないといけませんね。
PENTATONEのプロデューサーもジョブ・マルセ氏。もう不動の名プロデューサーですね。
そんなプロデューサー案なのか、今回の作品のコンセプトは、とてもマニアックで興味深い。
つねに新しいことにチャレンジしていくマイナーレーベルらしい、すごく斬新なコンセプト。
![085[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0855B15D.jpg)
二重協奏曲集
児玉麻里&児玉 桃、デボラ・ネムタヌ&サラ・ネムタヌ
ローレンス・フォスター&マルセイユ・フィル
https:/
取り上げる作曲家も、オーケストラも自分は、いままで聴いたことがなかった。
作曲家はチェコの作曲家であるボフスラフ・マルチヌー。
![220px-Martinu_1943[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_220px-Martinu_19435B15D.jpg)
20世紀の作曲家で、彼の創作期間としては、チェコ・パリ時代の第1期、そしてアメリカ時代の第2期、最後にヨーロッパ(ニース、ローマ)に戻っての第3期と区分けされるようだ。まさに国際的に活躍した作曲家だったのだが、アメリカに滞在した1940年代が、まさに彼の創作活動の頂点だった。
マルチヌーは、400作を残したじつに多作な作曲家で、そのジャンルも、交響曲/バレエ音楽/管弦楽曲/協奏曲/室内楽曲/ピアノ曲/歌曲/合唱曲/そしてオペラ(歌劇)にまで及び、もうほとんどの曲を作曲しているのではないか、というくらいで驚愕の一言、大変な才能の持ち主であった。
作風も、その創作期間の時代とともに変遷していったようで、第1期の実験的書法、第2期の創作活動の頂点にあたる様々な曲へのアプローチ、そして最後のヨーロッパに戻っての第3期の新古典的、あるいは新印象主義的ともいわれる作風で形式にとらわれない自由な作風。
児玉姉妹の奏する『2台のピアノのための協奏曲』は1943年の絶頂期だった頃の作品。そして、ヴァイオリン、ヴィオラのほうの曲も1950年代ということで、いわゆる脂の乗り切った絶頂のときの作品を堪能できる、という感じなのだ。
自分が、今回のアルバムを聴いて、初マルチヌーを経験したのだが、自分が捉えた彼の作風の印象は、ロマン派などの古典主義のわかりやすい旋律よりも、もう少し難解な筆致で、でも現代音楽のような前衛的で、まるっきり実験的なアプローチでもなく・・・
その中間色にあたるような、程よい革新的な装いを持つ。
でも、その骨子にはややチェコの民族音楽的な旋律も垣間見えて、東欧色豊かで、色彩感のようなグラデーションっぽい音感も味わえて、自分はカッコいいと感じる。
古典主義をもう少し進化させた新古典主義というのが、やはり一番合う表現かな?
自分的にはクル感じの作曲家だ。
そして、オーケストラがマルセイユ・フィルハーモニー管弦楽団。
これも自分には初めて。マルセイユは、ご存知パリについで2番目にフランスでは大きい都市で、コートダジュールとも言われ、港町、いわゆるバカンス都市ですね。
そんなマルセイユがオケを持っているとはもちろん知らなかった。
彼らの情報をネットで調べてみるんだが、ほとんど皆無。ディスコグラフィーも1,2枚ある程度で、本当に未知数のオーケストラ。
なんで、マルセイユ、そしてマルセイユ・フィルなのか?はプロデューサー、企画のみが知る、というところだが、作曲家のマルチヌーは、チェコ出身とはいえ、その壮年期の大半をパリで暮らし、「エコール・ド・パリ」のメンバーとしても活躍していたので、フランスの音楽家にとっても自国の音楽としての自負があるのだろう。
マルチヌーの作品はチェコのスプラフォン・レーベルが熱心に紹介を続けているそうだが、フランス・マルセイユで録って、マルセイユ・フィルのオケで演奏することは、マルチヌーに対するフランス・オマージュの意味合いもあるのだと思う。
今回、このマルセイユ・フィルとの競演ソリストとして、ヴァイオリンとピアノが選ばれた。
「2つのヴァイオリンのための協奏曲」のほうは、フランスのデボラ&サラ・ネムタヌ姉妹。
そして、「2台のピアノのための協奏曲」のほうが、児玉麻里・桃姉妹。
2組の美人姉妹によるヴァイオリンとピアノの競演で、ネムタヌ姉妹はもちろんのこと、児玉姉妹もフランスを拠点にして活躍するアーティスト。
しかも、姉妹用ということで、きちんとヴァイオリンとピアノで、2台デュオで演奏するコンチェルトを、マルチヌーはきちんと作曲していたんだね。協奏曲については、様々な楽器のための30曲近くものの協奏曲を作ったらしいので、本当に興味旺盛で、多才な作曲家だったといえる。
そうすると・・・マルチヌーの曲を、フランスのオケで、フランスで録って、ソリストもフランスに所縁のある2組の姉妹。
なんか、フランスの香りいっぱいで、あまりによく仕込まれているアイデアだと感心しました。(笑)
録音場所は、マルセイユ、フリシュ・ラ・ベル・ド・メ。
わからず。(笑)
ライナーノーツ・ブックレットに、写真が載っていた。
う~ん。微妙。なんか見た感じ、そんなに専用スタジオのようにも見えないし、微妙な感じだが、録音を聴いた限りでは、空間もしっかり録れているし、すばらしかったので、そんなに問題ないのだろう。
でもキッツキッツで録っていたんですね。(笑)
さっそく聴いてみる。
マルチヌーの曲の印象は、既述の通り。カッコいい曲で、自分は気に入った。
自分は、ピアノのほうが、はるかに印象に残るというか、自分の好みに合う。
それは、やはり録音のよさ。
このアルバムを最初聴いたときは、正直なところ、かなり違和感があった。
いままでのPENTATONEサウンドとは、かなり異質な感じ。録音レベルが小さく、オフマイク気味。
PENTATONEサウンドはどちらかというとエネルギー感が大きいほうなのだが、この録音は、音が遠いなーという感じで、例によって最初、なんだ、冴えない録音だなと思い、どうしよう~と焦ってしまった。(笑)
でも音量を思いっきりグイっと上げると、隠されていた録音の良さがわかってきた。
ダイナミックレンジ超深し!!!
これってジャン・マリさんの影響が大きいのかな?
ジャン・マリさんの最近手がけた作品は、みんなこんな感じなのだ。逆にエルド・グロード氏単独の作品は、こういう作風とまたちょっと違うんだな。
音声波形を録る上で大切なパラメーターが、ダイナミックレンジと周波数レンジ。
通称、D-レンジとF-レンジ。
高域⇔低域などの高い音から低い音の幅を表すのが、横軸の周波数レンジ(F-レンジ)。
逆に音量の上から下までの幅を表すのが、縦軸のダイナミックレンジ(D-レンジ)。
人間の耳の構造って、1人1人でみな違う特性で、聴こえ方、好みのサウンドは違うと思うのだが、自分は音が高い⇔音が低いの幅が広い、つまりワイドレンジであることよりも、音量の上辺、底辺の深さが広いほうが、自分の耳に思わず反応してしまうのだ。
自分の耳は、周波数レンジよりもダイナミックレンジの広さのほうに思わず反応してしまう。
いい録音だなーと思うのは、この縦軸の深さが深いことのほうにドキッとしてしまうのだ。
そういう意味でも、ヴァイオリンの曲よりも、ピアノの曲のほうが、その深さを思いっきり感じ取れて、こっちのほうが録音ぜんぜんいい!という印象だった。鳴りきるときの音の沈み込みが秀逸といおうか。
だから、児玉姉妹のピアノの曲のほうが、すぐに好きになった。
でも、それは曲の特徴にもよるようだ。ヴァイオリンよりもピアノの曲のほうが、より凶暴で激しい旋律、そういう落差を感じやすい曲なのだ。とてもアバンギャルドな雰囲気でカッコいい。すぐにピアノ曲だけ何回もリピートして聴く感じになった。
ここの旋律は、麻里・桃姉妹のどちらが弾いているのかは、さすがにわからない。(笑)
でもその華麗でありながら、畳み掛けるような乱打の打鍵は、自分をかなり興奮させる。
東欧感溢れる異国情緒な旋律で、このような高速乱打の世界。
シビレル、じつにいい曲!
ピアノのほうを思いっきり聴き込んで余裕が出てくると、ヴァイオリンのほうも聴いてみると、これまたいい。(笑)・・・というか良さがわかってきた。
こちらはずいぶん穏やかな作風。
でも複雑な重音やパッセージが多用された難曲で、弾くには相当のテクニックが必要、難しそうな曲という感じを受ける。
もちろんネムタヌ姉妹の演奏は、はじめて聴くが、この難曲をものの見事に自分のものとして演奏していて、聴き込んでいくにつれて、その良さがよく感じ取れてきた。
児玉麻里・桃姉妹によるPENTATONEの新譜第2弾は、とてもユニークなコンセプトでまとめられていて、商業主義第一優先のメジャーレーベルでは到底考えも及ばない柔軟な発想のアルバムだった。
記念撮影。
児玉麻里・桃。そしてジャン・マリさんとエルド・グロード氏。指揮者のローレンス・フォスター。そして今回のコンセプト企画に大きな影響を及ぼしたと思われるプロデューサーのジョブ・マルセ氏。
こういうビッグフェイスがいっせいに揃って記念撮影すること自体、やはり自分は、日本人の仕掛け人がきっといる!と確信するのです。(笑)
人間の耳の構造って、1人1人でみな違う特性で、聴こえ方、好みのサウンドは違うと思うのだが、自分は音が高い⇔音が低いの幅が広い、つまりワイドレンジであることよりも、音量の上辺、底辺の深さが広いほうが、自分の耳に思わず反応してしまうのだ。
自分の耳は、周波数レンジよりもダイナミックレンジの広さのほうに思わず反応してしまう。
いい録音だなーと思うのは、この縦軸の深さが深いことのほうにドキッとしてしまうのだ。
そういう意味でも、ヴァイオリンの曲よりも、ピアノの曲のほうが、その深さを思いっきり感じ取れて、こっちのほうが録音ぜんぜんいい!という印象だった。鳴りきるときの音の沈み込みが秀逸といおうか。
だから、児玉姉妹のピアノの曲のほうが、すぐに好きになった。
でも、それは曲の特徴にもよるようだ。ヴァイオリンよりもピアノの曲のほうが、より凶暴で激しい旋律、そういう落差を感じやすい曲なのだ。とてもアバンギャルドな雰囲気でカッコいい。すぐにピアノ曲だけ何回もリピートして聴く感じになった。
ここの旋律は、麻里・桃姉妹のどちらが弾いているのかは、さすがにわからない。(笑)
でもその華麗でありながら、畳み掛けるような乱打の打鍵は、自分をかなり興奮させる。
東欧感溢れる異国情緒な旋律で、このような高速乱打の世界。
シビレル、じつにいい曲!
ピアノのほうを思いっきり聴き込んで余裕が出てくると、ヴァイオリンのほうも聴いてみると、これまたいい。(笑)・・・というか良さがわかってきた。
こちらはずいぶん穏やかな作風。
でも複雑な重音やパッセージが多用された難曲で、弾くには相当のテクニックが必要、難しそうな曲という感じを受ける。
もちろんネムタヌ姉妹の演奏は、はじめて聴くが、この難曲をものの見事に自分のものとして演奏していて、聴き込んでいくにつれて、その良さがよく感じ取れてきた。
児玉麻里・桃姉妹によるPENTATONEの新譜第2弾は、とてもユニークなコンセプトでまとめられていて、商業主義第一優先のメジャーレーベルでは到底考えも及ばない柔軟な発想のアルバムだった。
記念撮影。
児玉麻里・桃。そしてジャン・マリさんとエルド・グロード氏。指揮者のローレンス・フォスター。そして今回のコンセプト企画に大きな影響を及ぼしたと思われるプロデューサーのジョブ・マルセ氏。
こういうビッグフェイスがいっせいに揃って記念撮影すること自体、やはり自分は、日本人の仕掛け人がきっといる!と確信するのです。(笑)
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番のサラウンド録音 [ディスク・レビュー]
ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番という曲は、ピアノ協奏曲の中でも、もっとも技巧的に難しく弾くのが困難な曲と言われている。それは、この曲に限らず、作曲者ラフマニノフの手の大きさが人並み外れて大きいことに起因する。彼がふつうに届く鍵盤の間隔も、普通のピアニストにとっては、かなり肉体的限界への挑戦となるのだ。
その作品群の中でも、このピアノ協奏曲第3番は、その肉体的限界に加えて、とりわけその音数の多さ(譜面上の音符の数)、そして大変な技巧を極めた曲なのだ。
昔からこの曲を弾けるピアニスト、録音として残してきているピアニストは極めて少なく、オーディオファンとしては、悲しい想いをしてきた。ラフマニノフのピアノ協奏曲としては、2番のほうが出世作として有名なのかもしれないが、自分は断然3番のほうが好きである。
自分のこの曲に対する昔から抱えている悩みとして、自分のイメージする理想の演奏の録音に巡り会えることが極めて少ないことなのだ。ただでさえ録音が少ないのに、その中で、さらに自分が思い描く理想の演奏である録音は、皆無だった。
自分の経験からすると、クラシックファンにとって、その曲を覚えた演奏家の演奏が、いつまでも自分の頭の中のリファレンスとして残るもので、それを超える演奏に出会えるのは、なかなか難しい。
自分が、この曲でリファレンスとしているのは、この音源。
チャイコフスキー: ピアノ協奏曲第1番&ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番
マルタ・アルゲリッチ
演奏としては、アルゲリッチらしい強打腱で乱暴で突っ走る感のある演奏で、緩急はあまりなく一本調子のところもある。第1楽章のカデンツアもない。これより名演奏なものも実際多いだろう。でもこの演奏が、自分のこの曲についてのリファレンスなのだ。ラフ3の興奮処、魅せ場は、これを基準にしている。
こればかりは個人の感性によるところが大きい。
この盤は、1980年の古い録音。新しい録音で、優秀な演奏の録音をずっと探し続けてきているのだが、これは!というのになかなか巡り会えないのだ。
また自分がクラシックの音源を聴く場合は、必ず演奏とそして録音の良さという2点から選ぶのが筋でもある。オーディオファンであるので、録音の良さは必須条件で、やはり録音のよくない音源は、自分の愛聴盤として挙げられないのである。
でも、このラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番だけは別。
演奏第1主義。
この曲に関しては、まずその演奏解釈が第1優先なのだ。
この曲は、このような演奏であれば、まさに感動する、自分のツボに嵌る、という理想の演奏体系・造形が自分の中にすでに構築されている。そう言い切れるだけ、実演含め、この曲の演奏に触れてきた。
これは自分がとても不思議に感じていることなのだけれど、この曲は、CD/SACDなどのオーディオ音源よりも、実演含めた映像素材のほうが、とても感動するのだ。これがどうしてなのか?自分でも説明できない。
自分がいままでこの曲で大感動したのは、ほとんど映像素材といっていい。
まずここから入った。
「ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番」・・・この曲をひとことでイメージづけするのなら、
「ダイナミズムと甘美な旋律が融合した音の絵巻物語」
まずダイナミックでないといけない。40分強あるこの曲は、いわゆる旋律の流れとしてきちんとした筋書があって、その要所要所に魅せるための決め処のテクニックの披露、随所にはめ込まれている甘美な旋律の流れなどがある。第1楽章のカデンツアや、第2楽章の華麗なトリルの部分などなど、そのそれぞれの名所は、全体のフレームを華麗に魅せるために要所要所に散りばめられている布石となっているのだ。
そしてこの曲で私が最も興奮するところ、終盤のエンディングにかけてのグルーブ感、テンポを上げて 一気に盛り上がり、その頂点で派手な軍楽調の終止に全曲を閉じる部分。 この賑やかな軍楽的な終結は「ラフマニノフ終止」と呼ばれているもので、この部分で私はいつも体全体に稲妻のようなゾクっとくるのを感じるのが快感なのだ。この部分の感動を味わいたくて、最初からずっと聴いているみたいな.....
このラフマニノフ終止に至る劇的な感動は、まさにその間に仕込まれた数々の決め処の見せ場があるからこそ、生きてくると思うのだ。このエンディングで、40分強という長大でロマンティックな旋律で綴られた音の絵巻物語を、このフィニッシュで一瞬にして完結させてしまう圧巻のその瞬間! このラストの瞬間を聴いたと同時に、いままでの布石が走馬灯のように頭の中を駆け巡り、その余韻の素晴らしさ、そして楽曲を弾ききった達成感、その長い壮大なドラマが完結したような興奮が一気に最高潮ヴォルテージに達する。
まさに音の絵巻物語なのだ。
そういう感動のメカニズムを達成するには、演奏する側に必要な要素は、まず躍動感&パワー、そしてダイナミズム。ダイナミズムがあるからこそ、弱音表現などの緩急の差も生きてくる。
この曲の華麗でダイナミックな演奏は、やはり映像素材などの映像付きで鑑賞すると感動の度合いが違うと感じるのは、そこなのかもしれない。それがCDではなかなか自分の琴線に触れる作品に出会えないのに、映像ソフトではこのように感動作品に出会えるという理由なのかと思ってしまう。この曲は視覚効果というか、速射砲のような運指、体全体を激しく揺らすダイナミックな演奏風景を観ながら聴くという眼・耳の両方からの相乗効果で、脳に与える刺激が何倍にも膨れ上がる、ということ。
また、2番は、どちらかというとオーケストラが先に走って、それにピアノが追随していくスタイルなのだが、3番は、全く逆。ピアノがつねに先を走ってオーケストラを誘導する。そういう意味でも、ピアニストにとって、つねに見せる要素の強い曲と言えるのだと思っている。
これが、この曲が実演、映像ソフトなど映像から入る作品に向いていると思う理由なのである。
そういうことを考えると、やはりこの曲は、男性ピアニストに有利な曲であることは仕方がないことなのだろう。
自分がこの曲で感動していた演奏としては、2004年のゲルギエフ&ウィーンフィルのサントリーホールでの来日公演。イエフィム・ブロンフマンをソリストに迎えてのこの曲の演奏は、観ていて鳥肌が立った。まさに近代稀にみる名演奏という評判に相応しい名演であった。
そして、ロシアのピアニスト、デニス・マツーエフ。
まさに叩いて叩いて叩きまくる。その圧倒的な力技の奏法に、演奏中にピアノの位置がずれてしまう(笑)、というくらい凄いダイナミズムの代表のようなピアニストなのだが、この人のこの曲の演奏もじつに素晴らしいものがあった。ベルリン・フィルのDCH(Digital Concert Hall)で出会った(2010年か2011年の定期公演の演奏)。ゲルギエフ/ベルリン・フィルとの競演で、ベルリンフィルハーモニーでこの曲を披露していたが、まさに圧巻だった。
このマツーエフは元々乱暴な弾き方をするピアニストで、凄い荒々しい演奏なのだが、これがこの曲と妙にマッチしていて、じつに鳥肌もので素晴らしいと思った。この曲には、やはりパワー&ダイナミズムが必要不可欠なのだな、と改めて考えさせられた。
この曲を聴衆に対して感動させるには、こうだ!というようなお手本のような演奏だと思う。
いまでもアーカイブで観れると思うので、ぜひご覧になってほしい。自分がラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番で理想とする演奏がそこにある。
いまでもアーカイブで観れると思うので、ぜひご覧になってほしい。自分がラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番で理想とする演奏がそこにある。
マツーエフのこの曲は実演にも接したことがある。ゲルギエフ&マリインスキーの公演でサントリーホールで聴いた。期待を裏切らない素晴らしい演奏だった。
こうしてみると、ラフマニノフはロシアの作曲家。ロシア人指揮者のゲルギエフがこのような優秀なラフマニノフ弾きを育て、次々と世に送り出すのが上手なのは、もう彼らロシア人からするとロシア音楽を背負っていく宿命みたいなものなのだろう。
確かに男性ピアニスト有利な曲ではあるが、女性ピアニストでも素晴らしいラフマニノフ弾きがいる。
我らが小山実稚恵さんだ。
小山実稚恵さんは学生時代より特に3番がお気に入りで、この曲を聴かないと寝れないというくらい好きであり、その後ピアニストとしての夢をかなえた。
日本でこの曲を初演したのはまさに小山さんなのだ。(ちなみに指揮は小泉和裕さん。)
そして小山さんは日本一のラフマニノフ弾きとしての評価を不動のものとしている。
ご本人がもっとも好きだという曲だけあって、この曲には特別の思い入れがあるようで、国内で頻繁にこの曲の演奏会を開いてくれる。この曲が大好きな私にとって生演奏を聴こうと思ったら、必然と小山さんの演奏会に出かけることになる。
そして小山さんは日本一のラフマニノフ弾きとしての評価を不動のものとしている。
ご本人がもっとも好きだという曲だけあって、この曲には特別の思い入れがあるようで、国内で頻繁にこの曲の演奏会を開いてくれる。この曲が大好きな私にとって生演奏を聴こうと思ったら、必然と小山さんの演奏会に出かけることになる。
小山さんのこの曲の公演は、もう軽く10回~20回くらいは行っていると思う。
つい最近新しいところでは、小山さんのデビュー30周年記念コンサートでサントリーホールで、この曲を演奏してくれた。自分は、そのとき聴いて大感動した。
小山さんのラフ3は、女性ピアニストならではの解釈で、とても柔らかい女性的な表現でありながら、肝心の緩急の部分、要所要所の魅せる部分、全体のロマンティックな流れなど申し分なかった。まさに日本でのこの曲の第1人者である。
序章は、長くなってしまったが、ここからが本番である。(笑)
この曲に対するこだわりがあまりに強すぎるため、長いこと自分のこれは!と思える音源に出会えなかったのだが、BISの新譜で、なんとこの曲のSACD5.0サラウンド録音がでた。
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番、第3番
エフゲニー・スドビン、サカリ・オラモ&BBC交響楽団
1980年生まれのロシア・サンクトペテルブルク生まれのピアニスト、エフゲニー・ズドビン。
BISレーベルが、デビュー以来、ずっと育ててきている若手の男性ピアニストだ。
BISレーベルが、デビュー以来、ずっと育ててきている若手の男性ピアニストだ。
この人のBISの新譜は、いままで必ず自分の日記で紹介してきた。
ラフマニノフ、メトネル、スクリャービン、チャイコフスキーなどを得意レパートリーとして録音を残してきている。最近ではベートーヴェンのコンチェルトやスカルラッティ・ソナタを日記で取り上げた。
とにかくこの人の演奏、録音は外れがないのだ。
いままで期待を裏切られたことがない。
いままで期待を裏切られたことがない。
素晴らしい演奏に、素晴らしい録音。
このズドビンが、ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番。
そしてBIS録音。SACDの5.0サラウンド録音。
そしてBIS録音。SACDの5.0サラウンド録音。
全てが揃った。
相当心ときめいた。
ラフ3のサラウンド録音は、いままでないことはなかったが、自分の好みではなかった。
ついに自分の本懐が遂げられる時がやってきた!
新譜の封を切って、トレイに乗せて、ドキドキしながら聴く。
・・・以下沈黙。(苦笑)
やっぱりそう世の中簡単にうまくいくことってないんだなぁ。
期待していたズドビンのラフ3は、自分の理想としていた演奏とは程遠いものであった。
期待していたズドビンのラフ3は、自分の理想としていた演奏とは程遠いものであった。
要所要所での決め処、魅せ処が、まったく自分の理想とかけ離れていて、全体のスケッチ、絵巻物語のようなストーリーが描けていないような感じがした。(描けていないと言ったら言い過ぎかもだが、自分の理想とあきらかに違う。)
確かに全体としては無難にまとまって演奏しているのかもしれないが、自分はこの要所要所での決め処の甘さが許せなかった。ここが甘いと全体の骨組み、そして最後のシャットダウンに至るときの壮大な余韻の感動が弱くなってしまう。終焉に向けて一気にエネルギーをぶつけていく瞬発力を養うためには、それまでの間の壮大なドラマの描き方がとても大切なプロセスになると思うのだ。録音はBISなのでいいのだが、自分にはやはり演奏解釈という点で、そこが残念賞であった。
いままで裏切られたことのなかったズドビンでさえを持っても、満足できない自分。
この曲に対するこだわりは、もうほとんど病気なのかもしれない。
返って、2番のほうがとてもいい演奏であった。自分は2番は合格点。
アルバムとしてのトータルバランスとしては優秀でいい録音作品の部類なのだと思う。
3番に対する自分のこだわりが邪魔をしているだけ・・・
ラフマニノフの曲風は、よくロマンティック、メランコリック、映画音楽のようだ、.....とか言われるが、確かに、うっとりするような華麗・甘美なメロディの調べは、いにしえのクラシック作曲家達の曲風とは一線を画している彼独特の旋律のように感じる。
また、ラフマニノフは 映画音楽のようだといわれるけど、映画音楽のほうが彼の作品を参考にしたわけで、ギリギリのところでポップスに行かない、そういうひとつのクラシックとしての敷居の高さを守っている、そういうすごい才能があると思う。
そんなラフマニノフの作品は、いまから40年ほど前までは、「鐘の前奏曲」とピアノ協奏曲第2番が良く知られていて、さらに交響曲第2番やパガニーニ狂詩曲がコンサート・プログラムに徐々に取り上げられるようになって来たかな・・・ といった状況だった。
だからラフマニノフといえば、大ピアニストで作曲もした人というのが大方の音楽ファンの認識だったと思う。しかし ここ40年で状況は大きく変わった。
・3曲の交響曲 管弦楽曲
・ピアノ協奏曲
・室内楽曲
・ピアノ独奏曲
・声楽曲・オペラ
・ピアノ協奏曲
・室内楽曲
・ピアノ独奏曲
・声楽曲・オペラ
作曲家ラフマニノフの全貌が レコード音楽を中心に明らかになったと言える。
そうしてみると 単にピアニストの余技どころではなく、グリーグ、シベリウスあたりと堂々と肩を並べるべき大作曲家であるというように認識も変わって来た。そして 何よりもラフマニノフの音楽に特有の先が見えないようなメランコリックな雰囲気が 今の時代にフィットしている感じがする。
そうしてみると 単にピアニストの余技どころではなく、グリーグ、シベリウスあたりと堂々と肩を並べるべき大作曲家であるというように認識も変わって来た。そして 何よりもラフマニノフの音楽に特有の先が見えないようなメランコリックな雰囲気が 今の時代にフィットしている感じがする。
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番。
自分にとって、この曲に対する音源探しの旅はこれからも続くのだろう。
今回の件で、いったいいつになったら本懐を遂げられるのだろう?と想うことしきりだ。
エディット・マティスの芸術 [ディスク・レビュー]
スイスの歌姫である我が永遠のディーヴァ、エディット・マティスの初のベスト作品集、素晴らしい!マティスのすべて、そして彼女の魅力が余すことなく詰め込まれている。限定盤なので、完売とともに廃盤になる。急いだほうがいい。予想していた以上に素晴らしかった!
マティスが活躍した1960~1982年の録音なので、古い録音なのだが、録音もじつに素晴らしいのだ。少なくとも我がステレオ2chシステムでは、かなりのハイレベルで鳴る。そのクオリティの高さに驚愕した。
自分の永年のマティスへの想いを遂げることができた、と思う。
![601[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6015B15D-4bb80.jpg)
エディト・マティスの芸術(7CD)
https:/
2018年2月11日に80歳の誕生日を迎えるマティスだが、そのセレモニー・アルバムとして企画された。彼女が生涯にわたって録音を重ねてきたオペラ、オラトリオ、そして晩年の歌曲を、すべてと言っていいくらい全部盛り込まれている。
オペラ、オラトリオの部分は、もちろんマティスが歌っている部分の抜粋になる。
全7枚をじっくり聴き込むこと繰り返し数回、マティスのすべてを理解できた。永年の彼女に対する想いの自分の溜飲は十分に下げたかな、という気はした。
マティスは、1960~1990年代に活躍したソプラノで、ドイツ圏のソプラノとしてはトップクラスの美貌、それもどちらかといえば愛嬌のあるルックスが大きな魅力で、初来日時の人気ぶりは今なお語り草になっている。
「とにかくキュートで可愛い!」というのが当時のマティスの大きなインパクト。
若いときはもちろんのこと、歳を重ねていってもその可愛らしさは、相応で兼ね備えているから、まさに理想的な歳のとり方かも?
もちろん自分はリアルタイム世代を知らないので、後世に知ってずっと憧れていた、そんなディーヴァだった。
マティスのずばり得意とした分野は、ドイツ歌曲や宗教音楽、モーツァルトを中心としたドイツ・オペラの世界。
今回、彼女の作品を、全部聴き込んで、マティスの声質、歌などの「マティスの世界」はこれだ! というものを捉えることができた。
オペラの世界では、ソプラノには大きく、スブレット、リリック、ドラマティックの3つのカテゴリーに分けられるのだそうだ。
スブレットは、柔らかくしなやかな声で、ある程度の高音域が充実し、中音域をよく出せること。優れた言語能力(特にドイツ語)と演技力だけでなく、繊細な体つきと外見が要求される。歌手は若い少女の外見、生き生きとした性格でなければならない。
それに対して、リリックというのは、非常に柔軟で、明るい響き、敏捷性のある声であること。高音域や早いコロラトゥーラを歌う能力があること。
要求される性格はスブレットと大差はない。リリックがスブレットと異なることは、高音が歌えるかどうか、早いコロラトゥーラのパッセージを歌えるかどうか、そしてより明るい音色を持つかということである。
リリックな声を持つ歌手は、イタリアオペラの暖かい響きと美しいレガートラインを歌うのに適していて、外見はより柔らかく女性的であることなどが代表格。
最後に、ドラマティック・コロラトゥーラ。
高音域も充実した、柔軟で、かつ気品ある叙情的な線を描ける声であること。リリックよりもパワフルで、リリックよりも幅広い音域を伴うコロラトゥーラを歌い、劇的な感情を噴出させる能力をもつ必要がある。またこの声は、コロラトゥーラでも重めの音楽を含むイタリア語によるオペラの役を歌うことが要求されることが多く、リリック・コロラトゥーラより豊かな声量が必要。
性格のタイプはリリックソプラノやスブレットに代表されるものに比べ、より高貴な人物として描かれることが多い、のだそうだ。
ドラマティックは、まさにメタリックな響きでかつ気品ある歌声が条件。歌だけではなく、舞台を支配できるような見た目の魅力も要求される。
マティスは、この中では、リリック・ソプラノと呼ばれる範疇に入る歌手と言われている。
ずばりマティスの声質、歌い方は、声に硬質な芯があって、明暗をはっきりさせた、まさに「楷書風」の歌い方なのだ。
そして、とても品格がある。声の響き方に、孤高の気品の高さが漂う感じ。
確かに、なによりも明るい響きがある。
そして思うことは、非常に古風な歌い方だということ。現代のオペラ歌手の歌い方で、このような歌い方をする人はいない。昔の時代の歌手の雰囲気がある。これが自分が抱いたマティスへの率直な印象。
そう感じてしまうのは自分が近年体験してきているオペラのスター歌手というのは、まさにホールを圧するかのような巨大な声量で、圧倒的な存在感を示すというタイプの歌手が多く、上のジャンル分けでいうと、ドラマティックの部類だからなのだと思う。
つまりイタリア・オペラのプッチーニやヴェルディといった華やかさ、ワーグナーのような力強さのような持ち味って、まさに、このドラマティック・ソプラノなのだと思う。
マティスは、明らかに違う。
もっと軽い感じで、明るい響きを持った声質、そして、とても古風で気品のある「楷書風」の歌い方。。。それがマティスなのだ。ドイツ語のかっちりした響きとぴったり合致する印象がありますね。
ただ、インタビューで彼女は、コロラトゥーラは歌えない、と言っているし、彼女の作品の中では、そのような技巧を聴くことはない。
マティスは、強力な個性は感じさせはしないものの、澄んだ美声を持つリリック・ソプラノで、技巧的にも長け、舞台での演技力も、歌の演出力も大変優れている。
オペラでのレパートリーの中心は、やはりモーツァルトで、スザンナ、マルツェリーナ、デスピーナなど。ほかにエンヒェン、アンナ、ライヒなど、リリックの役は数多く歌っている。
マティスが活躍した1960~1982年の録音なので、古い録音なのだが、録音もじつに素晴らしいのだ。少なくとも我がステレオ2chシステムでは、かなりのハイレベルで鳴る。そのクオリティの高さに驚愕した。
自分の永年のマティスへの想いを遂げることができた、と思う。
![601[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6015B15D-4bb80.jpg)
エディト・マティスの芸術(7CD)
https:/
2018年2月11日に80歳の誕生日を迎えるマティスだが、そのセレモニー・アルバムとして企画された。彼女が生涯にわたって録音を重ねてきたオペラ、オラトリオ、そして晩年の歌曲を、すべてと言っていいくらい全部盛り込まれている。
オペラ、オラトリオの部分は、もちろんマティスが歌っている部分の抜粋になる。
全7枚をじっくり聴き込むこと繰り返し数回、マティスのすべてを理解できた。永年の彼女に対する想いの自分の溜飲は十分に下げたかな、という気はした。
マティスは、1960~1990年代に活躍したソプラノで、ドイツ圏のソプラノとしてはトップクラスの美貌、それもどちらかといえば愛嬌のあるルックスが大きな魅力で、初来日時の人気ぶりは今なお語り草になっている。
「とにかくキュートで可愛い!」というのが当時のマティスの大きなインパクト。
若いときはもちろんのこと、歳を重ねていってもその可愛らしさは、相応で兼ね備えているから、まさに理想的な歳のとり方かも?
もちろん自分はリアルタイム世代を知らないので、後世に知ってずっと憧れていた、そんなディーヴァだった。
マティスのずばり得意とした分野は、ドイツ歌曲や宗教音楽、モーツァルトを中心としたドイツ・オペラの世界。
今回、彼女の作品を、全部聴き込んで、マティスの声質、歌などの「マティスの世界」はこれだ! というものを捉えることができた。
オペラの世界では、ソプラノには大きく、スブレット、リリック、ドラマティックの3つのカテゴリーに分けられるのだそうだ。
スブレットは、柔らかくしなやかな声で、ある程度の高音域が充実し、中音域をよく出せること。優れた言語能力(特にドイツ語)と演技力だけでなく、繊細な体つきと外見が要求される。歌手は若い少女の外見、生き生きとした性格でなければならない。
それに対して、リリックというのは、非常に柔軟で、明るい響き、敏捷性のある声であること。高音域や早いコロラトゥーラを歌う能力があること。
要求される性格はスブレットと大差はない。リリックがスブレットと異なることは、高音が歌えるかどうか、早いコロラトゥーラのパッセージを歌えるかどうか、そしてより明るい音色を持つかということである。
リリックな声を持つ歌手は、イタリアオペラの暖かい響きと美しいレガートラインを歌うのに適していて、外見はより柔らかく女性的であることなどが代表格。
最後に、ドラマティック・コロラトゥーラ。
高音域も充実した、柔軟で、かつ気品ある叙情的な線を描ける声であること。リリックよりもパワフルで、リリックよりも幅広い音域を伴うコロラトゥーラを歌い、劇的な感情を噴出させる能力をもつ必要がある。またこの声は、コロラトゥーラでも重めの音楽を含むイタリア語によるオペラの役を歌うことが要求されることが多く、リリック・コロラトゥーラより豊かな声量が必要。
性格のタイプはリリックソプラノやスブレットに代表されるものに比べ、より高貴な人物として描かれることが多い、のだそうだ。
ドラマティックは、まさにメタリックな響きでかつ気品ある歌声が条件。歌だけではなく、舞台を支配できるような見た目の魅力も要求される。
マティスは、この中では、リリック・ソプラノと呼ばれる範疇に入る歌手と言われている。
ずばりマティスの声質、歌い方は、声に硬質な芯があって、明暗をはっきりさせた、まさに「楷書風」の歌い方なのだ。
そして、とても品格がある。声の響き方に、孤高の気品の高さが漂う感じ。
確かに、なによりも明るい響きがある。
そして思うことは、非常に古風な歌い方だということ。現代のオペラ歌手の歌い方で、このような歌い方をする人はいない。昔の時代の歌手の雰囲気がある。これが自分が抱いたマティスへの率直な印象。
そう感じてしまうのは自分が近年体験してきているオペラのスター歌手というのは、まさにホールを圧するかのような巨大な声量で、圧倒的な存在感を示すというタイプの歌手が多く、上のジャンル分けでいうと、ドラマティックの部類だからなのだと思う。
つまりイタリア・オペラのプッチーニやヴェルディといった華やかさ、ワーグナーのような力強さのような持ち味って、まさに、このドラマティック・ソプラノなのだと思う。
マティスは、明らかに違う。
もっと軽い感じで、明るい響きを持った声質、そして、とても古風で気品のある「楷書風」の歌い方。。。それがマティスなのだ。ドイツ語のかっちりした響きとぴったり合致する印象がありますね。
ただ、インタビューで彼女は、コロラトゥーラは歌えない、と言っているし、彼女の作品の中では、そのような技巧を聴くことはない。
マティスは、強力な個性は感じさせはしないものの、澄んだ美声を持つリリック・ソプラノで、技巧的にも長け、舞台での演技力も、歌の演出力も大変優れている。
オペラでのレパートリーの中心は、やはりモーツァルトで、スザンナ、マルツェリーナ、デスピーナなど。ほかにエンヒェン、アンナ、ライヒなど、リリックの役は数多く歌っている。
ここで、マティスの歌手としての経歴を紹介してみる。(マティスの経歴については、ネットで調べても、きちんと書かれているのは、ほとんど皆無で、東京文化会館音楽資料室で調べてきました。それを紹介します。とても貴重な資料だと思います。)
エディット・マティスは、1938年2月11日に、スイスのルツェルンで生まれた。
ルツェルンの音楽院で学び、チューリッヒの音楽教育家エリーザベト・ボスハルトに声楽を師事した。1959年に、ケルン歌劇場と契約。ケルンでの活躍で、しだいにマティスの名は知られるようになる。
1960年にザルツブルク音楽祭に初出演。この年からドイツ各地の歌劇場に客演する。
1962年には、グラインドボーン音楽祭の「フィガロの結婚」に出演。
ハンブルク、ミュンヘン、ウィーンの国立歌劇場でも歌って成功を収めた。
1963年までケルン歌劇場のメンバーだったが、1960~1972年の間は、ハンブルク国立歌劇場にも属し、1963年からベルリン・ドイツ・オペラと客演契約を結んでいる。
1970年ニューヨークのメトロポリタン歌劇場に「魔笛」のパミーナを歌って初出演し、同じ年ロンドンのコヴェントガーデン王立歌劇場にも出演した。
指揮者、ピアニストのベルンハルト・クレーと結婚し、ロンドンを本拠地に、世界各地で歌っている。
ザルツブルクで1月に開催されるモーツァルト祭の常連でもあり、ここで初期モーツァルト・オペラの上演に参加して高い評価を得ている。オペラのほか、リサイタル歌手、歌曲の歌手としてもさかんな活動を行っている。
初来日は1963年。ベルリン・ドイツ・オペラのメンバーとしてだった。
このときはベーム指揮「フィガロの結婚」でケルビーノを歌って評判にもなっている。
テノールのペーター・シュライアーと組んでの二重唱は、各地で好評を博し、レコード録音もされた。
マティスの録音については、自分は、少し誤解していたところがあったようだ。
自分は、彼女の録音は軒並み廃盤が多くて入手が困難という認識をずっと持っていたのだが、じっくり調べてみると、いわゆるオペラ、宗教曲、オラトリオの一員として歌っているものは多く、オンラインのタイトル表示から、それに気が付かないということだけのようだった。
今回ベスト作品集を聴いてみて、思ったこと。
マティスは確かに、オペラ、宗教曲、オラトリオとしてキャリアをスタートさせたが、彼女の声、歌の表現を十分に堪能できて、自分が魅かれるほうは、晩年に演奏会活動、録音をスタートさせたリート歌曲の世界のほうではないか、と思ったことだ。
マティスは、リート歌曲の世界では、モーツァルト、シューマン、ブラームス、ヴォルフを残している。これがどれもじつに秀逸。
特に今回のベスト作品集では、ヴォルフの「イタリア歌曲集」が盛り込まれていて、CDとしては初販売なのだそうだ。大変貴重な音源。
自分がマティスの存在を知って、彼女に魅かれたのは、シューマンの「女の愛と生涯」。
「詩人の恋」と並んで、シューマンの2大連作歌曲でもある。
この「女の愛と生涯」。男性と出会い・恋心・異性と結ばれる不安・結婚・出産・死別・・・と順当に進行する内容で、「詩人の恋」のようなドラマティックな展開がない。しかし一方で童話作家の故佐野洋子さん風に言えば「ふつうがえらい」的なストーリーであって、平凡な中にあるささいなときめきやドラマを描いているのだ。
そういう魅力が、自分にとって、詩人の恋には負けていない、シューマンの連作歌曲集の中でもとても気になる歌曲のひとつになっている。
特に「わたしの指の指輪よ」。この旋律の美しさには涙する。最も有名な旋律で、この美しさに心揺さぶられない人などいないだろう。
この「女の愛と生涯」で、自分がこれだ、と思える録音になかなか巡り会えなかったのだが、ゴローさんの日記で、マティス盤を知った。
![3db982514a91a79f94b47d49b49a6f755B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_3db982514a91a79f94b47d49b49a6f755B15D5B15D-96491.jpg)
これを入手するのは、じつに困難を極めた。全集の中の1枚という位置づけで、単盤では売られていない代物だし、しかもいまは廃盤だ。
それを必死な想いで中古市場で見つけた。
そんなお宝盤なのであるが、それが今回のベスト盤では、この「女の愛と生涯」、全曲入っているのだ!!!
もうこれだけで、絶対買いなのだ!
もうお宝盤ではないのだ!
このベスト集をみなさんにお勧めするのも、ずばり、この歌曲を聴いてほしいからだ。
マティスが歌う「女の愛と生涯」。まさに自分の追い求めていたこの歌の理想の表現の世界。
今回改めて聴いてみたが、やっぱりじつに素晴らしい。
そしてモーツァルト歌曲集。
マティスってやっぱりモーツァルトの人なんだなーとつくづく思わさせてくれる作品。
モーツァルトを歌っているときの彼女は、まさに活き活きとしていて、彼女の1番いい面を聴いている感覚になる。
ただ、今回のベスト作品集では、このモーツァルト歌曲集の入っている曲が少なくて、ちょっと不満。
ぜひ単盤で、こちらのほうも購入することをお勧めしたい。
素晴らしいの一言です。これぞ、マティスの世界!と呼べる録音だと思います。
この盤が、一番マティスらしいと思います。
![058[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0585B15D.jpg)
モーツァルト歌曲集
マティス、クレー、越智敬
https:/
マティスのモーツァルトと言えば、こちらもぜひお薦めしたい単盤。
こちらもベスト作品集の中には、あまり入っていないので、単盤購入としてお勧めしたい。
宗教曲もマティスの得意なレパートリーだったのだが、モーツァルトの宗教曲の傑作といっていいミサ曲のなかで最も広く知られる『戴冠ミサ』、華やかな声の動きが際立つ「アレルヤ」で有名なモテットなどの4曲。
これがじつにいい。素晴らしい録音。自分の愛聴盤です。
![349[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_3495B25D.jpg)
戴冠ミサ、エクスルターテ・ユビラーテ、他
マティス、クーベリック&バイエルン放送響、クレー&シュターツカペレ・ドレスデン、他
https:/
今回のベスト作品集では、バッハのカンタータや『マタイ受難曲』などの宗教曲、『フィデリオ』『ばらの騎士』、有名なカール・ベームとのモーツァルト、カルロス・クライバーとの伝説の『魔弾の射手』録音、そして我らが小澤征爾さんともベルリオーズの『ファウストの劫罰』の録音を残しているのだ。
本当にお宝限定盤なのだ。
今回このベスト作品集を聴いて、ようやく長い間、霧に包まれていたエディット・マティスの世界がわかったと言えるかもしれない。
リアルタイム世代を知らないだけに、余計に憧憬の念が強かった。
最後に録音評。
オーディオにとってソプラノなどの女声再生って、ほんとうに難しい。
マティスの声は、オーディオ再生するには非常に難しい、ということを申し上げておきたい。
彼女の声質は、とても硬質で芯があるので、強唱のときに、かなり耳にキツく感じるのだ。
ボリュームコントロールがとても大切になる。
近代のオペラ歌手のアルバムは、どんなにボリュームを上げていても、強唱のときにうるさく感じることはあまりないのだが、マティスはかなりキツイ。
普段聴いているVOL設定で聴いていると、隣接の住人からクレームをもらうこと多々だし、自分でも聴いていて、かなり耳にキツイと感じることが多い。
昔の録音なので、ダイナミックレンジがあまり広くないのか、とも思うが、うまくボリュームコントロールして聴くことが大切。
録音自体は、じつに素晴らしいです。声の響きかた、S/Nなどの音のクリア感、鮮度感など、古い時代の録音とはとても思えないくらい。
拙宅のステレオ2ch再生でもじつによく鳴ってくれます。
なんか本懐を遂げた感じです。(笑)
池田昭子さんのオーボエ作品集 [ディスク・レビュー]
N響の華であって日本を代表するオーボエ奏者の池田昭子さんの7枚目のソロアルバム。
以前にも自分の日記で何回も特集したが、木管奏者、とりわけオーボエ奏者が自分のソロ作品集を出せるって、まさに華形スターの証拠なのだと思う。
自分は取り分けオーボエのソロ作品集には目がなくて、世界のオーケストラの首席オーボエ奏者が出すオーボエ・ソロのアルバムは、かなりコレクターしてきている。
特に、バッハ、モーツァルトのオーボエ作品集を録音するのは、ひとつの登竜門というか、晴れ舞台、一流の証のような気がする。普段は超一流オケの首席オーボエ奏者という立場で演奏し、その一方でソリストとして、このバッハ、モーツァルトを出すというのは選ばれし者だけが得られる特権のように見えてしまうのだ。
自分にとって、このバッハ、モーツァルトのオーボエ作品集で最初に虜になったのは、ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者のアルブレヒト・マイヤー氏の作品。そしてロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席オーボエ奏者アレクセイ・オグリンチュク氏の作品。本当に擦れきれるほど聴いた愛聴盤。
特に、バッハのオーボエ作品というジャンルは、オーボエ奏者にとって、ひとつの定番なのかな、と常々感じていた。ホリガー、ウトキン、ボイド、マイヤーなど 名だたる名手が同じような選曲のアルバムを作っている。
池田昭子さんは、N響の定期公演をはじめ、今まで、いろいろな実演に接してきたことはもちろんのこと、NHKでN響が登場する様々なTV番組でも拝見することも多く、とても親近感がある。
![m_ikedaweb5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_ikedaweb5B15D5B15D.jpg)
ご存知美人で、清楚な感じで、まさに華がある奏者。
もう隠れ大ファンと言っていい。(別に隠れる必要はありませんが。(笑))
美人奏者といっても、いわゆるギラギラしたこちらにグイグイ主張してくるような熱いタイプではなく、どちらかというと控えめで、涼しい感じの1歩引いた和風美人の佇まいが、なんとも魅力的だ。
自分とはひと回りも違うんですね。
ちょうど自分が前職時代で、人生の壁にぶつかり、暗黒の時代を過ごしていた1997年に、颯爽とクラシック業界に登場した。いま振り返ってみると、なんか自分の人生の明暗と入れ替わりというか、新しい時代の幕開けみたいな感じの存在のように思える。
東京藝術大学卒業。(1997年)
卒業時に、皇居内桃華楽堂にて御前演奏を行う。
1996年にオーボエコンクール第1位。(日本管打楽器コンクールなど)
1997~2002年 東京交響楽団在籍。
2000~2003年 ドイツ、ミュンヘンのリヒャルト・シュトラウス音楽院に留学。
2004年に、NHK交響楽団に入団。
まさに留学で、ミュンヘン在住でいらっしゃった2000~2003年は、その頃自分はというと、大病を患って、あえなく3年間会社を休職。いったん北海道の実家の親元に戻って、療養生活をしていた人生で最悪の暗黒の3年間だったのだ。(笑)
クラシックどころではなかった。
だから池田さんの活躍を認識するようになったのは、やはりN響に入団してからの活躍がメインになる。
N響ではオーボエが本職だが、じつはイングリッシュホルンの奏者としても、有名なのだ。
自分の記憶では、確かNHKの番組で、ダッタン人の踊りのあの異国情緒溢れるなんとも切ないメロディを、イングリッシュホルンで朗々と歌い上げていたのは、確か池田さんだったと思う。はっきり脳裏に刻まれている。
「のだめカンタービレ」のテレビドラマ版では、あのオーボエ黒木くんの吹き替えをやっていたのも、じつは池田さんだったそうだ。
N響首席オーボエ奏者の茂木大輔さん主催の「のだめコンサート」の東京初進出。
調布で開催されたが、自分ももちろん馳せ参じた。
オールN響メンバーという豪華なオケ編成で、池田昭子さんもソリストとして登場。
もちろん黒木くんの吹き替えでやったモーツァルトのオーボエ協奏曲をソリストとして演奏されていた。
なんかつい最近のような気がするよ。(笑)
終演後のサイン会。
手前から、高橋多佳子さん、茂木大輔さん、そして池田昭子さん。
前置きが長くなった。
そんな池田さんの3年振りの7作目のソロ最新作。
まさにオーボエ・ソロ作品集が大好物の自分を十分に満足させてくれる大傑作と相成った。
![886[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8865B15D.jpg)
池田昭子: Partita For Oboe Solo-j.s.bach, C.p.e.bach, Telemann
https:/
J.SバッハとC.P.Eバッハの親子やテレマンの無伴奏作品を収めた「パルティータ~無伴奏オーボエ作品集~」。オリジナルはフルート向け作品だそうだが、オーボエとしてフューチャリングされた作風もとても魅力的。
どれもバロック時代の作品だが、ご本人のインタビューでは、「自分はもともとモダン楽器の奏者。バロック時代の古楽奏法を学んでいる訳ではないので、それを下手にマネしても中途半端。自分なりに信じてモダン・オーボエとしてインスピレーションで演奏しています。」とのこと。
古楽様式に関しては尊重しつつも、やや苦手意識もある自分ではあるが、このアルバムを一聴して、思ったのは、純粋に美しい音楽として楽しめて、彼女の芯のしっかりとした音色で見事にその旋律を描き切っているということ。
そこに古楽もモダンも関係ないような・・・そんな卓越した次元の高さを感じる。
確かにバッハやテレマンの曲の旋律は、古典派でもないし、後期ロマン派でもなくて、やはりそれはバロック音楽そのもののメロディの音楽なんだけれど、聴いていて、それをあまり意識しないこと。オーボエの暖かい色彩に富んだ音色で、彼女のオーボエは芯が太くて安定している、そんな音色で奏でられる曲は聴いていて最高に気持ちの良い音楽だった。
音楽的にかなり楽しめる1枚だと思いました。
そして録音評であるが、これがちょっと驚きだった。自分は、かなり例によって(笑)、ここに反応してしまった。
レーベルがマイスター・ミュージック。
不勉強ながら存じ上げなかったので、調べてみたら大変なことを知った。
ヨーロッパにおいて、クラシック音楽の正式な録音を許可された、日本人初のディプロム・トーンマイスターによるレーベルなのだそうだ。
このマイスター・ミュージック、1993年に設立。このレーベルを立ち上げた平井義也氏は「トーンマイスター(Tonmeister)」というドイツの国家資格を日本人で初めて取得した人なのだ。
トーンマイスターに関しては、もう何回も日記で取り上げてきたので、今更深くは言及しないが、まさにドイツで始まった教育制度で、単に録音技術だけではなく、音楽学、作曲法、音響工学、電子工学などを総合的に教育される音の職人のこと。
日本で現在レコーディングエンジニアをやっている人で、このトーンマイスターの資格を持っている人は、じつは皆無なのだそうだが、平井さんは、その資格をきちんと取得した日本でも希有な職人なのだ。1970年代にデトモルト音楽大学に留学して理想論からピアノ、チューバなどの実技までをこなすと同時に、ドイツ各地でカール・ベームやカール・リヒターらの録音現場に立ち会う生活を送った。そしてこの資格を見事に取得したのだ。
マイスター平井さんの存在は、確かに昔、マイミク友人さんにコメントで指摘されて、その存在は記憶にあった。でもこうやって自分で学んでみて、”いまこのとき”に初めてその存在をしっかり理解でき認識できた。(笑)
世の中ってそういうもんだよな。
そのマイスター平井さんの録音のこだわりは、「シンプル」であること。
ちょうどコンサート・ホールの一番いい席で体験するような自然な音場を再現するために、まず、2本のマイクを1か所に立てるワンポイント録音を採用する。
収録する作曲家にふさわしい「響き」に演奏家の「個性」、そして楽器ごとの「バランス」などを勘案し、全てを満たした「一点」を広いホールの空間から探し出すという至難の業。
そこで生かされるのが、トーンマイスターとしての平井の鋭い耳と、経験と、なにより感性なのだそうだ。
更に、マイクにもこだわる。トランジスタ・マイクが録音現場の主流となっている中、ナチュラルで、奥行きのある音を求めて、マイスター平井は真空管マイクを使用。スウェーデン人、デットリック・デ・ゲアールが作る、世界で数組しかないというそのマイクは、高さ27cm、重さ2.2kgという世界一の大きさを誇る。
これが平井さんの録音の秘密を生む必須アイテムなのだ。
今回の池田さんのアルバムは、大田区民センターの音楽ホールで収録されているのだが、池田さんは、このマイクの前で吹いていたに違いない。(笑)
マスタリングの部分も拘りがあって、編集が済んだハードディスクから直接CDの原盤を作る、ダイレクト・カッティング方式で臨場感のあるサウンドを作るのがポリシー。でもこれは確かにそうなんだけれど、実際は大量マスタリングなどでは、大量生産に向いていないしコストも高くつく。
今回のクレジットを見ると、制振合金「M2052」によるマスターディスクを使用してのカッティングとある。
日本で唯一のトーンマイスターの資格を持つマイスター平井さん、そして拘りのある真空管マイク、そしてダイレクトカッティング。
マイスターミュージックというレーベルは、こんなに高音質に拘りに拘りぬいたレーベルだったのだ。
池田昭子さんは、過去7枚のソロアルバムは、すべてこのマイスターミュージックからリリースしている。
オーディオファイルの自分にとって、この部分は相当反応してしまった。
じゃあ自分が聴いたそのサウンドの印象はどうなのか?
それは確かにいままでのオーボエ・ソロ作品集では聴いたことのない、ある意味変わったサウンドであった。自分はいままで体験したことがないと言える。
まず、オーボエの録音レベル、音圧が異常に高い。
再生した途端、自分は思わず、プリのVOLを普段聴いているポジションから10dB下げたくらいだ。
かなり近接的な録音で、オーボエの音が前へ前へ出るという感じのエネルギー感溢れるサウンド。オーボエの録り方でこのように聴こえる作品は珍しいな、聴いたことないな、と思った。
オーボエ・ソロ作品に多いのは、背景の空間をある程度広めに認識させて、オーボエをややオフマイク気味に録って遠近感を出させるようなサウンドが多いのだけれど、池田さんの作品は、空間はさほど主張せずに、どちらかというとオンマイク気味で、その音圧、録音レベルが高いという感じ。コンサートホールの最前列やかなり前方の至近距離で聴いている感じで、オーボエの音がかなり強調されているような印象を受ける。
それで、驚くのは、その解像度の高さ。池田さんの息継ぎの音がはっきり聴こえるのが驚きなのだ。かなり生々しく聴こえる。これは例の真空管マイクの解像度が高いことを意味している。
ピアノのペダルノイズが聴こえたりとか、演奏者のブレスが聴こえたりとか、いわゆる演奏ノイズが聴こえるのは、自分のオーディオシステムの解像度の高さを試されているみたいなのだが、この部分には、ひたすら驚いた。
演奏に集中できなくなるほど目立つのも困りものだが、こういう暗騒音、演奏ノイズというのは、演奏にある程度の臨場感を与える上でもとても効果的で、自分は肯定派だ。
非常に解像度の高い一種特徴のある優秀録音だと思った。マイスター平井の作風ですね。他の小編成の室内楽でも聴いてみたいです。
素晴らしい録音だと思う。ただのCDです。もうこういう次元だと、SACDだから、とか、ハイレゾだから、とかのスペックって関係ないとつくづく思う。やはり”録音がいい”、というのは収録、編集のステージのところで決まっちゃうもので、ここの段階が高い水準のものは、ユーザへ届けるスペックなんて、どれを使おうが関係なくて、みんないい録音に感じるというのは真実の定説なんだな、ということをますます意を強くした。
せっかくの池田さんのディスクレビューなのに、結局また自分のテレトリーで話をして申し訳なかったですが、どうしてもここに反応せざるを得ず、オーディオマニアのオーディオマインドをくすぐるじつに秀逸な録音に仕上がっているディスクだと思う。
これはぜひお薦めです!
以前にも自分の日記で何回も特集したが、木管奏者、とりわけオーボエ奏者が自分のソロ作品集を出せるって、まさに華形スターの証拠なのだと思う。
自分は取り分けオーボエのソロ作品集には目がなくて、世界のオーケストラの首席オーボエ奏者が出すオーボエ・ソロのアルバムは、かなりコレクターしてきている。
特に、バッハ、モーツァルトのオーボエ作品集を録音するのは、ひとつの登竜門というか、晴れ舞台、一流の証のような気がする。普段は超一流オケの首席オーボエ奏者という立場で演奏し、その一方でソリストとして、このバッハ、モーツァルトを出すというのは選ばれし者だけが得られる特権のように見えてしまうのだ。
自分にとって、このバッハ、モーツァルトのオーボエ作品集で最初に虜になったのは、ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者のアルブレヒト・マイヤー氏の作品。そしてロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席オーボエ奏者アレクセイ・オグリンチュク氏の作品。本当に擦れきれるほど聴いた愛聴盤。
特に、バッハのオーボエ作品というジャンルは、オーボエ奏者にとって、ひとつの定番なのかな、と常々感じていた。ホリガー、ウトキン、ボイド、マイヤーなど 名だたる名手が同じような選曲のアルバムを作っている。
池田昭子さんは、N響の定期公演をはじめ、今まで、いろいろな実演に接してきたことはもちろんのこと、NHKでN響が登場する様々なTV番組でも拝見することも多く、とても親近感がある。
![m_ikedaweb5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_ikedaweb5B15D5B15D.jpg)
ご存知美人で、清楚な感じで、まさに華がある奏者。
もう隠れ大ファンと言っていい。(別に隠れる必要はありませんが。(笑))
美人奏者といっても、いわゆるギラギラしたこちらにグイグイ主張してくるような熱いタイプではなく、どちらかというと控えめで、涼しい感じの1歩引いた和風美人の佇まいが、なんとも魅力的だ。
自分とはひと回りも違うんですね。
ちょうど自分が前職時代で、人生の壁にぶつかり、暗黒の時代を過ごしていた1997年に、颯爽とクラシック業界に登場した。いま振り返ってみると、なんか自分の人生の明暗と入れ替わりというか、新しい時代の幕開けみたいな感じの存在のように思える。
東京藝術大学卒業。(1997年)
卒業時に、皇居内桃華楽堂にて御前演奏を行う。
1996年にオーボエコンクール第1位。(日本管打楽器コンクールなど)
1997~2002年 東京交響楽団在籍。
2000~2003年 ドイツ、ミュンヘンのリヒャルト・シュトラウス音楽院に留学。
2004年に、NHK交響楽団に入団。
まさに留学で、ミュンヘン在住でいらっしゃった2000~2003年は、その頃自分はというと、大病を患って、あえなく3年間会社を休職。いったん北海道の実家の親元に戻って、療養生活をしていた人生で最悪の暗黒の3年間だったのだ。(笑)
クラシックどころではなかった。
だから池田さんの活躍を認識するようになったのは、やはりN響に入団してからの活躍がメインになる。
N響ではオーボエが本職だが、じつはイングリッシュホルンの奏者としても、有名なのだ。
自分の記憶では、確かNHKの番組で、ダッタン人の踊りのあの異国情緒溢れるなんとも切ないメロディを、イングリッシュホルンで朗々と歌い上げていたのは、確か池田さんだったと思う。はっきり脳裏に刻まれている。
「のだめカンタービレ」のテレビドラマ版では、あのオーボエ黒木くんの吹き替えをやっていたのも、じつは池田さんだったそうだ。
N響首席オーボエ奏者の茂木大輔さん主催の「のだめコンサート」の東京初進出。
調布で開催されたが、自分ももちろん馳せ参じた。
オールN響メンバーという豪華なオケ編成で、池田昭子さんもソリストとして登場。
もちろん黒木くんの吹き替えでやったモーツァルトのオーボエ協奏曲をソリストとして演奏されていた。
なんかつい最近のような気がするよ。(笑)
終演後のサイン会。
手前から、高橋多佳子さん、茂木大輔さん、そして池田昭子さん。
前置きが長くなった。
そんな池田さんの3年振りの7作目のソロ最新作。
まさにオーボエ・ソロ作品集が大好物の自分を十分に満足させてくれる大傑作と相成った。
![886[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8865B15D.jpg)
池田昭子: Partita For Oboe Solo-j.s.bach, C.p.e.bach, Telemann
https:/
J.SバッハとC.P.Eバッハの親子やテレマンの無伴奏作品を収めた「パルティータ~無伴奏オーボエ作品集~」。オリジナルはフルート向け作品だそうだが、オーボエとしてフューチャリングされた作風もとても魅力的。
どれもバロック時代の作品だが、ご本人のインタビューでは、「自分はもともとモダン楽器の奏者。バロック時代の古楽奏法を学んでいる訳ではないので、それを下手にマネしても中途半端。自分なりに信じてモダン・オーボエとしてインスピレーションで演奏しています。」とのこと。
古楽様式に関しては尊重しつつも、やや苦手意識もある自分ではあるが、このアルバムを一聴して、思ったのは、純粋に美しい音楽として楽しめて、彼女の芯のしっかりとした音色で見事にその旋律を描き切っているということ。
そこに古楽もモダンも関係ないような・・・そんな卓越した次元の高さを感じる。
確かにバッハやテレマンの曲の旋律は、古典派でもないし、後期ロマン派でもなくて、やはりそれはバロック音楽そのもののメロディの音楽なんだけれど、聴いていて、それをあまり意識しないこと。オーボエの暖かい色彩に富んだ音色で、彼女のオーボエは芯が太くて安定している、そんな音色で奏でられる曲は聴いていて最高に気持ちの良い音楽だった。
音楽的にかなり楽しめる1枚だと思いました。
そして録音評であるが、これがちょっと驚きだった。自分は、かなり例によって(笑)、ここに反応してしまった。
レーベルがマイスター・ミュージック。
不勉強ながら存じ上げなかったので、調べてみたら大変なことを知った。
ヨーロッパにおいて、クラシック音楽の正式な録音を許可された、日本人初のディプロム・トーンマイスターによるレーベルなのだそうだ。
このマイスター・ミュージック、1993年に設立。このレーベルを立ち上げた平井義也氏は「トーンマイスター(Tonmeister)」というドイツの国家資格を日本人で初めて取得した人なのだ。
トーンマイスターに関しては、もう何回も日記で取り上げてきたので、今更深くは言及しないが、まさにドイツで始まった教育制度で、単に録音技術だけではなく、音楽学、作曲法、音響工学、電子工学などを総合的に教育される音の職人のこと。
日本で現在レコーディングエンジニアをやっている人で、このトーンマイスターの資格を持っている人は、じつは皆無なのだそうだが、平井さんは、その資格をきちんと取得した日本でも希有な職人なのだ。1970年代にデトモルト音楽大学に留学して理想論からピアノ、チューバなどの実技までをこなすと同時に、ドイツ各地でカール・ベームやカール・リヒターらの録音現場に立ち会う生活を送った。そしてこの資格を見事に取得したのだ。
マイスター平井さんの存在は、確かに昔、マイミク友人さんにコメントで指摘されて、その存在は記憶にあった。でもこうやって自分で学んでみて、”いまこのとき”に初めてその存在をしっかり理解でき認識できた。(笑)
世の中ってそういうもんだよな。
そのマイスター平井さんの録音のこだわりは、「シンプル」であること。
ちょうどコンサート・ホールの一番いい席で体験するような自然な音場を再現するために、まず、2本のマイクを1か所に立てるワンポイント録音を採用する。
収録する作曲家にふさわしい「響き」に演奏家の「個性」、そして楽器ごとの「バランス」などを勘案し、全てを満たした「一点」を広いホールの空間から探し出すという至難の業。
そこで生かされるのが、トーンマイスターとしての平井の鋭い耳と、経験と、なにより感性なのだそうだ。
更に、マイクにもこだわる。トランジスタ・マイクが録音現場の主流となっている中、ナチュラルで、奥行きのある音を求めて、マイスター平井は真空管マイクを使用。スウェーデン人、デットリック・デ・ゲアールが作る、世界で数組しかないというそのマイクは、高さ27cm、重さ2.2kgという世界一の大きさを誇る。
これが平井さんの録音の秘密を生む必須アイテムなのだ。
今回の池田さんのアルバムは、大田区民センターの音楽ホールで収録されているのだが、池田さんは、このマイクの前で吹いていたに違いない。(笑)
マスタリングの部分も拘りがあって、編集が済んだハードディスクから直接CDの原盤を作る、ダイレクト・カッティング方式で臨場感のあるサウンドを作るのがポリシー。でもこれは確かにそうなんだけれど、実際は大量マスタリングなどでは、大量生産に向いていないしコストも高くつく。
今回のクレジットを見ると、制振合金「M2052」によるマスターディスクを使用してのカッティングとある。
日本で唯一のトーンマイスターの資格を持つマイスター平井さん、そして拘りのある真空管マイク、そしてダイレクトカッティング。
マイスターミュージックというレーベルは、こんなに高音質に拘りに拘りぬいたレーベルだったのだ。
池田昭子さんは、過去7枚のソロアルバムは、すべてこのマイスターミュージックからリリースしている。
オーディオファイルの自分にとって、この部分は相当反応してしまった。
じゃあ自分が聴いたそのサウンドの印象はどうなのか?
それは確かにいままでのオーボエ・ソロ作品集では聴いたことのない、ある意味変わったサウンドであった。自分はいままで体験したことがないと言える。
まず、オーボエの録音レベル、音圧が異常に高い。
再生した途端、自分は思わず、プリのVOLを普段聴いているポジションから10dB下げたくらいだ。
かなり近接的な録音で、オーボエの音が前へ前へ出るという感じのエネルギー感溢れるサウンド。オーボエの録り方でこのように聴こえる作品は珍しいな、聴いたことないな、と思った。
オーボエ・ソロ作品に多いのは、背景の空間をある程度広めに認識させて、オーボエをややオフマイク気味に録って遠近感を出させるようなサウンドが多いのだけれど、池田さんの作品は、空間はさほど主張せずに、どちらかというとオンマイク気味で、その音圧、録音レベルが高いという感じ。コンサートホールの最前列やかなり前方の至近距離で聴いている感じで、オーボエの音がかなり強調されているような印象を受ける。
それで、驚くのは、その解像度の高さ。池田さんの息継ぎの音がはっきり聴こえるのが驚きなのだ。かなり生々しく聴こえる。これは例の真空管マイクの解像度が高いことを意味している。
ピアノのペダルノイズが聴こえたりとか、演奏者のブレスが聴こえたりとか、いわゆる演奏ノイズが聴こえるのは、自分のオーディオシステムの解像度の高さを試されているみたいなのだが、この部分には、ひたすら驚いた。
演奏に集中できなくなるほど目立つのも困りものだが、こういう暗騒音、演奏ノイズというのは、演奏にある程度の臨場感を与える上でもとても効果的で、自分は肯定派だ。
非常に解像度の高い一種特徴のある優秀録音だと思った。マイスター平井の作風ですね。他の小編成の室内楽でも聴いてみたいです。
素晴らしい録音だと思う。ただのCDです。もうこういう次元だと、SACDだから、とか、ハイレゾだから、とかのスペックって関係ないとつくづく思う。やはり”録音がいい”、というのは収録、編集のステージのところで決まっちゃうもので、ここの段階が高い水準のものは、ユーザへ届けるスペックなんて、どれを使おうが関係なくて、みんないい録音に感じるというのは真実の定説なんだな、ということをますます意を強くした。
せっかくの池田さんのディスクレビューなのに、結局また自分のテレトリーで話をして申し訳なかったですが、どうしてもここに反応せざるを得ず、オーディオマニアのオーディオマインドをくすぐるじつに秀逸な録音に仕上がっているディスクだと思う。
これはぜひお薦めです!
![327[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_3275B15D.jpg)

![502[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5025B15D.jpg)

![653[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6535B15D.jpg)
![112[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_1125B15D.jpg)
![513[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5135B15D-28b72.jpg)

![5135x2P9RaL._AC_SY355_[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5135x2P9RaL._AC_SY355_5B15D.jpg)
![132[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_1325B15D.jpg)
![037[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0375B15D.jpg)
![693[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6935B15D.jpg)
![256[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2565B15D.jpg)
![932[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_9325B15D-42383.jpg)

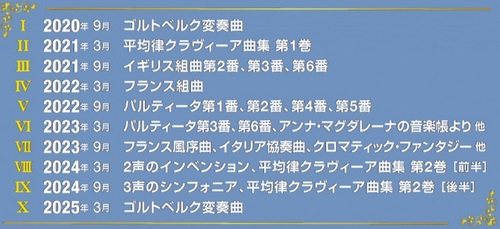
20Noriyuki20Kamio.jpg)
![232[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2325B15D.jpg)
![304[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_3045B15D.jpg)
![636[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6365B15D.jpg)
![938[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_9385B15D.jpg)
![882[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8825B15D.jpg)
![423899_316651781727172_1107422723_n5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_423899_316651781727172_1107422723_n5B15D5B15D.jpg)
![6_1[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6_15B15D-8c3cb.jpg)
![10_KKC1171[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_10_KKC11715B15D.jpg)
![6_2[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6_25B15D-b107b.jpg)
![2_1[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2_15B15D.jpg)
![2_2[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2_25B15D.jpg)
![615[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6155B15D.jpg)




![207[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2075B15D.jpg)
![083[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0835B15D-d3b41.jpg)
![14468161_1299313830088945_7401486772665747408_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_14468161_1299313830088945_7401486772665747408_o5B15D.jpg)


![82976159_3654351844604896_1249675718942523392_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_82976159_3654351844604896_1249675718942523392_o5B15D.jpg)
![81227967_3590645410975540_6608649539651895296_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_81227967_3590645410975540_6608649539651895296_o5B15D.jpg)
![104820403_4198194176887324_7884290060147779203_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_104820403_4198194176887324_7884290060147779203_o5B15D.jpg)
![25940505_2237479445_208large[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_25940505_2237479445_208large5B15D.jpg)


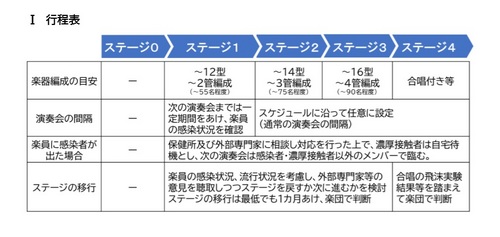
![100997169_3874899475884459_3428846450241437696_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_100997169_3874899475884459_3428846450241437696_o5B15D.jpg)
![101440624_3874899609217779_1272262999196827648_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_101440624_3874899609217779_1272262999196827648_o5B15D.jpg)
![100502363_3195003397286584_3002400955602829312_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_100502363_3195003397286584_3002400955602829312_o5B15D-6d921.jpg)
![100090247_3195003507286573_283610795227480064_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_100090247_3195003507286573_283610795227480064_o5B15D-80342.jpg)
![101196314_3874899452551128_2569283843450208256_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_101196314_3874899452551128_2569283843450208256_o5B15D.jpg)
![100932227_3878863735488033_8492024082273927168_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_100932227_3878863735488033_8492024082273927168_o5B15D.jpg)
![101542491_3874899455884461_5317771293200744448_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_101542491_3874899455884461_5317771293200744448_o5B15D.jpg)
![557[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5575B25D.jpg)
![105571082_3265424683577788_1569569518087821980_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_105571082_3265424683577788_1569569518087821980_o5B15D.jpg)
![105046800_3265424860244437_8806585588495560088_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_105046800_3265424860244437_8806585588495560088_o5B15D.jpg)
![104834414_3265424816911108_7064525027814128518_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_104834414_3265424816911108_7064525027814128518_o5B15D.jpg)
![104873549_3265424640244459_3502173790383355245_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_104873549_3265424640244459_3502173790383355245_o5B15D.jpg)
![105702676_3265424696911120_7047901794357261685_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_105702676_3265424696911120_7047901794357261685_o5B15D.jpg)
![105038329_3265424773577779_3701938561860920203_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_105038329_3265424773577779_3701938561860920203_o5B15D.jpg)

![98268566_3181368908650033_2843964959287672832_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_98268566_3181368908650033_2843964959287672832_o5B15D.jpg)
![98274396_3181368915316699_5159368320889126912_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_98274396_3181368915316699_5159368320889126912_o5B15D.jpg)

![23511268_2027685104133259_2303008298154319827_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_23511268_2027685104133259_2303008298154319827_o5B15D.jpg)

![AS20160411001997_comm[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_AS20160411001997_comm5B15D.jpg)
![442[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_4425B15D-8ff2d.jpg)
![727[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_7275B25D.jpg)
![295[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2955B25D.jpg)
![605[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_6055B15D.jpg)

![790[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_7905B15D.jpg)


![109208786_3249777445066051_4941723852859135440_o[2].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_109208786_3249777445066051_4941723852859135440_o5B25D.jpg)
![100798575_3121288034581660_8278509768952250368_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_100798575_3121288034581660_8278509768952250368_o5B15D.jpg)
![94476871_3047770748600056_21586497039761408_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_94476871_3047770748600056_21586497039761408_o5B15D.jpg)
![96371399_3068448376532293_672933925454086144_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_96371399_3068448376532293_672933925454086144_o5B15D.jpg)
![96142327_3068446746532456_7157462359110320128_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_96142327_3068446746532456_7157462359110320128_o5B15D.jpg)
![96021802_3068444979865966_8700665355766333440_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_96021802_3068444979865966_8700665355766333440_o5B15D.jpg)
![95490325_3064187810291683_6272371862576037888_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_95490325_3064187810291683_6272371862576037888_o5B15D.jpg)
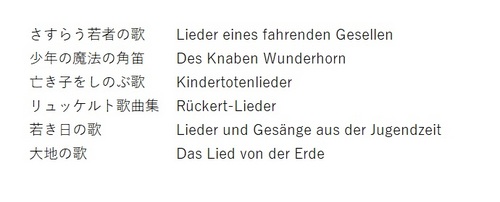
![258[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2585B15D-25503.jpg)
![193[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_1935B15D.jpg)
![m_1854788466_245B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_1854788466_245B15D5B15D.jpg)














![459[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_4595B15D.jpg)
![76200134_2030390896993141_8069815250750275584_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_76200134_2030390896993141_8069815250750275584_n5B15D.jpg)



![72628656_2030390903659807_4449610393811156992_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_72628656_2030390903659807_4449610393811156992_n5B15D.jpg)

![551[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_5515B15D.jpg)


![83079533_2833254116735981_954274748861251584_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_83079533_2833254116735981_954274748861251584_o5B15D.jpg)

20Hikaru.jpg)

![838[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_8385B15D.jpg)
![53190964_1052084104973601_6277321279808733184_n[3].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_53190964_1052084104973601_6277321279808733184_n5B35D.jpg)
![news1637419[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_news16374195B15D.jpg)


![26231079_1649011068525593_9661414788841510_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_26231079_1649011068525593_9661414788841510_n5B15D.jpg)






![29027869_2092484010998613_5405559436341699704_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_29027869_2092484010998613_5405559436341699704_n5B15D.jpg)

![36698231_1528928107212944_1310490583248142336_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_36698231_1528928107212944_1310490583248142336_o5B15D.jpg)
![1462767_859963410703167_6441965509203805186_o[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_1462767_859963410703167_6441965509203805186_o5B15D.jpg)

![264[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_2645B15D.jpg)
![m_25940505_1825453179_222small5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_25940505_1825453179_222small5B15D5B15D.jpg)
![m_25940505_1825453180_238small5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_25940505_1825453180_238small5B15D5B15D.jpg)
![m_25940505_1825453177_200small5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_25940505_1825453177_200small5B15D5B15D.jpg)
![097[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_0975B15D.jpg)
![1912490_10151927106181863_1791452699_n5B15D[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_1912490_10151927106181863_1791452699_n5B15D5B15D.jpg)
![25552228_10155141185600857_7280434861141426764_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_25552228_10155141185600857_7280434861141426764_n5B15D.jpg)
![26167902_10155162532240857_1313934975516700436_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_26167902_10155162532240857_1313934975516700436_n5B15D.jpg)
![24909789_10155114427290857_6293726926418721308_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_24909789_10155114427290857_6293726926418721308_n5B15D.jpg)
![26169615_10155175274060857_4497081703454313632_n[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_26169615_10155175274060857_4497081703454313632_n5B15D.jpg)
![m_DSC04866[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_m_DSC048665B15D.jpg)
![book02[1].jpg](https://akira-nonaka.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_ea6/akira-nonaka/m_book025B15D.jpg)



